「EWEN」&「魔王ゼファー」クロスオーバー企画第3弾
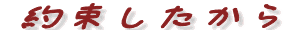
|
第2回 ―― 雪羽 今聞いたことは、現実だったのか、それとも夢だったのか。 目の前に、きゅっと唇を結んだ聖の思いつめた顔がある。 大好きな聖。ずっとずっと会いたかった。とうとう一年半ぶりに会えるこの日を、私がどんなに心待ちにしていたか。 それがこんな形で、粉々になってしまうなんて。 「夢を見るのは、いいことだと思うんだ」 私の引きつった表情に気づいて、聖はあわてたように言葉を続けた。 「でも、現実と夢の割合が逆転してはいけないと思う。オレたち、いつもアラメキアのことばっかりだったろう?」 ぼんやりと、ただ言葉が流れてくるのを聞いている。 「ふたりで空想にふけるのは、最初はとても楽しかったよ。おととしの春、きみがオレの家に遊びに来てくれたときも、ずっと家の庭で空想したよね。もし、ここからアラメキアに行けたら、どうしよう。もし向こうの住民の家に泊まることになったら。冒険の旅には、どんなものを持っていったらいいだろうって」 「空想?」 私は、まじまじと聖を見つめた。 「忘れたのか、聖。――本当に、庭の雑木の中で穴が開いたんだ。私たちは、その穴をアラメキアに通って行ったんだぞ」 「あれは、オレたちふたりが相談しながら、頭の中で考え出した空想だったんだよ」 聖は、苦しそうな呼吸をしていた。 「二メートル以上絶対に離れないって決まりを作って、大きなリュックを持って、歩いたり電車に乗ったりして、半日かけて姫路城に着いた。そこが精霊の都のお城だっていうことにしようって、オレたちライトアップされた姫路城を見上げながら、たくさん話した。あの旅行は、とっても楽しかったよ。そして帰ってきてから――」 彼は竹刀の袋を開けて、精霊の女王から賜った、アラメキアの草木が変化してできた緑の鞘を取り出した。 「ふたりで、木の鞘をアクリル絵の具で緑色に塗って、アラメキアの思い出ということにしたんだ」 「違う!」 私はテーブルの端をつかんだ。世界がさかさまになってしまったようで、怖くてたまらなかった。 「なぜだ、聖。……なぜ、何もかも忘れてしまった。私たちは、確かに行ったのだ。何日もかけて魔族の国を旅して、魔族の襲撃も受けた。ミネアスの大河を越えるときは、渡し守の意地悪で、離れ離れになってしまった。そして、リューラの都にたどりついて、精霊の女王さまの病を、持っていった塩で癒したではないか!」 聖は、しばらく答えなかった。薄い茶色の目を細めて、次のことばを言おうかどうか、迷っているようだった。 でも、やがて、吐き出すように言った。 「オレは行ってないよ。アラメキアになんか、行ってない」 「どうしてしまったんだ、聖」 両目から、熱いものがあふれるのを感じた。 「おまえは、私を守ると約束してくれたではないか。女王さまに雪羽の騎士になるかどうかと訊かれたとき、安請け合いはできない、もっと剣の修行をしてから返事をしたいと――」 「やめろよ! そんな話、もう聞きたくない」 聖は怒鳴った。 私に向ける表情が、ぞっとするほど冷たい。 喫茶店じゅうの人が、こちらを見ているのに気づき、私たちはうなだれてしまった。 下を向いた拍子に涙が頬を伝うのを感じ、私はうろたえてバッグをつかみ、喫茶店を逃げるように飛び出した。 「雪羽!」 会計をすませてから出て来たのだろう。聖が、後ろから叫びながら、私を追いかけてきた。 私は走るのをやめて、立ち止まった。 本当は、聖に追いかけてきてほしかった。ケンカ別れなどしたくない。聖といっしょに過ごすはずの大切な時間を、だいなしにしたくない。 「雪羽」 聖は、振り向いた私の肩にそっと手を置いた。 「ごめん」 「……」 「オレ、きみのことが、小学生のときからずっと好きだよ」 「……私もだ」 「好きだから、ふたりでいられる時間を大切にしたい。本当は片時も離れたくないのに、兵庫県と東京じゃ、いつも会えるわけじゃない。それにオレたち、これから高校生になる。将来のこととか、自分の考えとか、もっともっと話し合わなければならないことが山ほどあるのに、空想の話ばかりして時間をムダにするのは、いやなんだよ」 「……聖」 「たぶん、ゼファーさんや佐和さんが、きみにそういう空想をする子になってほしいと望んだんだね。オレも最初は、アラメキアのことを話してる雪羽に魅かれた。キラキラ輝いてて、大好きだった。でも……今は、苦しいんだ。ついていけない。オレ、もう雪羽のことが、わからないんだ」 聖は、長い睫毛を震わせながら、懸命に涙をこらえているようだった。 「お願いだから」 私の額にかかる前髪を撫でながら、ささやいた。 「オレの前では、もうアラメキアの話をしないと約束してくれ」 「そんな……聖」 「そうでないと、オレ、きみとはもう付き合えない」 考える前に、私はいやいやをするように首を振っていた。 「無理だ……聖。そんなこと、約束できない」 その答えを聞いた彼の顔が、みるみる強ばった。 「オレと、アラメキアと、どちらを選ぶんだよっ」 私は思わず目を閉じ、ぎゅっと奥歯を食いしばった。聖の剣幕は、今にも私を叩きそうなほど、激しく見えたのだ。 でも、何も起きなかった。 「……ごめん、頭が混乱して、どうしたらいいかわからない」 聖の声が、ひどく遠くから聞こえた。 「今はきみの家に行けない。今晩泊めてもらう友だちの家に、いったん荷物を置いて来るよ。それから、もう一度話そう……携帯はちゃんと開けておくから」 聖が立ち去る足音が消えてからも、私はずっと目を閉じて、道の真ん中に立っていた。 そうしていれば戻ってきてくれると、頭のどこかで期待していたのかもしれない。 やがて、そろそろを目を開くと、聖はもうどこにもいなかった。 歩き出したけど、足の感覚がほとんどなかった。まるでぐらぐら揺れ動く地面を歩いているようだ。 家にたどりつくと、すぐに玄関の扉が開いた。 「おかえり」 工場の制服を着ていない、休日の父上が出てきて、扉を押さえてくれた。 「あれ。聖は?」 「……」 私は声もなく、父上の胸に飛び込んだ。今の私が心から泣ける唯一の場所に。 「もう、大丈夫か」 自分の部屋まで抱きかかえて運んでもらうと、父上はそのままベッドのそばに胡坐をかいて、私が泣き止むのを待っていてくれた。 母上が持ってきてくれた、蜂蜜入りの温かいミルクが、涙でひりひりする喉を心地よく潤した。 「聖は、オレかアラメキアか、どちらかを選べと言った」 ベッドの縁に足を垂らして座り、父上に今日あったこと一部始終を話した。 「今でも夢を見ているようだ。聖は私とアラメキアに行ったことを完全に忘れている。わざと忘れたふりをしているわけじゃないと思う」 「受験中も、ときどきはテレビ電話で話していたのだろう。今までに思い当たるようなことはなかったのか」 私は首を振った。 「それまでは、まったくいつもの聖だった」 「そうか」 父上はため息をついた。 「今日、ディーターから電話があったんだ。この数日、聖の様子がおかしいと。家族を顔を合わせることも避け、問いつめると、ひどい暴言を吐いたと」 「ご両親に暴言だなんて。聖は、絶対にそんなことをする人じゃないはずだ」 聞いたことが、信じられなかった。 「聖はいつも、ディーターさんや円香さんのことを、とても大切に思っている。まるで人間が違ってしまったみたいだ」 私は、今日の彼のぞっとするほど冷たい目を思い出した。「……いったい、どうしてしまったんだろう」 父上は、しばらく何事かを思案していた。 「俺かアラメキアかのどちらかを選べ、と言ったんだな」 「うん」 「昔、俺も似たようなことを言ったことがある」 「父上が?」 父上は、どこか遠くの景色を見つめているような眼差しになった。 「俺は、精霊の騎士だった。アラメキアの女王はすべて、ぴったりと影のように寄り添うべき騎士を持つ。俺はその騎士として、どんなときも精霊の女王を危険から守るべき務めを担っていた。だが次第に、おのれの分を超えて、女王に自分だけを見てほしいと願うようになった」 そして、苦い色の笑いをこぼした。 「ある日、俺は女王に詰め寄ったんだ。あなたは、アラメキアのことしか頭にないのですか、と」 「それで?」 私は、母上がこの会話を聞いていたらどうしようと、心の隅で心配しながらも問いかけた。 「きっぱりと言われたよ。アラメキアのことしか、考えたことはないと」 父上は、低い小刻みな笑い声をたてた。 「俺はそれを聞いたとたんに、焔のような怒りに全身を包まれた。『それならば、おまえの大切なアラメキアを、この手で滅ぼしてやる』と女王に宣言したのだ。その瞬間に俺の身体は、光から暗黒なるものへと変化していた」 私は息をするのも忘れていた。 「俺は、今の自分の運命を悔いてはおらん」 父上は私に笑いかけた。「そうでなければ、地球に来て佐和と出会うことは、なかっただろうからな。だが――あんな形で騎士の務めを放棄し、魔王となったことは、やはり過ちだったのだと思う」 「……」 父上の言いたいことが、ようやくわかってきた。 「ことによると、聖も」 父上は続けた。 「俺と同じ葛藤の中にいるのかもしれん。『俺を選ぶのか、アラメキアを選ぶのか』――雪羽は、この問いにどう答えるつもりだ?」 「え?」 「今のままならば、精霊の女王と同じ答えを出すことは、聖を永久に失うことだ。おまえに、それが耐えられるか」 「わた……しは」 ぼんやりと、くぐもった声で答える。 聖を永久に失う。私は、聖を永久に失う。 「そんなこと……」 また、はらはらと涙が落ちるのを感じる。 「そんなこと、できない。私は聖が好きだ」 「それなら、アラメキアのことは忘れろ」 父上は、穏やかな声で言った。 「むずかしいことではない。おまえが聖を選んだ瞬間に、アラメキアのことは、ただのおとぎ話としてしか思い出せなくなる――今の聖がそうであるように。もう二度と精霊の女王に会うこともなく、アラメキアの言葉を理解することもできなくなるだろう」 「そんな……」 私は、あえいだ。 「そんなことをすれば、私は魔王ゼファーの娘ではなくなってしまう!」 「それでいい。俺はおまえがどんな選択をしても、受け入れる」 父上は、やさしく微笑んだ。「おまえが幸せになれるほうを選べばいい――そうしなさい」 「父上!」 私は、わあわあ泣きじゃくりながら、大きな胸にすがりついた。 「アラメキアのことを忘れてしまうなんて……私は、父上の故郷の言葉も思い出も理解できなくなる」 「わかっている」 「父上とヴァルがアラメキアの話をするたびに、馬鹿にしたような目つきで見るかもしれないのに」 「それでいい。俺はかまわぬ」 「……父上」 父上のぬくもりに抱かれて、私は赤子のように、いつまでも泣いた。 夕方、私は聖の携帯に連絡を入れた。 「話したいことがある。近くまで来てはくれないか」 『わかった』 小学生のとき行ったきりの、うちの近くの公園のことを、聖は覚えていてくれた。それがとても嬉しかった。 カラスがうるさいほど鳴き交わす夕暮れの公園で、私は聖を待つ間、じっと今までのことを思い返していた。 最初に出会ったとき。聖は黒猫姿のヴァルの言葉を、ちゃんと聞き取れたのだっけ。 私がアラメキアの話をしても、じっと考え深い表情で聞いてくれた。 この公園で、父母と絶縁状態だった祖父に、心をこめて話してくれた。 駅前通りの舗道の真ん中で、マフラーに隠れて、はじめてのキスをした。 そして、アラメキアでの冒険の数々。 私はいつのまにか、一生彼の隣を歩めると信じていた。 いつか時が来たら、ふたりでアラメキアに行き、ふたりで力を合わせて平和な世界を築くのだと信じていた。 『オレ、強くなる。そしてアラメキアに行くときは、少しでもきみを守ってあげられるようになりたい』 約束したのに。小学校のときに約束したのに。聖は、その約束さえも忘れてしまったのか。 夕闇の作りだした網の中をくぐるようにして、聖がゆっくりと近づいてきた。 「雪羽」 私を見ても、ほとんど表情を変えない。 「聖。来てくれて、ありがとう」 あなたのことが、私は大好きだった。 「よく考えて、結論を出した。聖を選ぶか、アラメキアを選ぶか」 これからだって、ずっと死ぬまで好きだと思う。 「聖を大切に思っている。でも、私はアラメキアを忘れることなどできない」 愛している。聖。いつまでも。 「だから――すまない」 彼は一瞬、目を吊り上げたが、ゆっくりと元の無表情に戻った。 「わかったよ。それが雪羽の結論なんだな」 冷たい声。まるで憎み合っている者同士のように。 「もう、二度と会わない」 「聖……」 お願い、お願いだ。聖。私をそんな目で見ないで。 「さよなら。雪羽」 彼は、くるりと身体をひるがえすと、歩き始めた。一度も振り返らずに。 「……聖」 彼の姿が木立の向こうに消えたあと、私は静かに地面に崩れ落ちた。 心臓なんか止まればいいのに、耳の内側を規則正しく脈が打っている。 息なんてしたくないのに、後から後からしゃくりあげてしまう。 私は、聖を失っても、まだ生きているのか。 精霊の女王さま。 あなたもきっと、父上が去ったあと、こんなにお辛かったのですね。 もう決して人を好きにならないと、心に固く誓われたのでしょうね。 今すぐに、あなたに会いたい。そしてお聞きしたいのです。あなたはどうやって、この苦しみに耐えられたのですか。――私には、とうてい耐えられそうにありません。 木枯らしが吹き過ぎる。花ひとつない冬の公園には、答えてくれる声はどこにもなかった。 |