「開幕前の解説は、旧YX35便の通信士、新婚のチェンとロロが担当いたします」
「時は1870年、舞台は、フランスはパリが誇るオペラ座」
「この三年前から、オペラ座では不可解な事件や事故が次々と起こっていました。しかもその原因は、オペラ座を陰から支配する『ファントム・オブ・オペラ』だという噂」
「つまり、意に副わないキャストや演目が選ばれると、ファントムが邪魔をするってことね」
「しかも、神出鬼没で姿をまったく現さない。人々がおびえるのも当然だな」
「それで、このファントムをうちのキャプテンが、ヒロインのクリスティーヌをユナさんが演じるって?」
「あの強引さと可憐さの組み合わせがぴったりだと思わないか? しかもクリスティーヌの恋人のラウル役は、ランドールだって」
「うわあ。こりゃ、演技じゃなく、マジで命がけの舞台になりそう」
「オペラと言えば、うちのお話ではもともと、たくさんのオペラや楽曲が作中にからんできたね。――レオンカヴァッロの『道化師』、ワーグナーの『トリスタンとイゾルデ』、シェークスピアの『オテロー』。でも、今回はあえてミュージカルに挑戦することになったんだ」
「しかも、シリアスかと思うとズッコけるし、大騒動。さあ、いよいよ開幕のベルです。ゆっくりお楽しみください!」
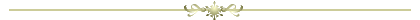
今日は新作オペラ「ハンニバル」の初日。
オペラ座は朝から喧騒の中だった。
背景や大道具を直す槌音。大慌てで衣装の埃をはらう者に飾り羽根の兜を捜す者。バーにつかまり、何度もポーズを確認するバレリーナたち。
そこに、オペラ座の新しい支配人たち(コウ・スギタ、ドクター・リノ)と、後援者ラウル・シャニュイ子爵(ランドール・メレディス)が訪れる。
「あれは……クリスティーヌ?」
「おや、子爵閣下は、あの娘をごぞんじですか。あの娘は運がいい。実は先ほど、総仕上げの立ち稽古で、天井から背景幕が落ちてくるアクシデントがあったとかで、主役を演じるはずの歌姫が役を降りてしまったのです」
その代役を急遽務めることになったのが、クリスティーヌ・ダーエ(ユナ・三神)。すぐれた才能と美声を秘めたバレエダンサーだった。
「大成功よ。すばらしい歌声だったわ。おめでとうクリスティーヌ」
「ありがとう。メグ」
地下の祈祷室で感謝の祈りを捧げるクリスティーヌのもとに、友人のメグ・ジリー(ハヌル看護師)がやって来る。
「今日こそ、あなたの秘密を教えて。あなたに歌を教えてくれるという教師のことを」
「私の亡くなった父は音楽家だったの。死の床で、父は私に約束してくれた。天国から音楽の天使を送ってくれると」
両親を亡くし、寄宿生としてこのオペラ座に来たときから、ひとりの男性がどこからか、彼女にいつも語りかけてくれたというのだ――地下の礼拝堂で、寄宿舎のベッドで。
「でも、私も姿を見たことはないの。とても、厳しい先生なのよ。ときどきひどく怒られるわ。『声が小さい。何言ってるかわからん。まともな奴に替われーっ』って」
「まあ。口の悪い天使さま」
「でも、私が上手に歌うといつも、リボンを結んだ一輪のバラを届けてくれる。そして、私の声を《ギャラクシー・ヴォイス》と呼んで、褒めてくれるの。星々の間に奏でられる、伝説の声のことなんですって」
音楽の天使 私の導き手 守護者
あなたの光を 私に注いで
音楽の天使 もう隠れないで
謎に満ちた 不思議な天使よ
今も 彼が私のそばにいる
「小さなロッテ」
「ラウル!」
楽屋のクリスティーヌのもとを、ラウルが訪れた。
「僕のことを覚えているかい。子どものころ、僕たちは海辺の別荘で遊んだね」
「ええ。私たち、いろいろなことを話したわ」
「ということは、僕たちは幼なじみになるんだな。覚えておけよ。このサイトの小説では、幼なじみは絶対に結ばれない」
「まあ、そんなネタバレを……」
「今夜はゆっくり積もる話をしたい――今から外に出られるかい?」
「……無理だわ。音楽の天使は厳格な方なの」
「生意気な若造め!」
鏡の裏からふたりの様子を覗いていたファントム(レイ・三神)は憎憎しげに毒づく。
「クリスティーヌをおまえなどに渡すものか」
おまえに見せてやろう
暗闇の中の私の真実を
鏡をのぞいてごらん
私はそこにいる その中に
私がおまえを導く 音楽の天使だ
私のところへおいで 音楽の天使よ
ラウルの存在に苛立ったファントムは、ついにクリスティーヌを鏡の隠し通路へと招き入れ、オペラ座の地下に広がる壮大な迷宮へといざなった。
私の魂と あなたの声が
ひとつに 結びついている
ファントムオブオペラはここにいる 私の心の中に
この迷宮の中では
夜が 目の光を奪う
ファントムオブオペラはここにいる おまえの心の中に
船は長い地下水路を抜け、ファントム自身が「甘美な音楽の主操縦席(コクピット)」と呼ぶ場所へとたどり着いた。
そこは、湖の上の小島のような場所。無数のロウソクが灯り、妖しく美しい舞台装置の数々で飾られている。
ファントムは、白いマスクに顔を覆っているが、理知的な薄茶色の瞳をした男だった。甘い声が彼女を愛撫するように包んだ。
「クリスティーヌ。おまえの歌声をはじめて聞いたとき、私は思った。
《ギャラクシー・ヴォイス》。この声の持ち主こそ、私の音楽に翼を与えてくれる声だと」
「あなたはどうして、こんな場所に隠れて住んでいらっしゃるの?」
「夜こそは、宇宙の深淵。世界を覆う真実。光は真実を写さず、何も見せてはくれぬ。暗闇の中でこそ、音楽はもっとも美しく奏でられる」
ファントムは、彼女の体を背中からそっと抱き取った。
やさしく 巧みに
音楽はおまえを包み込む
聞いて感じ取れ おまえをとりこにするものを
心を開き ファンタジーに身をまかせよ
もうおまえは抗えぬ
夜の音楽がもたらす暗黒に
目を閉じて 未知の世界へと旅立つのだ
今までの世界の記憶を捨てて
音楽が おまえを解き放つだろう
私のもとへと
クリスティーヌは、彼の歌の魔力に囚われて恍惚となりながらも、思った。
(なぜ、彼は顔を見せないの? 見たい、彼の素顔を。その下に隠されている秘密を)
誘惑に負けて仮面をはずすと、途端にファントムは、性格が正反対に変わったかのように、口を極めて彼女を罵り始めた。
「くそ、この詮索好きで、好奇心の強い女め。呪われろ!」
突然の変容に、クリスティーヌは声もない。
ファントムは両手で顔を覆い、うめいた。
「見たのか。この顔を見たのか」
「……」
「もう一度、目をそらさずに見る勇気がおまえにあるか。まるで地獄の炎で焼かれたガーゴイルのようだったろう」
「私そんなつもりじゃなかったの。……ごめんなさい」
クリスティーヌは狼狽しつつ、仮面を彼に返す。
彼は元通りにそれを着け、低くうめくように言った。
「それでも、そんな悪魔の落とし子でも、ひそかに日の当たる場所に出たいと願うこともある。だからオペラ座を陰から支配しようとした。そのためなら、どんな脅迫めいたことも、悪事もした」
彼はクリスティーヌをじっと見つめて、訴えた。
「だが、ある日きみを見出し、その歌声を心の底から愛したのだ。オペラ座の観客すべてを魅了するプリマドンナに育てたいと思うようになった。私のしていることは、間違っていない。どんな醜い獣でも、美を夢見る権利くらい持っているだろう?」
切々と訴える声に、クリスティーヌは打ちのめされた。
(この人はどれだけの間、ひとりで慟哭してきたのだろう。これほど才能にあふれ美しい音楽を創り出せる人が、顔を仮面で隠し、自らの運命を呪いながら、気の遠くなるような歳月を生きてきたのだ――この暗闇にたったひとりで)
彼女の目から、一滴の涙が伝い落ちた。
「私を恐れないでくれ。おまえなら、きっとわかってくれる。この恐ろしいモンスターの中に人間がいることを」
ファントムの噂でパリ中が持ちきりになり、オペラは連日の盛況となった。
そこへ、ファントムから『私の劇場の運営方針』と題した手紙が主だった関係者に送りつけられる。
二万フランの給料をファントムに支払うこと。五番ボックスの席を彼のために常に空けておくこと。
コーヒーカップは、机の角からぴったり18センチ、15センチの場所に置いておくこと。
そして、次のオペラ『イルムート』のキャスティングを入れ替え、台詞のない役しか宛がわれなかったクリスティーヌを、歌姫カルロッタ(シェフ・ジョヴァンナ)の代わりに主役に据えよ。さもないと、おそろしい災難がふりかかるであろうと。
だが、スキャンダルを恐れた支配人たちは、その命令に従わない。
そこで、ファントムは主演女優の喉に毒を盛って歌えなくしてしまい、劇は途中で大混乱に陥った。
ファントムを見かけた、道具係のブケー(タオ機関長)は、彼の後を尾ける。
天井裏でファントムに鉢合わせしたブケーは、首にロープを巻きつけられ、舞台で宙吊りにされた――かのように見えたのだが。
「なにをぉぉ。エンジンの手動操作で鍛え上げた、この体をなめるなーっ」
強靭な腕力でロープをつかんで逆噴射したため、すぐにロープが切れて命を取りとめたのだった。
「ラウル。来て! ファントムは命令を聞かなかったことを怒って、今度はあなたを狙うかもしれない」
クリスティーヌは彼を伴い、地下から最も遠いところ、オペラ座の屋上へと必死で逃げた。
「クリスティーヌ。落ち着いて。『ファントムオブオペラ』なんかいるわけはない」
「いいえ、いるわ。私は彼の迷宮に行ったもの。暗黒の世界。星の光が夜の闇にのまれる世界へと」
屋上で、彼女は途方に暮れたようにラウルを見つめた。
「それに私はこの目で彼を見たの。おぞましい顔だった。でも――彼の音楽はすばらしかった。魂がゆすぶられるほど美しい、天上の音色。二度と忘れられない、あの夜」
クリスティーヌは、舞い散る粉雪の中で凍えたように立ち竦んだ。
「私は、彼のとりこになってしまった――もう逃げられない」
「クリスティーヌ。君は夢を見たんだ。夢に決まってる」
「いいえ、夢じゃない。あの人の目。この世のすべての悲しみを秘めていた。私を睨みつけながら、罵りながら、懇願していた。天国へのあこがれにあふれていたあの目」
「クリスティーヌ」
ラウルは彼女を力の限り抱きしめた。
「暗闇の世界の話は、もうたくさんだ。僕たちがいるのは光の世界だ」
「ラウル――私は彼に囚われていく自分がこわいの。夜のない世界へ逃れたい、陽の中にいる自由が欲しい。光があふれる場所で生きていたい」
「僕がきみを守る。きみを愛している、クリスティーヌ」
「本当に……ラウル?」
私と分かち合うと言って
たったひとつの愛を たった一度の人生を
その言葉さえあれば 私はあなたについてゆく
人生をふたりで分かち合おう
訪れる夜 訪れる朝を
私を愛して
あなたに望むことは ただそれだけ
「……ごめんなさい。ストップ」
「どうしたんだ、ユナ」
「ここ、『激しく口づけを交わす』って台本に書いてあるけど、レイが見てる前では無理かもしれない……」
「……お、俺も、まだ死にたくないよ」
気持を寄り添わせるラウルとクリスティーヌに、物陰から見ていたファントムは打ちのめされた。
ふたりが去ったあと、よろめき出ると、地面には無残にも、彼がクリスティーヌに贈ったバラが、一輪落ちていた。
(光あふれる生活と穏やかな愛情を、あの若者は惜しみなく与えようとしている。だが、私がクリスティーヌに与えられるのは、暗黒の深淵と、互いを滅ぼし尽くすほど激しい、音楽への熱情だけ)
ファントムは、狂気のような絶望と怒りに駆られて、雪空に向かって叫んだ。
「今に見ていろ。おまえたちは、きっと後悔する。ファントムに背いたこの日を」
新年の仮面舞踏会がオペラ座で盛大に催された。この三ヶ月間ファントムは現われず、しばらく不吉なことばかり続いた由緒ある劇場に、ようやく数年ぶりの平和が訪れた。
色とりどりの華やかな衣装をつけた仮面の紳士淑女で埋め尽くされた会場は、世紀末の華美と退廃とに満ちあふれた。
マスカレード
さあ 仮面のパレードだ
マスカレード
正体を見破られぬように 顔を隠せ
大勢の賓客に、裏の厨房はてんてこまいだった。
「三百人分のご馳走を、私とあんたで作るんだよ。息する暇もないよ」
「ひええ」
「誰だーっ。こんなところに酒瓶をころがしたのは。重点清掃箇所決定!」
「ああっ。すみません。今からお祈りの時間です」
「ドクター……栄養剤の点滴を……」
たくさんの顔と顔
飲み干せ 飲みつくせ
光と音楽に溺れるまで
突然、おぞましい冷気が祝宴の会場に吹きつけた。
招待客たちが見上げると、大階段の上にファントムが悠然と立っていた。
「なぜ静まるのだ、みなさん。ここは仮面舞踏会だろう? ファントムが来るのはあたりまえだ」
主演俳優のごとく颯爽と階段を降りてきた彼は、一冊の台本を叩きつけた。
「この三ヶ月、私はきみたちのために新作のオペラを書いていた。タイトルは『勝利のドンファン』。これが完成したスコアだ」
人々は恐怖のため身じろぎもしない。
「さて、リハーサルを始める前に、作者としていくつか注文をつけたい」
ファントムは、北欧神話の軍神テュールさながらの迫力で、次々と命令をまくしたてた。
「まずカルロッタは演技の勉強をし直せ。ドンファンは、もっと減量を。
支配人にも忠告する。きみたちは事務所に引っ込んでいろ。芸術の場に出てくる必要はない。
衣装係、赤と白と黒を基調にした斬新でセンスの良い衣装を。大道具、二十秒で舞台転換できるように整えておけ。
命令を聞けない者は、1グラムだって俺のオペラ座の貴重な酸素を吸わせてやる義理はない。宇宙に放り出す」
「あわわ。キャプテン、演技じゃなくて本気だぞ」
「――そして、クリスティーヌ・ダーエ」
ファントムは彼女に、冷然とほほえみかける。
「きみは努力家だ。美声にも恵まれている。宇宙を駆け巡る《ギャラクシーヴォイス》と呼んでもよいほどの。だが、それ以上のレベルを目指すなら、もっと勉強が必要だ。きみの師である私のもとへ戻るがいい」
その薄茶色の目の魔力は、たちまち彼女を魅了する。
「離すものか。おまえは私のものだ」
そう言い残し、ファントムは炎とともに消えた。
ラウルが後を追おうとするが、バレエ教師のマダム・ジリー(安永ユウ管制官)に止められる。そして彼女の部屋で、秘められたファントムの過去が明かされる。
「今から三十年近く前……って、どうして私がこんな年増の役なのよ」
「仕方ないだろ。もともと、女性キャラが少ないんだから、うちの小説は」
「三十年近く前、木星調査移民団のロケットが爆発し、ファントムはその爆発に巻き込まれて、顔に大怪我を負ったの」
「……それ絶対、時代考証でひっかかるって」
サーカスに売られて見世物にされていたファントムは、まだオペラ座の寄宿生だった頃のマダム・ジリーに助けられて、オペラ座の地下に匿われて暮らすことになった。
「それ以来、彼の世界はこのオペラ座の中だけ。ここは彼の遊び場だった。そして今や、彼の芸術の領域、彼はここの領主であり船長なの。作曲家であり建築家、またすぐれたバイオリニストにして一級の航宙士。ファントムは天才だわ」
「いや、狂人と化した天才だ。僕は彼の手からクリスティーヌを守ってみせる」
思い悩むクリスティーヌは、心の煩悶に答えを出すため、こっそりオペラ座を抜け出して、父の墓所へと向かう。
(私はどうすればいいの。ラウルのことは小さい頃から好きだった。彼は幸福な子ども時代の思い出。幼いロッテにとって、とても大切な人)
御者台にいるのがファントム自身であることも知らずに馬車を降り、クリスティーヌは墓場を悄然と歩き続ける。
(ファントムのことを、父が送ってくれた音楽の天使だと思っていた、この十年間、彼は私にとってかけがえのない人だった。ずっと私を暖かく見守っていてくれた。何も知らないあの頃に戻れたら――いいえ、それはもう叶わない夢)
突然、墓地の中に反響する声。
「私は十年間、おまえのそばにいた。父親として友人として。それなのに、おまえは私を裏切るのか」
「ああ、あなたの声をもう一度天井越しに聞き、姿の見えないまま、その気配に酔うことができたら」
「おまえの魂はすでに私のものだ」
「どんなに抵抗しても、従うほかはないの?」
この胸の高鳴り
抗いながらも
魂は従っている
私はおまえの 音楽の天使
あなたは私の 音楽の天使
「さあ 私のところへ」
「クリスティーヌ。待て。彼に近づいちゃいけない!」
馬で彼らを追いかけてきたラウルは、ファントムと剣を交える。
幾十閃か斬りむすんだあと、ラウルはファントムに剣を振り下ろそうとするが、クリスティーヌの悲鳴にとどめられる。
クリスティーヌとともに馬上の人となったラウルは、恋人のぬくもりを背中に感じながら、口の中でつぶやいた。
「クリスティーヌ。きみはやはり彼を……」
ファントムの新作オペラ、『勝利のドンファン』の初日がやってきた。
ラウルらオペラ座の関係者は、ファントムを罠にかけようと画策する。
「クリスティーヌを主役に据えれば、彼は必ず聞きに来る。幕が下りると同時に、配置していた武装警官を一斉に――」
「つまり、ミス・ダーエを囮にするわけですね」
クリスティーヌは不安に怯えながら、開幕のときを待っていた。
「怖いの……彼は私を奪い去ってしまう。私を決して放さず、あなたとの仲を永久に裂いてしまうわ」
「だいじょうぶだ。きみは言われたとおりにしていればいい」
「私に歌うことを教えてくれた方を、裏切って差し出せというの?」
「クリスティーヌ。勇気を出して。すべては、きみの肩にかかっている」
満員の観客の前で幕は上がった。
ファントムの書き下ろしたオペラ、『勝利のドンファン』。
その斬新な音楽と踊り、強烈な衣装と効果は、観客の眉をひそめさせながらも、五感を揺さぶり、次第に魅了していく。
主人公のドンファンは無類の女好き。従者と入れ替わり、若い娘を家に引き入れ、たぶらかそうと企んでいるという筋立てだった。
ところがドンファン役のピアンジ(メカニックのドミンゴ)が幕の後ろで控えていたとき、ファントムは彼の前に耐圧式の酒のボトルをころがし、気を取られているあいだに、こっそり入れ替わってしまう。
そして何事もなかったかのように、舞台に現われる。
もう後戻りはできぬ
後ろを振り返るな
ごっこ遊びは もう終わりだ
「もし」と問いかけるのは やめろ
抗うことをやめ 夢に堕ちていけ
荒れ狂う炎が 魂を満たし
欲望が 扉を開ける
甘い誘惑が 目の前に横たわる
「この声は……ファントム?」
クリスティーヌはおののきながら、彼に答えて歌う。
あなたに連れてこられたところ
ここでは言葉は干からび 会話は途切れ
沈黙へと融けていく
ここに来た理由がわからない
心の中はすでに あなたとからみ合う
抗うこともできず 沈黙の中で
思い直すことはできない
私はもう 心を決めてしまった
歌いながら、彼女はボックス席にいるラウルに、目で合図を送った――『ファントムが、ここにいる』と。
ラウルは急いで、警官を舞台の回りに配置する命令をくだした。
心のうちでは、クリスティーヌがすでに引き戻せないほど強く、ファントムに惹かれていることを知りながら。
もう後戻りはできない
最後の扉を開けてしまった
橋を渡り それが燃え落ちるのを見つめるだけ
もう 後戻りはできない
「クリスティーヌ。この孤独から私を救い出してほしい。この暗黒の中を私の手を取って導いてくれ」
「あなたは音楽の天使? ――それともファントムオブオペラ?」
「どちらでもいい。私はもう何も望まない。きみが私のそばにいてくれるなら。きみが私を必要としてくれるなら。ひとことでいい、嘘でもいい。愛してる。そう言ってくれ」
「私は――私はもう、自分が何を望んでいるのかわからないの。彼なの? それともあなたなの?」
クリスティーヌは震える手で、自分の心を試すかのようにファントムの仮面を剥ぎ取った。
醜く崩れた、人ではない顔。
会場は、つんざくような悲鳴で包まれた。
ファントムはクリスティーヌを抱きかかえると、奈落の底まで一気にロープを伝い降りた。
警官が一斉に飛び掛ろうとする。だが退路を確保するため、ファントムはあらかじめシャンデリアの鎖を切っておいた。
ばりばりと天井を破り、崩落してくる巨大シャンデリアに、会場の観客たちは大パニックに陥る。
ラウルは、マダム・ジリーの道案内を受けて、ファントムの住む地下迷宮へと急いだ。
「お願い、私を光の中に帰して」
「だめだ!」
ファントムたちが船でたどりついたのは、あの地下湖の小島だった。
「この醜い顔のせいで、私は誰にも愛してもらえなかった。父と母でさえも、私を見捨てた。もの心ついたときには、衣服のかわりに顔覆いをかぶせられていた。優しいことばをかけてもらったことなど、一度もない。……いつも私はひとりだった」
「――」
「私がどんなひどい罪を犯したというのだ。ずっと暗黒の深淵の中で、ひとりで生きていけというのか。誰とも愛を分かち合うこともなく……そして、富も名声も美貌も、すべてを持っているあの男が、太陽の下へと、おまえを奪い去ってしまう」
ファントムは、狂気に取り憑かれたように、叫んだ。
「そんな哀れみに満ちた目はもうやめろ。おまえは、この醜い男と一生この暗闇で暮らすのだ。自分の運命を呪うがいい。私は永遠に、おまえをいたぶり、苦しめてやる!」
「わたしは、あなたの顔にはもう恐れを感じない」
クリスティーヌは大きく見開いた目を彼の顔からそらさず、決然と言った。
「本当に歪んでいるのは、あなたの魂だわ。自分の運命を呪って人を憎む心が、今の孤独を引き寄せたのよ」
「……うるさい、聞いたふうなことを!」
「クリスティーヌ!」
そのとき、ラウルが彼らのもとにたどりつく。
「これは、うれしい客だ」
彼をみとめ、ファントムは高らかに笑った。「きっと来ると思っていたよ」
「頼む。彼女を放してくれ。おまえに人の情けがあるならば」
「そんなものはないね。私に人の情けを教えてくれた者など、ひとりもいない」
「クリスティーヌを愛しているんだ!」
「それなら、入ってきて、助ければいいだろう。どうぞご勝手に」
ファントムは、仕切りの柵を開け、ラウルを導き入れる。
だがその瞬間、すばやく彼の首にロープを巻きつけて、柵に縛り付けた。
「さあ、クリスティーヌ。選ぶんだ。この男を見殺しにして自由を得るか。それとも、彼の命と引き換えに、私とここに暮らすことを選ぶか」
「なんて、卑怯な!」
「クリスティーヌ。やめろ、何も言うな」
「逆らっても無駄だ。拒めば、こいつが死ぬだけ。偽りの愛で彼の自由を買え」
ファントムの口元に浮かぶ残酷な笑いに、クリスティーヌはまなじりを吊り上げた。
「音楽の天使。私はあなたに……ずっとあこがれていた」
「……」
「あなたの暗い過去に涙したこともあった。でも、今はその涙も凍りついて、憎しみの涙へと変わっていくわ」
「彼を墓に追いやるのか。それとも、ここに残ると誓うか」
「あなたを信じていたのに……あなたを愛していたのに!」
暗闇の中で生きてきた 哀れな人
どんな人生を あなたは知っているの?
神さま 私に勇気を与えてください
あなたに教えたいの あなたが孤独でないことを
クリスティーヌは湖の中に立つファントムに近づき、彼と唇を重ねた。
愛情をこめて。何度も。何度も。
「ふ……ふはは」
ファントムは、力ない笑い声をあげた。
「もういい。もうやめた」
「ファントム?」
彼はふらふらと歩き始めた。
「ふたりとも出て行け。ここで見たことは、すべて忘れろ。誰にも会わないように外に出て、決してここの秘密を漏らすな」
「……」
「いいから、行け! 二度と私の前に姿を見せるな!」
地下の王国は、元通り永遠の静寂を取り戻した。
「クリスティーヌ」
ファントムは力を失い、うずくまった。
「これでいい。きみは光の中で生きるべき人だ。こんな暗闇ではなく」
クリスティーヌ 君を愛してる
君だけが 私の歌に翼を与えてくれる
「これで幕は降りた」
ファントムは、涙に濡れた目をゆっくりと上げた。
その揺らめく視線の先に、クリスティーヌが微笑みながら立っていた。
「戻ってきたの」
彼女は、内緒話を打ち明けるように密やかに、彼の耳元にささやいた。
「あなたと分かち合いたい、たったひとつの愛を。あなたのそばで生きたい、たった一度の人生を――あなたを愛している」
《ギャラクシーヴォイス》。
まるで、星々の間で奏でられ、宇宙に鳴り響くという、伝説の声。
「まさか。そんな」
彼は息ができなくなったように、あえいだ。
「できるものか。きみをこんな暗黒の中に引きずり込むなど」
「だから、あなたも光の中に出るのよ。音楽の天使」
クリスティーヌは彼の手をとって立たせた。
彼女の後ろには、カルロッタ、ピアンジ、支配人、マダム・ジリー、メグ、ブケー、大勢の俳優や裏方たちが立っていた。
そしてラウルが進み出た。
「あなたを、正式にオペラ座の専属監督として迎えたい。ファントムオブオペラ」
「お約束します。二万フランの給料と、五番ボックスの永久使用権を授与しましょう」
「あなたの書いたオペラは最高だったわ。私たちは、もう一度あなたの指揮の下で歌いたいの」
「シャンデリアは大破し、客席は燃えてしまったけれど、何、みんなの力を合わせれば劇場は再建できるさ」
「ファントムオブオペラ。ようこそ、私たちのオペラ座に!」
「こんなことが……罪深い私に許されるのか」
彼は激しく懊悩しながら、クリスティーヌを見た。
「私たちは皆、あなたが必要なの」
微笑みながら、彼女は答えた。「いっしょに美を夢見ましょう」
私と分かち合うと言って
たったひとつの愛を たった一度の人生を
その言葉さえあれば 私はあなたについてゆく
人生をふたりで分かち合おう
訪れる夜 訪れる朝を
あなたに望むことは ただそれだけ