「あ、葺石先生、藤江さん」
「奥野くん、お疲れ。もうヤマドリの出番終わったんやな」
「気の弱そうなところが、よう出とったで」
「ははは。地が丸出しでしたね」
「でもよかったやない、奥さんがたくさんいる役で。現実には欲しくても、ひとりもおらんのに」
「ああん、先生。藤江さんが苛めます」
「まあまあ。次はいよいよ、ひっくんの出番やな」
「はい。師範も聖くんの舞台センスには驚いてましたよ。これやったら将来、ハリウッドも夢じゃないって」
「そやけど、この原作、結局最後は、ひっくんが外国に連れてかれて、冷たい父親と継母の下で育つんやろ。それを考えたら、泣けてくるわ」
「なあに。今日はそんなことは、俺がさせへん。天が許しても、この葺石惣一郎が許すものかぁ!」
「あほらし。ひとりで言うとき」
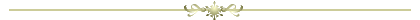
配役表:
蝶々(長崎出身の娘) : 円香・グリュンヴァルト
ピンカートン(合衆国海軍士官) : ディーター・グリュンヴァルト
シャープレス(長崎在住の合衆国領事) : 鹿島康平
スズキ(蝶々の女中) : 柏葉瑠璃子
ゴロー(斡旋屋) : 柏葉恒輝
ケイト(ピンカートンの妻) : 鹿島 茜
ドローレ(蝶々とピンカートンの子ども) : 聖・グリュンヴァルト
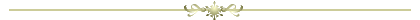
第二幕(第二部)
「その子は……ピンカートンの子どもなのか」
「ええ、そうです」
蝶々は誇らしげに、まだ三歳にも満たぬ男の子を抱きかかえて、膝に座らせた。
「日本人で、このような薄茶色の瞳の子どもがいますか。透き通るような白い肌。柔らかく、ところどころに金の混じった茶色の髪は」
「彼はこの子のことを……」
「知りません。アメリカにお帰りになってから生まれたのですもの」
彼女はいとおしげに、息子の頬に口づけた。
「お願いします。領事さま。あの方にどうぞ手紙を書いてくださいませ。この可愛い、すばらしい男の子があなたを待っているよと。そうすれば、何をおいても、あの方は私のもとに帰ってきてくださるはず」
それを聞いたシャープレスは、息が詰まるような感覚に襲われ、胸を押さえた。
「神よ、あなたは何ということをなさるのだ!」
「ねえ、坊や」
母親は子どもの髪を梳きながら、おかしそうに言った。
「このおじさまが、何とおっしゃったかわかる? お父さまが戻っていらっしゃらないって。母さまがあなたを抱いて毎日町に行き、『どうか、この哀れな母子に食べ物を恵んでください』と頼んで歩けと、そうおっしゃるのよ。そうでなければ、母さまに芸者になって、知らない男に身をまかせろとおっしゃるのよ」
「おやめなさい! そんな言葉を……子どもに聞かせてはなりません」
領事は耐え切れなくなって、両手を縁側に着き、嗚咽を飲み込んだ。
そして顔を上げ、このうえなく優しい声で言った。
「坊や、いい子だね。お名前は?」
「ドローレともうします」
蝶々が代わりに答えた。
「ドローレ? 日本の名前ではないようだが」
「イタリア語で【悲しみ】という意味ですわ。教会の神父さまに教えていただきました」
「悲しみ……」
「ピンカートンさんは、【苦しみの子】というお名前だそうです。ですが、私にはお母上の気持がわかります。きっと母の苦しみを喜びに替えてくれるという願いをこめて、そう名づけたのだということを。だから、私もこの子が、私の悲しみを取り去ってくれることを願うのです」
「……おお」
「あの人が帰ってきてくれるときには、私はこの子を【喜び】と呼びますわ。領事さま、お手紙を書いてくださいますわね」
「今から領事館に戻り、きっと書きましょう」
シャープレスは力なく立ち上がった。そして、うちひしがれたように背中を丸めて、丘を下って行った。
家の裏手から、突然スズキの金切り声が聞こえてきた。
『この、ガマ蛙! 腐れ外道!』
彼女はゴローを引きずって、家の表に回ってきた。
『奥さま。この男は、いつも私たちの不幸を願って、あることないこと言いふらしているのです。よりによって、あの子の父親は誰だかわからない、などと言って』
『そんなことは、言ってないじゃないか』
スズキの拳骨を避けるように頭を覆うと、ゴローはわめいた。『俺はただ、あの子はアメリカ人でも日本人でもないと言ったんだ。どこに行っても、人々からのけものにされると』
『なんですって』
蝶々はそれを聞いて、悲鳴を挙げた。そして、奥の箪笥の引き出しを開け、短刀を取り出し、鞘から抜いた。
『もう一度、私の前で言ってごらん。この嘘つき!』
ゴローは転がるように逃げ出した。蝶々は門のところまで追いかけていく。『今度、この家に顔を出してごらん、殺してやる!』
蝶々は戻ってくると、手の短刀に気づき、あわてて鞘に戻して襟元にしまいこんだ。スズキは子どもをぎゅっと抱きしめ、奥の間に連れて行った。
『ああ、どうして、こんなことを言われなければならないの? 私のかわいい子』
桜の幹を何度も叩く。そのたびに花びらが、はらはらと落ちてきた。
『私の悲しみ、私のドローレ! おまえの父上が、きっと仇を取ってくれるわ。そしておまえの悪口を言う人のいない遠い国へと、私たちを連れて行ってくれるわ』
そのとき、遠くからドーンと空気を揺るがすような音が響いてきた。
『奥さま!』
奥の部屋から、スズキが飛び出してきた。『港の大砲です。軍艦が入港したのです!』
蝶々は、庭の築山に登ると、手をかざして遠くを見た。
『白い船だわ。星条旗を掲げてる……名前は……だめ、春霞で見えない。スズキ、望遠鏡よ』
『はいっ』
『ああ、身体が震えて……持てないわ。スズキ。私の手を支えていて……だめよ、あなたも震えているじゃない。……もっと下。船腹よ。船の名前は――エイブラハム・リンカーン号!」
蝶々は庭の中を興奮し、両腕を広げて歩き回る。
『みんな、嘘つきだわ。私にあきらめろと言っておいて、私の気持を試していたんだわ。あの人は帰ってきた! ねえ、私が言ったとおりでしょう』
『はい、奥さま。そのとおりです』
『忙しくなるわ、スズキ。旦那さまはすぐに戻っていらっしゃる。桜の木を揺らして、花を落すのよ。部屋中を花の香りでいっぱいにするの』
(蝶々)
お花を全部 全部よ。
桃も菫もジャスミンも
茂みに咲いた花も 草花も
木に咲いた花も全部
(スズキ)
庭が冬枯れのようになってしまいますわ。
(蝶々)
ここを春一杯の香りで満たしたいの。
もっと採って。
(スズキ)
よく この生垣のところにいらして
泣きながら 遙か遠く
何もない彼方を ご覧になりましたわね。
(蝶々)
待っている人が着いて
もう海には何も頼むことがないわ。
土に涙を流したけれど
土は花をくれたわ。
『あの方は私を忘れていなかったのだわ』
彼女は感極まり、うずくまって両手で顔を覆った。
『奥さま、そんなにお泣きにならないで』
『泣いているもんですか。笑っているのよ。ねえ、あと一時間くらいでこの丘を登ってこられるかしら』
『もっとかかるでしょう。船の仕事は時間がかかります』
『じゃあ、二時間ね。もう花瓶は全部使ったわ。壁にも椅子にも箪笥にも飾りましょう。花びらや小さな花は、床に蒔くのよ』
部屋に夕闇が迫り、薄暗い室内は花の濃厚な香りでいっぱいに満たされた。
『スズキ。化粧を手伝って』
女中がランプを持ってきて、女主人の化粧台の前に置いた。
蝶々はじっと鏡の中を覗き込みながら、溜め息をついた。
『やつれたわ。もうあの頃の私ではない』
『奥さまは、泣きすぎたのですわ』
『どうしよう。ピンカートンさんは、私のことをわかるかしら。私を見ても、素通りしてしまわないかしら』
『大丈夫でございますよ』
『頬紅をさしましょう。あの子を呼んできて。あの子の頬にも頬紅を。せっかくの対面なのに、顔色の悪い子だと思われたくはないわ』
外はすっかり暗闇に包まれた。
スズキは出て行き、庭の灯篭に火を入れて、戻ってくる。
『結婚式のときの帯を締めるわ。そして、あの白いヴェールも』
『おきれいです。髪には赤い花を挿しましょう』
『こっちへおいで。ドローレ』
蝶々は、息子と女中を障子のそばに座らせた。
そして、口で指を湿らすと、障子に三つの穴を開けた。
『お父さまが丘を登っていらっしゃるのを、ここから見ていましょう。じっと声を殺して、内緒なの。そしてお父さまが庭に入ってきたら、障子をわっと開けるのよ。ああ、どんなに驚かれるかしら』
三人は、息をひそめて穴を覗いた。
着物の両袖を広げた蝶々のシルエットはまるで、本物の白い蝶のようだった。
美しいハミングコーラスが静かに流れる。
新しい一日が明け、夜通し聞こえてきた遠くの海鳴りも聞こえなくなった。その代わりに、小鳥の呼び交わす囀りが、次第に高くなってきた。
部屋の中に、黎明の光がひたひたと入り込んできた。
蝶々は強張った体をそろそろと動かして、壁にもたれて寝入ってしまっているスズキの肩に手をかけた。
スズキははっと身を起こし、座布団の上で眠っているドローレの様子を確かめた。そして蝶々の顔を見上げた。
『奥さま』
その物問いたげな視線に、蝶々は首を振った。
『お仕事が忙しいのよ。でも、いらっしゃるわ、きっと。遅れているだけ』
『はい……』
彼女は息子を抱き上げると、奥の間に向かった。『少し眠るわ。でもあの人が来たら、すぐに起こしてね』
(蝶々)
おやすみ かわいい坊や
私の胸でおやすみ。
おまえは神さまと
私は苦しみと一緒。
金の星の光は おまえのものに。
坊や おやすみ。
『ああ』
スズキは畳によろよろとひざまずくと、椅子の腕につかまって身体を起こした。『お気の毒に。奥さま』
玄関の引き戸を、ドンドンと叩く音がする。
『こんな朝早くに、誰かしら』
迎えに出たスズキは、そこに現われた背の高い人影を見て、はっと数歩、後ずさった。
「旦那さま……」
「しっ」
ピンカートンは指と口の間で鋭い音を立てると、家の中を見回した。
「蝶々さんは……」
「眠っておられます。でもすぐに」
「いや」
彼は力なく、首を振った。「起こさないでほしい」
その後ろから現われたシャープレスの悲痛な表情を見て、スズキは身を強張らせた。
ふたりのアメリカ人は足音をしのばせて、部屋の中に入った。
「奥さまは一晩中、お子さまといっしょに起きて、お待ちになっておられました」
押し殺した声で、主人の背中に言葉を投げつける。
「どうして、俺が帰ってきたことがわかったのだ?」
「毎日毎日、港を見ておりましたもの。私たちは、アメリカの全ての軍艦の名前と色を覚えてしまいました」
シャープレスが呻いた。
「わたしの言ったとおりだろう」
「ゆうべは、ふたりで庭中の花を摘んで、部屋に撒き散らしました。いっぱいのお花で旦那さまをお迎えしたいと……」
「言ったとおりだろう!」
「かわいそうに」
ピンカートンは両膝を畳につき、蒔かれた花びらに手を伸ばした。「桜の……花だ、またあの季節が巡ってきたのか」
「いいえ、三年目の春です!」
スズキは身をよじるようにして叫んだ。「三年間、奥さまはお待ちになっていました。あなたの戻って来られる日を、今か今かと……」
彼女は急に口をつぐんだ。庭に花のような色のドレスを着た、ひとりの金髪の女性のたたずむ姿を見つけたからだ。
「あの方は……どなたです」
「……」
「話したほうがいい、ピンカートン」
「……何と言えばいい」
「事実をだ! あれはおまえの妻だと」
スズキはそれを聞いて、すべてを了解し、ずるずると縁側に尻餅をついた。
「奥さまの太陽は、永久に沈んでしまいました」
「スズキ。聞いてくれ」
領事は激昂を鎮めると、静かに言った。
「こんなに朝早く来たのは、きみにだけ話をしたかったからだ。きみの助けが必要なのだ」
「わたくしに、何をしろと……」
「蝶々さんを説得してほしい。ピンカートンは、せめて子どもだけは引き取りたいと言っている。あそこにいる夫人も同意している」
「お子さまを、アメリカに? 奥さまをひとり残して」
「ドローレの将来のためなのだ」
「最後の宝である子どもさえ、奥さまから奪うとおっしゃるのですか!」
「わかってくれ。わたしも近々、本国へ帰ることになっている。もうきみたちの面倒を見ることはできない。極貧の中にきみたちを捨て置くわけにはいかないのだ。子どもさえいなければ、蝶々夫人は、また別の男のもとに嫁ぐこともできよう」
「なんと、ひどい……」
「まず庭にいるあの女性と、話してくれないか。彼女も動揺して、中に入れないでいる。連れてきてほしいのだ」
「奥さまがあの人に気づいたら……」
「そのほうがよいかもしれない。真実を知るためには……いや、あの賢い人はもう、うすうす気づいているだろうが」
「わかりました……」
スズキは立ち上がり、おぼつかない足取りで、庭のピンカートン夫人のもとに歩み寄った。
うずくまり、畳の上の花びらを握りしめていたピンカートンは、ふと我に返ったように部屋を見回した。
「この部屋は何も変わっていない。その小さなランプの位置まで同じだ」
彼は立ち上がり、奥の文机に近づいた。
「俺の写真だ……まるで死んだ男の肖像だ。いっそ、本当に死んでしまったほうがよかったのかもしれん」
「わたしは何度も忠告したはずだ!」
シャープレスは、再び湧き上がる激しい憤怒に顔を赤らめた。
「あの人は真剣だと。何度、求婚されようが、親族たちに見放されようが、周囲の人々に嘲られつつ、惨めで貧しい生活に甘んじようが、彼女はきみを待ち続けたんだ。わたしたちの忠告にも、一度も耳を貸そうとしなかったよ」
「俺はこの世に、それほどの愛情が存在するのを知らなかった。母親にさえ見捨てられた子どもだ。女とは、打算でしか愛を交わしたことがなかった」
「ここでの短い生活の間に、きみは何を学んだんだ」
「ああ。この部屋に帰ったときに、一瞬にして俺の犯した罪がわかった」
ピンカートンは、のろのろと答えた。「ここは死刑台だ。俺はたった今、ここで死んだ。たぶん、二度と微笑むことはないだろう。心に安息を覚えることも、もうないだろう」
「それは、あの人も同じだ」
「赦してくれ……もうここにはいられない。あとはあなたに任せる。あの人に救いを与えてやってくれ」
庭に出たピンカートンは、桜の花びらが目の前に舞い散るのを見て、髪を掻き毟った。
(ピンカートン)
さようなら
喜びと愛の 花咲く家よ。
あの和やかな面影をいつも
恐ろしい責め苦とともに 思い出すだろう。
さようなら 花咲く家よ。
沈鬱なおまえに私は耐えられない。
私は逃げて行く 卑怯者なのだ。
彼の姿が消えたあと、部屋の中にひとりで立ち尽くしていたシャープレスは、ピンカートンの妻ケイトが、スズキとともに近づいてくるのに気づいた。
「領事さん」
「ピンカートン夫人」
「この日本の人が、私にすべて話してくれました」
彼女はスズキの肩に手を置いた。「蝶々さんがどれだけの愛情と信頼をこめて、この三年間、私の夫を待っていたかを。あの坊やをどれほどの慈しみと注意深さを持って育ててきたかを」
「そうです。私は話しました」
スズキは言った。
「半年に満たないわずかな日々に、どれほど奥さまと旦那さまが睦み合って暮らしておられたか。そのひとつひとつの思い出を、奥さまと私は何度、思い返してなつかしく語らっていたか」
「おお、その言葉を聞いただけで、私の胸がえぐれるようだ」
シャープレスは、深い同情に涙を浮かべた。
「領事さん」
ケイトは静かだが、強い調子で言った。
「私がアメリカからはるばる日本に来た理由を、どうしても皆さんにお伝えしたいのです」
「それは……?」
「夫のベンジャミンと私は、一年前に結婚しました。最初の数ヶ月は平穏でした。夫はあの寛容な微笑をいつも浮かべていました。けれど、日が経つにつれ、私は気づいたのです。この人は決して本当に微笑んでいるのではない。いつも心の底に凍えた塊を抱いていると」
「ああ、それはわたしも感じたことがあります」
シャープレスは同意してうなずいた。
「半年後にはもう、私たち夫婦の仲は冷え切っていました。それでも私は表面を取り繕って、結婚生活を続けようとしました。その――初めから私たちの結婚には、家柄や出世といった打算があったのです」
美しい顔を、恥じらいの蔭が雲のように覆った。
「けれど、ベンジャミンはだんだんと精神的に不安定になっていきました。薬を飲まずには夜も寝られず、酒も度を過ごし、何かを必死で忘れようと苦しんでいるように見えました。私はある日、問い正したのです。何度も何度も問い正しました。そして彼は、愛する人を日本に見捨ててきたことを、ついに告白したのです」
彼女は目の縁にうっすらと涙を浮かべ、毅然と顔を上げた。
「私は、いっしょに日本に行くことを求めました。もし、相手の女性が彼のことをすっかり忘れていれば、私たちはもう一度やり直す道を探れるかもしれない。でも、もし相手も彼のことを想い続け、待ち続けていたら……」
ケイトは急に口をつぐみ、目を見張った。
いつのまにか、広間に蝶々が立っていて、彼らを見つめていたのだ。白いヴェールを花嫁のように被った彼女は、静かにひざまずき、両手をついてお辞儀した。
「はじめまして」
蝶々は、しっかりとした声で挨拶をした。「ピンカートンさんの奥さまでいらっしゃいますね?」
「……はい」
戸惑いながら、ケイトは答えた。
「ひとつだけ、うかがってよろしいでしょうか。あの方は元気でおられます?」
「はい」
「ああ、よかった」
彼女は、安堵して目を閉じた。「よかった、本当に……神さま、感謝します」
「蝶々夫人。この女性は……」
シャープレスは、喉を詰まらせながら言った。
「あなたのことを、とても案じておられるのです。そしてできるだけの償いをしたいと。ドローレのことも、本国へ連れて帰って、合衆国の教育を受けさせたいと願っておられます」
「あの子を、私から引き離すと……?」
蝶々は一瞬、まなじりを険しくしたが、すぐに穏やかな微笑を浮かべた。
「いいえ、そのほうがよいのでしょう、あの子にとって。黒髪の子どもに混じっていじめられるよりも、金髪の子どもとともに、お父さまのお国で育ったほうが、きっと良いわ」
「わかっていただけますか」
「ええ。あの子をお願いいたします」
「大切に育てますわ」
蝶々はすっと陽炎のように静かに立ち上がった。「ただし、条件があります。ピンカートンさんに直接迎えに来てほしいのです。あの方は近くにおられますか?」
「はい。すぐそばに」
「それでは半時間後、迎えに来てください。そうすれば、あの子を渡します」
それだけ言い置くと、彼女は背筋をぴんと伸ばして、奥の間に入っていった。
スズキは、シャープレスとケイトを門まで見送った。
「凛とした態度でいらしたわ」
「蝶々夫人は潔くピンカートンをあきらめたということだろうか。それならよいのだが」
「ああ。そんな。奥さま」
胸騒ぎがしたスズキは、あわてて家に取って返した。
そして、奥の間で倒れている蝶々を見つけた。『奥さま!』
駆け寄ると、あわてて抱き起こす。
『ああ、心臓がまだ打っている。でも、なんて弱々しい。捕らえられた小さな虫が翅をばたつかせているよう』
蝶々はうっすらと目を開けた。
『まぶしいわ。夜が明けたのね。春がいっぱい……。お願い。障子を閉めて』
スズキは言われたとおりにしながら、激しく泣いた。
『スズキ。あの子はどこ?』
『あちらで遊んでおいでです』
『いっしょに遊んでやって。それがすんだら、一番いい着物を着せてね、遠い国に旅立つのだから』
スズキをむりやり追い立て、蝶々は後ろ手に障子を閉めた。
そして、部屋の中央に座り、胸にはさんでいた短刀を取り出して、鞘に彫られている銘文を声に出して読んだ。
『【誇りを持って生きられぬ者は、誇りを持って死ぬ】』
蝶々は目を閉じ、瞼を震わせた。『ああ、私は……』
短刀を見つめていると、障子がガラリと開き、ドローレが走りよって来る。蝶々は、思い切り抱きついてきたその小さな身体を、両腕で受け止めた。
『ああ、私の可愛い子!』
(蝶々)
おまえ 小さな神さまであるおまえ!
かわいい坊や
百合の花 薔薇の花。
決して知っては駄目よ
おまえのために、おまえの清らかな瞳のために
蝶々が死ぬということを。
それはおまえが海の彼方に行って
大きくなった日に母親に見捨てられたのを
悔やむようなことにならないためなのだから。
『さあ、これで遊びなさい』
蝶々は息子に、小さなアメリカの国旗を与えて、座布団の上に座らせた。そして被っていた白いヴェールを取り、息子の頭に被せた。
そして、自分は鏡の前に行き、短刀を静かに振り上げた。
「蝶々さん!」
そのとき、ひとりの男が、風のように飛び込んできた。
彼女の手から無理矢理、短刀を取り上げると、その全身を抱きすくめた。
「ああ、なんてことだ。なんてこと……」
「ピンカートンさん?」
「死なないでくれ、蝶々さん。きみが死んだ瞬間に、俺も生きてはいられない」
翡翠のような両眼からぼろぼろと涙をこぼしながら、ピンカートンは彼女の頬を両手ではさみこんだ。
「俺も母に見捨てられた。俺の母も、俺の目の前で死を選んだのだ。それなのに……あれほど憎んでいた父と同じことを、俺はしようとしていた」
「ピンカートンさん、違います」
蝶々は、穏やかに無邪気に微笑んだ。
「私は死のうとしていたのじゃありません。誇りを捨てようとしていたのです」
「誇り?」
「女の誇りです」
シャープレス、ケイト、そしてスズキの三人が、部屋の敷居のところで、呆然と成り行きを見つめている。
彼女は刀をそっと握りなおし、安心させるようにわざと逆手に持つと、自分の長い髪の真中に、刃を当てた。
畳の上に、さらさらと黒髪が落ちていく。
「私は今、死にました」
蝶々は晴れやかな声で言い、立ち上がった。
「ピンカートン夫人、お願いがあります。私をドローレといっしょにアメリカに連れて行ってください。乳母として、身の回りの世話をしたいのです。母親に見捨てられた子どもと思わせたくないのです。お給料はいりません。ピンカートンさんには、絶対に近づきません。いつも決して目の届かないところにいますから」
「蝶々さん」
ケイトは、深い慈愛の微笑をたたえた。
「私も、あなたに言わなければならないことがあります。私は本国に帰れば、ピンカートンを告訴するつもりです」
「告訴?」
「ええ、重婚の罪で訴えます。彼にはあなたという、法律的にも立派な妻があるのですもの。……ねえ、領事さん」
「ああ、わたしが立証人だ」
シャープレスは威厳をもってうなずいた。
「ねえ、スズキさん」
「はい、結婚生活の事実は、私が証言します」
スズキは、必死に叫んだ。
「蝶々さん、あなたもアメリカに来て、証人になってください。判決が出れば、あなたが正式な妻となり、わたしとの結婚は解消されます。合衆国の軍人は、世界中のどこであっても、合衆国の法律が適用されることを彼は認めることになるでしょう。降格は免れませんが。最悪の場合、多少の期間は牢獄に入るかもしれませんが……」
ケイトは、茶目っ気のある笑みを見せた。「お待ちになれますわね」
蝶々は呆然と、彼女の早口の英語を反芻していた。
「……はい、ピンカートン夫人」
「ピンカートン夫人は、あなたですよ」
「でも――でも、ピンカートンさんの気持は」
「彼に、異存があるはずはありません」
ケイトが視線をめぐらした先には、ピンカートンがドローレを抱きしめながら、すすり泣いている姿があった。その手には、白いヴェールが握られていた。
「俺の息子、俺のドローレ――俺の蝶々さん」
「さあ、呼んでいますよ。行っておあげなさい」
シャープレスの暖かい手に押し出されて、蝶々はゆっくりと、愛する人のもとに向かった。