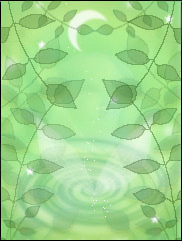
あなたの歌が聞こえる
『美玖……、美玖』
誰かに呼ばれたような気がして、振り返る。
でもそこには、誰もいない。
遠い昔に聞いたなつかしい声。でもそれがいつだったか、誰の声だったのか思い出すことはできない。
あきらめて、また歩き始めた。カサカサと地面の枯れ葉を踏みしめる音はなぜかふたり分だ。この林を歩いているのは彼女しかいないのに。
「あ」
サンダルの先が木の根にひっかかって、前につんのめりそうになった。
とたんに目に見えない力で体が支えられる。暖かく、優しい何かが彼女を包み込む。
いったいなぜ……。
そう問いかけることばが頭をよぎる前に、彼女の目はぼんやりと何かを探し求めるようにあたりを見回した。
「婦長さん」
病棟から小道を下ってくる女性に手を振った。ピンクのナースキャップをかぶった40歳ほどの魅力的な女性である。
「美玖ちゃん」
「なんだ、婦長さんだったのね。今私をつかまえてくれた人。ありがとうございます」
「え?」
彼女は一瞬きょとんとしたが、すぐに得心した様子で、美玖の背後に立っている痩せた青年に向かって微笑んだ。
(手柄を取っちゃって、ごめん)
そんな困った笑顔で。
その青年、日下部怜は首を振りながら、寂しそうに微笑み返した。
『心の病から来ている症状です。ある特定のものだけが、彼女の網膜には像を結ばない。ある周波数の音だけを、彼女は聞くことができない。
彼女は、愛しながら決して会うことのできないあなたという存在を感じなくなるために、あなたにつながる全ての情報を無意識に排除しているのでしょう。
このままなら彼女は一生、あなたを見ることも、あなたの声を聞くこともできないでしょう』
「もう三ヶ月になります、美玖がここに入院してから」
美玖の主治医・霧島の診察室に座ると、怜は両手でぐっと自分の膝を鷲づかみにした。
「良くなる兆しが全然ない。いったい彼女の正式な病名は何なんですか?」
「恋人であるあなたに関する一切の記憶がないことから、心因性の逆行性健忘症の一種だと考えられます。だが」
すべての希望をこめた彼の視線を、医師の黒縁の眼鏡の無慈悲な反射が拒絶している。
「特定の人間の声や姿を知覚することができないという症状は、わたしも今まで見たことがない。世界にも報告された症例はないのです」
「治らない……のですか」
「考えうるかぎりのあらゆる療法をこころみてはいますが……今のところは効果をあげていません」
「いっそ退院させて元の生活に戻れば、何か思い出すということはないのですか」
「今でもときおり、何かをしている途中にぼんやりしてしまうことがよくあります。自分がどこにいるかわからないことも。そういった意識の混濁や、ときおり前触れなしに訪れる不安感。
それらが軽くならないと、日常生活に戻るのは難しいでしょう」
「そうですか……」
怜はうなだれた。
やはり。
やはり美玖は、このまま彼を見ることも、彼の声を聞くこともできないのか。
影のように、たとえどんなにそばについていても。
いつも思い出す光景がある。
どこかの地方都市の県民ホールの楽屋の裏手。
押し寄せてくる大勢のファンの中に、美玖がいたのだ。
2時間のステージのあとで疲れ切っていた。自分たちの人気に酔いしれ、同時にいら立ち、不安だった。
華やかに着飾った少女たちの中で、ちっとも垢抜けない服装の彼女を見つけたとき、動揺した。
彼女は昔と何も変わらない。彼のにごった心を見抜くような透き通った美玖の瞳。
怜は思わず目をそむけた。
拒絶。
そのしぐさの意味がわかったのだろう、それ以後、彼女のほうから連絡を絶った。次に彼女と再会したのは、この病院の中だった。
(俺は自分のおかした罪の罰を受けているのだ)
と思う。彼女を見えないふりをした罰に、美玖は本当に俺のことが見えなくなってしまった。
できることなら、フィルムを逆回しにするように、あのときに戻ってやり直したい。
「霧島先生。たった数分でいい、美玖と話がしたい。……今までのことをあやまりたいんだ。何とかして、俺のことばを彼女に伝えていただけませんか」
消え入りそうな声でつぶやく眼の前の若い男を、精神科医はじっと見つめた。
そして、そばに立っていた看護師に言った。
「白石美玖さんを、呼んできてください」
「霧島先生、こんにちは」
美玖は部屋に入ってくるとき、無邪気なほどうれしそうな声をあげた。そのあけっぴろげな笑顔は、まるで小学生の少女のよう。
対する霧島医師も、いつもの冷徹な表情からは想像もつかないほど、おだやかに微笑んでいる。
「気分はどう?」
「はい、今日は頭痛もないし、とてもいいです」
「それはよかった。じゃあ面接を始めるから、その椅子に座って」
山吹色のニットのセーターの裾を直しながら、彼女は無造作にすとんと腰をしずめる。
「美玖さん、その椅子、さっきまで別の人が座っていたんだよ」
霧島のことばに、
「あら、そう言えば、ほんのり暖かいわ」
と、初めて気づいたように答える。
「その人があなたのために、椅子を引いてくれたのに気づきましたか?」
「え、でも私、自分で椅子を引きましたよ」
不思議そうに問い返す。これが医師の言っていた、記憶の混濁なのだろう。
「それにその人は今も、あなたのかたわらに立っている」
「でもここには、看護婦さん以外誰もいないわ」
「名前は日下部怜。彼はあなたにひとこと話がしたいと言っています」
「……なんですか。それ」
美玖の表情がにわかに曇り、きょときょとと視線が落ち着かなく動いた。
「日下部くんは、「ブルーカオス」というバンドのボーカルをしていたときにあなたと知り合った」
「先生……、冗談を言ってらっしゃるの?」
「長いあいだ恋人同士だったが、不幸な別れ方をした。それ以来あなたは、彼を見ることができず、その声を聞くこともできない」
「先生。それって……、治療のため? 私に嘘のお話をして、どんな反応をするかを見ているの? そうなの、……そうなんでしょ?」
「そんなつもりはないよ。落ち着いて」
彼女はいきなり、わっと泣き始めた。
「せん……せい。そんな意地悪しないで……。私、私何でも言うことを聞きますから。おくすりもちゃんとのみますから……。先生にきらわれたら、わたし生きていけないよ。……せんせいだけが、わたしのこと……」
「美玖さん、わかった。この話はやめにしよう」
胸に抱きついてくる彼女を医師はそっと押し戻す。替わりに手を取って、安心させるようにぽんぽんと叩いた。
「もうこのへんで終わりにしよう。さあ、今日は風もない、いい天気だから散歩でもしていらっしゃい」
「はい……」
怜は彼女の横顔を見て、愕然とした。
美玖が医師を見上げる瞳には、相手を信頼しきった、まるで恋人に向けるような光が宿っていたからである。
「日下部さん。もうわかったでしょう」
彼女が出て行ったあと、霧島は怜に向き直った。
「美玖さんにあなたのことを話すと、今のようにパニックを起こし、幼児のようになってしまいます。意識の下にあなたの記憶を拒否する思いがある。もし強要すれば、心が壊れてしまう恐れがあるので、治療には時間をかけたいのです」
「美玖は……」
怜は半分、医師のことばを聞いていなかった。
「霧島先生、あなたのことを好きなのではありませんか?」
30代後半の医師は、唇の端を少しゆがめて笑った。
「精神科の患者は特に大きな不安感を抱いているとき、担当医に恋愛感情を抱いていると一時的に錯覚することがあります。治療が進めば忘れ去る気持ちです」
「でも……」
「心配ですか?」
自分にはもう決して向けてもらえない美玖の優しいまなざし。甘えた声。
霧島に激しく嫉妬している自分を感じ、怜は惨めさに身体を震わせた。
「おまえ、毎日美玖ちゃんの病院にいりびたってるんだってな」
ベース担当だったシヴァこと柴田の問いかけに、窓の外を向いたままうなずく。
数週間ぶりの都会の雑踏。人々が忙しく行き交う姿を冷え冷えとしたガラス越しに見ながら、怜は自分がその一員ではない疎外感を味わっていた。
「メジャーからの誘いは、あるんだろ」
「ああ」
「シングル一枚でも出しておけ。まだ「ブルーカオス」のレイの名をみんなが覚えているうちに。急がないと、この世界では半年が大昔だ」
派手なウィッグとコスチュームを脱いだこのふたりが、かつて日本中を熱狂させたグループのメンバーであることを、このコーヒーショップの中に気づく者はいない。
「歌えない……、今のままでは」
カップに目を落としながら、怜はぼんやりとつぶやいた。
「彼女への罪滅ぼしのために歌わないつもりなのか」
答えないでうつむく怜の顔を、柴田はのぞきこんだ。
「あきらめろ。おまえたちはもう終わったんだよ。おまえが今していることは自己満足だ。そんな押しつけの愛情は、美玖ちゃんのためにならない」
「ああ……、そうなのかもしれない」
ため息とともに、投げやりなことばを吐き出す。
「ときどき、もう限界だと思うことがある。美玖にとってまるで俺は空気だ。存在しないんだ。憎しみをぶつけられたり罵られるほうがどれだけ楽か。自分が本当に消えていきそうになる」
「辛いな」
柴田は同意して、うなずいた。人々の熱い視線を浴びることに慣れきってしまった彼らにとって、無視され忘れられるということは、普通の人以上に耐えられない恐怖と感じられた。
「それでも俺は、一生美玖のそばにいると決心したんだ」
「そして、歌を捨てるのか」
ぴくりと、カップの取っ手にかける怜の指が動いた。
そうだ。「ブルーカオス」を解散するときに、一度歌を捨てた。
いくら五線譜の前に向かっても、自分の内側から何のメロディも浮かんでこない。その苦しさから、逃げ出した。
美玖のためじゃない。ただ美玖を口実に、歌うことから逃げているだけだ。
「レイ。俺は」
ベーシストは、タバコの吸殻を灰皿にぐいっと押し付けた。
「俺は、おまえの才能を惜しんでいるんだ。おまえは、人の心に深く訴えかける天性の歌声の持ち主だ。解散した今だからこそ、わだかまりを捨ててそう思う。
……レイ、歌い続けろ。おまえにできることはそれしかない」
「でも、たったひとりの女の耳にさえ、俺の声はとどかない」
怜は自分を嘲けるように、ひきつった笑いを洩らした。
「そんな俺に、歌う資格なんてあるんだろうか」
「資格があるかどうかは、おまえの歌を聞く人が決めることだ」
柴田は静かに立ち上がり、怜の肩に手を置いた。
「レコーディングのときは、たとえ何があっても駆けつけるからな。俺のギターでおまえの最高の音を引き出してやるよ。……連絡を待ってるぜ」
南病棟と北病棟のあいだをつなぐ屋根つきの渡り廊下。
春の雨に塗りこめられた人気のないその空間に、一組の男女が抱き合って立っていた。
霧島医師と美玖だ。
しばし呆然とそれを見ていた怜は、本館の非常口からまっすぐに雨の中庭を抜け、渡り廊下に向かった。
医師はふたことみこと何かをささやくと、彼女のからだをポンと押して、病棟に入らせた。そして怜を待ち受けていたかのように、落ち着いた物腰で振り返った。
「先生、あんたは……」
長い髪に水滴をちりばめて歩いてくる怜を、霧島は冷ややかな目つきで見返す。
「誤解しないでもらいたい。一時的な虚血で倒れそうになった彼女を抱きとめていただけです」
「嘘をつけ!」
怜は憎悪をこめて答える。
「少なくとも、美玖の側はそうは思っていない」
「それは前にも説明したはず。擬似的な恋愛感情は……」
「あんたのほうはどうなんだ!」
「どういう意味です?」
「あんたは独身だと聞いている。もしかすると、あんたのほうこそ美玖のことを……」
「私は医師だ。医師として患者を気にかける以上の感情を、彼女に持ったことは一度もありません」
「とても、そうは見えなかった!」
「日下部さん、あなたは冷静な判断ができていない。あらぬ妄想に取り憑かれている」
怜は奥歯をぎりっと噛みしめると、彼を突き飛ばすようにして、屋内に入っていった美玖を追いかけた。
「美玖!」
叫ぶなり、廊下を歩いていた彼女を振り向かせ、腕をつかんで乱暴に揺すぶった。
「美玖! 俺を見ろ! 見るんだ」
彼女は自分に何が起きているのかわからず、恐怖に目を見開く。
その表情に、彼はますます逆上した。
あの医者に微笑んでも、俺には微笑まない気か。
「俺の声、ほんとは聞こえているんだろう? 美玖。もうこんなことやめてくれ! ちゃんと俺に答えてくれ!」
「痛い! 何なの、この、からみついてくる……。息ができないっ。……助けて! 誰か!」
「復讐なのか。俺に仕返ししているつもりなのか? なら、もう十分だろう!」
もがく美玖を、ありったけの力で怜は押さえつけようとする。
霧島が追いかけてきて、怜の首筋をつかみ、彼女から引き離した。
「この、馬鹿っ!」
霧島の怒声が、雷鳴のように廊下に響き渡る。
壁に叩きつけられた怜を、彼は眼鏡越しににらみつけた。
「もう二度と、ここに来るな」
つめたく押し殺した声。
「貴様は、この人の心に巣食う害虫だ。……次にここに現われたら、ただではすまさん」
片隅でうずくまりながら、怜はそのことばが痛みをともなって自分に降りそそぎ沈殿していくのを、ぼんやりと感じていた。
この医者のいうとおりなのかもしれない。
もうこれ以上、美玖のそばにいてはいけないのかもしれない。
あれほど彼女を裏切っておきながら、心の底から彼女に詫びたいと思っていながら、さっき自分の心を支配していたのは、美玖に対する怒りだけだった。
人はいったい、自分を見つめてくれない人をどれだけ愛していられるのだろうか。語りかけてくれない人のそばで、いつまで待つことができるのだろうか。
俺はだめだ。俺は、もう美玖を愛せない。
10日が過ぎた。
怜はあれ以来、ぷっつりと病院に姿を見せなくなった。
「寒いわ。……霧島先生」
庭を散歩していた美玖は、カーディガンの前をかき合せながら、身をすくめる。
「そうだね。春とは言え、風はまだ冷たい」
「そうじゃないの……。いつも私を暖かく包んでくれていたものが、なくなってしまった……、そんな気がして、寂しくて。涙が出て。なんだか私、ずっと変なんです」
霧島はにっこりと微笑んだ。
「きみを包んでいてくれたものって?」
「わかりません。とても大切なもの。……なくしては、いけないもの」
「それがなんだか、知りたいかい?」
ためらった末、彼女はうなずく。
「……はい」
「そうか」
そのとき、彼は背後に立つ人の気配を感じた。
「先生」
「あなたでしたか」
医師は美玖に、ゆるやかに続く芝生の向こうのベンチで待っているように告げてから、怜のもとに歩み寄った。
「このあいだは失礼なことをしました。赦してください」
肩にギターケースを抱えたまま、怜は深く頭を下げる。
「約束どおり、もう二度とここには来ません。ただ今日だけ……最後に一回だけ、美玖に会わせてください。彼女の前で歌うだけです。どうせ、俺の声は聞こえません。許可していただけますか」
「わかりました、許可しましょう」
「霧島先生。……どうか美玖のことを、これからもよろしくお願いします」
じっと彼を見据えながら声を震わせてそう言うと、彼はふたたび一礼して、まっすぐに美玖のもとに向かった。
「いちかばちかの賭け、ね」
霧島が振り向くと、ナースキャップをかぶった女性が意味ありげに微笑んでいた。
「何のことです、婦長? わたしはそんなギャンブルのような治療をした覚えは、一度もありませんよ」
「そうかしら。もし彼がこのまま彼女をあきらめてしまったら、どうなると思うの」
「それなら、彼はそれだけの男だと言うことですよ。治療の邪魔になるだけです」
「なるほど」
ふたりは一瞬、すべてをわかりあった者同士の視線をからみあわせ、そのまま並んでベンチのほうを見つめた。
「美玖」
返事はない。彼女はただ前方を見つめて、おだやかな春の日差しの中で座っている。
正面にひざまずき、ありったけの思いを込めて、彼女を見つめる。
「この一週間、曲を作っていたんだ。解散前はどんなにがんばっても何も作れなかったのに、次々とメロディが頭の中に浮かんできた」
彼女は何かに聞き入るように小首をかしげた。でも、それは怜のことばにではない。
たぶん、遠くでさえずる小鳥の声。
「きみを死ぬよりつらい目に会わせた。それなのに俺はきみに腹を立て、ますます傷つけてしまった。ずっとそばにいようと決意したのも、本当はきみのためじゃなかった。ただ自分が楽になるために、赦してほしいと願ってきただけだった。
たぶん俺はこのまま、一生赦されることはないんだと思う。きみに完全に忘れ去られることが、俺への永遠の刑罰なんだと思う。
俺には歌うことしかないと、シヴァに言われた。考え続けて、その意味がやっとわかった。
二度とここへは来ない。美玖。でも俺はきみを思い続けて、歌を作る。最高の歌を作るために死ぬまで歌い続ける。きみがほかの男を愛して幸せになったとき、いつかその歌に耳を傾けてほしい。
俺のことは……忘れたままでいいから」
怜は美玖の隣に座ると、ギターをかき鳴らし始めた。
静かなアルペジオで始まるバラード。
『 狭い部屋 膝をかかえ
ぼくの歌をいつも 最初に聞いてくれたのは きみだった
小さなステージ ライトが消えて
人々が去ったあとも ひとり待ってくれたのは きみだった 』
歌いながら、怜の頬に涙が伝った。
「レイよ! レイの声だわ!」
中庭の向こうにいた若い女性の患者が、最初に気づいて大声を上げた。
『 たくさんのざわめきの中で ぼくはきみの声をさがしていた
果てしない雑踏の中で きみの笑顔だけを求めていた
きみがいなくなってから ずっと
暗闇の中を 歩きながら 』
おだやかな春風に乗って流れてくる、よく通る低く甘い歌声に、患者や病院のスタッフたちはふと足を止めた。まるで幼い頃の思い出にひたっているような表情で、誰もが聞き入っている。
『 今 きみはどうしているだろう
きっと ぼくのことなど忘れて
どこかの家の 幸せな窓辺にたたずんでいる
でも 神がゆるしてくれるなら
いつか ぼくの歌がとどいて
ほんの少し ほんの少しだけ 笑ってくれるといい 』
ギターピックが手から離れ、芝生に落ちた。「美玖……?」
「怜……」
美玖の目から、とめどなく涙があふれている。
「怜……、どこ? 遠くからあなたの歌が聞こえる。……どこにいるの?」
「……美玖!」
そのとき瞳がすっと焦点を合わせた。
「怜」
美玖はためらいのない真直ぐなまなざしで、ただぼろぼろと泣いている彼を見上げて微笑んだ。
「――会いたかった」
「あなたが見えない」の続編です。
メールで続編を熱望してくださった方のおかげでふたりを幸せにできました。どうもありがとうございました。