「EWEN」&「魔王ゼファー」クロスオーバー企画第3弾
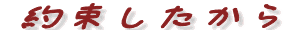
|
第1回 ―― 聖 駅の改札を出たとたんに、僕は彼女を見つけた。 雪雲から漏れる冬の午後の淡い陽射しを浴びて、周囲の景色から浮き出るように輝いている女の子。 華奢な顎を縁取る白い手編みのマフラー。おそろいの青いマフラーを指先で確認しながら、僕はなぜだか晴れがましい気持で、彼女にゆっくりと近づいた。 「聖」 雪羽は僕を見つけて、首を傾げるようにして、にっこり笑った。 以前の彼女なら、もっとあけっぴろげに笑ったのだと思う。僕を見つけたら走り寄ってくれたのだと思う。もちろん僕だって。 僕たちが最後に会ったのは、二年近く前、中学二年のとき。あのときはお互いに、まだほんの子どもだった。 今は違う。待ちに待った二年ぶりの再会を、じっくりと踏みこたえることができる。ふたりとも、それくらい大人になったのだ。 「久しぶり」 僕も余裕の笑みを浮かべた。――成功したかどうかは、わからないけど。 「高校合格おめでとうございます」 雪羽は少しおどけたように、ぺこりと頭を下げた。 「こちらこそ、おめでとうございます」 僕も、同じように返した。「すごいよ。関西に住んでる僕でも都立T高校って名前を聞いたことがある。がんばったんだな」 「運がよかっただけだ」 雪羽は、こともなげに言った。「聖こそ。前期入試で第一志望に通ったんだろう」 「オレは、家から一番近い学校っていうだけだよ」 肩をすくめながら、答える。「偏差値だってたいしたことない。全然すごくなんかないって」 会話が途切れた。 僕たちは、お互いの顔をちらりと見ると、くすくす笑い始めた。 「なんだか、大人の会話みたいだな」 「うん、社交辞令そのものだ」 僕は雲をぶち破るみたいな勢いで、うーんと両腕を伸ばした。 「あー、よく勉強した。オレたち、よくやったよな」 「うん、がんばった」 「この一年で一生分の頭を使った。わき目もふらず、雪羽のことも考えないようにして、ただひたすら」 次のことばを言うまでに、少し間が空いた。なんだか胸がいっぱいになってしまったのだ。 「一日も早く会いたかったから。そして、合格を雪羽に笑顔で報告したかったから」 「私もだ」 もう一度、会話が途切れた。だけど今度のは、自然な沈黙だった。僕たちは、お互いの目を見つめながら、どれだけこの二年、お互いのことを想っていたかを確かめ合った。 すごくもどかしく、でも幸せな時間が流れていく。 「そろそろ行こう。家で両親が待っているんだ」 「なんだか、悪いな。ご馳走まで気を遣わせちゃって」 「とんでもない。ふたりとも、聖に会うのをすごく楽しみにしているぞ」 僕は手に持っていたバックパックと竹刀袋を肩に背負い直すと、並んで雪羽の家に向かって歩き始めた。 揚げたてコロッケのいい匂いがしてくる肉屋や、おいしそうなイチゴが店先に並べられた八百屋。冷蔵庫のドアに電気仕掛けのマスコットがゆらゆら揺れている電器屋。お年寄り向きの柄物がショーウィンドウに飾られた洋服屋。 東京の下町は、この時間でもけっこう賑やかだった。西宮ではこういう商店街は、あまりない。 雪羽はお母さんの買い物や食事の支度も手伝うと言っていたから、ここらへんで夕食の買い物をしているのだろうか。 「ディーターさんや円香さんは元気か?」 「うん、変わりない。ゼファーさんの工場はどう?」 「このところは、順調だと聞いている」 そんなとりとめのない会話を交わしながら、歩いていると、突然、誰かが呼ぶ声がした。 「雪羽」 目を上げると、前方に、背の高い、白いコートを着た若い男が立っていた。 光線の加減か、髪と目が藍色に見える。そのせいで、ぞくっとするほど神秘的な雰囲気を漂わせている――なにか、この世の存在ではないみたいな。 「悠里おにいちゃん」 雪羽は、とたんに弾かれたように彼のもとへ走り寄った。「こんな時間に珍しい。大学は?」 「今は、休みだ。こうやって日の光を浴びるのは久しぶりだな」 悠里という名の男は、柔らかく微笑みながら雪羽の頭を撫でた。いとおしくてたまらないという仕草だ。 僕はみぞおちのあたりが騒ぐのを感じた。 「そっちの子は?」 「ああ、聖だ。高校入試が終わって、兵庫県から遊びに来てくれた」 男の視線を受けて、僕はつかつかと歩み寄った。挑戦的に見えないように、 「はじめまして。聖・グリュンヴァルトです」 手を差し出した。 彼は、僕の手を軽く握ると、からかうように笑った。 「会えてうれしいよ。女王の心を捕らえて離さない騎士に」 その瞬間、顔がかっと熱くなるのを感じた。馬鹿にされたと感じたのだ。表情にも表われてしまったのだろう。雪羽が心配そうな顔をして、ちらりと僕を見た。 「じゃあな。雪羽。御父君によろしく」 「ああ。天城博士とふたりで、また遊びに来てくれ」 彼が駅のほうに行ってしまうと、雪羽は説明した。 「あの人は、天城悠里。私の五歳上の幼なじみで、理工大学に通っている」 「ふうん」 「生命科学を研究していて、毎日実験に明け暮れているそうだ」 心臓がどきんと打った。それは僕が大学に行ったときに、専攻しようとひそかに思っていた科目だった。 なぜか僕は少し前から、自然や生命ということにすごく興味を持っている。僕と同じことを、今目の前に現れた男がすでに研究していると聞いて、なぜだかすごく腹が立ってしかたなかった。 「そんな幼なじみがいるって、一度も聞いたことなかったな」 「忘れていたんだ。このところ、お互い忙しくて行き来がなかったし」 雪羽のことばには、弁解をするような調子がひそんでいると思えた。 僕たちは気まずい雰囲気のまま、また歩き出した。 「……悠里は、ナブラ領を治める王だったんだ」 「ナブラ領って?」 「アラメキアに行ったとき、最初に着地したところだ」 「……アラメキア」 「一晩農家に泊めてもらったことを、覚えているだろう? あそこから東と南に広がる一帯が、すべて悠里の領地だった」 後半のほうの説明を、僕はほとんど聞いていなかった。 商店街がもうすぐ途切れるという四つ角に、喫茶店があるのを見つけたからだ。 「雪羽。家に着く前に、少しだけ話したいことがあるんだ」 僕は、勇気を奮い起こして、言った。「――ふたりだけで」 雪羽は、怪訝そうな顔をしたが、うなずいた。「別にかまわないが」 彼女の腕を取ると、その喫茶店に導いた。 店先に樹木の植木鉢で囲まれた小さな前庭のようなスペースがあった。そこまで来ると、僕は衝動的に雪羽を抱きすくめた。 もう限界だ。雪羽に会いたくて会いたくて、爆発しそうな感情を必死に抑えながら、この二年を過ごしてきたんだから。 いきなりのことだから、きっとびっくりしているだろう。でも、僕は構わずに、唇を重ねた。 「ごめん」 唇が離れる合間に、途切れ途切れにささやいた。「早く雪羽とこうしたくて、死にそうだった……死ぬほど、会いたかった」 たぶん、そのときの僕は必死だったんだ。今から、どうしても話さなければならないこと。もしかすると、それは雪羽を傷つけてしまうかもしれない。 それに、悠里という男の存在を知ったことも、心が騒ぐ原因だった。 今ここで、雪羽の僕に対する気持を、もう一度はっきりと確かめておきたい。 雪羽は最初は戸惑っていたが、僕のキスをちゃんと受け入れてくれた。 僕たちはようやく身体を離すと、喫茶店の扉をくぐった。 窓際の席を選び、注文を終えると、雪羽はコップの水を、こくこくと一気に飲み干した。 そして、オーバーを脱いだ僕を目を細めながら、まっすぐ見つめた。 「なんだか、聖は変わった」 「ああ。この一年で、背はずいぶん伸びたな」 「着ている服も、違う」 「東京へ来るのが決まってから、あわてて新しいのを買ったんだ」 「なんだか……聖だけ、本当の大人になってしまったようだ」 雪羽は、ピンク色に染まった頬を隠すように、両手を添えた。 僕も、さっきのキスからずっと心臓が高鳴ったままだ。 「雪羽も大人になったよ」 「そうだろうか。私はまだ子どものままだ」 「誕生日からすれば、オレより半年分は子どもだけど」 それが合図のことばだったかのように、僕はバックパックをまさぐって、テーブルの上にことりと小さな包みを置いた。 「誕生日おめでとう。二週間遅れで」 「えっ」 「誕生日のプレゼントと、合格祝いを合わせたつもり」 雪羽はおずおずと包みを手に取った。 「……私は聖に、合格祝いを用意してこなかった」 「いいんだよ。ねえ、開けてみて」 白い指先がかさかさと包装紙を鳴らして、中から出てきたのは、クローバーの形をしたペンダントだった。 「きれい」 「西宮北口のデパートで見つけて、ずっと買おうと思ってたんだ。絶対に似合うと思って」 「こんな高いものを……これ、ダイヤだろう」 「そんなに高くないよ、ちっちゃいし」 雪羽は、不安げにじっと僕の顔を見た。「でも、それでも何万円もするのではないか?」 「実は、ちょっとだけバイトをしてたんだ」 安心させる意味で、僕は本当のことを打ち明けた。 「オレの合格発表は十日前だったから、昨日までのあいだ、近所のコーヒーショップで短期バイトをした。往復の新幹線代も稼ぎたかったし、服も買ったし」 「それだけで、こんなに?」 「その店、夜は酒を出すんだ。でも、オレは九時に上がらせてもらってたけど」 雪羽の目が驚愕に見開かれる。 「聖も、酒を飲んだのか?」 「十五歳でそんなことしたら、捕まっちゃう。飲まないって」 ――表向きは、ね。 でも、そんなことを言えば、雪羽が怒るのは目に見えているので、僕は黙っていた。 「大変な思いをさせてしまったな」 「雪羽。あんまり、うれしくなさそうだね」 「そんなことない。うれしい――うれしすぎて、どうやって表わせばいいか、わからないだけだ」 雪羽は感極まったように目を閉じて、ペンダントをぎゅっと握りしめた。「ありがとう、聖。私のために、これほどまでしてくれて。一生の宝物にする」 「よかった」 僕は吐息をついた。雪羽の喜ぶ顔を見ると、十八歳だと偽ってバイトをしたという後ろめたさが、消えていく。 「なあ、早く着けてみせて」 「あ……、そうだな。化粧室に行ってくる」 雪羽は、席から立ち上がった。「ついでに、両親に少し遅れると電話してくる」 彼女が行ってしまったあと、コーヒーを口に含んだ。こんなことで、軽い勝利の興奮に包まれている自分が、馬鹿みたいだ。 でも、そうやって心を奮い立たせねばならなかった。 それほどに、今から言わなければならない言葉を言うためには、勇気が必要だったのだ。 雪羽の携帯から、少し帰りが遅くなると連絡を受けたゼファーさんと佐和さんは、その前に、僕の父からも電話を受けていたらしい。 ――想像だけど、たぶんこんな会話だったはずだ。 「ディーターか」 『ゼファー。久しぶりだな。聖はそっちに着いたか?』 「いや、まだだ」 父とゼファーさんは、三年前にゲーム機のコピー商品を製造している組織のアジトに、ふたりで侵入したことがある。それ以来、お互いを「戦友」だと認め合っている仲だ。 『世話になりついでに、頼みがあるんだ』 打ち明ける父の声は、とても苦しそうだったと思う。 『このところ、急に聖の様子がおかしくなった。家族ともほとんど会話をしないし、毎晩深夜まで、家に帰ってこないんだ』 「まさか、聖が?」 『雪羽ちゃんに会いに行くのも、ぎりぎりまで迷っているようだった。何か、心に持っていることがあるらしい。――すまないが、ゼファー、そっちにいる間、聖の様子に気を配っていてくれないか』 ペンダントを薄いブルーのセーターの胸にきらめかせた雪羽を見つめながら、僕はとりとめのない会話を続けた。いやなことを一刻でも先延ばししているかのように。 「お父さん、映画の仕事で今度は北海道に行くらしい」 「次の監修作品が決まったのか」 お父さんの殺陣の大ファンである雪羽は、身を乗り出してくる。 「今度の映画は、時代劇ぽいけど、架空の世界を舞台にした和風ファンタジーなんだ。だから、本当の時代劇では絶対にありえない、山賊と馬車のチェイスシーンとか石の城での決闘とかが出てくるんだって」 「ふうん、面白そうだ」 「でも、映画の仕事に、お父さんはあまり乗り気じゃないんだ。葺石流の門下生を教えることのほうが大事だって」 「そうなのか」 「それに、もうすぐ鹿島師範がお父さんに、師範の座を譲るって言ってるし」 雪羽はそれを聞いて、なんとも言えない、少し切なげな表情をした。 「鹿島さんは、自分の実力がディーターさんに劣っていると感じたときは、すぐに師範を譲ると言っていた」 「うん」 「ディーターさんは、ついに鹿島さんを完全に越えてしまったんだな」 直接ふたりの刀を受けている僕も、そのことはしみじみと感じていた。 お父さんの強さと言ったら、このところ、鬼神のようだ。いつまで経っても、追いつけるどころか、日増しに離されていく。 僕は、葺石流の修行を続けるのを、何度あきらめようと思ったかしれない。 この数ヶ月、高校受験にかこつけて、お父さんと手合わせするのを避けていた。そのことも、僕の心を重くしている原因のひとつだ。 「聖はやはり、どこへ行くときも、その木刀を持っているんだな」 気がつくと雪羽は、僕の隣の席に置いた竹刀袋に、なつかしそうに目を注いでいる。 「ああ、できるだけ毎日、素振りをしろって言われてるからね」 「精霊の女王さまが下さった、その緑の鞘があれば、アラメキアで聖は私のそばから離れて自由に行動できる」 「……」 「あれからもうすぐ二年か。今度は、いつアラメキアに行けるのだろうな」 「雪羽」 たまらなくなって、僕は彼女のことばを遮った。 「それが、オレの話したいことなんだ」 「そういえば、ふたりだけの話があると言っていたな」 彼女は、僕を見つめ返した。「いったい、何のことだ?」 胸がずきずきと疼く。 僕は、とても残酷なことを言おうとしているのだろう。でも、それは僕たちふたりのためだ。 遠距離恋愛の僕たちが、どんなに離れていても、これからもずっと互いを想っていくために――大人になってもずっと愛し合っていくために、これは必要な痛みなんだ。 「聖、どうしたんだ」 顔を伏せている僕に、雪羽が気遣わしげな声を出した。 「……アラメキアの話はやめにしないか?」 雪羽がさっと表情を変えるのを、僕は全身で感じ取っていた。 「アラメキアなんていう、おとぎ話を信じるのは、もういい加減にやめよう」 |