「ローレル博士。長いお務めご苦労さまでした」
「SR12型シーダ。その軽口、カイトにそっくりになってきたわね。残念ながら、今日だけの仮出所よ。面白いものを見せてくれるって言うから、特別の許可をもらったの」
「確かに見ものですよ。なにしろ『マイフェアレディ』という二十世紀の古典ミュージカルを、セフィたちが再現するんですから」
「でも、聞いたところによると、AR8型セフィロトのために、原作にはない役を無理矢理作っちゃったというじゃない?」
「はい。だからセフィはちゃんと実名で、しかもロボット役で出るんです」
「それに、ヒギンズ教授をイツキが演じるというのは、どういうこと? イツキは死んでるはずでしょう」
「ロボット以上に細かいことによく気がつく性格は、小じわの元ですよ」
「シーダ。そろそろ初期化されたい?」
「はいはい。実は、国立応用科学研究所のマザーコンピュータ【テルマ】が、今回の企画に全面協力してくれたんです。古洞樹博士の【人格移植プログラム】をもとに、博士の擬似体が一時的に生み出され、それが、実際の体と寸分変わらぬ超リアルなホログラフィーとして舞台に立つんです」
「なるほど。これは相当お金がかかってるわね」
「はい。国家的プロジェクトのミュージカルですよ。うんと楽しみましょう」
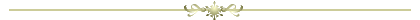
二十世紀初頭。イギリスはロンドン、ウィンポール街にあるヘンリー・ヒギンズ教授の屋敷では、今ひと騒動が持ち上がろうとしていた。
「無茶だよ、ヒギンズくん」
ふたりの男が、なにやら言い争いをしながら、舞台に登場する。
「六ヶ月であの花売り娘に美しい話し方を教え、社交界に出せるレディにすると約束したはずだ。それなのに、学会への出席で、ロンドンを長期間留守にするって? いったい彼女との約束はどうなるんだ」
文句を言っているのは、インド帰りの方言研究者、ピカリング大佐(犬槙魁人)。ヒギンズ教授と気が合って、少し前から彼の屋敷に滞在している。
このピカリング大佐というのが、美貌の青年のうえ無類の女たらしで、屋敷の滞在中に次々とメイドたちに甘い言葉をかけ……いや、これは本筋にはかかわりのないことである。
「どうもしない」
著名な言語学者のヒギンズ教授(古洞樹)は、痩せて枯れ木のような長い脚を組み、いつもの無愛想な口調で答える。
「俺がいなくとも、代わりの者にやらせればすむことだ」
「今回の君との賭けのことでは、僕も責任を感じてるんだ。あの子を守る責任をね。きみのやり方は、ちょっとひどすぎるぞ」
「それは心外な言い方だな。あのじゃじゃ馬の調教には、むしろ俺よりも、もっと適役がいるんだよ」
「適役?」
「おおい、セフィロト」
中央奥の扉から、まだ少年と言っていいほどの若者(AR8型セフィロト)が出てくる。
「お呼びですか、マスター」
「俺はこれから半年間、学会でロンドンを離れる。そのあいだの留守をおまえに頼みたい」
「はい、承知しました」
「それと、もうひとつ。こないだから我が家に引き取っている花売り娘の教育係となって、話し方と礼儀作法を叩き込んでやってほしい」
「わたし、がですか」
驚いたような声を出したものの、表情が明らかに乏しい。そのギャップは見る者に違和感を感じさせる。
「ですが、わたしはロボットなのですよ」
「わかっている。おまえを作ったのは俺だからな」
「ロボットが、人間の教育係になるなどという話は、聞いたことがありません」
「そもそも、人間と寸分たがわぬ外見と知性を持つロボットという存在が、前代未聞だ」
ヒギンズ教授は、平然と答えた。
「この数日、あの女を特訓してみて、わかった。あの石ころを教育することは、生の人間には不可能だ。何度教えても、覚えない。少しきつく言えば、ガチョウのような声で泣き出す。宿題はしない。居眠りはする。チョコレートは欲しがる。あんな女にかかわるのは、俺はもうこりごりだ!」
俺は普通の男 普通の暮らしを望んでいる
好きなように生き やりたいことをやるだけ
一般的な男 変わった趣味もなく 世のしがらみなんてお断り
自分の道を進む ごく普通の男さ
だが女が人生に入り込めば 静かな生活は終わり
地下室から天井裏までリフォーム その次は男をオーバーホール
計画なんてそっちのけ やりたいことなど何もできない
女とかかわれば 一生はだいなし
「だから、セフィロト。女の相手はロボットがいいのだ。忍耐強く、眠くもならず、与えられた責務を忠実に果たすロボットこそが、女の教育係にふさわしい」
「……はあ」
「わかったかね」
「承知しました」
「それでは……おおい、イライザ!」
小部屋の扉から、町の花売り娘イライザ・ドゥーリトル(古洞胡桃)が、寝ぼけ眼で出てくる。
「言われたことは、できるようになったかな」
「うん」
「『うん』じゃない、『はい』だ! それでは、言ってみろ」
「あーとおーど・あんぷしゃーには、ありけーんは・おとんど・うかない」
「だめだ、だめだっ。『ハートフォードハンプシャーには、ハリケーンはほとんど吹かない』、だろ!」
「ちゃんと、そう言ってるじゃねえかよう」
「二日間、ぶっつづけで教えて、これだ」
ヒギンズは、こめかみに拳を当てて、溜め息をついた。
「もういい。俺は明日の船でニューヨークに行って来る。しばらく帰ってこない」
「ええっ」
イライザは、あんぐりと口を開けた。「半年間で、あたいをりっぱなレディにしてやるという約束は、どうなったんだよう」
「忘れてはおらん」
「メイドや一流の店の店員にだってなれるて、言ったじゃねえかよ。シバの女王にだってなれるって」
「ああ言ったさ。だから、おまえの教育は、明日からこのセフィロトが担当することになった」
「あ、あたいは、あんたが直接教えてやるって言ったから……」
「もう決まったことだ。決定は覆さん!」
ヒギンズは、荒々しい足音を立てて部屋を出て行く。
「ヒギンズくん、ちょっとひどすぎやしないかね」
あとを追いかけてきたピカリング大佐は、廊下で、眼鏡の奥から友人をにらみつけた。
「あれでは、あまりに彼女が可哀そうじゃないか」
「俺ははじめから、あの女を教育する気などない」
ヒギンズ教授は、片方の口角を上げて、冷たく笑った。
「俺の目的は最初から、セフィロトをもっと人間らしく育てる、その一点だけだ」
「セフィロトを?」
「俺は、人間と寸分違わぬロボットを目指してセフィロトを創った。だが、見てのとおり、セフィロトは人間そっくりというには、まだ何かが足りない」
「それは、まあ」
(それは、創ったおまえ自身が、あまりに人間性に乏しいからだ)
ピカリングは心の中で、こっそり毒づいた。
「俺はようやく気づいた。完璧であればあるほど、人間から遠ざかっていくのではないかと。それで、イライザを引き取ることにしたんだよ。あの、どうしようもない、不完全の見本みたいな女に接することで、セフィロトは人間らしい不完全さを学んでくれるんじゃないかとな」
「それでは、イライザを引き取ったのは、はじめからセフィロトのためなのか」
「そう。セフィロトがイライザの教育係なのではなく、イライザがセフィロトの教育係なのだ」
ヒギンズ教授は胸を張った。
「半年後が楽しみだ。社交界のパーティに出て、セフィロトがロボットであることがバレなければ、俺たちの研究は大成功。一気に、ヒューマノイド型ロボットへの評価が高まる」
そして、声を落としてささやいた。
「そうすれば、俺とおまえが言語学者の隠れ蓑を着て、実はロボット工学者であることも、もうまわりに隠す必要はなくなるだろう? まったく、キリスト教が幅を利かすこのヨーロッパでは、人間そっくりのロボットの研究は、とことん忌み嫌われているからな」
「何て奴だ」
ピカリング大佐は、あきれて吐息をついた。
「なんだよう。約束が違うじゃないか」
先ほどの部屋では、イライザが放心したように座り込んでいた。
「あいつ、あたいのこと見捨てたんだ。あたいがあんまり、物覚えが悪いから」
「そんなことはないと思いますよ」
セフィロトは、あたりさわりのない慰めを口にした。
「イライザさんだって、努力すれば、きっとできます。わたしがお教えしますから」
「私は教授に教わりたかったんだ。あんたなんかに教わりたくない。あんたなんか――ただの人形じゃねえか!」
言ってしまってから、イライザははっと口を押さえた。だが、普通の人間なら確実に怒らせてしまっただろう侮蔑の口調も、セフィロトは気にも留めない。
「わたしは、あなたを教育するようにマスターから命令されています。半年間で言葉と礼儀作法を、あなたに徹底的に叩き込むように。マスターの命令は絶対なのです」
無表情な顔で、『徹底的に叩き込む』などと言われると、背筋にぞっとするものを感じる。
「や、やだよ。あたい、家に帰る!」
「帰しませんよ」
完璧な微笑で、セフィロトは言った。
「うわああん」
イライザは閉じ込められていた小部屋から、四つんばいで這い出した。
「『あいうえお』が完璧に言えるようになるまでは、食事もおやつもチョコレートもなしだなんて、ひどすぎるよー」
おまけに、もう二日間も寝ていない。ロボットのセフィロトは夜も眠らなくてすむのをいいことに、朝から夜中までイライザを特訓しているのだ。
「ヒギンズ教授の……バカ。あたいはあんたに教えてもらいたかったのに」
今に見やがれ エンリー・イギンズ
後悔して涙に暮れたって、もう遅い
今にあんたは一文無し 私は金持ち
泣きついて「助けて」だなんて いい気味さ!
今に見やがれ エンリー・イギンズ 見てやがれ!
「五分間、いい空気は吸えましたか?」
きっちり五分ゼロ秒後、セフィロトが部屋から出てきた。「さあ、それでは詩の朗読の続きです。どうぞ」
「ス……スパインのあみゃあ、おんもに、ひらのにふる」
「スペインの雨は、主に広野に降る、です」
いくら間違えても、セフィロトは小バカにしたような表情もしなければ、声を荒げることもない。淡々と繰返しを命じるだけ。
イライザには、ヒギンズ教授の怒鳴り声さえ、なつかしく思えるほどだった。
「では、次は?」
「おまきね、ありがとごぜえました」
「お招きありがとうございました、です」
「ああん、ちゃんと言ってるじゃねえか」
「とんでもない。今のあなたの発音とイントネーションの誤謬率は81%です」
「あんたなんか顔も見たくない。あたいをひとりにして! うわああん」
その夜、疲れ果てたイライザが、とぼとぼと居間に入ってきて、ソファに崩れ落ちるように座った。
「こんなんだったら……花売り娘のままのほうがよかった」
ソファの下に、ヒギンズ教授のスリッパが置いてあった。
イライザはそれを見つけると、そっと手にとって、ぬくもりを確かめるかのように、何度も手の中でこすった。
雫が一滴、目からこぼれてスリッパの上に落ちた。
「イライザさん」
その様子を見ていたセフィロトは近づいてきて、いぶかしげに訊ねた。
「なぜ、そのスリッパを見て泣くのですか」
「あ、あんたには関係ないだろ」
「スリッパに、あなたを悲しませる要素があるのですか。それならば目の届かないところへ片付けてしまいますが」
「あんたは、やっぱり人形だ。人間の気持がわからないんだね」
イライザは、くすくすと力なく笑った。
「人間がものを触って、なつかしくなる気持は、あんたには永久にわかりっこないよ」
「なつかしい……」
セフィロトは、眉をひそめた。
「あなたは、そのスリッパの持ち主であるヒギンズ教授を、なつかしいと思っているのですか。いつも、あれほど罵っているのに」
「人間には、思ってることの反対を言ったりしたりすることだって、あるのさ」
「では、ヒギンズ教授を罵るということは、あなたはヒギンズ教授がお好きだということですか」
「うるさいよ!」
イライザは真っ赤になって、甲高い悲鳴をあげた。
「私はあいつから、りっぱなレディになれるように教育してほしかっただけだ。おまえみたいな無表情な人形なんかじゃなく、怒鳴られてもいいから、ちゃんと心のある人間に」
セフィロトは、しばらく黙っていた。
「すみません」
ようやく、彼は答えた。「わたしにも、心があればよかったのに。ロボットの人工知能ではなく、本物の心が」
イライザの胸がズキンと痛む。そのときのセフィロトの声は、とても寂しそうに聞こえたのだ。
彼は教授の机に行くと、銀の器を持って戻ってきた。
蓋を取ると、中からチョコレートをつまみあげて、イライザの口に入れた。
「ご褒美です。今日は、誤謬率が79%に下がりましたから」
「あ、ありがとう」
「今のは、とてもよい発音でしたよ」
セフィロトは、穏やかに微笑んだ。
特訓は、それからも続いた。
「いいかげんに、眠らせておくれよう」
「だめです。きちんと言えるようになるまでは」
「だって、もう夜中の三時だよ」
「まだ夜中の三時です」
「あんただって、そろそろ充電する時間なんじゃないの」
「あと少しはだいじょうぶ。さあ、もう一度」
「あーとおーど・あんぷしゃーには、ありけーんは・おとんど・うかない」
「違います。ロウソクの炎を揺らすように、Hを発音するんです」
「できない。できっこねえよ、あたいには。苦労せずに何でもできるロボットにはわからねえんだーっ」
イライザが驚いたことに、そのときセフィロトは両手を出して、彼女の手を握りしめた。
その手は、本物の人間のように柔らかく、温かかった。
「イライザさん、確かに私は人間ではありません」
セフィロトは彼女の目を見つめながら、言った。
「でも、人間ではなくとも、人間のことばの美しさを知ることはできます。人はことばで、さまざまなことを表現できます。確かに、犬や猿や海の生き物にも言語があります。でも、それを芸術として高めることができるのは、人間だけなのです」
彼の真摯さに圧倒されて、イライザはものも言えない。
「人の心に浮かんだ美しい考えを、美しい音で表現する。シェークスピアもミルトンも欽定訳聖書も、あなたが話すのと同じことばで書かれたのです。あなたはその崇高なことばに取り組んでいるのですよ」
「……」
「さあ、元気を出して。もう一度」
「……ス」
「なんですか?」
「スペインの雨は……主に広……野に降る」
「……言えた」
「スペインの雨は、主に広野に降る」
「やった。今の発音は誤謬率0%です。雨はどこに降るんですか?」
「広野に。広野に」
「その広野は、どこの国?」
「スペイン。スペイン」
大変な大騒ぎに、ピカリング大佐がベッド(誰のベッドかは問うまい)から飛び出してくると、セフィロトとイライザは抱き合って、踊っていた。
「何が起こったんだ?」
「言えた。言えたんです!」
大声で叫んでいたセフィロトが突然、仰向けにばったり倒れた。
「……すみません、ピカリング大佐。わたしを充電装置のところに連れていってくださいますか」
大佐とセフィロトが去って行ったあとも、イライザはまだ興奮が冷めやらない。
「これで、ヒギンズ教授に褒めてもらえる。今度こそ、あたいに笑いかけてくれるわ」
一晩中でも 踊り明かせる
それでも踊り足りないくらい
体いっぱい 翼を広げて
今までできなかったことも きっとできる
どうしてこんなに 胸がドキドキするの
まるで心臓が 空に舞い上がった気分
あの人が私と ダンスをしてくれたなら
一晩中だって 踊り明かせるわ
次の日。
ドアベルが鳴り、セフィロトが玄関へ出ると、ひとりの清掃人風の男(栂野健園長)が立っていた。
「あっしはアルフレッド・ドゥーリトルというもんですが」
帽子を取り、執事の服を着ているセフィロトに取次ぎを頼む。
「ヒギンズの旦那さまはおいでかね」
「教授は、一ヶ月前からニューヨークの学会に行って、あとしばらくは戻りませんが」
「なんと!」
アルフレッドは、がっくりと外の階段に腰を落とした。
「そいつは誤算だ。せっかくイライザをネタに、たんまり稼がせてもらおうと思ってたのに」
「イライザのことをネタに、強請りにいらしたのですか?」
セフィロトは彼をのぞきこんで、にっこり笑った。
「な、なにを言う」
「口の中で、そうつぶやいておられるのが私の耳まで聞こえましたので。もし差し支えなければ、警察に連絡させていただいて、よろしいでしょうか」
「ぶるぶる。この頃の若者は、気が早くていけねえや」
アルフレッドは、セフィロトの肩に腕を回して、胸をぽんぽんと叩いた。
「父親が娘を心配するのは、当たり前だろう。もしかすると無理矢理ここへ連れてこられて、死ぬより辛い目に会っているかもしれねえって」
「それなのに、お金で解決するのはどうしてです?」
「額に汗して育て上げた娘だ。そこからほんのちょっぴり、おこぼれをもらおうっていうのは、親の慎ましい願いというもんじゃねえか。なに、五ポンドで十分だよ。若い旦那。それ以上でも以下でもいけねえ。人間てもんは、金がないと幸せにはなれねえが、分をわきまえない大金を手にしちゃ不幸になるだけだからな」
「すばらしい。あなたは、旧約聖書のことばに精通しておられるのですね」
「これぞ長年の下町生活で得た、人生の知恵ってもんよ」
「もっと、いろんなことを、わたしに教えてください」
セフィロトは、アルフレッドの隣に座って、わくわくした表情で頬杖をつく。
神さまは 怠けず働けと鉄の腕をくださった
神さまは 鉄の腕をくださったけれど
「鉄の腕? それならわたしも持っています」
「はは。若いのに、たいしたもんだ」
運がよけりゃ 運がよけりゃ
誰かが代わりに 働いてくれる
まっとうな人生 おくるのもいいが
運がよけりゃ 暴れ放題
女は男と結婚し 愛の巣作って世話を焼く
男を釣るため 女はいるが
運がよけりゃ 餌だけ食い逃げだ
「男を釣る? 人間の女性が男性をどうやって釣るのですか?」
「なんだい、そんなことも知らねえのか。イライザをじーっと眺めてみろ。あいつは俺に似て、別嬪だからな。いっぺんで釣られちまうぜ」
『親愛なるヘンリー
こちらは順調だ。
イライザは、みるみるうちに貴婦人らしい物腰とことばを身につけている。きみの読みは当たったようだよ。
この分なら、週末にアスコット競馬場に行くという計画は、実行に移せそうだ。とは言え、まだまだ、うわべだけのレディ。心配の種は尽きないがね。
おっと、きみの真の狙いはセフィロトのほうだったな。
セフィロトは、驚くほど人間らしくなっている。表情も豊かになり、怒ったり笑ったりするときは、人間かと錯覚を起こすほどだ。イライザや使用人たちや、下町の人間たちとの交流が功を奏しているようだ。
ただひとつだけ、心配なことがある。
セフィロトがときどき、イライザのことをじーっと真剣な、思いつめた眼差しで見ている。少なくとも僕にはそう見えるんだ。
ロボットが人間に恋するなどということが、ありうるだろうか?
いや、バカなことを言った。忘れてくれ。とりあえずは、週末のアスコット競馬は、イライザだけではなくセフィロトにとっても大切な舞台になりそうだ。
ピカリング大佐』
『親愛なるヘンリー
残念ながら、アスコット競馬場でのイライザの社交界デビューは、失敗に終わったようだ。
途中までは、うまくいっていたのだよ。セフィロトがくれぐれも、話題は健康と天気だけと言い聞かせていたからな。何を聞かれても、空模様と病気の話題しか話さないように仕向けたのだ。
それから、セフィも……おっと、言い間違えた。実はイライザがこの頃、彼のことを「セフィ」と呼ぶようになったのだ。セフィロトも、そう呼ばれると、どこか嬉しそうでね。ときおり、
「釣られるって素敵なことです」
などと、意味不明のことを呟いている。
……話が横道に逸れたな。セフィも、とてもうまくやっていた。人間じゃないなんて、誰も疑いもしなかったよ。
だが、競馬が始まったとたん、イライザが興奮してしまってね。 とんでもない大声で馬を応援し始めたんだ。
「ケツをからげて、すっとばせーっ」ってね。
いや、今でも思い出すたびに、腹の皮がよじれるよ。セフィは蒼白になってたけどな。
とりあえず、イライザをセフィロトの成長のために利用するという僕たちの計画は、いよいよ最終段階だ。次はもっと慎重にいかなければ。
ピカリング大佐』
『来月ノ 舞踏会ニ 間ニ合ウヨウニ 帰国スル。いらいざヲ、どれすト 宝石デ 飾リ立テテクレ。モチロン、せふぃろとガ えすこーと役ダ。イヨイヨ、俺タチノ 実験ノ 成果ヲ 試ストキガ 来タゾ。 取リ急ギ へんりー・ひぎんず』
トランシルヴァニア大使館での、女王と皇太子を迎えての舞踏会。各国からの賓客が続々と到着する。そして、白のイブニングドレスをまとったイライザと、タキシードを着たセフィロトが腕を組んで現われると、一躍、場の注目の的となった。
アメリカから帰国したヒギンズ教授と、ピカリング大佐は、柱の後ろから二人の様子を、じっとうかがっている。
「しまった。イヤな奴に出くわしたぞ。ピカリング」
「誰だ?」
「昔、俺のロボット研究仲間だったカーパシーだ。俺と同じく言語学者という触れ込みで、上流社会の連中に取り入って、あちこちに出没している。おまけに、ヒューマノイド型ロボットに大反対の立場を取っていて、俺がセフィロトを作ったことも、うすうす感づいているんだ。奴にセフィロトの正体を見破られたら、外国の大使館にロボットを入れたと、大騒ぎになる」
固唾を飲んで彼らが見守っている中、カーパシー(柏所長)は、イライザとセフィロトのそばに近づき、ねぶるような目で彼らを見た。
「はじめまして。カーバシー教授です」
「ごきげんよう。カーバシー教授」
「あなたがたは、ヒギンズ教授のご親戚だそうですね。教授の家に滞在しておられるとか」
「はい、そうです」
セフィロトに教えられたとおり、せいいっぱい完璧な英語と優雅な物腰で応対しようとするイライザと、カーパシーの狙いが自分であることも知らず、彼女を守るため必死で受け答えするセフィロト。
ついに、カーパシーは彼らのそばを離れ、大使夫人のもとに赴く。
「カーバシー先生。あなたは、あのふたりの身元が怪しいとおっしゃっていたけれど、どうでしたの?」
「私の思ったとおりでした。ヒギンズ教授は、とんだ食わせ物です。普通の人間ではないと思っていましたが、やはりそうです。――私の分析によるならば、彼らは、ひそかにお忍びでロンドンに滞在している、外国の王室と縁(ゆかり)のある人物ですな。間違いありません!」
「見たか、カーパシーのマヌケ面を。『外国の王室の人間に間違いない』だと?」
舞踏会から家に戻ってきたヒギンズ教授一行は、おおはしゃぎだった。
「奴でさえ、セフィロトがロボットだということを疑ってもいない。俺の自律改革型ロボットの研究は、大成功だ!」
「おめでとう、ヒギンズくん」
「ああ、きみのおかげだよ、ピカリング」
「何を言う、きみこそ素晴らしかった」
自分たちの功績を讃え合う、ふたりのロボット工学者。その中でイライザは完全に取り残され、落ち込んでいる。
「あ、あの、教授」
見かねて、おずおずとセフィロトが申し出た。
「イライザもすばらしい成功を収めました。皇太子殿下からダンスに誘われたのですよ。誰もが、妖精のようにチャーミングで、完璧な貴婦人だと、褒めちぎっていました」
「それがどうした」
ヒギンズは酷薄にも、そう言い放つ。
「俺にとっては、そんな花売り娘、どうでもよかったんだ。俺が育てたかったのは、おまえだよ、セフィロト。おまえを人間らしく育てることが、今回の実験の目的だったんだ」
「……そんな」
セフィロトは絶句する。
部屋の隅で、イライザがすっと動いた。
ソファの下にあったヒギンズのスリッパを鷲づかみにすると、思い切り教授に向かって投げつけ、部屋を飛び出した。
「イライザさん!」
「どうしたんだ、あいつは?」
憮然とした表情で顔を拭っているヒギンズを、セフィロトはにらみつけた。
「なんてひどいことを、おっしゃるんですか。マスター」
「なんだ?」
「彼女は、あなたのために頑張ったんですよ。あなただけのために。そのことがわからないんですか」
「俺の知ったことじゃないね」
「人間は誰だって、喜んだり悲しんだり、傷ついたりする心があるんです。あなたにとって、他人は全部、自分のために都合よく動く人形なんですか? そんなものは、わたしひとりで十分です――いえ」
セフィロトはぐっと唇を噛みしめて、それから言い放った。
「わたしも、もうごめんです。長い間、お世話になりました」
「なんだと?」
「わたしは、ここを出て行きます。今日からもうあなたは、わたしのマスターではありません!」
呆然とするふたりを残して、セフィロトもまた外へと駆け出した。
「今に見やがれ……エンリー・イギンズ。見てやがれ」
とぼとぼとロンドンの下町を、イライザは歩いていた。
なつかしいコベント・ガーデン。昔、ここで花を売り歩いていた。だが、古巣へ舞い戻ったというのに、かつての仲間たちは誰も、イライザだとはわからないのだ。
彼らとの間にできてしまった大きな溝に、気づかざるを得ない。
イライザは回廊の柱の前で立ち止まった。
「ここで、教授とはじめて出会ったんだわ」
イライザの脳裏に半年前の情景が、昨日のことのように浮かんでくる。
「バカみたい。最初から相手にされていなかったのに。勘違いもいいところよ」
夜も温かい 小さな部屋と大きな椅子
それってすてきじゃない?
たくさんのチョコレートに たくさんの石炭
ほっぺたから足の先まで温かくなる
それってすてきじゃない?
ゆったりと腰をかけて
春が窓辺に来るまで 決して動かないわ
誰かの頭を 膝枕
その温かくて 優しい感触は
私を守ってくれる人
それってすてき すてきなことじゃない?
柱の根元に腰をかけながら小さな声で歌っていると、不思議なことにイライザは、ヒギンズ教授ではない、別の男性の面影が浮かんでくるのに気づいた。
半年間、いつも彼女のそばにいてくれた人。
彼女の口に、ぽんとご褒美のチョコレートを押し込んでくれた人。
温かく優しい手で、彼女の手を握ってくれた人。
彼女の成功を喜んで、居間でダンスを踊ってくれた人。
いつも彼女を見守り、やさしく気づかってくれた人。
「セフィロト……」
イライザの目から熱い涙があふれた。「セフィ」
「はい」
後ろから、聞きなれた声が聞こえる。
振り返ると、柱の陰から茶色の髪をした若者が出てきた。
「お呼びですか」
「呼ばないわよ」
イライザは涙を拭いてから、つんと顔を上げた。
「発音の練習をしてただけ」
「誤謬率はゼロパーセント。完璧な発音です」
「あなたのおかげだわ」
彼はイライザのそばに座り、膝の上に置かれた彼女の手にそっと片手を重ねた。
「ご褒美に、膝枕をしていただいて、いいでしょうか」
貴婦人は、優雅に慎ましく、こっくりとうなずいた。