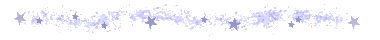FIN
クリスマスを題材にした掌編集です。
ちょっとせっぱつまった人たちが出てくるお話を集めました。
§2 廃園の薔薇
うちのメイドは、夕方から元気がない。
箒を持つ手をときおり止めては、南の斜面に面した窓からぼんやりと、ふもとの村のほうを見やっている。
「そなたが静かだと気味が悪いな。エルゼ」
私は書物から目を上げ、揶揄するようにことばをかけた。
「雹が降るか吹雪になるか。いずれにせよ、ろくなことが起きそうもない」
「あ、はい。ご主人様」
彼女はあわてて振り向き、
「お茶をご所望ですか?」
と、とんちんかんな答えを返す。
……まったく聞いていなかったのか。
私は吐息をついた。
「お茶はよい。掃除の途中だろう。早くすまさぬと夜が明けて、明日になってしまうぞ」
そこまで言って、ようやく気づいた。
明日はクリスマス・イヴだったのだ。
そういえば、村から届く灯りがこのところ華やかさを増していると思った。
エルゼがこの屋敷に奉公に上がってきてから最初のクリスマス。
村にいたころは、家族や友人とこの日を過ごしていたのだろう。歳相応に胸ときめく思いもしただろう。そのときの思い出に、不意に胸をつかまれてでもいたにちがいない。
神の子の御誕生(みあれ)を祝う祭り。色とりどりのまばゆい光に彩られた通り。熱い果実酒のスパイスの芳香。暖かいご馳走。広場ではミサから帰った人々が夜通し笑い、踊る。
私には何の関係もないものだ。
神の創りたまわぬ生命。闇の眷属。吸血鬼の末裔である私には。
「エルゼ」
「はい」
「明日の夜から一日、暇を取らせる。久しぶりに両親のもとに帰り、ゆっくりするがいい」
「え……?」
彼女はみるみる、不安に目を曇らせた。
「どうして、ですか」
「いやなのか?」
「いやです。村に行く用事があれば、昼間にすませています。夜はご主人様のそばにいてお仕えするのが、私の役目です」
「だが、明日は人間にとって特別な夜だ」
「だって!」
彼女は箒を投げ出すと、ずかずかと安楽椅子の私に詰め寄った。
「ご主人さまはおひとりになると、絶対ろくでもないことを考えるんだもの。夜の庭を散歩して薔薇を手折りながら、昔のことを……亡くなられたローゼマリーさまのことを思い出すに決まってるんだもの!」
「そんなことはしない」
「嘘つきの性悪伯爵! そう言っていつもどこか遠いところを見ているくせに!」
彼女はひざまずいて私の胸元にぎゅっと顔を押し付けると、押し殺した声でつぶやいた。
「ご主人様の心の中を全部掃除しちゃいたい……。もう二度と昔の悲しいことを思い出さないように……。私のことだけを見てくださるように……」
「エルゼ」
私はそのことばを聞いて、ようやく悟った。
クリスマスを懐かしむ彼女を見て私がいたたまれなかったように、彼女も追憶にひたる私を見て、辛く感じていたことを。
自分が愚かであることは百も承知だ。だがどうしても、睫毛に涙をたたえているエルゼの細い肩を抱きしめずにはいられなかった。
『 闇の中を歩んでいた民は、光を見た 』
古の預言者が、神の子の誕生を予言した詩だという。
行く手に永遠の闇しか見出すことのできぬ私に、光を受けいれる力があるのだろうか。
人ならぬ者にも、クリスマスを祝う資格があるのだろうか。
腕の中にいるこの娘は、私にとって光そのものだった。
|
FIN
「廃園の薔薇」は掌編集「夏の断片」で初出した、吸血鬼の伯爵と人間のメイドのお話です。
今回のお話は、朧豆腐さんのところの妄想掲示板(笑)のカキコで偶然生まれたネタです。
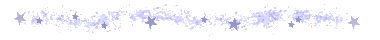
§3 クリスマス・ララバイ
イヴの真夜中、クリスマスツリーの飾りたちが1年にたった一度のおしゃべりを始めることを、あなたはご存知だろうか?
「わたしがこの中では一番の古株じゃな。なにせ1985年生まれなのだから」
木彫りの人形が、ほーほーと髭をしごきながら、得意気に言った。
ほかの飾りたちは「またか」と思ったが、みな謙遜なので黙っていた。それに、相手が赤ら顔の福福しい聖ニコラスでは、威張られる方もさほど腹も立たないというものだ。
「私は1997年生まれですけど」
やや控えめな女性らしい声で、白い布製の天使が話を継いだ。
「エリック坊やの曾おじいさまにあたる方が、幼稚園のクリスマスバザーでそのまたお父さまに買っていただいたという由来があるのですよ」
「あらあら、よく見るとあなた、金髪代わりの毛糸が取れかけているのね」
「それは、エリック坊やのお父さまが3歳のときに、私の頭をぎゅっと引っぱったからですわ」
「男の子のおうちの飾りさんたちは、みな大変な試練の中を通ってこられたのですね」
気の毒そうに、つややかな赤いりんごがため息をついた。
「その点、わたくしはエリック坊やのお祖母さまがお嫁に持っていらした飾りですので、ほらニスだって60年間ちっとも剥げずにおります」
「女の子は、ものを大切に扱いますからね。ここのご一家は総じてものを大切にする方たちだと思いますけど」
「私たちをこんなに長い間、祖父母から孫へと受け継いで大事にしてくださいましたものね」
「長い歴史の中には、悲しい出来事もありました」
木のつるをからめた丸いリースが、静かな口調で言った。
「私は2003年生まれですが、その年は戦争があったのです。ほら、私についているクリスマスらしからぬ黄色いリボン。これは戦地に行った兵士たちが無事帰るようにと願いをこめて飾ったものなのですよ」
「戦争はいやですね」
「本当に、誰にとっても得にならない辛いことです」
「いいですよ、辛くても悲しくても、みなさんにはちゃんと思い出があって」
そのとき木の根元のほうから、とげとげした声が上がった。
「私を見てください、お菓子屋のおまけの、ただのボール紙製のジンジャーブレッドマンです。何の思い出も由来もありゃしない。ただ引越しのときに、おもちゃ箱の底にまぎれてきただけです」
「それでも、きみ」
綿でできた雪が、ふわふわと体を揺らしながら彼を慰めた。
「どんな安物であれ、君はここまで連れてこられて、エリック坊やにこうしてツリーに飾ってもらったんじゃないですか。それは誇りに思わなくちゃ」
「そうです、こんな素晴らしい場所で飾られる栄誉など他にありませんよ」
「それは私も感謝してるんですけどね」
明るい紅白の縞模様のステッキ型キャンディーが、話を暗いほうへ戻した。
「誰にも見てもらえないっていうのは、どうも気がめいってしかたありません」
「ご一家はいつここにお戻りなのでしょう。ねえ、ベツレヘムの星さん」
「私に聞かないでくださいな」
少し涙ぐんだ声で金色の大きな星が答えた。
「一番てっぺんにいるからって、たかが皆さんよりも数十センチ上なだけなんです。皆さんより火星の赤茶けた大地がほんの少し、よく見えるだけなんです」
「家財道具を全部残してあたふたと地球へお帰りになってから、もう何年経つでしょう。どなたか数えた方はいらっしゃいませんか」
「あ、わたしが」
雪の結晶がきらきらと銀粉を落とす。
「私は自分の角を折りながら数えてました」
「だって、あなたの角は6つしかないじゃないですか」
「だからそれが、四周と3つだったんです。だから27年です」
「27年。エリック坊やはどんなに大きくなったことでしょう」
「会いたいですねえ」
飾りたちは、暗く冷たい部屋の中でもまばゆいばかりに輝く蛍光グラスファイバー製のツリーにぶらさがりながら、透明なドーム越しにじっと空に目をこらした。
火星の明けの空には、今まさに小さな星が昇ろうとするところだった。
かつては青く輝いた星。
今は核の連鎖反応で死の大地と化した星。
それでもツリーの飾りたちにとって、それは懐かしい故郷。永遠に愛する人たちがいるべき場所だったのだ。
彼らはまたやってくる1年間の眠りを前に、声を合わせて子守唄のように優しく、こうささやいた。
「エリック坊や。メリークリスマス」
|
FIN
レイ・ブラッドベリの「火星年代記」のモチーフがいくつかあります。
歴史の中で2003年は、後世の人からどのように位置づけられるのでしょう。
そんなことを考えてしまう年の終わりです。
§4 ヒカリ金融
――クリスマスイヴだと言うのに、今日は私の命日になるかもしれない。
玄関から押し入った2人組を見たとたん、睦美はつぶさにそう感じとった。
ヤミ金融。今や巷に悪名とどろきわたるその手の業者に、彼女は一ヶ月前、百万もの大金を借りてしまったのだ。
あちこちのカードの支払いが滞り、あとはお決まりの転落。
あの頃は、頭がおかしくなっていたのに違いない。愛想よく金を用立ててくれるこいつらが、まるで天使のように見えたのだから。
「ミッキー」と呼ばれる男は目の覚めるような金パツをツンツンにおったてて、「ユーリ」は長身黒ずくめのサングラス。なまじ美形であるだけに、凄みのある笑いを浮かべる様は見る者を心底ぞっとさせる。まるで細密な銅版画に描かれた悪魔だ。
今さら彼らの正体に気づいたところでどうなるものでもない。彼らが土足でマンションのあちこちを家捜しするあいだ、睦美はリビングの真ん中でぼんやりと立っていることしかできなかった。払えるお金があるなら、もうとっくに払っている。
「さてと。ほんとにすごい数の洋服だな」
キンパツがからかうような声を上げて、クロゼット替わりにしている奥の部屋から戻ってくる。
「なんとか依存症候群ってやつか」
「そうらしいねえ」
彼らの言うとおりだった。『買い物依存症候群』、それが睦美の病名。
いつもは普通のOLとして地味な毎日を送っているが、一ヶ月に一度か二度、たががはずれたようになり、一流ブティックでかたっぱしから数万から数十万もするスーツやドレスを買いあさる。
ブランドものが好きだとか見栄を張りたいとか、そういうレベルの問題ではない。ただ買うという行為に陶酔しているのだ。だから買ったものはそのまま一顧だにせずハンガーに吊ってある。
翌月カード会社の請求書が回ってきて死ぬほど後悔するが、それもいっとき。またしばらくすると、麻薬中毒患者のようにふらふらと出かけていく。
いずれこうなるのは、時間の問題だった。
気がつくと、ふたりの男はどっかと居間のリビングのソファに腰をおろしていた。
「おい、早くしろよ」
「え?」
「着てるものを全部脱げって言ってるだろ」
顔を見合わせ、ククと下卑た笑いを口の端にのぼらせる。
ああ、そうか。私は今からこいつらに輪姦(まわ)されるんだ。そしてどこかのマンションに閉じ込められて、ボロボロになるまで売春させられる。
妙に醒めた意識の隅でそう考えた。
わかっていながら、その道を選んだのは自分ではないのか。
やり直せるものなら、やり直したい。だが、人生にはリセットボタンなどない。すべてを新しくして一からスタートする術はどこにもないのだ。
みじめな思いにうちひしがれながら、彼女はゆっくりと服を脱ぎ、ついに下着に手をかけた。
「もうそれでいい。まずは、その壁にかかっている青いのからだ」
「なんですって」
黒い長髪の男の指図に、睦美は一瞬あっけにとられた。
「着てみろって言ってんだよ。おまえがうちから借りた金で買った、そのお洋服をよ」
金パツの男が愉快そうに、言葉を引き取る。
「さあ、楽しいファッションショーのはじまりだ」
それから延々と、睦美は自分の買い漁った服を身につける羽目になった。
着替え終わると、歩け、回れ、ポーズをつけろと命じられ、思う存分野次られて、また次の服に着替えさせられる。
さすがにこんなことを一時間も続けると、ふらふらになってしまったが、許しを乞うても彼らは容赦しない。
二時間後、ついにすべての服を着終わり、疲労困憊してぺたんと尻餅をつく。
「これでわかったろう」
黒い服の男が立ち上がり、床に両手をついてあえいでいる彼女を冷ややかに見下ろした。
「おまえは必要以上のものを手に入れ、飽くということを知らなかった。一度も袖を通したことのない服。その服を作るのに、どれだけの人間が夢を見、汗を流したか。おまえはその労苦を、自分のいっときの満足のためにドブに捨てた」
「え……」
睦美は、彼の口から出る意外なことばに驚いて顔を上げた。
「借金のカタに、こいつは全部持っていってやるよ。この世の中には一着のドレスが欲しいと願ってかなえられない女たちがいるんだ」
キンパツが言ったのがまるで合図だったように、数人の黒服の男たちがどこからともなく現われ、あっというまに奥の部屋はからっぽになった。
睦美はよろめきながら立ち上がって、あたりを見渡した。こんなにこのマンションは広かったのか。なんという解放感。
それはまるで、彼女の過去のあやまちがすべて不思議な力によって消されてしまったごとくだった。
「全部いただいたぜ。残ってるのは、一文の価値もないようなボロだけだ」
借用証書をくしゃくしゃと拳の中で丸めながら、黒髪の男がにこりともせずに言い放つ。
「返してほしかったら、借金ミミをそろえて持って来い。それまでは二度とうちの事務所の敷居をまたぐな」
「だけど、ちょっと可哀そうだから替わりにこれをやるよ。俺たちからのクリスマス・プレゼント」
もうひとりが、紙袋を差しだした。
「着てみろや」
その明らかに大衆向けのデパートの袋には、数千円の商札のついた安物のセーターとスカートが入っていた。
だが不思議とそれは、今まで買ったどの高級ブランドよりも睦美のからだにぴったりと合った。淡いブルー系の色も、彼女の白い肌に映えていた。
「よく似合うぜ」
そう言ってにっこり笑う二人組の顔を呆然と見ているうちに、彼女の目から大粒の涙があふれだした。
「ありがとう……」
やっとのことでそれだけ言うと、彼女は両手で顔をおおって、声をあげ泣いた。
「ミカエルさま」
黒ずくめの男は、街を歩く上司の背後から声をかけた。
「なんですか。ウリエル」
「今宵は聖なる御子の誕生の夜。いつもなら私たちも天上でみそば近く、主をほめたたえているはずですのに、さびしくは思われませんか?」
「その務めは、ガブリエルが代わりに立派に果たしていてくれるでしょう」
天使長は、本来の姿をほうふつとさせるような輝く微笑を浮かべた。
「それより、さっきの服は?」
「はい、今頃天使たちの手によって、全世界の貧しい者たちのところに届けられているはずです」
「仕事がはやいですね」
「それはもう。翼がありますから」
ふたりは立ち止まって、雪がちらつきはじめた都会の摩天楼の空を見上げた。
「主も二千年前、光のささぬ貧しい馬小屋の中を誕生の場所と定められました。光は闇の中にいるのが一番似合うのですよ」
「はい、おっしゃるとおりです」
「私たちは、絶望している者のもとに希望を置いてくるようにと、神に遣わされたのです。それはどんなに光り輝く大聖堂にいるよりも、尊いお役目だとは思いませんか?」
|
FIN
これも、「夏の断片」で出てきた「光金融有限会社」の二人組です。
shionさんのずっと以前の掲示板のカキコがヒントになりました。
この掌編集はこれで終わりです。
みなさまも楽しいクリスマスをお過ごしになりますように。