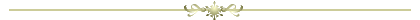ENDE
尊敬するSF作家レイ・ブラッドベリ風を目指してみました(おこがましい)。
「ウは宇宙船のウ」に載っている「駆け回る夏の足音」は、テニスシューズにあこがれる少年のお話です。
§5 ボクはペット
分厚いカーテンの布地をとおして朝の光の粒子が入ってくる。
部屋の隅で丸まって寝ていたボクは、うーんと身体を伸ばした。
彼女のベッドに這い寄ると、幸せそうに眠りこけている彼女のほっぺたをぺろりとなめた。
「う……ん、おはよう、フーちゃん」
「ワン!」
彼女は目をこすりながら起き上がると、にっこりしてボクの頭をなでて言った。
「もうこんな時間。おなかがすいたよね」
彼女が洗面所で顔を洗うあいだも、キッチンでごはんを作っているあいだも、ボクはひとときも離れず彼女の足元にまとわりつく。長い尻尾があれば、もっとボクのうれしい気持ちが表わせるのに、それがちょっと悔しい。
やがて、彼女はボク専用のお皿に水とエサを入れてくれた。
出来合いのドッグフードなんかじゃない、ちゃんと栄養を考えた手作りのエサだ。
ボクが床でぴちゃぴちゃ食事をしているあいだ、彼女は目を細めながらボクを見ている。
食事が終わると、お風呂場でボクのからだをきれいに洗ってくれて、朝の日課は終了。
彼女は、家で何かを書くお仕事をしている。若いけれど「先生」とほかの人間に呼ばれているらしい。
とても集中力の要るお仕事なので、彼女が机の前に座るとボクは静かにしていなければならない。退屈だ。
「ク〜ン」
玄関のドアを爪でガリガリかいていると、
「お外に出たいの?」
と扉を開けてくれた。
「うわあ、いい天気」
早い秋の訪れを思わせる高い空をまぶしそうに見上げる彼女の首筋は、とても綺麗。
「あまり遠くまで行っちゃだめよ」
「ワン!」
承諾の意味で一声鳴くと、ボクはトコトコ走り出した。
四足で歩くのがへたくそだったボクが一匹で散歩に出られるようになったのは、つい最近のことだ。車に気をつけながら、いつものコースを通る。
電柱でおしっこをしたいけど、おまわりさんに怒られたことがあるから、我慢ガマン。
通学途中らしい、制服を着た男子生徒たちに会った。
「あ、あいつ」
奴らはボクを見つけて駆け寄ってきた。
「フミアキじゃねえか」
ボクを取り囲んだ人間たちの目を、だまってじっと見上げた。
昔はボクを見ると、よってたかって蹴ったり、なぐったりしたこいつらも、彼女からもらった首輪をつけているボクには何もしなくなった。ボクは彼女のものだから。
のんびりと、長く伸びた毛をペロペロなめて身づくろいしていると、すぐに奴らは怯えたような顔をして行ってしまった。残されたボクはまた平然と、歩きだす。
「おかえり、フーちゃん」
散歩から帰ると、彼女はニコニコしてドアを開けた。
玄関で、汚れた手や足を濡れタオルでふいてくれる。
「お散歩、楽しかった? どんなものを見たの?」
ボクの5本の指の間も丁寧にぬぐいながら、彼女は話しかける。
ボクがしゃべれていろんなお話ができたら、どんなにかいいのに。そう思うと、ひどく悲しくなる。
彼女とはじめて会ったのは、線路のわきだった。
電車に飛び込もうとしていたボクを必死になって止めてくれたのが彼女。
高校の同級生の執拗なイジメに人間の尊厳をずたずたにされ、ことばを失い、教師も親も医者も怖くて、あいつらと同じ人間であることにさえ絶望したボクを、彼女は家にひきとって面倒を見てくれた。
「人間として生きられないのなら、人間以外のものになってもいいから、生きて」
彼女はボクに生きる意味を与えてくれた。
ボクは彼女のためだけに、生きられると思った。
楽しい1日が終わって彼女が眠りにつくと、ボクは暗闇の中で長いあいだ彼女の寝顔を見ている。
ときどきそっと起こさないように、彼女の白い手を舌でなめる。
「アイシテル」
そのことばを彼女に伝えたいと、いつか心から願ったとき、ボクは人間に戻れるのだろう。
|
ENDE
人間に変身する猫が出てくる短編を書いたあと、このお話を思いつきました。
猫の話は近日アップ予定。
§6 ヒカリ金融
高坂はふたりの黒服の男の前で震えていた。
無理もない。彼の前には300万円もの債務証書がつきつけられているのだ。
「わ、わたしがおたくに借りたのは、30万だったはずだ。それがたった1ヶ月で10倍になるなんて」
「ああ? なにフザけたことぬかしてんだよ」
眼前の金パツの男がテーブルをばんと叩いて、凄む。
「こちとら商売なんだよ。だいたいうちの利子が高いことくらい、百も承知だったんだろう? 借りるあてがなくてうちに泣きついてきたくせに、今さら何をしらばくれてんだ!」
彼の言うとおりだった。不況のどん底、不渡りを何度も出しかけた会社の金策に走り回って、もうカードローンも消費者金融も借りられるところはすべて借りてしまった。
あと残るのは、ヤミ金融と言われる不当な高利をむさぼる業者だけだったのだ。
「まあまあ。ミッキー」
それまで背後に隠れるようにして座っていた男が、仲間の肩をぽんぽんと叩く。
「そんなにびびらせたら、片付く話も片付かねえだろ。おまえはすぐアツくなっていけねえ」
と諭すように言うのが、通称ユーリ。黒いロン毛の男。
日本人のくせにふざけた名前だが、ふたりとも本名を知られたくないほどあくどいことをしているのだろう。
金を借りに来たときは、天使のように微笑んでいたのに。
いや、あのとき通常の精神状態ではなかった高坂にとっては、金を貸してくれる者はすべて天使に見えていたに違いない。
今は、悪魔だ。
残酷な笑いを顔にへばりつかせ、魂さえもしゃぶりつくす悪魔。
「どうするよ」
「そうだな。こいつには息子しかいねえから、娘をソープに売り飛ばすってワザも使えねえしな」
「もうめんどっちいから、車道に突き飛ばして保険金いただくってことにしようぜ」
失禁寸前なほどガクガクと膝をならしながら、それでも高坂は頭の隅で思う。
いっそのこと、本当に殺してくれたほうが、どれだけ楽になることか。
もうこの世に未練などなかった。
生きていても、社員や債権者の皆様に申し訳が立たない。
そうだ。死のう。ここを出たらすぐ、どこかのビルから飛び降りよう。
「あんたさ。今死ぬこと考えてただろ」
気がつくと、金パツの男がまっすぐに彼の目をのぞきこんでいる。
「え?」
「わかるんだよ。こういう商売やってっとさ。目がすわると言うか、影が薄くなると言うか」
「てめえだけ楽になろうなんざ、いいご身分だな」
ロン毛の男が、不機嫌に後を引き取る。
「てめえの息子が今何してるか知ってるのか。大学の友だちのところを駈けずり回って、五千、一万と借りては社員の未払いの給料を払おうとしてんだぞ」
「え……?」
「てめえの女房もな。毎日債権者の電話におびえながら、それでも平気な顔してるだろ。もう三ヶ月も給料入れてないのに、せいいっぱいのご馳走を作ってよ。てめえのその脂ぎった体が心労で倒れないのは、女房の気遣いのおかげだってことが、わからねえのかよ」
「あ、あんたたち、何を……」
金パツの男がテーブル越しに、グイと彼の胸倉を掴む。
「あんたには、その愛情に応える責任があるってことだよ。中途半端なリタイアは赦さねえ。あがいて、あがいて、みっともなく生きてみやがれ。死ぬのはそのあとだ!」
そして、高坂を突き飛ばすと、激昂してテーブルの上の債務証書をくしゃくしゃと丸める。
「300万、耳をそろえて持ってくるまでは、二度と俺たちの前に顔を出すな!」
雷鳴のようなその怒鳴り声に、高坂は鞄をひっつかむと一目散に事務所を飛び出た。
路上に出ると、さっきまで自分がいたビルを見上げる。
『光金融有限会社』
窓に張られた看板を見つめながら、高坂はひとり首をひねった。
いったい、今のできごとは何だったのだろう。
不思議なことに、さっきまでの絶望した気分はウソのように消えていた。
そうだ。早く家族のもとに戻ろう。死ぬなんてとんでもない。
3人で力を合わせれば、なんとかなる。借金は何年かかっても少しずつ返していけばいいんだ。
高坂は、瞳に新しい力をみなぎらせて、夏の灼熱の舗道を歩き始めた。
高坂が出て行ったあと、ふたりはおだやかに微笑み合った。
「ミカエルさま。堂に入ったヤミ金融業者ぶりでしたよ」
ロン毛の男がからかうように言う。
「やめなさい、ウリエル。ほめことばになっていませんよ」
「それにしても我らの主は、とんだことを天使たちにお命じになったものです。罪人たちを教会で待っていてはならない。罪のただ中に出て行って、彼らを救いなさい、とは」
「天使は人間たちの目の届かぬところで、神の命令を行うことが本業です。ウリエル。彼が置いていった10万をこっそり彼の家に戻しておきなさい。奥さんが隠したまますっかり忘れていたへそくりか何かに見せかけるのです。
それから、ラファエルが確か悪徳弁護士に偽装するのが上手でしたね。ほかのヤミ金融業者が彼を苦しめぬよう、こっそり脅かしておくように命じなさい。
なんだか、でも……」
天使の長は、コキコキと首を鳴らしてから、にっこり笑った。
「このお仕事、ヤミつきになりそうで怖いです」
|
ENDE
「天使の高利貸し」は、鹿の子さんのメールの中に書かれていた一文から生まれたネタです。
鹿の子さんは「8月31日主義」で、私は「夏の断片」で同じテーマで掌編を書くことにしました。
ありがとうございます〜。