「EWEN」&「魔王ゼファー」クロスオーバー企画
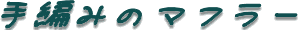
|
第1回 (1) ディーター ミルク色の霧がたちこめている。 吐く息よりも粒子の細かい、とろりと濃密な湿気は、生まれ故郷の北アイルランドを思い出させた。 なだらかな坂を上がっていくと、墨絵のように、黒ずんだ木々の間に病院の灰色の建物が見えてくる。 病院はきらいだと言い続けているのに、一生縁が切れそうもない。もっとも今日は自分の治療のためではないのが、わずかな救いだが。 「精神科の霧島先生は、ご在室ですか」 診療時間の終わった静かな午後のロビーで、けだるげな姿勢のままコンピュータに向かっていた女性に話しかけた。 声だけですっかり日本人だと思われていたのだろう、視線を上げて俺の顔を見ると、彼女は一瞬驚いたように口をぽかんと開けた。 この国に14年も住むと、こういう反応にも慣れっこになってくる。 「し、診察ですか?」 「いいえ。葺石惣一郎博士からの預かりものを届けに来ました、グリュンヴァルトと言います。前もってメールでアポを取ってあるのですが」 「少々お待ちください」 受付の女性は、慣れた手つきで受話器を耳に当てた。 確認が終わると、俺にむかってうなずく。 「診察室のほうへどうぞ。4階のエレベータの右手になります」 病院は、どこも同じ空気がする。 清潔そうな消毒アルコールの中に、ほんのかすかに混じる尿の臭い。最先端の科学と太古から紡がれてきた人間の生と死が混じり合う、矛盾だらけの空間。 説明のとおりに進み、霧島医師の名を書いたプレートがはめてあるドアを見つけた。 ノックしようとすると同時に内側からドアが開き、ひとりの男が出てきた。 アジア人の年齢は見かけではわからないが、俺より少し年上に見える。毛先が少し遊んでいる漆黒の髪と細い面立ち。 印象的な男だった。とりたてて着ているものが上質と言うわけではないのに、なぜか身分の高い人間のような雰囲気を漂わせている。 彼は軽い会釈をすると、俺の脇をすりぬけ、エレベータに向かって歩いていった。 ドアの内側には、黒縁の眼鏡をかけた白衣の医師が立っていた。 「よくおいでくださいました。グリュンヴァルトさん。霧島です」 「すみません、診察のお邪魔をしたでしょうか」 「いえ、彼は患者ではありませんよ。ときどき遊びに来てくれる、わたしの友人です」 握手をし、明るい室内に招じ入れられた。 勧められた椅子に座る前に、今日の来訪の目的、ドイツ語の蔵書が数冊入った紙袋を渡す。ドクトル・フキがずっと以前から頼まれていたものだ。 「重いのに、わざわざすみませんでした」 「いえ、東京には仕事で来たついでですから」 「葺石先生とは、こっちで学会があるたびに飲み仲間に入れていただいてるんですよ。ともかく、はちゃめちゃに楽しい思いをさせてもらってます」 さもありなん。苦笑している俺に、 「酒がほどよく入ってくると、いつも決まったようにおっしゃるんですね。『俺は最高の息子を持った幸せ者や』って」 からかうような笑み。 「今日あなたにお会いして、先生がそうおっしゃった意味がわかりましたよ」 どんな表情をすればよいのかわからず、そのまま微笑み返した。 用事が終わればすぐ辞するつもりだったのに、気がつくと30分ほども雑談を交わしていた。 すぐれた精神科医だと思う。彼の診療を受けることのできた患者は幸運だ。ドクトル・フキに出会うことのできた俺と同様に。 戸外に出ると、もう霧はだいぶ晴れていた。病院をぐるりと取り囲んでいる冬枯れの林が、わずかな緑のしずくを陽光にきらめかせている。 このまま駅に向かえば、円香と聖との待ち合わせ場所にちょうどいい時間に着けるだろう。 歩きながら、さっき彼から聞いたことばを思い巡らしていた。 『俺は最高の息子を持った幸せ者や』 円香の父親は確かに本心からそう言ってくれているのだろう。あの人はそういう人だ。その点は掛け値なしにうれしい。 だとしても、俺にはやはり、円香はもっと普通の男と結婚していたほうが、よほど幸せだったのではないかと思える。普通の日本人で、精神をわずらったことがない、テロリストの過去も持たない普通の男。そうであってくれたほうが、葺石家はよほど平和だっただろう。 正門に向かって、ゆっくりと林のあいだを抜けるなだらかな径を下っていくと、突然木々の間から声をかけられた。 「おい、そこの背の高いやつ」 びっくりして振り向くと、男が木の幹にまたがって、じっとこちらを見下ろしていた。 さっき霧島医師の部屋のドアのところですれ違った男だ。 「手伝ってくれ。おまえくらい背が高ければ、台に乗らなくても届くだろう」 「なにを?」 彼は、右手に持っていたのこぎりを、少し振って見せた。 「この大きい枝を付け根のところから切らなきゃならない。切る間、枝全体をつかんでいてくれればいい。ひとりでやると、先がゆらゆら動いて切りにくいんだ」 「――わかった」 命令することに慣れている人間だと思った。急いでいると拒否することもできたはずだが、考えるより先に身体が動き始める。 横渡り2メートルくらいのかなり太い枝だった。彼の言うとおりに両手で下からしっかりと支えてやると、小気味良いのこぎりの音がしゅるしゅると響く。 ものの2分も経たないうちに、枝は幹からすっぱりと離れた。 「すまんな」 切り離された枝をゆっくりと地面に置くと、男ははしごを使わずにひょいと飛び降りた。 「助かった。今日霧島先生に頼まれたんだ。林の中に一本、危険な枝があるから切っておいてほしいって。危険というのはつまり」 「ああ。わかるよ」 俺は、彼の切り取った痕の、ごく滑らかな断面を見上げて答えた。 「ちょうどいい高さの枝だったからな。俺の入院していた病院でも、裏庭にあった木が切り倒されたことがある。そこでふたりの患者が誘われて、首を吊った」 「ふうん、それは確かに誘うような枝ぶりだったんだろうな」 考え込むように顎をなでると、彼はふと俺の顔をまじまじと見つめた。 「よく見ると、おまえ日本人じゃないな」 「ああ。ドイツ人だ」 「ことばがうまいから、わからなかった。俺はこの世界の人種の違いというのに、疎いんだ。俺の目から見ると、日本人もドイツ人もほとんど変わらない。結局は魔族でも精霊でもない、同じ人間だからな」 そうだろう? そう言って、彼はにっこりと白い歯を見せて笑った。 (2) 円香 突然、がくんという軽い衝撃とともに、エレベータが止まった。 しばらく待ってみたが、動き出す気配がない。それどころか、天井の蛍光灯さえ暗くなってしまった。 「ええっ。なんやの。ほんまの故障?」 私はげんなりとして、叫んだ。操作パネルの赤い非常ボタンの蓋をひっぺがして、何度も押したが、答えは返ってこない。 まいった。 ディーターと聖との待ち合わせまで、あと一時間ある。それまでの暇つぶしにと、駅の近くのモール街をぶらつこうなどと思ったのが、間違いだった。 エレベータは1階と地下1階のちょうど中間で宙ぶらりんになっているらしい。どんどんと扉を叩いたが、外から返事があるはずもなく。 念のために携帯を試してみたけれど、やっぱり通じなかった。 「はああ、最悪」 ため息をついてから、ふと後ろを振り向く。 このエレベータには、私のほかにもうひとりの乗客が乗っていた。30歳代半ばくらいかな。かなり美人な、ショートカットの女性。 彼女は私と目が合うと、小首をかしげて微笑んだ。 「困りましたねえ」 その穏やかな口調は、全然「困った」という感じではない。こちらの気分まですっと落ち着いて、ひとりであたふたと騒いでいることが急に恥ずかしく思えた。 「非常ボタンを押したから、係の人が見つけたら、すぐ応答してくれるはずやねんけど」 「そうね。それまで待つしかなさそうですね」 私は覚悟を決めた。じたばたしても、始まらない。 「ねえ、座りません?」 と誘う。今日は、臨床心理士の全国研究発表会ということで、気合の入ったスーツを着ていたのだけれど、ためらわずストンと床に腰をおろした。 「誰も見てへんし。助けが来るまでゆっくりくつろぎましょう」 「ええ、そうね」 その美人さんも、同調して腰をおろした。 「なんだか、不思議な気分ですね。エレベータの中って立つものなのに、こんな風に座るなんて。なんだか別の空間みたい」 「貴重な経験かもしれへんね」 「関西ご出身?」 「はい、兵庫県の西宮から。東京へはこの週末、息子と夫といっしょに来てるの」 「ええっ。結婚してらっしゃるんだ。……学生さんだと思ってました」 むむ。やっぱり。 30を過ぎても相変わらず私の童顔は健在。11歳の息子と5歳の娘がいると言ったら、一度冗談だと思われて、大笑いされたことがあったっけ。 「ねえ。もしよかったら」 彼女は、持っていたバッグの中をごそごそし始めた。 「ここで、ピクニックしません?」 「はい?」 差し出された掌に乗っていたのは、ラップに包まれた大きな三角形のおにぎりだった。 (3) 聖 お父さんとお母さんに全然つながらないので、僕はあきらめて携帯をしまった。ドイツ語と日本語でそれぞれにメールを打つのは、めんどくさい。 待ち合わせの場所に約束より一時間も早くついてしまったのだ。閉会式が予定よりずっと早く終わって、解散もそれだけ早くなった。師範と仲間たちは、そのまま新幹線で関西に帰ることになっているけど、僕だけがひとり、別行動を許可してもらっている。 秋の三連休を使った全国選抜の少年剣道錬成会に参加するため、僕たちはおとといから東京に来ていた。 同じく、お父さんはテレビの殺陣の仕事で、お母さんは、仕事の会合で東京へ。こんなチャンスはめったにないので、全員の用事が終わる3時に駅前で待ち合わせ、ということになっているのだ。 実は内緒だけど、今晩はホテルにもう一泊して、明日は3人でディズニーランドに行くことになってるんだよね。もちろん学校はズル休み。 われながら子どもみたいだけど、けっこうわくわくしている。妹抜きでお父さんやお母さんと行動できるのは、本当に久しぶりなんだ。 妹はまだ5歳。さんざん迷ったあげく、友だちの誕生パーティのほうを自分で選んだわけだから文句は言えないけど、おじいちゃんといっしょに玄関で見送ってくれたときは、ちょっと泣きそうになってた。 楽しさをひとり占めするうしろめたさもあって、そうだ、妹に何かおみやげを買ってあげようと思いついた。 駅のコインロッカーにバッグを預けて(竹刀は友だちに頼んで、持って帰ってもらっている)、さっそく行動開始。 女の子って何を喜ぶんだろう。もしこれが男なら、アメコミのモンスターのフィギュアなんかで決まりなんだけど。こんなもん買って帰ったら、あいつは怒るだろうな。 結局、東京って言ったって、神戸や大阪で買えないほどめずらしいものは全然ない。 ようやく一軒の店でそれなりに可愛い小物を見つけたころには、待ち合わせの場所からだいぶ離れてしまっていた。 すぐそばは川沿いで、公園になっている。 自動販売機で缶入りのホットレモンを買うと、誰もいないベンチに座って、棒になった足を投げ出した。 それにしても、寒い。東京は関西よりずっと寒いみたいだ。まだ11月の終わりだというのに、手がかじかんでしかたがない。 背中を丸め、暖かい缶を両手に抱え込むようにして飲んでいると、向こうからひとりの女の子が歩いてきた。 僕と同じ年くらいだろうか。温かそうな手編みのブルーのマフラーをくるりと首に一巻きして、紺色のチェックのコート、手には黒い猫を抱いている。 髪の毛は真っ黒のストレート、肌が雪のように白い。まっすぐ前を向いて、きりりとした目をしていて。 思わず見とれそうになって、あわてて顔をそむけた。女の子は、僕の座っているベンチのそばを通り過ぎていった。 抱いている猫に話しかけている様子。そこまでは、別に不思議でもなんでもない光景だった。 問題は、その次だ。 『今日は姫さまにつきあっている暇はニャいんです。わたしには大事な使命があるんだから』 「え、ええっ」 猫が、ことばをしゃべっている。 僕は思わず缶を落として、ベンチから立ち上がっていた。 |