「EWEN」&「魔王ゼファー」クロスオーバー企画
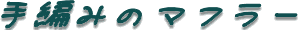
|
第2回 (1) 雪羽 「その猫、今しゃべったよね」 驚いた表情を浮かべてベンチから立ち上がった男の子を見て、しまったと思った。 まさか、ヴァルとの会話を聞かれていたなんて。普通の人間には『にゃお』としか聞こえないはずのヴァルのことばを。 彼は普通の人間ではないのだろうか? 確かに、異国風の顔をした子ではあるけれど。 「気のせい」 あたしはそっけなく言って、なんとかこの場を逃げ出そうとした。でもヤツはすぐあとを追ってきた。かと思ったら、地面に落とした缶をあわてて拾いに戻って、ゴミ入れに捨てて、また走って追いついてきた。 「そんなことない。何を言ってるかわからなかったけど、でも確かに人間のことばだったよ」 背が高いからてっきり中学生かと思っていたけど、話す声はまだ高い。もしかすると、あたしと同じ小学生なのかもしれない。 「あたしが、猫のかわりにしゃべるふりをしていただけだ」 「うそだ。だって同時にしゃべってたじゃないか」 母上が編んでくれた手編みのマフラーに、彼の手が触れた。あたしは立ち止まり、きっと振り向いて怒鳴った。 「無礼者!」 「あ、ご、ごめん」 彼はとたんに手を引っ込めて、恥ずかしそうにうなだれた。 「ごめん、もう絶対さわらないから」 そうやってしょんぼりしたのを見て、心臓がとくんと跳ねた。睫毛が長くて、上目使いにこちらを見ている目は透きとおった茶色。今まで見たこともないほど、キレイな色だった。 本当にこの世界の人間ではないのかもしれない。興味がわいてきて、思わず聞いてしまう。 「おまえ、もしやアラメキアから来たのか?」 彼は、けげんそうに頭を振った。「知らない。アラメキアって?」 「知らないのなら、よいのだ」 「ねえ、アラメキアってどこだよ。ヨーロッパ? ドイツ? それならオレ、そっちから来たかもしれない」 と食い下がってくる。それを聞いて、あたしは首をかしげた。 「お父さんがドイツ人なんだ」 「日本人ではないのか」 「お母さんは日本人。だからオレも生まれたときからずっと日本に住んでて、ドイツの地名なんかはよく知らないんだ」 「どちらにしても、アラメキアはドイツなどではない。この地球上の国ではないからな」 「地球じゃ、ない?」 「こことは異なる世界。精霊が治める、魔族や妖精たちの住む国だ」 『姫さま!』 ヴァルが、甲高い声を上げて抗議する。『見知らぬ人間に、そのような秘密をお話しニャさって、よいのですか?』 「あ、猫がまたしゃべった」 しっかり現場を目撃されてしまう。今度こそ言い逃れできないではないか。ヴァルの粗忽モノめ。 「いっぺん抱かせてくれない? すごく可愛い」 彼が両手を伸ばすと、ヴァルは牙を剥きだした。 「いてっ。噛まれた」 そのまま、あたしの腕をすりぬけて地面に飛び降り、さっさと駆けて行ってしまった。ヴァルはコイツが気に入らないのだろう。 男の子は、痛そうに噛まれた手の甲をさすりながら、 「追いかけなくていいの?」 「よい。用事を言いつけるときは、ちゃんと戻ってくる」 「ふーん、賢いんだな」 「あいつは、父上とあたしの家臣なんだ。アラメキアから来た」 あたしは、さぐるように彼の顔を見上げた。 「あたしの父上は、アラメキアで魔王だった。人間や精霊との戦いに敗れ、追放されてやって来たこの地球で、母と結婚し、あたしが生まれたんだ」 どうして、こんなことまでペラペラ話しているのだろう。 自分でもわからなかった。でも、たぶんここまで聞いたら、あたしのことを頭のおかしな人間だと思って、逃げ出す。それか、思い切り鼻で笑われる。今までだってそうだった。 みぞおちのあたりにチクリとする痛みを感じながら、あたしはそう考えていた。 でも、その子は笑わなかった。馬鹿にした目で見ることもなかった。考えこむような表情で、話を聞いているだけだった。 「あたしの言ったことを信じるのか?」 「それは……よくわからない」 彼は、肩をすくめるようなポーズをした。 「たしかに、普通なら冗談だと思うよ。でも、心から信じている人の話すことだったら、どんな不思議な話でも信じられる。 オレ、きみに会ったばかりで、きみのことをよく知らないし、情報が足りなくて、どう考えればいいかわからない。でも……」 にっこりと笑いかける。 「その話、信じたいと思うよ」 あたしは、息が詰まってとっさに返事ができない。頭の中でぐわんぐわんと鐘が鳴っているようだ。 気がつくと、現実に着メロが鳴り響いていて、彼がポケットから携帯を取り出しているところだった。 『Vater』 と言ったあと、全然わからない言葉でしばらく会話して、また携帯をしまった。 「今のは何だ?」 「ドイツ語。お父さんからかかってきたんだ」 「お父上といつも、ドイツ語で話しているのか?」 「たいていはね。それか英語。お母さんとは日本語で話してる。あ、それから」 とっても得意げに胸をそらした。「関西弁もしゃべれるよ」 あたしは、それを聞いてようやく納得した。 彼がヴァルとの会話を「にゃお」ではなくて、「ことば」として聞き取れたのは、普通の人間よりずっとたくさんの「ことば」に囲まれているからなのだろう。 「で、オレの名前、聖・グリュンヴァルトっていうんだけど?」 あたしのことをまっすぐに見ている。こんなに心の中まで入ってくるような目で見られるのは初めてだ。 「あ、あたしは瀬峰雪羽」 「じゃあ、雪羽、これで時間はたっぷりできたから、もっと話してくれる?」 「何を?」 「アラメキアの話に決まってるじゃないか」 (2) ゼファー こいつは、俺に似ている。不思議なことに、会ったときからそう直感した。 その背の高いドイツ人と俺は、駅までのなだらかな坂道を歩きながら、どちらともなく言葉を交わしていた。 途中で携帯を取り出すと、外国語でひとことふたこと話をした。 「息子なんだ。別の用事で東京に来ている。誰か友だちと会ったらしく、待ち合わせの時間を延ばしてくれと言ってきた」 と俺に説明した。 自分の息子にしては、話し方がどこかよそよそしいように感じたのは、俺の勘違いか。それとも、父親と年頃の息子というのは、そんなものなのかもしれない。俺には娘しかいないからわからないが。 「息子とは、自分の国のことばで話すのか」 「小さい頃から、そうしてる。日本に住む以上、ドイツ語が役に立たないのはわかっているんだけどな」 と肩をすくめる。この国で異邦人として暮らしていると、せめて子どもには自分のことばだけでも伝えたくなるものらしい。俺が雪羽に魔族のことばを教え込んだように。 それから俺たちは自然のなりゆきで、自分のことを語りだした。 互いの名前。どういう経緯でこの国に来たのか。霧島先生とは、どういう知り合いなのか。 それは俺にとっては、自分につけられている不愉快な病名を打ち明けることでもあった。自分を異世界の魔王だと思い込む、妄想型の統合失調症。 その結果浴びることになる奇異なものを見る視線を身体の片側を固くして待ったが、答えは意外なものだった。 「俺も、DIDだったんだ。入院してたと言ったろう? 全部で3回、4年間病院にいた」 「DID?」 「解離性同一性障害。多重人格といったほうがわかりやすいか」 「聞いたことがない。この世界には、いろんな病名があるものなんだな」 「たぶん、人間の数だけ病名はあるよ」 そいつは青緑色の瞳で俺を見て、笑った。 似ているはずだ。別の世界から来た異邦人というだけではない。精神を病んだ人間というレッテルを貼られていることまで、俺たちふたりは同じだったのだ。 「仕事は何をしているんだ?」 そんな素性なら、外国人の風貌をしている分、生きるための糧を得るには俺以上に苦労していることだろう。 コンピュータのプログラマー、と彼は答えた。 「でも、今はそれ以外のいろいろのほうが忙しいかな」 「それ以外のいろいろ」というヤツが、実は曲者だったのだ。 ディーター・グリュンヴァルトとは、その業界ではかなり有名な男だったらしい。あとで娘の雪羽に彼のことを話したら、ひどく怒られた。 『なんで、サインをもらってきてくれなかったんだ。何年か前に大ヒットした『レジェンド・オブ・サムライ』というハリウッド映画のことを、父上は知らなかったのか』 雪羽はなぜか、小さい頃からテレビの時代劇を見るのが大好きだ。だから言葉づかいもすっかり時代劇風に染まっている。 だがそのときの俺は、「コンピュータ」ということばに注意を奪われ、それ以上のことを尋ねるのを忘れてしまっていた。 「コンピュータのことがわかるなら、これを見てくれないか」 上着の内ポケットに入れておいた、折り畳んだ薄い書類を取り出して、渡した。 「これが何の図面か、おまえならわかるんじゃないか?」 広げると、彼は真剣に細部に見入っていた。 「コンピュータの図面には見えないな」 しかし2枚目の紙をめくると、金色の眉を少しいぶかしげに寄せた。「これ……今年の春発売された、ゲーム機の設計図じゃないか?」 「ゲーム機?」 「ああ、外見はこんな感じだ。息子が欲しがっていたから覚えている。5万円もするのに、生産が追いつかないくらい爆発的に売れていると聞いた」 「そうだったのか」 いろいろな考えが俺の中でめぐって、もう少しでパチリと正しい場所にはまりそうな気がする。 「実は……」 『コージョーチョー!』 そのとき、聞き覚えのある声がした。 人間の姿のヴァルデミールだ。長い黒髪をばさばさと揺らして、走ってくるところだった。 『とうとう、見つけ……』 俺のかたわらにいるディーターに気づいて、「あっ」と口を開き、牙を剥きだす。 『こいつニャんだか、姫さまにベタベタしてたガキと、そっくりのニオイですよ』 『雪羽に?』 『そうですよ。こいつもきっと悪いヤツだ』 『……それより、何を見つけたんだ』 そちらも気になるが、こちらのほうが大事だ。先をうながすと、ヴァルデミールは得意げに胸をそらして、予想どおりの返事をした。 『もちろん、コージョーチョーが探してらした、テキの本拠地です』 (3) 佐和 「おいし〜い!」 関西から来たというその女性は、指についているご飯粒までなめた。まるでゼファーさんみたいに、おいしそうに食べる人。 「こんなおいしい鮭のおにぎり、初めて食べた。なにかコツがあるの?」 「ううん、別に普通に握ってるだけ」 「スパイスは愛情、ってヤツかなあ。いつもバッグに入れて持ち歩いてはるの?」 「ただの習慣なんです。娘が小さい頃からの。娘も主人もおにぎりが大好きだから」 私たちはその調子で、停電したエレベータの中に座り込んで、時ならぬピクニック。ずっとおしゃべりに花を咲かせていた。 彼女の名前は、円香・グリュンなんとかさん。ドイツの方と結婚しているそうだ。本当に楽しそうに笑い、聞くときは真剣に聞いてくれる。私もだんだん彼女のペースに引き込まれて、時間さえ忘れるほどだった。 「円香さんて、とても聞き上手なのね。私、これほどしゃべったのは久しぶりです」 「ほんま? よかったあ。いつも「おまえは、しゃべりすぎや」って、上司に怒られてるから」 彼女は、ぺろりと舌を出す。 「私、臨床心理士の仕事をしてるの。だから、相手の話を聞くことは職業みたいなもん。あ、臨床心理士っていうのは」 「わかります。私の主人も、とてもお世話になったから」 私は、うなずいた。 「主人は若い頃、病院の精神科にかかっていたの」 「へえ、奇遇やなあ。うちの旦那サマも、ずっと心の病気で入退院を繰り返したことがあるんよ」 「え、ほんとう?」 「うん、だから私がこの仕事についたのは、旦那サマのおかげ。今はときどき私の相談にも乗ってくれるし」 「そうだったんですか」 「佐和さんのご主人は? もうすっかり、よくなられたの?」 「ええ。でも――」 そのとき前触れなしに、天井のライトがぱっと明るくともった。 ついで、スピーカーから、あわてた男性の声が聞こえてくる。ようやく、ビルの管理室の人が気づいてくれたのだ。 エレベータはすぐに上に上がり始め、1階に着いた。閉じ込められていたのは20分くらいだったろうか。そんなわずかな時間でも、扉が開いたときの開放感は胸にしみるほど心地よかった。 係員が扉の前にいて、ぺこぺこと謝ってくれた。ブレーカーが上がってしまったことによる停電らしくて、原因はただいま調査中、とのことだった。 「やれやれ、よかったねえ。ひどい目に会ったけど」 彼女はまるで遊園地のアトラクションから出てきたみたいな調子で、言った。「でも、楽しかったね」 「ええ」 私もいつのまにか、彼女と語り合えるひとときをくれた停電に、感謝したくなっている。 「あ、聖から着信? ディーターからもメール来てる」 円香さんはしばらく、エレベータの中で使えなかった携帯をチェックしていたが、 「なんだか結局、待ち合わせの時間が延びることになったみたい。焦って損した」 「まあ、そうですか」 「佐和さん、急いでる? すぐ帰らないといけない?」 「いえ。そんなことはないですけど」 「それやったら、今からここへ一緒に行こ? おごるから」 彼女は携帯の画面を切り替えて、どこかのレストランのサイトを表示させた。 「この店。近くやし、めちゃおいしいパティスリーを出すって。『栗いっぱいのマロンパイ』なんか、もう最高やて!」 そう言って、彼女はいたずらっぽく、私の目をのぞきこんだ。 「それに佐和さん、まだ話し足りないこと、何かあるんと違う?」 |