「EWEN」&「魔王ゼファー」クロスオーバー企画
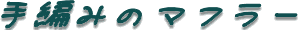
|
第3回 (1) 円香 「最高〜。ほっぺたが落ちそう!」 さすが「東京グルメガイドブック」、評価どおり文句なしの三ツ星やわ、この「栗いっぱいのマロンパイ」。佐和さんの注文した「あつあつアップルパイのバニラアイス添え」も、めちゃ美味しそう。……どないしよう、あっちも食べたくなってきた。 「円香さんて、甘いもの召し上がられるのに、細いんですね」 「ううん、うちの家族は酒飲みばっかりで、甘いもの嫌いな人ばっかりなんよ。だから、たまに友だちと食べに行くチャンスがあると、つい誘惑に負けてしまう」 ようやく最初の興奮がおさまると、私は熱い紅茶を口に含んだ。 それにつられたのか、彼女もほっそりした指でティーカップを持ち上げる。 かなり長い時間、ふたりは根競べみたいに、向かい合って紅茶をすすっていた。 「じゃあ、佐和さん。そろそろ本題に入ろうか?」 「はい」 佐和さんはカチリとカップを受け皿の上に置いて、居住まいを正した。 「円香さんのような専門家の方に、私の話を聞いていただけるなんて。本当は長いあいだ相談したくて、でも誰にも相談できなかったんです」 「ご主人に関係のあること?」 「主人と、それから娘です」 彼女は艶のある毛先を指でかきあげると、話し始めた。 「正人さんと出会ったのは、今からもう14年も前になります。私が暴漢に襲われているところを助けてくれたのが、きっかけでした。 そのとき、彼は自分のことを「ゼファー」という名前で、アラメキアという国から来たと言いました」 「うんうん」 「それから少しして正人さんは犯罪に関わっていたことがわかって逮捕されたあと、精神病院に入院しました。そこで、彼の病名を知らされたんです。子どもの頃からずっと、自分のことを異世界の魔王だと思い込んでいる、妄想型の統合失調症だということでした」 「……ふーん」 「それでも、彼のことを好きでした。みんなに反対されたけど、……今でも父親などは口もきいてくれませんけど……結婚したいという気持ちは変わりませんでした」 「幸せやねえ、佐和さん」 しみじみとそうつぶやくと、佐和さんははじめはびっくりしたような顔をして、次にとても嬉しそうににっこりと微笑んだ。 「はい、私幸せです。結婚して後悔したことは一度もありません。ただ一度だけ……」 そして、テーブルの上のおしぼりをきゅっとつかんだ。 「あなたは魔王なんかじゃないって、主人に向かって怒鳴ってしまったことがあるんです。そのときの夫の表情が今でも忘れられません。何も言わずに私に背を向けてしまったのを見て、夫の心をえぐるほど酷いことばを言ってしまったことに気づきました」 「ああ……私もあるよぅ」 私もディーターを傷つけることばを言ってしまった場面を、これでもかというほど思い出せる。知らずに言ってしまったこともあるし、売り言葉に買い言葉だったこともあるし、毒の量を冷静に量ったうえで放ったことばもあった。 サイアクな自分が赦せなくて、顔も見られなくなるほど落ち込んで、それでも赦してもらえる喜び。そして自分も同じだけ相手を赦していける喜び。 「夫婦って、赦したり赦されたり。その繰り返しなんやないかなあ」 「ほんとうに、そうです」 佐和さんは、とても綺麗な涙のしずくを目の縁に浮かべて、うなずいた。 「私、それから二度と、夫がアラメキアの魔王だったことを疑わないと自分の心に誓いました。その誓いを破ったことは、たぶん今までありません。でも……でも」 ふたたび彼女の顔が、今の冬空のように曇っていく。 「なにがあったの?」 話すべきかどうか、彼女はとても迷っているようだった。こういうときに、ついせっかちになって訊きすぎてしまうのが、私の悪い癖。 「あ、ちょっとすいませ〜ん」 私は突然、店中の人が振り返るくらいの大きな声を上げて、手を振った。 「あつあつアップルパイのバニラアイス添え、もうひとつ追加ね」 そして連れに向き直って、にんまりする。 「だって、めったに来ない東京での、せっかくのチャンスやもん。これくらいの贅沢、いいわよね」 「はい」 佐和さんはきれいな目を楽しげに細めると、くすくす笑った。 数秒して、彼女は意を決したように唇をきゅっと結んでから、おもむろに話し始めた。 「実は、小学校5年になる娘のことが、とても気がかりで」 「お嬢さん。雪羽さんておっしゃったっけ?」 「はい。雪羽が、『私がお父さんのあとを継いで、魔王になる』と言い出したんです」 (2) 聖 「アラメキアでは、木や花のあいだを、小鳥や蝶々のように精霊が飛び回っているんだ」 雪羽は小さな両指を組んで、お父さんから聞いたというアラメキアの話をしてくれた。まるで自分の心まで飛ばしてうっとりと夢を見てるみたいに話すのを見ながら、僕はなんてキレイなんだろうと思った。 アラメキアのことは全然知らないけれど、話だけでこんなに雪羽を輝かせてしまうのだから、本当にすばらしいところに違いない。 僕のお父さんも生まれ故郷の北アイルランドの話をするとき、こんなふうになつかしくてたまらない顔になる。「エメラルドの島」と呼ばれるほど美しいところ。行きたいと僕が言うと、お父さんのエメラルド色の目はちょっぴり悲しそうに見える。 「オレのお父さんときみのお父さんは、少し似てるね」 と僕は言った。 「オレのお父さんも、自分のふるさとにもう二度と帰れないと言ってた」 「同じ地球の上の国なら、飛行機で帰れるだろう」 「お父さんは、自分の国でたくさんの人を殺して、それでもう帰れないんだって」 「ホント……なのか」 雪羽は驚いたように何度も目を瞬きながら聞いている。その視線を感じながら、ベンチから立ち上がって、うーんと伸びをした。 「オレ、そのことを3ヶ月前の11歳の誕生日の夜に、お父さんから話してもらった。なぜその日だったかと言うと、お父さんは11歳のときにIRAというソシキに入って、少年兵になったからだって。お父さんはそこで、たくさんのツミをおかした。爆弾を作ったり、人殺しをしたり」 僕は雪羽を安心させたくて、少しだけ笑った。 「ほんとうはもっと前から、何となくわかっていたんだけどね。でもその話を直接聞いたとき、オレやっぱり動揺した。お父さんのことを少し恐いって、キライだって思ってしまったんだ。本当は世界で誰よりも大好きなお父さんなのに、その一方でキライだなんて。変だよね。でもなぜかわからないけど、今までみたいに素直に話せなくなった。 お父さんもお母さんも、それ以来オレのことを心配してる。今度、妹を家に残して三人だけでいっしょに過ごす計画を立ててくれたのも、そのためなんだ」 「そうか。やっぱりあたしとおまえは似ているな」 雪羽はマフラーをくるっと首に巻きなおすと、ゆっくりと考え込むように言った。 「あたしの父上も、アラメキアで戦争を起こした。たくさんの魔族が自分のせいで死んでしまったことを、父上はとても悔いている。 だから、あたしはいつか、追放された父上の代わりに、アラメキアに戻って魔王になりたい。王もなく、放り出されて苦しい生活をしているかもしれない魔族が幸せに暮らせるように、力を尽くしたいんだ」 息がつまってしばらく物も言えなかった。きちんと自分のしなければならないことを決意している雪羽は、僕と同じ5年生とは思えないほど、りっぱで気高く見えた。 「オレ、きみに比べると、お子様だ」 つくづく自分が恥ずかしくなってしまう。 「悪いことをしたからお父さんがキライだなんて、そんなバカなことを考える暇があったら、きみみたいに自分にできることを考えなくちゃいけないのに」 「そんなことはない。おまえは一生懸命にお父上のことを考えていると思うぞ」 雪羽は肩をいからせ、両手の拳をぎゅっとにぎりしめた。 「ありがとう。なぐさめてくれて」 「それに、偉そうなことを言って、あたしだってお子様だ。アラメキアに帰る方法など、まるでわかっていないのだからな」 と言って、悔しそうに唇をかみしめる。「早く、なんでもできる大人になりたい」 「アラメキアに行くって、タイムマシンよりむずかしいのかな」 「家臣のヴァルも、戻る方法はもうないと言っている。でもそれだけではなくて」 雪羽は、真っ黒な目を遠くに向けた。 「あたしにはアラメキアに行く前に、どうしてもやっておかなくちゃならないことがあるんだ」 (3) ディーター 「俺は、下町の小さな部品工場で働いている」 突然現われた小柄な長髪の男に先導されながら、ゼファーと俺は並んで、駅とは逆の方向に歩き始めた。 「中小の町工場の抱える一番の問題は、資金繰りでも技術不足でもない。後継者がいないことなんだ。ご多分に洩れず、うちの工場も」 ゼファーは、自分の会社の悪口を言うためらいを乗り越えると、あとは早口で続けた。 「先代の社長が引退したあと、まったく別の仕事をしていた長男に、なかば頼み込むように経営を譲ったわけだ」 まいったというふうに頭を振っている彼の表情を見て、いったいどんな騒動が起こったのかわかったような気がする。 「仕事のことを何も知らない新社長か。現場の苦労を察するよ」 俺の同情のことばに、彼も苦い笑いを返した。 「新社長は、まったく無能というわけじゃない。彼なりに、経営をどう改善するかを一心に考えている。それだけに厄介でな」 「そのことと、さっきのゲーム機の図面に関係があるわけか」 「ある日、俺は社長室に呼ばれて、ひとりの男を紹介された。そいつは、株式会社ソムテックの河西と名乗った。開発したばかりの新製品の部品を生産してほしいと言う。創設まもないベンチャー企業ということで、はじめて聞く社名だが資金面は潤沢なようだった。 部品の設計書を見せられたが、全体像が今ひとつつかめない。何かの電子機械のスイッチだということだけで、まだ発表までは極秘だと言われた。納期は残業を見込んでもギリギリだったが、やってやれないことはない程度だ。だが、これだけの注文が定期的に入れば、経営は安定する。社長は大乗り気だった。今までに受けていた注文を切ってでも、こちらに社運を賭けようという意気込みが伝わってきた。 だが、俺はその男に何か胡散臭いものを感じた」 ようやく、ゼファーが言わんとしていることの意味がわかってきた。 「あの図面はどこから?」 「そこにいるヴァルデミールに命じて、こっそりヤツのあとをつけさせた。猫の姿でな」 「猫?」 「……まあ、気にしないでくれ。するとヤツは、都内の別な工場数箇所に立ち寄って、似たような話を方々に持ちかけていたそうなんだ。この設計図は、ヴァルデミールが隙を見て、ヤツのカバンから抜き取ったものだ」 「あくまでも仮定の話だが」 俺は考えをまとめた。 「ゲーム機の部品は、普通はメーカーの契約工場で厳重な管理のもとに生産されるものだ。 だが、その製造方法をなんらかの手段で手に入れ、高度な技術を持つ日本の小さな町工場にばらばらに発注する」 「違法なんだな」 「もちろん、違法だ」 「そうか。俺たちの工場はそうとも知らず、コピー品の製造に一枚噛まされかけている、というわけか」 「契約書はもう交わしたのか」 「いや、まだだ。来週早々にも正式の発注書が届くことになってる。だから今日が奴らの陰謀を食い止める、最後のチャンスだ。もしこのまま奴らの悪事に社運を賭けてしまえば、いつか数十人の従業員が路頭に迷うことになる」 ゼファーは静かに言った。だが、その全身に黒い怒りのオーラをまとっているように見える。近づくのに危険を感じるほどの強い気に、俺は思わず足をとめた。 この男はただの人間ではないと感じた。病気による妄想などではなく、彼は本当に「魔王」という存在なのかもしれない。 『コージョーチョー、ここです』 ちょうどそのとき、先頭を歩いていた男が振り向き、俺にはわからない言葉で何かを告げた。 彼の声音と緊張した様子から、ここがゼファーたちの探していた組織の拠点なのだろう。人通りの少ない通りに面した三階建てのビル、一階はシャッターが降りた倉庫用のスペースになっている。 「ディーター。ありがとう」 ゼファーは、別れのしるしに手を差し伸べた。「きみはここまででいい」 「今から、ここに忍び込むつもりなのか?」 「まあ、そんなところだ」 「だが、相手は違法行為に平気で手を染めている奴らだ。見つかればどう仕返しされるかわからない」 「承知の上だよ」 「奴らの犯罪の証拠となるものを見つける。そうでもしなければ、新米社長はきみのことばなどには耳を貸さない。……そういうことか」 ゼファーは肯定のかわりに、ふっと寂しげに微笑んだ。 そこには、人に理解されないまま、大きなものを守るために苦闘している男の顔があった。この高貴なまなざしの男のために、俺は少しでも役に立ちたいと心から願った。こんな気持ちになったのは何年ぶりだろう。迷いは一瞬で吹き払われた。 「俺は外国人だ。それに過去に大きな犯罪をおかしてもいる。今、面倒に関わったことがわかれば、たちどころに日本での滞在許可をなくす」 「わかっている。関係のないきみに迷惑はかけたくない。だからここで別れようと……」 「誤解しないでくれ。見つかったら困ると言ってるんだ。見つからないようにすればいい」 「え」と彼が怪訝な顔をした。 「手伝うよ。ひとりでも人数が多いほうが、探し物は早くすむし、それだけ危険は少ないだろう?」 「し、しかし」 「ここまで来てリタイアするのは、癪なんだよ」 『コージョーチョー! そいつを仲間に入れるんですか』 黒髪の男の抗議らしき声を背中に聞きながら、俺は妙な高揚感を覚えつつ、彼らの先陣を切って踏み出していた。 |