「EWEN」&「魔王ゼファー」クロスオーバー企画
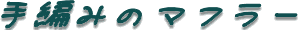
|
第4回 (1) ゼファー 『コージョーチョー、そんな見ず知らずのヤツを信用するニャんて』 文句を言っていたヴァルデミールも、俺の命令を受けると、しぶしぶとビルの裏側に回っていった。換気用の小窓から潜り込むつもりだ――もちろん猫に変身して。 ドアの外で待っていると、やがて内側から鍵が開く鈍い音がした。開けると、ヴァルデミールがノブにぶらさがって、にゃあにゃあと鳴いていた。 「中にはもう誰もいないらしい」 俺は横にいたディーターに彼のことばを通訳した。ガレージの外に横付けしてあったトラックがなくなっているので、例の河西とかいう男はそれに乗り込んでどこかへ行ったらしいと。 「だが、いつ帰ってくるかわからないな。急ごう」 「その猫は?」 ディーターは不思議そうな顔で、俺の腕に抱かれた黒猫を見つめている。説明する時間がないので、「偵察に忍び込ませておいた、俺の飼い猫だ」と答えておいた。まさか、この猫とさっきの男が同一人物であるとは、いくら説明しても理解できまい。 真っ暗な倉庫の中を用心して進む。紙のダンボール箱に混じって、うちの工場で見慣れている電子基盤用のプラスチックダンボールが整然と積み上げてあった。 ディーターが、箱の側面の英文を印字したラベルに目を留めている。外国のどこかの都市の名も書いてあるらしい。 「ここにある部品はみな、外国に輸出されるわけか?」 英語を読めない俺が尋ねると、 「そうだな。ごく普通の機械部品にまぎれこませてあるようだ。向こうで組み立てて、そこから独自の密売ルートに乗せる。違法な商品を公然と刑務所の囚人たちに組み立てさせる国も、アジアにあると聞いた」 「証拠になるかどうかわからんが、一応撮っておこう」 俺は上着のポケットから、持参した小型カメラを取り出して、倉庫の様子を何枚か写真に収めた。 そのあいだにディーターは奥の部屋に進み、コンピュータを見つけた。スクリーンセイバーが明滅している。 「電源を切ってないということは、すぐ戻ってくるつもりかもしれない」 舌打ちしながらも、彼は椅子を引き寄せ、器用な手さばきでキーボードを叩き始めた。 俺はその横で部屋のあちこちに積まれたダンボールを調べた。 その中から、重大な証拠となるものを見つけた。あの設計図どおりに組み立ての終わった試作品だ。これが今春発売されたばかりのゲーム機の模造品なのだろう。俺はそれに向かって、数回シャッターを切った。 「あった」 ディーターもコンピュータの画面から何かを見つけたようだ。彼は上着の内ポケットから、俺には名前もわからない小さな記録媒体のようなものを取り出して、機械の穴に差し込む。 「通関業者へのシッピングインストラクションの書類ファイルだ。これで船積みの予定がわかれば、警察に密輸の情報を提供できる」 俺は自分の工場の社長を説得することしか考えていなかったが、彼はあわよくば、奴らの組織自体をぶっ壊すことを視野に入れているらしい。何故こういうことに場慣れしているのか知らないが、なんとも心強い味方ができたものだ。 『コージョーチョー! 奴らが』 部屋の入り口近くで見張らせておいたヴァルデミールが叫ぶと同時に、ガレージのシャッターがガラガラと上がる音がした。俺たちはとっさに、身体を屈めた。冬の早い入り日が倉庫に射し込み、三人の長い人影が動いているのが、床に伏せていてもわかる。 こんなに早く戻ってくるとは思わなかった。まずいことになった。なんとかして外に逃げ出さなくてはならない。俺はともかく、ディーターだけでも。 奴らのうちふたりは入り口で荷物の搬入を始め、残りのひとり――そいつが河西だった――がまっすぐ俺たちのいる奥の部屋に入ってきた。ヴァルデミールは機転を利かせて、その前に躍り出た。俺たちが見つからぬように、奴の目を引きつけるつもりだ。 いきなり現われた猫に、男は一瞬あっけにとられたようだったが、驚くほど俊敏に足を蹴り上げた。それをよけそこねた俺の従臣は、まともに腹にその一撃を食らってしまった。 「まったく、どこから入り込みやがった」 いっしゅん息が止まって動けなくなったヴァルデミールをぐいとつかみ上げ、動物をいたぶる喜びに顔をゆがませた河西は、おおきく腕を上に振り上げた。 (壁に叩きつけられる) そう思った瞬間、俺の隣で空気が動いた。 気がつくと、ディーターがそいつの脇に手刀をめりこませていた。男は声も立てず、ぐにゃりと身体をクラゲのように床に横たえた。 「最低のクズ野郎」 見下ろしながら吐き捨てるようにつぶやくディーターの目はまるで別人で、一瞬氷が張った湖面に見えた。 「当て身」というのだろうか、その動きすらも、俺には見えなかった。彼は何かの武道を究めた男なのかもしれない。 床にのびている男のそばからヴァルデミールを拾い上げている間に、ディーターがすばやくコンピュータからメモリー用の媒体を引き抜き、ぐいと俺の袖を引っ張った。「こっちだ」 俺たちは中腰になったまま、反対側の廊下に出た。廊下の突き当たりに、煤で汚れきった小窓がある。 それを押し上げて、ディーターは窓枠をつかみ、ひょいと身軽に出て行く。俺もかろうじて何とか身体を押し込んだ。 降り立ったところはゴミバケツが並んだ、狭く汚い路地だった。後ろも見ずに一気に走り抜けると、見覚えのある通りに出た。 「あんなところに逃げ道があったなんて、よくわかったな」 俺たちふたりは足を止めて倉庫を振り返った。 「いつまで経っても、前もって逃走経路を確保する習慣が抜けない」 ひどく苦々しい口調で、ディーターはつぶやいた。「もう少し離れよう。今頃、他のふたりに気づかれている頃だ」 さらに人通りの多い、駅への方向を目指して俺たちは歩き始めた。 「もしかすると、もうこんな証拠はいらないかもしれない」 と、まっすぐ前をにらみながら彼は言った。 「どういうことだ?」 「誰かがあそこに忍び込んで調べていたことがわかれば、奴らは危険を感じ、部品調達をあきらめて即座にここを引き払ってしまうだろう。そうなれば、捕まえることはむずかしくなる」 「だが少なくとも、うちや、この地域の工場は被害を免れる」 それは本心だった。情けない話だが、実際は奴らと対決するより、さっさといなくなってくれるほうが俺としては嬉しい。 「これだけの証拠があれば、うちの社長を説得できるよ。大勢の従業員たちが救われることになる。全部、あんたのおかげだ、ディーター。 それに、このヴァルデミールの危ないところを助けてくれ……」 はっとした。ディーターのもの問いたげな視線を横から浴びて、自分が今うっかり、あの猫を「ヴァルデミール」と呼んでしまったことに気づいた。さっきの黒髪の男と同じ名前であることを、さぞかし不審に思っているだろう。 「ゼファー」 ディーターは碧色の瞳でまじまじと俺を見ていた。さっきの氷のような目とは全然違う、深い森の奥のような優しい色。 「きみのような人が、この世界で生きていくのは大変じゃないのか?」 はっとした。彼のことばに込められた意味。それはもしや、俺が本当にアラメキアから来た魔王であることを、心から信じてくれるということなのか? 感動のあまり自分の身の内が震えそうになるのを、ようやく止めた。目の奥に押し込めた水滴のなごりが、声をわずかに濡らした。 「最初はな。大変だったこともあるよ」 「そうだろうな」 「でも、妻と娘がいてくれた。ふたりは俺のかけがえのない財宝だ。だからこの世界で生きてこれた」 「うん」 彼は、それ以上は何も言おうとはしなかった。俺たちは、ただ並んで歩いた。その距離のとり方が、じんと痺れるほど心地よかった。 腕の中のヴァルデミールが「にゃあ」と鳴いて、俺の顔をバツが悪そうに見上げた。 『コージョーチョー。わたくしの数々の暴言、謝りとうございます。このお方は悪い人なんかじゃニャかった。コージョーチョーを助け、わたくしの命を助けてくれました』 『そうだな』 『この人とそっくりの匂いをした、姫さまのそばにいるあの男の子も、ことによると悪いヤツではニャかったのかもしれません』 俺はそれを聞いた瞬間、ああと悟った。 「ディーター。あんたの息子は誰かと会って、待ち合わせに遅れると言っていたな」 「ああ」 「もしかしたら、その相手とは、俺の娘の雪羽かもしれん」 「え?」 「確信はないが、そんな気がする。俺たちが不思議な力で引き合わされたように、子どもたちもどこかで出会っているのかもしれない」 「そうだったんだ。それならいいが」 ディーターは安堵したと言うふうに、晴れやかな顔で空を見上げた。 「実は、息子の電話は嘘じゃないかと勘ぐっていたんだ。俺に会いたくないための口実だったんじゃないかって」 「どうして、そんなことを?」 「今、ちょっと親子の間がこじれてる」 彼は、少し困ったように笑いながら、目を伏せた。 「それは俺の過去の過ちが原因なんだ。息子は今、そのことに自分なりに気持ちの整理をつけようとして苦しんでいる。俺はそれを、ただじっと見ていることしかできない」 「父親と息子というのは、いろいろあるんだな」 と俺は慰めを口にした。だが、とうとう自分の跡継ぎとなる息子を授からなかった俺にとっては、そういう苦労もちょっぴりうらやましくさえある。 「あんたには、息子のほかに娘がいると言ってたな」 「ああ、5歳になる」 「どうだ。可愛くないか?」 とたんに、彼は絶句した。顔を見ると、自分に腹を立てているような表情をしていた。 ようやく、かすれ声で答える。 「それが……めちゃくちゃ可愛い。世の中にこんなに可愛いものがあるのかっていうくらい」 「ははっ。やっぱりな」 俺は心から同意しながら、青空に向かって笑い声をあげた。 (2) 佐和 「雪羽は小さい頃から、とても変わった女の子でした」 私はつっかえながらも、心に秘めていたことを円香さんに話し始めた。 「子どもらしくないと言うのかしら。普通の女の子が興味を示すようなことには見向きもしないで、むずかしい本ばかり読んで、いつも空想にふけっているんです。 言葉づかいも、教えたわけでもないのに、とても古風な物言いをして。学校では慕ってくれる友だちもいるんですけど、大抵はいつも、回りのみんなから浮いている感じで。担任の先生にも、人間関係がうまく作れないから、一度専門家に診てもらったらどうかと言われたりしたこともありました」 あのときのショックを私は昨日のことのように思い出せる。膝が崩れて、倒れそうなほど動揺した。 私はあのとき、自分の娘を信じてやれなかった。学校の先生より、母親の私のほうが雪羽のことをよく知っていると、胸を張って言えなかった。 「雪羽が小学3年のときでした。買い物から帰ってきて、夫と雪羽が話しているのを聞いてしまったんです。夫は雪羽を膝に乗せて、わからない言葉でしゃべっていました。 そのとき私の中に怒りというか、とても醜い思いが湧いてきたんです。 この子にアラメキアのことを教えないで。まだ嘘と本当の区別もつかない子どもなのよ。そう叫んでしまいそうになったんです。わたし……私、本当ははじめからずっと、心の奥底でゼファーさんを信じていなかったのかもしれない」 それは、自分でも認めたくない気持ちだった。でも認めなければならない。 「勇気を出して、よく言えたね。佐和さんは偉い」 そのことばを聞いたとき、熱い悲しみがいちどきに胸にこみあげて、でもゆったりと笑っていてくれる円香さんの顔を見ていると、不思議なことに悲しみは安らぎへと姿を変えていくようだった。 私は、あふれでた涙をハンカチでぬぐうと、大きく深呼吸をして背筋を伸ばした。 「ごめんなさい。泣いたりして。ずっと誰にも言えないことだったから」 「そうよ。言葉っていうのは不思議なもの。自分の気持ちを言葉にするだけで、人類の悩みの半分は解決するの」 「ほんとにそうです。なんだか、すっきりしました」 円香さんは、ポットから私のカップに紅茶を注いでくれながら、自分に言い聞かせるような調子でゆっくりと言った。 「夫婦や親子って、不思議なもんやと思う。こんなに長い間いっしょにいて、なにもかも通じ合っているのに、心の中のすべてを共有することはできないの」 「円香さんでも、そうなの?」 「うん」 彼女はカップを両手でかかえると、長い長い吐息を吐き出した。 「私、結婚したときは、ディーターの全部を理解しようと思てた。それが妻の務めやと信じて。でも、いくら理解しようとしても、彼の心にはどうしても私には見せてくれない部分があって、私はときどき自分を責めたりしたの。私では言葉も国籍も育った環境も、何もかも違いすぎる。どうして、よりによって彼が選んだのは私なんだろうって。 でも、そうじゃなかったって、やっとこの頃になって気づいたの。私が知らないでいたからこそ、彼は私のそばで安心していられたんやなって」 私は、その話の意味するところを理解できたわけではなかったけど、彼女が今まで体験してきたことの、ずっしりとした重みだけは感じ取れた。 「人間は、賢すぎてもロクなことあらへんなと思う。アホでええんよ。相手のことを全部知りたいと思うのは、ときには相手を支配したいという欲求の現われ。でも、支配するんじゃなくて、自分とは全然違うひとりの人間として認めてあげるの。 だから、全部わからなくていい。旦那さまと子どもたちのことを大好きで、いつもニコニコ笑っているだけの奥さんになれたらいい」 円香さんは、蕾から開いたばかりの花のように、柔らかく笑った。 「笑っているだけ……」 ことばほどに簡単なことではない。いや、一番むずかしいことなのだと思う。でもそれをちゃんと心がけて実行している円香さんは、世界一すばらしい奥さまなのだろうなと、私は思った。 この世界とは違う世界に思いを馳せているゼファーさんのそばで微笑んでいること。雪羽といっしょに、アラメキアを信じること。 私にできるだろうか。 「やってみます。できるかどうかわからないけど」 「佐和さんやったら、できるよ。だって、あんなに美味しいおにぎりを握れる人なんやもの。ふんわりとして、それでいて崩れなくて。そんな自然な愛情を形にできる人なんやもん」 「ありがとうございます」 私たちはお互いの顔を見つめて、にっこりした。宝物のような数時間を共に過ごし、私たちは互いを姉妹のように、敢えて言えば、戦友のように感じ始めていたのだ。 「あーっ、しまった」 突然、円香さんが大声で叫んだ。 「あつあつアップルパイのアイスクリームが溶けてしもたあ。もったいない」 「まあ」 手元のお皿に目を落として、茫然と口に手を当てている彼女の様子が、すごく可愛らしい。 「私の長話のせいだわ。……すいませーん」 私は自分でもびっくりするほど素早く、そばにいたウェイトレスさんを呼んでいた。 「彼女のアップルパイ、おかわりお願いします。それから『栗いっぱいのマロンパイ』、私にもください!」 (3) 雪羽 「あたしは、おじいさまという存在を知らないんだ」 駅からまっすぐ伸びる坂道を、あたしたちは白い息を吐きながらいっしょに上がって行った。 「母上の父親という人は、うちの両親が結婚したとき猛反対をして、母上を勘当したんだ。おばあさまは、ときどき内緒であたしの顔を見に来てくれるけど、おじいさまにはいっぺんも会ったことがない。 だから、あたしはアラメキアに行く前に、おじいさまに会いたい。会って、母上と父上と仲直りをさせてあげたいんだ」 聖はジャンパーの襟に顎をうずめて、だまって聞いている。 「おまえには、おじいさまやおばあさまはいるのか?」 と聞くと、申し訳なさそうに答えた。 「おばあちゃんはいないけど、おじいちゃんとはいっしょの家で暮らしてる」 「うらやましいな」 小声でつぶやいたあたしに、聖はびっくりするくらい大きな声で、 「雪羽。きっときみのおじいさんも、きみのことを愛して、気にかけてくれている。だって孫なんだから。ただ、今までそれを言うきっかけがなかっただけなんだ」 「そうだといいが」 「そうに決まってるよ」 懸命に私を慰めようとしている聖を見て、私は素直に彼の言うとおりなのだと思ってうれしくなった。 心の底から人のやさしさを信じている人って、とてもあたたかい。胸に抱いているヴァルのふわふわの毛の温もりみたいに、聖のあたたかさは、するっと私の心に入ってくる。 「おじいさんは、どこに住んでいるの?」 「このそばに家がある」 あたしは、坂の正面に向かって顔を上げた。 しばらく行くと、茶色にそまった落ち葉をいっぱい敷きつめた小さな公園が見えてきた。 静かなその公園のベンチの陽だまりに、年を取った男の人がひとりだけで座っていた。白い、少し薄くなった髪の毛をうしろにきれいに梳かしつけ、ひし形模様のグレーのセーターを着て、ぴしっと背筋を伸ばしている。 「あれが……」 「雪羽のおじいさん?」 あたしはこっくりとうなずく。会ったことはないけど、写真なら見たことがある。 聖はそれを見ると、カサカサと落ち葉を踏みしめながら、ひとりでベンチに近づいていった。あたしはびっくりして足を止めたまま、その後姿を見送った。 「すみません。道に迷ってしまって」 笑顔で、おじいさまに話しかけている。 「駅へは、どう行けばいいですか?」 おじいさまは、じろりと彼を見上げると、ぶっきらぼうに坂の下のほうを指さして、「あっちだ。まっすぐ下って行けば、すぐわかる」 「ありがとう。僕、兵庫県から来てるんです」 そして、ものすごく自然にベンチの隣に座った。 「兵庫県では、ひとつの古い家に、両親と妹と、それから祖父といっしょに住んでいます。祖父は、僕たち孫をとてもかわいがってくれます」 突然、見ず知らずの小学生からべらべらと話しかけられたおじいさまは、胡散臭そうにじろっと横目でにらんでいる。今にもかっと口を開けて怒鳴りだしそうで、あたしはハラハラして立っていた。 おじいさまはとても頑固で、よく家族を怒鳴る人だったそうだ。 でも、会社を母上の兄に譲ったあと、今は誰かとしゃべることもなく、ほとんど毎日ひとりでこの公園に来ていると母上が言っていた。 「家にいても、お兄さんやお嫁さんと折り合いが悪くて、けんかばかりしてるって。お父さんらしいわ」 そう言って、笑いながら台所に立つ母上の背中は、とても小さく見える。 本当は会いたいのだろうと思う。泣きたいくらい会いたいのだと思う。 どうして人は争いたくなくても、争い合ってしまうのだろう。心の奥では誰だってなかよくしたいはずなのに。 いつのまにか、あたしの目から涙があふれた。首に巻いていた母上の手編みのマフラーで、そっと頬のあたりを押さえると、マフラーは涙を吸い込むかわりに、それをキラキラとかがやく銀色の玉に変えてしまった。 身体の中心が熱く燃えて、じーんとしびれて、足が地面に着いているのか着いていないのかわからなくなった。 それと同時に、少し離れた聖の身体が銀色に光り始めた。 ベンチに座っていたおじいさまの表情が少し変わった。ぽかんと口を開き、何かを見つけたときの子どもの表情。 「僕のおじいちゃんは、いつも面白いことを言ったり、遊んだりしてくれます。大事なことをたくさん教えてくれて、時には怖いけど、いつも僕や妹のことを考えてて、父や母と同じくらい僕たちのことを愛してくれます」 聖は、心をこめて話しかけた。 「あなたにもし孫がいたら、きっとあなたも、そうしたいはずです。だって、自分が愛して育てた娘の子どもでしょう。それが当たり前のことじゃないですか?」 ふたりを包む空気が、銀色の薄いもやのようになって、あたりの色をにじませている。 おじいさまは目を上げて、うっとりと何かを見つめていた。あたしには、それが何かわかる。おじいさまは、母上の子どもの頃の思い出が映画のように心に映し出されるのを、見ていたのだ。 しばらくして、私は自分のそばに、ひとりの女の人が立っているのに気づいた。紫の長い髪をベールのように広げた、花のような人。 「精霊の女王さま」 「雪羽」 真珠みたいに輝く顔で、女王さまはあたしに微笑みかけた。 「あの少年を見ていると、魔王になる前、精霊の騎士だったころのゼファーを思い出します」 「聖が?」 「彼には、そなたを助ける騎士の資格があるのかもしれません」 聖はベンチからふわりと立ち上がると、おじいさまを手伝って同じように立ち上がらせた。 そして、あたしのほうに身体を向け、 「あの女の子が誰だか、わかりますか?」 指をさして、そうたずねた。 お祖父さまは目をこらして、じっとあたしを見つめた。その目にみるみる涙が浮かんだ。 「ああ、ほんとうに。……佐和に生き写しだ!」 |