「EWEN」&「魔王ゼファー」クロスオーバー企画
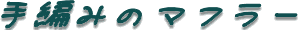
|
エピローグ レストランの外は、もう早い夕暮れの空の下。駅前の雑踏は華やかなクリスマスのイルミネーションで、色とりどりに飾られていた。 「あー。もうこんな時間。3時間もいたわけか」 円香は上気した頬を満足げにゆるませて、舗道の真ん中で大きく伸びをした。佐和も両手で口を覆ってげっぷを抑えていた。 「よく食べましたよね。結局ふたりでケーキ8個」 「もうお腹いっぱいで、晩御飯食べられへん」 「ほんと、私も。夕食の支度どうしよう」 と笑いながら佐和はふと、通りの行く手に視線をやった。 「あ、ゼファーさん」 「あーっ。ディーターやん」 ふたりは立ち止まって、舗道の向こうから歩いてくるふたりの男たちに目を見張った。 「えっ。隣を歩いてるあの金髪の方が、ご主人さまですか?」 「というと、その隣がゼファーさんやの? なんで、どうして? どうして、あっちもふたりいっしょやの?」 キャアキャア大騒ぎしている女性たちに、ディーターとゼファーもすぐに気づいた。 「あれ。円香?」 「佐和?」 「ディーター!」 円香が先頭を切って駆け寄ると、背の高い夫の胸に飛びつく。まるで、そこ以外の居場所はどこにもないという勢いで。 佐和もその後から追いかけてきて、ゼファーのそばに立った。 「ゼファーさん」 彼は頬をゆるめ、妻をいとしげに見つめた。 「佐和。あの人は知り合いか?」 「ええ。エレベータの中で出会ったの」 佐和は、円香たちの抱擁の様子をうっとりと見つめていたが、やがて宣言した。 「ゼファーさん、工場から家に帰ったときは、私たちも毎日ああしましょうね」 「え?」 そしてその一部始終を、もっと遠くから目撃していたもう一組。 聖と雪羽だ。 「うわ。ファティとムッティ、待ち合わせの場所に着く前に出会ったみたいだな」 聖が恥ずかしそうに顔をしかめてつぶやいた。 「あの熱烈にキスしてるふたりが、おまえのご両親か?」 「うん」 「ふうん。何ヶ月ぶりかの再会……なのか?」 「じゃなくて、今朝別れたばかりだと思うよ」 「ううむ……何と言うか、じゃあ、いつもああなのか」 「いつも、ああだよ。ああいうトシガイもない両親を持つと、子どもはほんと苦労するよ」 「……それにしても、なぜその横に、あたしの両親がいるのだろう」 「ええっ!」 二組の家族がそれぞれ別々に出会ったという奇跡を全員が理解するまでには、雑踏の中でのしばらくの立ち話が必要だった。 けれど、それはそう難しいことではなかった。なぜなら、グリュンヴァルト一家も瀬峰一家も、今日の出来事が偶然以上の何かの力によるものであることを、とっくに感じ取っていたからだ。 冴えた冬の満月が、地上の光のにぎわいの頭上にぽっかりと顔を出した頃、別れのときが訪れた。 「ありがとう。何もかも、あんたのおかげだ、ディーター」 「あれだけの証拠で、社長は納得してくれるのか」 「なんとかやってみる。それは工場長としての俺の仕事だ。警察にも届けを出す。奴らを捕まえるためにできるだけのことはするよ。うちの工場だけのことを考えている場合じゃない。全国の中小工場で、もう騙されるところがないようにさせないとな」 「無茶はするなよ」 ディーターとゼファーは微笑を交わした。 愛する家族のために、この小さな国を住処と定めた異邦人同士。だが、もう孤独を感じる必要はない。同じ空の下で闘っている仲間がいることを知ったのだから。 「円香さん、私、さっきのあなたたちを見て、やっとわかりました」 「何を?」 「はい。私に足りなかったのは、あの積極性です。私も今晩、ゼファーさんにうーんと迫ってやります」 「え……、ち、ちょっと」 「ふふ。冗談です」 目を白黒させている円香に、佐和はくすくす笑った。 「でも、もっと積極的になろうと決心したのは、本当です。私、今日からゼファーさんにアラメキアのことばを教えてもらおうと思います。雪羽と3人でたくさんアラメキアの話がしたい。私、自分だけ蚊帳の外に置かれていたのが寂しかったんだと気づいたんです」 「きっとそやね。がんばって」 円香は佐和の腕を取ると、ぎゅうっと自分の腕とからめ合った。「アラメキア語がドイツ語より易しいといいね」 「はい」 聖と雪羽は、向かい合って立っていた。 さよならを言うときが迫っているのがわかり、ふたりは言葉を交わせなくなってしまった。時がもうこれ以上進まないように、ふたりの間に芽生え始めたものを壊さないように、ただ見つめ合う。それでもやはり、時間は無情に過ぎていく。 雪羽が覚悟を決めて、自分の首に巻いていたマフラーをするっと外して、聖の首に巻いた。 「明日は寒くなると言っていた。ディズニーランドに行くなら、これを着けていくといい」 「いいの? きみのお母さんの手編みだろう」 「うん。あたしにとって大事なものだから、聖に持っていてほしいんだ」 「ありがとう」 聖は両手でマフラーをそっとつかみ、そこに残る雪羽のぬくもりを感じ取ろうとした。 「オレ、明日お父さんとよく話してみるよ。ちゃんと仲直りする。だってオレ、やっぱりお父さんのことが好きだから」 「うん、あたしも父上と母上と三人で、おじいさまの家を訪ねてみるよ。うまくいくかどうか、ちょっぴり不安だけど、おまえの教えてくれたことを信じてみる」 「雪羽」 「なんだ」 「オレ、強くなる」 聖は、決意を秘めたまなざしを真っ直ぐに向けた。 「中学になったら、お父さんから葺石流の剣術を学んで、強くなる。そしてアラメキアに行くときは、少しでもきみを守ってあげられるようになりたい」 「まさか……行ってくれるのか?」 「うん、いっしょにアラメキアに行こう」 精霊の女王の言葉を思い出して、雪羽はみるみる頬を赤らめた。――もしかすると聖は、女王が言っていたとおりに、この世でただひとりの、彼女に定められた騎士なのかもしれない。 「ありがとう」 「約束するよ」 次の瞬間、二組の父親と母親たちは口をつぐみ、驚いて顔を見合わせた。やがて、互いの若い頃を思い出して、幸せそうに微笑む。 聖は長いマフラーの端を雪羽の肩に回し、その影に隠れて、そっとふたつの唇を重ねたのだった。 終 お読みくださってありがとうございました。このお話は三周年記念企画人気投票で1位と2位の作品をクロスオーバーしたものです。 本編のこれからの展開とは異なる「お遊び企画」ですので、その点ご了承ください。 少しでも楽しんでいただけたら、幸いです。よろしければ、感想をお寄せください。 |