「EWEN」&「魔王ゼファー」クロスオーバー企画第3弾
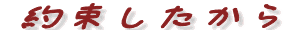
|
第3回 ―― 聖 「ちくしょう。どうすればよかったんだよ!」 公園を出るとき、思わず叫んだ。 振り返りたい。そして、雪羽のところに駆け戻っていって、やっぱりきみが好きなんだと言って、抱きしめたい。 だけど、絶対にそうさせないものが、僕の心の中を支配していた。 だから、背中の向こうに痛いほど雪羽の存在を感じながらも、足だけはずんずんと歩み続けている。自分の体が自分の思い通りに動かないなんて経験は、初めてだった。 歩調に合わせて、腹の底に、ぐるぐると溶岩のように煮えたぎる怒りが渦まいた。何もかも、腹立たしい。 (雪羽なんて、もうどうでもいい) 怒りの塊は、そう叫んでいる。アラメキアのことしか頭にない雪羽と、無理して遠恋する必要なんか、ない。 あのバイト先で知り合った女性たちに声をかければいいじゃないか。妖艶で大人びて、人生の楽しみ方をいっぱい知っていて、きっとキスも上手だ。 ひとりでは雪羽の代わりにならないのなら、何人とだって付き合えばいい。 何かが間違っていることに心の隅で気づきながら、僕はその怒りに翻弄されて、まともな思考ができないでいた。 「聖……と言ったか」 突然、行く手の街灯の向こうから声がした。 僕を待ち伏せていたように、ひとりの男が姿を現す。 「あなたは……」 白いコートに藍色の目、藍色の髪。確か、天城悠里という名前の、雪羽の幼なじみ。 「今日、きさまに会ったとき、不穏なものを感じていたのだ」 彼は射抜くような目で僕をじっと見つめると、懐からいきなり剣を取り出した。コートの陰に隠れていて、わからなかったのだ。 「余の目を逃れられると思ったか」 叫ぶが早いか、いきなり斬りかかってきた。僕は訳がわからず、よけるのがやっとだった。 「なんなんだよっ」 思いっきり、尋常じゃない。しかも、こいつ、ハンパじゃなく強い。二太刀目をかろうじて、竹刀袋をかざして防いだ。 間合いがいったん離れたのを見計らって、袋から木刀を取り出し、緑の鞘を投げ捨てた。 「オレが何をしたって言うんだ」 「雪羽を傷つけた」 「え?」 悠里は、剣を左手で小脇に持ち、身体をひねる独特の構えのまま、口を開いた。 「きさまが雪羽の騎士であるべく勉めるなら、何も口出しするつもりはない。だが、雪羽を傷つけるような真似をしたからには、余は容赦せぬ」 「……オレは何も雪羽を傷つけるつもりなんか、なかった」 やや上段に構えをとりながら、僕は反論を試みた。 「オレはただ、騎士だなんて呼ばれたくなかった。雪羽に、もう少しだけ現実を見てほしかっただけだ。幻なんかじゃなくて」 「黙れ、アラメキアを幻というか」 「あんたたちが、よってたかって、雪羽におとぎ話を吹き込んだんだな」 僕は、ふたたび憤怒の焔に全身を焼かれるような心地がした。 「アラメキアなんて、この世に存在しない。存在してはいけないんだ!」 「きさま」 敵は驚いたように、藍色の目を軽く見張った。 「ようやく、わかったぞ。アラメキアを無きものとしようとする力」 「どういう意味だよ」 「余は、二重の意味で、きさまを滅ぼさねばならぬ!」 悠里は電光石火のごとく、僕のふところに飛び込んできて、斜めから剣を振り下ろした。 空気が裂けるような音がした。とっさに後ろに飛びのいたが、もし動かずにいたら、まっぷたつにされていただろう。 まちがいない。こいつの持っているのは――真剣だ。 「嘘だろ。本気で斬り合うつもりか」 「ふん」 白いコートの男は、鼻でせせら笑った。「さすがだな。騎士と目されただけのことはある」 「騎士だなんて呼ぶなって、言ったろ!」 僕は、もう一度、正眼に構えなおした。手が震えている。真剣相手の命のやりとりなんて、生まれて初めてだ。 悠里はもう一度、剣をぐいと引いて構えた。 それほど長い剣ではないのに、手元で急に伸びてくる。間合いを見誤りそうになる。 お父さんなら、どう対処するだろう。きっとこれくらいの秘剣は簡単にいなしてしまうだろう。修行をサボらないで、もっと手合わせしておけばよかった。 凍えるような二月の夜だというのに、冷や汗がつうっと背中をしたたり落ちる。 僕は、剣を身体の右側に移し、剣先を立てた。今度は、「八双」という構えだ。 息をぐっと止める。今度は、こちらのほうから仕掛けた。 討ちかかるふりをして、相手を誘い込む。伸びてくる剣を素早くはじき返し、その隙をついて、小手を打つ。 うまく行ったと思ったのも束の間、僕の木刀は逆にはじきとばされていた。 やっぱり、力が違いすぎるのか。 地面にころがった僕の喉に、やつは細い剣先をぴたりと当てた。 (殺される) 思わず目を閉じたが、その瞬間、殺気はすうっと消えた。 「きさまは、何者かに記憶を奪い去られている」 悠里の深みのある声が聞こえ、目を開けた。 「なんだって――?」 「思い出せ。確かに、きさまはアラメキアに行ったのだ」 「嘘だ。行ってない」 「おのれの過ちを認める勇気を持たぬのなら、きさまは初めから騎士になる資格はない」 「まだそんなことを」 憎悪をこめてにらみ上げながら、僕は叫んだ。 「そんなに雪羽の騎士が必要なら、あんたがなればいいだろう」 吐き捨てるように叫ぶ僕を、悠里はただ、じっと冷ややかに見下ろした。 「たとえなりたくとも、なれぬ。余は長く、雪羽の身近にいすぎた」 低い声の中に、どこか哀しい響きがこもっていた。 「それに、余には、地球で修めた学問をアラメキアに持ち帰り、人間国を再建するという使命がある。魔族を救うという雪羽の使命とは似て、異なるもの。余と雪羽は、ともには歩めぬ」 「また、アラメキアか」 その言葉を聞くたびに、僕の心に煮えたぎるような怒りが生まれる。 「そんなにアラメキアに命を捧げたいのなら、勝手にそうすればいいだろう。自分の思いを殺して、一生誰も好きになることなく、自己満足に浸っていればいいんだ! あんたも、雪羽も!」 「きさま」 悠里はぎりっと奥歯を噛みしめた。握りなおした剣先が、街灯の光を受けて、きらりと光る。 「待て! そこまでだ」 夜道の向こうから、もうひとりの男が現われた。 雪羽のお父さん。ゼファーさんだ。 「剣を引け、ナブラ王。これ以上の手出しは無用だ」 悠里は何か言いたげに見つめ返したが、すぐに剣をコートの下に納めて、踵を返した。 固い靴音を立てて彼が去っていくと、ゼファーさんは僕のそばに片膝をついた。 「だいじょうぶか。立てるな」 「……はい」 「あいつは若い頃は、武勇をうたわれた勇者だった。よく、持ちこたえたな」 背中の埃をはらってくれるゼファーさんの顔を、僕はまともに見られないでいた。 「あの……雪羽は?」 「今、佐和といっしょに家に戻る途中だ。落ち着くまでに、少し時間がかかったのでな」 「……すみません」 ゼファーさんは僕の謝罪を聞いて、笑顔を消した。 「謝る必要はない。俺も昔、おまえと同じ選択をした者だ。おまえを責める資格など、持ってはいない」 「……」 「雪羽のことは、心配するな。俺たちがあの子を守る――親とは、そのときのための存在だ」 僕はその言葉を聞いて、おずおずと顔を上げた。 ここへ来る間際に、お父さんとお母さんに向かって吐いた酷いことばを思い出してしまったのだ。 心がずきんと痛む。でもその痛みは何者かに持ち去られたように、すうっと消えてしまい、代わりに傲慢な思いが湧き上がってきた。 「オレ、やっぱり、あなたたちは少しおかしいと思う」 僕は自信を取り戻し、次第に語気を強めた。 「あなたたちはみんな、アラメキアのことが何よりも大切だと言うけど、この世界に住んでいる限り、この世界のことをまず考えるのが本当でしょう? 夢を持つのは大事だけど、現実から逃避したって、何も生まれないよ」 ゼファーさんは、黙って聞いている。 「オレは、今の生活を大事にしたい。女王とか騎士とか、使命とか、そんなことばに人生を縛られたくない。雪羽にも、そうであってほしいんだ」 そのときの僕は、心から自分が正しいと思い込んでいた。自分は正しくて、相手が間違っている。自分の演説に酔って、一方的な優越感にさえ支配されていた。 無礼なふるまいをしている僕を、雪羽のお父さんはただ、じっと見つめて、静かに答えた。 「いずれ、わかるときが来る。だが、そのとき自分を責めるな」 ゼファーさんは、その場に僕を残して歩き始めた。 その背中を見つめながら、どうしようもないやるせなさに襲われた。 「もう知るもんか!」 道端に落としていた木刀の鞘を拾い上げると、僕はほとんど走るようにして駅に向かった。 友だちの家に戻ろう。途中のコンビニで、たくさんお菓子を買い込んで。そして一晩中寝ないで、面白い話をたくさんして、楽しく過ごそう。 全部、忘れてしまうんだ――ゼファーさんの言ったことも、悠里に剣で惨敗したことも、そして雪羽を傷つけて別れたことも。 もういやなことは思い出したくない。 僕は、ぎょっとして足を止めた。 左手に握ったままだった木刀の鞘が、ざわりと動いたように感じたのだ。 鞘は見る見る間に木の枝葉に変わり、生き物のようにうごめき、蔓が僕の腕にからみつき始めた。 「うわあっ!」 僕は恐怖のあまり悲鳴を上げて、ふりほどこうと腕を振り回した。 もう一度見ると、蔓や葉っぱなどどこにもない。元通りの、緑色に塗った木の鞘だった。 「今のは……なんだったんだ」 僕まで、雪羽たちのおとぎ話に洗脳されてしまったのか。 「それとも――」 そのとき心に、ある恐ろしい考えが浮かんだ。 雪羽のほうが正しくて、僕の記憶のほうが間違っているということ。 夜がしらじらと明けるのを待って、僕はゆうべ雪羽と別れた公園に戻ってきた。 ゆうべは友だちの家に泊まり、夜更けまで思い出話をしたり、ゲームをしたりして遊んだ。 小学校のときに東京に転校していった剣道仲間と久しぶりに過ごすのは、それなりに楽しかった。でも、僕はずっと心の底にわだかまるものを抱えて、とうとう朝まで一睡もできなかった。 新聞配達の音が静寂を破り、街が動き始めたころ、起き上がって、『出かけてくる』と置手紙をして、友だちの家を出た。 ひんやりと湿った公園のベンチに座り、じっと考え続けた。 竹刀袋をときどき開けて、木刀を取り出す。鞘は元のままで何の変化もない。 「雪羽……」 動くものもいない、白い冬の朝。寒さにかじかむ手でマフラーを強く握りしめながら、僕は雪羽に無性に会いたくてたまらなかった。 どうして僕たちは、こんなことになってしまったんだろう。 雪羽は、ふたりでアラメキアに行ったという。でも、僕には行ったという記憶がない。 悠里が言ったように、本当に誰かが僕の記憶を奪い取ったのか。でも、何のために? 第一、そんなこと、まともに信じられるはずないじゃないか。この地球とは別の異次元の世界。ゴブリンやグリフォンがいて、精霊が住んでいるという、ゲームみたいな世界。 そこで、雪羽は、魔王の娘という存在で、僕はただ一人、彼女に定められた騎士だという。 「冗談じゃない。勝手に人の未来を決められて、たまるもんか」 いつのまにか、大声でひとりごとを言っている。 「僕は、僕だ。誰の命令も受けない。誰からも支配なんかされない。たとえ、相手が雪羽であっても」 まるで呪文のように呟き続けている自分に気づき、口をつぐんだ。気持が滅入っていて、それでいて興奮している。めちゃくちゃな気分だ。 まるで自分が自分でないみたい。僕はいつから、こんな状態になってしまっていたんだろう。 アラメキアなど、おとぎ話だ、夢物語だと完全に否定しておいて、一方では、アラメキアに行くことを、ひどく恐れている。 『現実から逃避したって、何も生まれないよ』 ゼファーさんに偉そうな説教をしておいて、結局僕の心を占めているのは、自分のことだけ。自分が一番大事で、自分にとって損なことから逃げ回っているだけ。 (もしかして現実から逃避しているのは、オレのほうなのか。雪羽の騎士になることが怖いあまり、アラメキアの存在を否定しているのか) そこまで考えたとき突然、何かがいるのを感じた。とてつもない殺気をまとった存在が、間近にいる。 ベンチから弾かれたように立ち上がり、横に飛んで身をかがめた。 誰もいない。 竹刀袋から木刀を取り出し、鞘を払って構えると、剣先を360度探索するように回した。 ある一点で、剣先がぴたりと止まった。 何かに当たった。物質ではない何か。どろどろの気体のようなものだ。 僕は慎重に狙いを定めながら、深く呼吸をし、ぐっと息を止めて木刀を振り下ろした。 だが、刀は空を切るだけだった。何度も角度を変えて仕掛けてみたが、やはり何も手ごたえがない。 気のせいだったのか。あきらめて、木刀の握りをゆるめた。 その瞬間を待っていたかのように、見えない敵は襲いかかってきた。その拍子に刀は手から離れ、地面に落ちた。 真綿で首を絞められたみたいに、呼吸ができなくなる。 ああ、やっぱり僕は馬鹿だ。お父さんに、残心を忘れるな、勝負が終わっても気を抜くなと、口を酸っぱくして注意されているのに。 膝が力を失い、四つんばいになる。苦しまぎれに、絞められている喉に思わず手をやると、マフラーが指先に当たった。 雪羽のマフラー。 「雪羽……」 なんとかして、這ってでも木刀を取り戻さなければ。けれど、視界が急に狭まり、闇雲に突き出した手に触ったのは、木刀ではなく、投げ捨てていた緑の鞘だった。 残っていた力で鞘を鷲づかみにすると、自分の喉に向かって突き上げた。 草の葉や蔓が一息に広がって、空中に浮かんでいるものを包み込んだ。バチバチと火花が散り、その衝撃で見えない力も、そして僕自身も吹き飛ばされる。 一瞬気が遠くなり、地面に横たわった僕の耳に、かすかに声が聞こえてきた。 「聖――」 「……ゆ、雪羽」 ほとんど目が見えないまま、必死で起き上がろうとした。 伸ばした手を、誰かがぎゅっと掴んだ。 「聖」 オーバーも何も着ていない。フリースのパジャマ姿の雪羽が、涙をいっぱい目にためて、僕に何か言おうとしている。 「あぶない、ここから離れて」 必死に叫んだつもりだったが、声にならない。 「逃げるんだ。雪羽!」 雪羽は、僕の拳を両手で握りしめたまま、祈るように目を閉じて、唇を押し当てた。 その瞬間、雪羽が銀色の光に包まれるのが、見えた。 |