「EWEN」&「魔王ゼファー」クロスオーバー企画第3弾
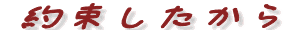
|
エピローグ ―― 雪羽 私はベッドから起き上がると、白み始めた窓の外を見つめた。 「眠れないのか」 いつのまにか、父上が部屋に入ってきた。父上もきっと、私を心配して一睡もしていないだろう。 「ううん」と私は答えた。 「大丈夫、少し寝たから」 「母上に、ミルクを温めてもらうか」 「今は要らない」 「それなら、もう少し寝ていろ。まだ夜は明けておらん」 無理矢理ベッドの中に戻されると、父上は私の額を大きな手でそっと撫でた。 長年、機械油にまみれた、荒れた手。この手で、父上は私と母上のために、懸命に働いてきたのだ。 「聖のことを恨んではならん」 父上は、子守歌のようにゆっくりと言った。 「恨めば、自分の真実を汚すことになる。いつか笑顔で話せるときが来る。俺と精霊の女王も、今では腹にあることを何でも話せる仲になった――多少、時間はかかったがな」 「父上は」 さんざん泣いたあとだったので、私は少し声がかすれていた。 「もし、精霊の女王がここに現われて、父上を今でも愛しているとおっしゃったら、どうする?」 父上は、喉の奥でクッと笑った。 「それは、愚問というものだな。人の思いは、決して後戻りはできない」 「そうだな」 「わかっているくせに、親をからかうものじゃない」 そうだ。父上と母上が20年近く大切に育んできた愛情を、私はよく知っている。だから私は安心して、ふたりが築き上げたこの家に帰ってくることができるのだ。 心ゆくまで、こうやって、ふたりのそばで泣いていられるのだ。 私も、そのような絆を、聖といっしょに育みたかった。 またあふれだした涙を隠すために、私は目元まで、掛け布団を引き上げた。 父上は何も見ないふりをして、額を撫で続けてくれる。 だが、その時私は、耳元で聖の声がするのに気づいた。 「……雪羽」 苦しい息の合間の、しぼり出すような声。 「聖!」 私は跳ね起きて、父上の制止も振り切って、部屋を飛び出した。 玄関で、手近な靴をひっかける。パジャマのままで夜明けの街を走った。 足は自然と、何かに導かれるようにして、ゆうべ聖と別れた公園に向かっていた。 聖は、何者かに馬乗りにされている恰好で、地面に仰向けになっていた。 駆け寄って手を握りしめると、薄茶色のきれいな瞳で何かを訴えるように、私を見た。 あの冷たい色ではない。いつもの聖に戻っている。 強ばった拳をしっかりと握りしめ、唇を当てると、聖の身体が銀色に光り始めた。 邪悪な気配は、その銀色の光を浴び、溶けるように次第に姿を消していく。 やがて、すべてが静寂の中に降り立った。 朝陽が木々の梢を、柔らかなオレンジ色の指で包み込み始めた。だが気がつくと、五本の指をぱっと広げたみたいに、まぶしい光が公園に満ちていた。 聖は立ち上がり、私のことをまじまじと見た。 どうすればいいのか、何を言えばいいのか、わからない。彼の目を見つめ返すのがやっとだ。 彼は黙って自分のオーバーを脱いで、パジャマしか着ていない私の背中にかけた。そして手編みのマフラーをはずして、首に巻いてくれた。 「雪羽」 苦しそうに言うと、もう次の瞬間、私は彼の腕の中にいた。 「――全部、思い出した」 「え……?」 「オレたち、いっしょにアラメキアに行った。森を抜けて、草原を突っ切って、旅をした。魔族の長老にも、精霊の女王にも、ちゃんと会ったんだ」 「……」 夢にまで見たことばに、胸が破裂しそうだ。 「ごめん。ごめんなさい」 聖は、ぼろぼろと私の肩で泣いていた。 「あんなにひどいことを言って、きみをあんなに傷つけて、オレ、どうしたら赦してもらえる?」 「こうしてくれるだけでいい」 私は、やっとのことで答えた。「これで、十分だ」 公園の入口に数人の影が見えた。 父上。悠里。それに、ヴァルもいる。みんな心配して、駆けつけてくれたのだろう。 「それだけじゃない」 聖は私から体を離し、何度もすすりあげた。 「オレ、出がけにお父さんとお母さんにひどいことを言ったんだ。――『自分たちが勝手に熱くなって、くっついただけだろ。生まれてくるほうは、迷惑なんだよ』って。お父さんとお母さんが、どんな思いで国を越えて結ばれたのか、オレは一番よく知ってるのに」 混血だということで、聖がときどき辛い目に会っていたことを、私はうすうす知っていた。その耐えていたものが爆発して、そんなことを言わせてしまったのだろう。 「オレ、高校に合格が決まってから、ますます自分がどう生きればいいか、目標を見失ったような気分になっていた」 少し落ち着いてきたのか、聖の声が自分の内側を見つめるように、いつもの考え深い話し方に変わっていた。 「雪羽の騎士になることを考えるたびに、そうなりたい自分と、拒否している自分がいた。オレはアラメキアのことで頭がいっぱいの雪羽といっしょにいるなんてイヤだ、オレを一番大切にしてほしい。オレのことを何よりも真っ先に見てほしいって――醜い気持でいっぱいになってた」 「すまない」 急激に、それまでの喜びが萎えてくるのを感じた。 「私も、聖のことだけを考えていたい。けれど、やはり私は、アラメキアを選ぶしかないのだ。それは、私にしかできないことなのだから。アラメキアの平和のために、この身を捧げたい。――それなのに、一方的に守ってほしいだなどと聖に言える資格はない。怒るのは当然のことだ」 「ううん」 聖は首を振り、力強く暖かい眼差しを私に注いだ。 「だからこそ、やっぱりオレ、雪羽が好きだ」 「……」 「アラメキアに夢中になっている雪羽が大好きだ!」 私は何も答えられずに、呆然としているだけだった。聞いたことばが信じられない。こんな私でも――聖は好きだと言ってくれるのか。 「私は、これからも聖よりアラメキアを優先してしまうかもしれないのに?」 「うん、わかってる」 「偉そうな口を利いて、ちっとも女らしくなく、自分の都合で聖を振り回して、命令ばかりしていて……」 「それでも、いい。ちゃんとついていく。オレ、雪羽の騎士になるんだから」 「え……?」 「オレ、まだきみの騎士にしてもらえるかな?」 彼は突然、私の前にひざまずいた。「騎士の誓いって、映画だと確かこんな感じだよね」 「ひ、聖」 私はうろたえて数歩、後じさった。 「待ってくれ。こんなところで。今、聖は動揺しているだけだ。もっと落ち着いて、よく考えて……」 「いくら考えたって、同じだと思うな」 まっすぐな、クソ真面目な目つきで私を見上げる。 「こういうのは、早いほうがいい。騎士になってしまったほうが、お父さんとの剣の修行にも身が入るし、また醜い考えに取りつかれそうになったら、この誓いを思い出せばいい」 「だが……」 私がどうすればいいか、わからないでいると、 「余が介添えをしてやろう」 いつのまにか悠里が、私たちのそばに立っていた。 「騎士叙任の儀式には、剣と介添え人が必要だ。余の剣を貸してやろう」 「悠里おにいちゃん」 「だが」 彼は険しい藍色の目を、聖に向けた。 「騎士とは、一度叙任されて終わりではない。たえず騎士であり続ける努力が必要だ。不適格とわかれば、いつでもその役目を失う。それでもよいな」 「はい」 聖はうなずいた。 「あなたが言っていた、オレの記憶を奪ったモノの正体、やっとわかりました。あれは自分のことしか考えない、オレ自身の弱い心だったんですね」 「そうだとも言えるし、そうでないとも言える」 「どういうことですか?」 「説明してもわからぬ。今は、まだわからずともよい」 謎めいた言葉だった。本当に何かの存在が、聖に取りついていたとでも言っているみたいだ。今の私たちには決してわからない、巨大な何かが――。 「だが、やがて再びそれと対峙するときが来よう。そのときまでに力を蓄えておけ」 「わかりました」 「そなたの剣を身体のわきに置け」 聖が言われたとおりに、木刀を緑の鞘に収めて地面に置くと、悠里は私に自分の剣を握らせ、聖の肩に左、右、左の順番に触れた。 「聖。そなたを騎士として叙任する。雪羽をそなたの主として守り、その命のある限り、これに仕えよ」 「はい」 聖は、頭が地面に着くほど深く拝礼すると、顔を上げた。 その顔は、今まで見たこともないほど神々しく、凛々しく、私は目がくらみそうになった。 本当に、私が女王で聖が騎士なのか。もしかすると、まったく逆に、聖のほうが王なのではないか。 そんな思いに囚われて、頭がぼうっとしていたとき、悠里が私に近づいてきて、聖に聞こえないように小声でささやいた。 「雪羽。これからも気をつけろ」 「気を……つけるとは?」 「目に見えぬ敵は、おまえと聖を引き離そうと、これからも何度でも狙ってくるだろう。ゼファーもかつて、その計略によって、精霊の女王との仲を引き裂かれたのだからな」 「なんだって」 戦慄して、私は叫んだ。「父上も?」 父上が邪念に取りつかれて魔王となり、精霊の女王に謀反を起こしたのは、陰で何者かが、そう仕向けていたのか。 「アラメキアにおいては、女王と騎士がひとつ心になることこそ、力ある存在を滅ぼす唯一の手段だからだ。敵はこれからも、聖の心を悪に染めようと攻撃してくるはず」 「敵とは、いったい誰なのだ」 悠里は首を振った。 「余にも、まだわからぬ。ただアラメキアを滅ぼし、その上で、この地球を掌握しようとする力――それだけは確かだ」 聞きながら、視界がくらくらと揺れているような思いだった。アラメキアを滅ぼしたうえで、地球を手に入れる? 理解できない。いったいどういう意味なのだろう。 混乱している私に、悠里は屈みこんで、なおも混乱するようなことを耳打ちした。 「それから、もうひとつ言っておく。おまえは今、三人の男を奈落の底に突き落としたのだ。そのことも忘れるなよ」 「え?」 悠里は、向こうで待っていた父上とヴァルのもとに歩いていき、ふたりの肩に腕を回して、高らかに笑った。 私たちは元通りふたりきりになった。 公園じゅうに、春を思わせる暖かな陽光がふりそそいでいる。 「雪羽。あの……」 聖は、さっきの威厳に満ちた様子とは打って変わって、恥ずかしそうに言った。 「騎士になったからって、敬語で話さなくて……いいよね?」 「あたりまえじゃないか」 私は吹き出しそうになった。 「今までと同じでいい。私たちはこれからも、変わる必要はない」 「そうだよね」 とたんに彼は、晴れやかな表情になった。「じゃあ、これからどこに行こう」 「これから?」 「昨日一日を台無しにしちゃったから、これから急いで取り返す。どこに行きたい? ……ああ、その前に、お父さんとお母さんに電話して謝らなきゃ。それに昨日ご馳走を用意してくれてた佐和さんにも」 「聖は、いつまで、東京にいられるんだ?」 「何日でも、高校が始まるまで」 聖はいたずらっぽく言ってから、愉快そうに付け加えた。 「うちのお母さんも、大学が始まるまでずっと、お父さんのいるドイツに押しかけて、そのまま結婚しちゃったんだ」 「……」 「だから、オレも春休みのあいだじゅう、ずっと雪羽のそばにいる」 突然口をつぐんだ聖は、真顔になった。その表情を見たとき、聖のさっきのはしゃぎようは、無理をしていたのだということがわかった。 聖は今でも心の底で、自分のことをひどく責めている。 「オレ……もしかして、これからも雪羽を傷つけるかもしれない。悠里さんは、オレの中にあったものが、『アラメキアを無きものにしようとする力』だと言っていた。だとすれば、オレはまたいつか、その力のせいでおかしくなってしまうかもしれない」 私に向けられた茶色の瞳が、不安に揺れている。 「だとしても、だいじょうぶだ」 私は、穏やかな、母親のような気持でほほえんだ。 「私がそばにいる。必ず聖を、邪悪な力から守る。だから聖も、私を守ってほしい」 「うん、約束する。ずっときみのそばにいて、きみを守る」 聖はおずおずと私の手を取った。そして、少しためらいながら言った。 「騎士になっても……キスは、いいよね?」 恥ずかしさに心臓がドキンとはねたが、同時に幸せがこみあげてきた――今までの悲しみが帳消しになって余りあるくらいの。 にやけそうになって、あわててツンと取り澄まし、顎を持ち上げる。尊大な女王がするように。 「ダメだ。手の甲になら、許す」 けれど我慢できなくなって、大笑いしてしまった。 「雪羽!」 聖は怒った声を出すと、私の首にかけていたマフラーをぐいと自分のほうに引っ張った。 その勢いで、私たちはぶつかるように体をくっつけた。 私たちのほかには、公園にはまだ他の人影はなかった。だが、もしいたとしても、たぶんマフラーの陰で、誰にも見えなかったはず。 お互いを抱きしめ合いながら、マフラーはとても長い間、ふたりの首に巻きついたままだった。 ―― 終 ―― よろしければ、感想をお寄せください。 |