「なんや、誰かと思うたら、藤江姉さんか」
「惣一郎。こないなところで油を売ってる場合か。あんたもオペラに出るんやろう」
「それを言うなら、姉さんもやないか」
「うん、ちょっと客席から舞台を見たくなってな」
「きれいなセットやな。庭も家も細部まで造りこんであって、まるで本物や。さすが太秦の映画スタッフ総出で準備をしただけはある」
「『蝶々夫人』か……。確かに円香とディーターが主演するにはぴったりの話やけどな。私、なんだか切なうなってしもて」
「なんでや」
「だって、蝶々夫人は、国に帰った夫のことを想ってずっと待つんやろ。まるで、聖がお腹の中にいたときの円香を見るようで……泣けてしまうわ」
「まあ、そやな」
「ディーターがよく引き受けたもんやって、みんなびっくりしとった。だって、ハリウッドのチェン監督からの主演の打診さえ、頑として断ったやろ。殺陣の監修ならともかく、映画に出るのは絶対いややって」
「そう。今回も出るつもりはなかったみたいやけどな。名精神科医・葺石惣一郎がちょちょいと細工をしたんや」
「細工? なんの」
「つまりな。あいつを強制的にユーウェンにしてある」
「なんでやのん! ディーターはもう人格統合されて、二度とふたつに分かれることはなかったんちゃうの」
「そこが俺の腕の見せどころや。催眠術や暗示や、ありとあらゆる手段を使ってだな」
「……あんた、今に医師免許、剥奪されるで」
「とんでもない。これはディーターのためや。あいつは、いくら言うてもユーウェンであった部分を隠して、いい子になろうとするんや。このままやと、将来また精神的に不安定にもなりかねん」
「それは困るわ」
「そこで、舞台という場を借りて、おおっぴらに自分を解放する場所を作ってやったというわけや。これも治療の一環なんや」
「ふうん。なんだかわかったような、わからんような」
「脇は、本物の映画俳優である康平くんや、一番ユーウェンのことを知り尽くしてる円香で固めてある。最高のオペラになるで」
「ディーターは歌も巧いし、おまけにあのルックスやし、康平くんとふたりで並べば、女性客がバタバタ卒倒するかもしれん」
「さあ、そろそろ行こか。俺も姉さんも、ほんの端役やから準備もいらんけどな」
「あーあ。私ももうちっと、ええ役がもらいたかったな。『魔笛』の夜の女王とか、『マイフェアレディ』のイライザとか」
「……それこそ、観客が卒倒してまうわ」
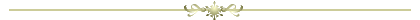
配役表:
蝶々(長崎出身の娘) : 円香・グリュンヴァルト
ピンカートン(合衆国海軍士官) : ディーター・グリュンヴァルト
シャープレス(長崎在住の合衆国領事) : 鹿島康平
スズキ(蝶々の女中) : 柏葉瑠璃子
ゴロー(結婚斡旋屋) : 柏葉恒輝
蝶々の伯父(僧侶) : 葺石惣一郎
蝶々の母 : 大谷藤江
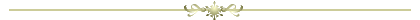
第一幕(第一部)
明治の御世となり、すでに数十年が経っていた。
長崎の町に居を構えるアメリカ人も、珍しくはない。
今日も、ひとりの金髪の青年が斡旋人とともに、丘を登っていく。
まばゆいばかりに白い制服と金の肩章とボタンが、合衆国海軍士官という男の身分を表している。
「まったく、なんと坂の多い街だ」
彼はつぶやきながら、汗ばんだ髪を掻き上げ、来た道を振り返った。
高台から見ると、長崎の町並みはどこも、煙るような桜に彩られていた。
「どこもかしこも同じような黒い瓦屋根、そして、同じ花だ」
嘲るような調子でつぶやく男の目は、自分が住む街からなるべく遠ざかりたいと願っているようだ。
「ピンカートンの旦那さま。あなたは運がいい」
坂道を先導していたゴローという日本人が、あえぎながらも陽気に言った。
「桜の花が見頃なのは、ほんの一週間。その最良の季節に、あなたは妻をめとられるのだから。それも最良の女性を」
「ふん、いくら褒めちぎったところで、斡旋料の上積みはしないぞ」
「もちろんですとも……ほら、見えました。あれ旦那さまの新しい愛の家です」
「欲深い商人め。こういう奴が外国のことばを操る巧みさと言ったら」
斡旋屋の後について、手入れの行き届いた庭を歩いていくと、小さな池の向こうに日本家屋が見えてきた。
「驚いたな。本当に竹と紙でできた家だ」
感嘆したように、彼は口笛を吹いた。「風が吹けば、飛んでしまいそうだ」
「とんでもございません。この柱の頑丈さを見てください。それにほら、この屋根の上等な瓦」
ゴローは顧客のご機嫌を取ろうと、あちこちを見せてまわる。
「ベッドルームはどこだ」
「こちらでも、あちらでもお好きなところに」
「何でも兼用ということか」
「襖を開ければ、ほらこのとおり大広間に。障子もこのとおり、するすると動かせます……おっと旦那さま」
ゴローはあわてて、ピンカートンの靴を指差した。「日本では、家の中は靴をお脱ぎにならないといけません」
「自分の家だというのに、靴をはく自由もないのか」
「靴を脱いでも、決して靴下は汚れません。働き者の女中と下男がきれいに掃除をしますゆえ」
ゴローがぽんぽんと手を叩くと、三人の日本人の召使が現われた。
「こちらは、身の回りのお世話をするスズキ。奥さまには以前から仕えていた女です。そちらは料理人と下男」
『旦那さまのおやさしそうな微笑を見て、安堵いたしました』
スズキは深々と丁寧な一礼をすると、人懐っこい調子の異国語で話しかけてきた。
『笑う門には福来ると申します。笑いは人の心のもつれを解きほぐします』
まったく日本語を解さないアメリカ軍人は、眉をひそめた。
「何を言ってるのだ、この女は」
「旦那さまの笑顔が素敵だと申しております」
「おしゃべり女め」
ピンカートンは庭を見るふりをして、彼らから離れた。
「俺の笑顔は、人をあざむくためだけのものだ。竹の空洞のように中身はない」
ゴローは、せかせかと庭に降りてきて、丘のふもとをじっと見下ろした。
「そろそろ、花嫁の行列が来るころです」
「準備は整っているか」
「すべて万端です」
「さすが優秀な斡旋屋だ。家も女も思いのままだな」
「それとともに、日本の戸籍係の役人、花嫁の親族、それからお国の領事さまがいらっしゃいます。……おお、噂をすれば」
坂道の下から、男の声が近づいてくる。
「やれやれ、もう少しだ。なんという石ころだらけの道だ。まったく年は取りたくない」
敷地内に、白髪まじりの温厚そうな男が、息を切らしながら現われた。合衆国の長崎領事、シャープレスだ。
「遠いところまでようこそ。領事閣下」
ピンカートンは彼と握手を交わした。
「ずいぶんと高台を選んだものだね。中尉」
「そのかわり、景色はすばらしい」
「本当だ。長崎全体と海が見晴らせる。港に停泊しているエイブラハム・リンカーン号のマストの旗まで、くっきり見えるな」
ふたりの男は、並んで景色を見つめた。
後ろでは、ゴローの指図で下男たちが飲み物の用意を始めた。
「いい家だ。障子も張り替えたばかり。タタミの匂いが青々としている」
シャープレスは数年の駐在中に、日本の文化によく精通していた。
「この家はきみが買い取ったのかね?」
「期限つきで借りました。999年のね」
ピンカートンは揶揄するように微笑んだ。「999年など永遠と同義語だ。しかも、予告なしにいつでも解除できるという約束です。この国には、契約という概念がまだない。どうとでもなります。家の間取りのようにね」
「確かに開国からわずか数十年。日本の社会はまだ幼い。しかし同時に驚くほど成熟している面もある。なにしろ、わが祖国の何十倍もの歴史があるのだ。馬鹿にしたものでもないよ」
「肝に銘じておきましょう」
「だが、そういう未熟さをうまく利用するに越したことはない」
「まったくだ」
ふたりは縁側に腰をかけると、ウィスキーを満たしたグラスを打ち鳴らした。
(ピンカートン)
世界じゅうどこでも 放浪者のヤンキーは
危険を物ともせずに
享楽し、取引する。
嵐が船と索とマストをめちゃくちゃにするまで
すべての土地の花々と
すべての美しい女の愛を
自分の宝にしなければ
人生に満足できない。
「危うい男だ。人当たりはよく魅力的だが、目の底には北海のような氷を抱えて、人の真心を寄せ付けない」
シャープレスは同国人の横顔を見つめながら、そっとつぶやいた。
「だから、俺は999年の契約で結婚するのです」
ピンカートンはウィスキーのお代わりを並々と注ぎ、少し持ち上げて笑った。「いつでも自由になれるという条件でね」
「なんという軽薄なことばだ。この男と結婚する女性は、真の愛を受けられるのだろうか」
領事は、日本人の斡旋屋に顔を向けた。
「花嫁は美しいかね」
「編んだばかりの花の冠のようにみずみずしく、金色の空の星のようにまばゆく、しかもただ同然。たったの百円でございます」
彼はにやりと嫌らしい笑いを浮かべた。「旦那さまもおひとりいかがですか」
「いや……遠慮しておこう」
そのとき、ピンカートンは突然、立ち上がった。
「まったく遅い。ゴロー。下まで迎えに行って来い」
「は、はい」
ゴローが走り去り、軍人が苛立った様子で庭を歩きまわるのを、シャープレスはじっと見つめた。
「落ち着かないようだな。花嫁にのぼせておられる?」
領事は軽い冗談のつもりだったが、ピンカートンは冷ややかに彼の顔を見返した。「のぼせているだと?」
「気に障ったのなら、失礼」
「いや、確かに……俺はのぼせているのかもしれません」
ピンカートンは、喉の奥を鳴らして小さく笑った。
「愛なのか、気まぐれなのか。彼女にはまだ、一度しか会っていません。けれど初めて会った瞬間、心臓が縛られたような心地がしました」
彼は歌うように、続けた。
「肌は透き通るようになめらかで、あでやかな日本のキモノを着た姿は、まるで屏風から抜け出たよう。身のこなしは無邪気で軽やかで――まるで俺には、蝶々がひらひらと舞っているように見えた」
「蝶々?」
「実際、彼女の名前は『お蝶』というのです。その優雅な気まぐれさを見ていると、追いかけていって、羽根を傷つけてでも自分の手に収めたいという衝動に駆られました」
ピンカートンが冷ややかな表情で、蝶を握りつぶすように両手の拳をぎゅっと握りしめたのを見て、シャープレスは背筋にぞっと悪寒が走るのを感じた。
だが、次の瞬間、彼は元の柔らかい笑みを浮かべた。「失礼。馬鹿なことを言ったようです」
「実はおととい、花嫁が婚姻の手続きのために、領事館を訪れた」
領事は真剣な調子で言った。
「副領事が応対に出たため、わたしは執務室から彼女の声を、聞くとはなしに聞いていたのだ。まるで鈴がころがるような神秘的な、それでいて一途な声……それを聞いて感じた。この人は恋をしていると」
「恋? まだ一度しか会っていない男に?」
「中尉。きみに忠告しておきたい。きみを信じきっている女性を惨く突き放し、蝶の羽をむしるようなことをしてはいけない。あの可愛い声を、悲嘆の嗚咽に変えてはいけない」
「心配のしすぎです。親切な領事閣下」
ピンカートンは、硬い防波堤のように心を閉じた笑みを浮かべた。
「あなたの年配の方は、みなさん悲観的な物の見方をなさる。ものごとは、考えるより先に飛び立つほうがうまくいく」
「……」
「もう一杯、いかがです?」
「いただこう。本国にいるあなたの家族の健康を祝して」
「そして、アメリカのどこかにいる未来のピンカートン夫人のために」
そのとき、丘の中腹から、ざわめく声が聞こえた。
「いらっしゃいました! 聞こえるでしょう、大勢の女たちの声が」
ゴローの大声が庭に響いた。
ふたりのアメリカ人は、門のほうに急ぐ。
『遅いわよ。蝶々さん』
『あと一息、ああ待って……花嫁衣裳って、すごく重いのよ』
たくさんの少女たちの集団。そして、角隠しと白いヴェールをまとった少女が息を切らしながら、遅れて現われる。
『ほら、後ろを見てごらん。広い海と広い空。花も木も、何もかもがすごくきれい』
『ああ、本当』
蝶々はあこがれるような表情で、空に向かって両手を広げた。
(蝶々)
喜ばしい春風が
海や大地の上を吹いています。
私は日本中で、いいえ、世界中で
一番喜びにあふれた娘です。
みなさん 私は愛に誘われて来たのです。
私は愛の戸口にさしかかりました。
ここには生者と死者の幸福が集まるのです。
新居に着いた花嫁は、出迎えに降りてきた外国人たちの姿に気づいた。
『ほら、みんな挨拶して。あれが私の美しい旦那さまよ』
蝶々はピンカートンの前に進み出ると、優雅に深くお辞儀をした。
「お目にかかれて、嬉しゅうございます」
娘たちも、真似をして口々に言った。
「おめにかっかって、うれしーございます」
ピンカートンは、うっすらと微笑んだ。「坂道は大変だったでしょう?」
「心が先に着きました。体よりも心が、とても早いのです」
蝶々は拙い英語で、懸命に自分の気持を表わした。
「愉快な挨拶だ」
ピンカートンの顔に、かすかに侮蔑の色が混じった。
「もっともっと、挨拶できます。たくさん覚えました。英語の、挨拶」
「ありがとう。今は結構」
シャープレスが見かねて話しかけた。
「蝶々さんとは、美しいお名前です。長崎の出身ですか」
「はい。長崎。大村で、生まれました」
彼女はまた生き生きと、身振り手振りで話し始める。
「家、とてもお金持ちでした。でも、大きな風が吹くと、大きな木も倒れる。家は今、とても貧乏。だから芸者になりました」
「彼女の家は、維新で没落した武士の家です。家族の生計を支えるために、彼女が身売りしたのです」
ゴローがこっそり後ろから、アメリカ人たちの耳にささやいた。
「ご兄弟かご姉妹は」
「いえ、母だけ、ひとりです」
「お父上は」
「……死にました」
「彼女の父は、不名誉な疑獄事件で断罪を受ける寸前、家で切腹したのです」
ゴローがまた、耳打ちした。だが、ピンカートンは花嫁の素性など関心がなく、切腹ということばに眉をひそめただけだった。
「まるで陶器の人形のようだ。美しいが、言葉がこれでは気持が通じ合わない」
「ピンカートン中尉。これだけ英語をしゃべるようになるために、彼女がどんなに苦労したか考えてみたまえ。きみは日本語をこれだけ話せるようになれるか」
「どうせ、俺には異国のことばを習い覚える必要などありません。長くいる気はないのですから」
シャープレスは不機嫌に口をへの字に曲げたが、どうしても気がかりなことを思い出して、蝶々に訊ねた。
「あのお嬢さん。大変ぶしつけな質問ですが、あなたはおいくつです?」
「いくつに、見えますか?」
「……二十歳くらい?」
「いいえ、ちょうど十五歳。なって少しです」
「十五歳!」
「十五歳だと?」
シャープレスとピンカートンは異口同音に叫んだ。
「もう、お婆さんです」
蝶々さんは恥ずかしそうに、くすくす笑った。
「この若さで身売りをしたということか。なんという」
アメリカ領事は、義憤に震えた。「まだ、お菓子を食べたい年頃ではないか!」
そのとき、庭の向こうからガヤガヤという集団のざわめきと、大きな笑い声が聞こえた。
「お役人さまと、ご親族のみなさまがお見えです」
「早く、祝宴の準備を」
ピンカートンに命じられて、ゴローは家の中にそそくさと引っ込む。
「失礼します。旦那さま」
蝶々は膝を少しかがめると、集団のほうに走っていった。
彼女と親戚のあいだで、おおげさな挨拶と、ぺこぺことお辞儀の応酬が始まる。
「まるで、首がバネでできたピエロのおもちゃだ」
ピンカートンはこらえ切れぬように口元に拳を当て、悪意のある笑い声を漏らした。
「たかが月極め契約の結婚に、これほど大仰な行列が来るとは。あの騒がしい女が俺の義母だと? あの飲んだくれが、俺の義理の伯父になると?」
彼はこっそり奥歯を噛みしめた。「虫唾が走る!」
親族やいとこたちは、ふたりの西洋人の男たちを怖そうに遠巻きに眺めている。
「おまえの花婿はどっちの方だ?」
「あちらよ」
「まあ、りりしくてお殿様のよう」
蝶々の母親は目をうるませている。
だが、口さがない同年代の女友だちは、やっかみ半分でささやき合った。
「背がなんて高いの。顔が見えないわ」
「透き通ったガラスのような目玉。どこを見ているのかわからない」
「ことばも通じないのに、外国人と結婚する蝶々さんの気がしれない」
「こんな結婚、うまくいくわけないわよ」
女友だちの中にいる蝶々の様子を観察していたシャープレスは、感慨深げにつぶやいた。
(シャープレス)
ああ、幸せな友よ!
ああ、幸せなピンカートン
貴方は運よく
清らかで蕾が開いたばかりの花に巡り合った。
この蝶々さんほど
美しい娘は見たことがない。
たとえ貴方には戯れ言でも
契約と彼女の真心を
大切になさるがいい。
彼女は真剣だ。
ピンカートンは進み出ると、蝶々の手を取り、親族から引き離した。
「おいで。家の中を見せよう」
ふたりは縁側から家の中に入った。
「気に入ったかい?」
ピンカートンは、後ろから柔らかく包み込むように彼女を抱きしめた。
「あ、あの、ピンカートンさま。ちょっと」
蝶々は真っ赤になり、体をよじって、するりと抱擁から抜け出した。
「すみません。あの……荷物がたくさん、重いのです」
「荷物?」
彼女は、両腕を広げて見せた。振袖の袂が、異様にふくれている。
「日本の着物は、袖がバッグになっているとは!」
あきれたようにピンカートンがつぶやいた。「こんな状態で、坂道を登ってきたのか」
彼は畳の上に片膝をつくと、蝶々の袖の中から手早く、入っているものを取り出してやる。
「それは、手ぬぐいといいます。それは留め金。それは扇で……あっ、鏡だわ。気をつけて」
「こうして着物の袖を広げた姿は、まさしく蝶だ」
不思議な感動を覚えながら、ピンカートンは、かりそめの妻となる娘を見つめた。
「この瓶は?」
「それはお歯黒。歯を黒く、するのです」
蝶々は人差し指で、自分の歯に塗る真似をしてみせた。
「ごめんだな。そんな気味の悪い習慣は」
「お嫌、なのですか。じゃあ、捨てます」
と惜しげもなく、庭に放り投げる。
「この箱は?」
「あ。それは……」
蝶々は彼から木の箱を受け取ると、畳の上にかしこまって正座した。
「これは、父の遺したもの。カタミ」
箱を開けると、中に入っていたのは数体の仏像だった。
「でも、これも捨てます」
「なぜ?」
「きのう、私は行きました。教会。ひとりでこっそりと」
蝶々は寂しげに、けれど少し誇らしげに説明した。
「誰も知りません。家族も、僧侶の伯父も。私、洗礼受けました。あなたの神さまは、私の神さま。あなたのお祈りは、私のお祈り」
その黒い瞳は熱を帯びて、きらきらと光った。
「あなたと新しい生活、始めます。あなたの喜ぶこと、好きになります。家族の喜ぶこと、忘れます」
ゴローがするすると障子をすべて開け放った。
式の準備が整った広間に、立証人として役人やシャープレス領事が入り、立って待っている。
正面に漆塗りの台が置かれ、その前に用意された椅子に蝶々は腰掛け、ピンカートンはその傍らに立った。
花嫁の親族や友人たちは、庭から式の様子を見守っている。
役人が立ち上がり、おごそかに誓詞を述べた。
「アメリカ合衆国海軍、砲艦リンカーン号中尉、ベンジャミン・フランクリン・ピンカートン殿と、長崎県大村の令嬢、お蝶が、夫婦の契りを結ぶことを、法によってここに認めます。
新郎はみずからの意志により、新婦は、証人としてここに居並ぶ親族一同の承諾によって」
ふたりは、台に置かれた誓約書にそれぞれ署名する。
「すべて、相整いました」
役人の宣言に、庭から娘たちの歓声があがる。
「蝶々夫人!」
「ピンカートン夫人よ」
蝶々は人差し指を振って訂正しながら、くすくすと笑った。彼女が庭に降りると、わっと人垣に包まれる。
役人たちも靴を履いて、庭に降りた。
「それでは、ピンカートン殿。結婚に関する手続きは無事終わりました。おめでとうございます」
「ありがとうございます」
「子孫の繁栄をお祈りします」
「努めましょう」
「領事さんも、お帰りになりますか」
「ええ、ごいっしょします」
シャープレスは去り際に振り返ると、ピンカートンの耳に、すばやく忠告のことばを残した。
「できるだけ思慮深くな」
賓客たちが立ち去るのを門まで見送ると、家の主は嫌な記憶を吐き出すような短い吐息をつき、頭を振った。
「厄介ごとが、ひとつ終わった。あとは客どもを、さっさと追い返そう」
庭ではゴローや下男たちによって、祝杯がふるまわれていた。
『血のように赤い酒! 番茶のような色の酒!』
『乾杯。乾杯!』
「今日の良き日を祝って」
ピンカートンは、元のように一部の隙もない笑みを浮かべて、客たちと杯を交わした。
突然、庭の一角で、祝宴には不似合いな怒鳴り声が始まった。
僧侶だという蝶々の伯父が、真っ赤な顔をして仁王立ちになっている。
『蝶々、今聞いた噂は本当なのか』
彼女は両手で口を押さえ、みるみる蒼ざめた。
『おまえが耶蘇の教会から出てくるのを見た者がいると。本当なのか』
『……本当です』
小さいが、しっかりした声で蝶々は答える。『私は、基督さまの洗礼を受けました』
『おまえは、家のひとり娘だ。仏壇は誰が守る。法事は誰が取りしきる!』
「あの、ろくでなしは何をわめいている?」
ピンカートンは、怒りを露わにゴローに問い正した。
『おまえは、日本の信仰を捨てるのか。心まで外国人に売り渡すのか』
『なんと恩知らずな!』
『ご先祖さまを捨てるのは、親を捨てることだよ』
『蝶々さん、ひどい』
口々に親族や友人たちが言い募っていたとき、ガラガラとガラスの割れる音が鳴り響いた。
ピンカートンがいきなり、酒瓶の乗っていたテーブルを蹴り倒したのだ。
「俺の家から、出て行け!」
彼は顔をひきつらせて叫んだ。「貴様らの顔など、見たくない。くそったれ。二度とこの家の敷居をまたぐな」
人々は彼のあまりの剣幕に蒼白になったが、僧侶の伯父が引き払うように促した。母親は蝶々のもとに駆け寄ろうとしたが、親戚たちに止められる。
『祟りを覚悟しろ、蝶々』
庭の入口で、袈裟をひるがえした僧侶は、もう一度仁王立ちになって叫んだ。
『おまえはわしらを見捨てた。だから、わしらもおまえを見捨てる!』
祝宴の会場は、悲惨な戦場の跡地と化した。
桜まじりの風が吹きすぎていく。蝶々はのろのろと立ち上がると、訴えるような目でピンカートンを見た。
「もう泣いてはいけない」
彼は、激しい憤怒のあとの、やや放心したような微笑を口元に浮かべた。「あれは蛙がぎゃあぎゃあ騒いだだけだ」
「でも、まだ聞こえます」
蝶々は居たたまれぬように、両耳を手でふさいだ。
「たとえ、おまえの親族や坊主、日本人すべてが敵となっても、おまえの美しい目の涙には値しない」
「本当に?」
蝶々は弱々しく彼を見上げた。「わかりました。もう泣きません」
たちまち晴れやかな笑顔に戻った彼女は、そっと夫の手を取った。
「おやさしいお方。あなたの暖かい言葉を聞いたから、もう悲しくないです」
「何をする?」
「聞きました。お国では、これが礼儀正しい、ご挨拶だと」
蝶々は愛情をこめて、小さな唇でピンカートンの大きな手に接吻した。
「どちらかと言えば、それは男が女にする挨拶だ」
「本当? では私に、挨拶してくれますか?」
「それにふさわしい、もっと別の場所がある」
ピンカートンは、衝動的に彼女を抱きすくめ、唇を重ねた。
心という壺の水が突如として溢れだしたような心地。それでもなお、蝶々に対する感情は、止むことなく津々と湧いてくる。
まだ一度しか会ったことのない夫に、これほどの憧れと尊敬に満ちた眼差しを向けてくる彼女の素直さ。
彼と結婚するために今まで信じてきた神々さえ捨て、異国の神を信じるという彼女の大胆さ。
そして、子どものように無邪気で、いたずらっぽくも妖艶にも見える彼女の微笑み。
この十五歳にしか過ぎない異国の少女に、ピンカートンの頑なな心が激しく揺さぶられようとしていた。
(2)につづく