「ああ、やれやれ、終わった。どっこらしょ」
「なんで姉さんが疲れるんや。ひとつしか台詞あらへんのに」
「何言うとうん。舞台のカナメは脇役やで。娘のことが気がかりでたまらんのに、伯父役のあんたに引きずられて、泣く泣く去っていく母親の名演技」
「確かに俺は、とことんワル役やったな。まあ、これでお役御免、ゆっくり舞台が見られる」
「それはそうと、台本ではまだ第一幕の途中やろ。何でこんなところで休憩が入るのん」
「ああ、この話は、原作にはない食事の場面が挿入されとるんや。それで長くなる分、本来は二幕ものなのに、三部に分けてある」
「夫の心をつかむも離すも、妻の料理次第や。食卓シーンは一番大事やで」
「普通のオペラにそんなもんあるかいな。テレビのホームドラマやないんやから」
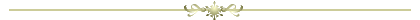
配役表:
蝶々(長崎出身の娘) : 円香・グリュンヴァルト
ピンカートン(合衆国海軍士官) : ディーター・グリュンヴァルト
シャープレス(長崎在住の合衆国領事) : 鹿島康平
スズキ(蝶々の女中) : 柏葉瑠璃子
ゴロー(結婚斡旋屋) : 柏葉恒輝
ヤマドリ公(求婚者) : 奥野茂人(門下生)
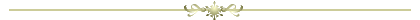
第一幕(第二部)
「ピンカートンさん。お食事の支度ができました」
花嫁衣裳から動きやすい着物に着替えた蝶々は、ひざまずいて障子を開け、夫を呼んだ。「どうぞ、こちらへ」
中国風の螺鈿細工の小さなテーブルに、ふたりは差し向かいで腰かけた。
「夫婦が向き合って、話しながら食べる。お国の習慣は、日本とは違います」
彼女は恥ずかしげに、頬を染めた。
「日本のご馳走。料理人がたくさん作りました。お腹が空いたでしょう。だって、結婚の宴は、めちゃめちゃでしたから」
スズキがそばで給仕を務め、酒を注いだ。ふたりは箸を取り上げた。
日本に不慣れな夫に、蝶々は食卓に並んだ料理を、ひとつひとつ説明し始めた。
「これはお刺身」
「……生の魚。人間の食べるものじゃないな」
「酢れんこんは、いかが?」
「酸っぱい。腐って、穴が開いているわけではないのか」
「これは、叩き牛蒡です。とてもおいしい」
「木の根まで食べるとは!」
「山鳥の串焼きも、香ばしくて」
「醤油、味噌。どうして日本の料理は全部同じ味付けなのだ」
ピンカートンは、うんざりしたように箸を置いた。
「リンカーン号のコックに頼んで、ときどきアメリカ料理を届けてもらうほうがよさそうだ」
「これは、私作りました。大村寿司。大村の娘がお嫁に行くとき、かならず大村寿司を作ります」
「いや、もういい。腹がいっぱいだ」
「まだ少し、食べていないのに?」
「疲れているようだ」
蝶々はそれを聞いて、しょんぼりとうなだれた。
「疲れる、私の親戚のせいですね? ピンカートンさん、とても困らせたから」
ピンカートンは黙ってナプキンを置き、立ち上がった。
「でも、うれしかったです、怒ってくれて」
あわてて、蝶々も彼のあとを追った。「親戚が、私捨てたとき、あなたは、怒ってくれた。私のために」
障子を開けると、昼間は大勢の客でごったがえしていた庭が、ひっそりと静まり返っていた。
ときおり薄闇の中に、桜の花びらが白くはらはらと舞い落ちる。
「いつのまにか、もう夜だ」
「静かです。昼間のこと、嘘みたい」
「寂しくはないのか。おまえは、もうひとりなんだぞ」
ピンカートンは乱暴に、ぎゅっと彼女の肩を引き寄せた。
「寂しく、ありません。捨てられて、幸せです」
彼はじっと妻の顔を覗き込んだ。指で、その桜色の唇でなぞった。
「家族など必要ない。おまえは、もう俺のものだ」
そして、何か答えようと動いた唇を、すばやく完全に塞いだ。
「ピンカートンさん……」
蝶々は空気を求めてあえぐと、うわずった声で彼の名を呼んだ。
「結婚したあと、『ピンカートンさん』と呼ぶ、おかしいですか」
「別に俺は、どう呼ばれてもかまわない」
「お国のご家族、あなたのことを何と?」
「ベンジャミンというのが、俺の名前だ」
彼は蝶々から離れると、背中を向けて庭を見た。「……『苦しみの子』という意味だ」
「苦しみ! どうしてなのです?」
「聖書の中に出てくる昔の聖者の名前だ。その子を産んだとき、母親が難産のために死ぬ間際に『ベン・オニ――苦しみの子』と叫んだ」
「まあ」
彼女は口を覆い、眉を悲しそうに下げた。「それでは、あなたのお母さまも……」
「母は、俺を産むとき死んだわけではない。今では、ごく普通にあるアメリカ人の名前だ」
ピンカートンは、かすれた低い声で呟いた。「だが、母にとって、俺が苦しみの子であったことに、違いはない」
そして、拳を眉間に強く押し当てた。「……なぜ、こんなに感情が高ぶるのだ。俺はどうかしている!」
「ピンカートンさん」
夜風がささやくように、蝶々が言った。
「ベンジャミンとは呼びたくありません。私はずっと、あなたを呼びます、ピンカートンさんと」
「それでは俺も、蝶々さんと呼ぼう」
ピンカートンは、蝶々のうるんだ目の縁を、そっと指の腹でぬぐった。
「また泣いているのか」
見つめているうちに、どんどん熱情が胸を駆け上がるのを感じ、軍人はゴローがしていたように、三度手を叩いた。
スズキが小走りに現われ、お辞儀をした。
「障子を全部閉めてくれ」
女中はするすると紙の扉を閉める。部屋を照らす行灯が、にわかにふたりの顔を明るく映し出し、他のすべてのものを闇に沈めた。
「私たち、ふたりだけ……」
蝶々が夫の青い目を見つめながら、たどたどしい言葉でつぶやいた。
「わめきたてる坊主もいない」
ピンカートンは笑いながら答えた。
彼の指が待ちきれないように、首筋や襟元をまさぐっているのを感じ、蝶々は恥らって微笑んだ。
「夜着に、着替えます」
彼女はスズキをともなって、衝立の向こうに隠れた。
そこには、蝶々のための鏡が置かれていた。
するすると衣擦れの音を立てて帯を解く。スズキに手伝ってもらいながら白い着物に着替え、寝化粧をほどこす。最後に、薬指で紅を引く。
ひとつひとつの動作が、蝶々にとっては、不運な少女時代から幸福な結婚生活へと進んでいく儀式でもあった。
彼女の着替えの気配を感じながら、ピンカートンは庭に出した椅子にもたれながら、ぼんやりと呟いた。
「こんな、おもちゃの人形のような娘が、俺の妻だなんて。わずかな海外駐在のあいだの慰みになればいいと思っていた。なのに、あの思いつめたような瞳! 夜を切り取ったような黒い瞳を見るだけで、俺は険しい崖を落ちていくような心地になる」
彼はぎゅっと目を閉じた。「どこで俺は間違えたのだ」
『旦那さま、おやすみなさいませ』
スズキがお辞儀をして去っていったあと、白い着物に結婚式のヴェールをかぶった蝶々が、ゆっくりと縁側を降りてきた。
その美しさに心奪われ、狼狽して思わず立ち上がってしまったピンカートンは、心の中で自分を嘲った。
「遅かったね」
「丁寧に、お化粧したのです」
蝶々は身をよじるようにして、顔を隠す。「子どもっぽいと、言われたくないのです」
「こっちを見て。子どもなどではない。とても、きれいだ」
ピンカートンは彼女の手を取り、口づけた。
(ピンカートン)
魅惑に満ちた眼差しの かわいい子
今では君はすべて私のもの。
君は百合の花のような着物を着ている。
真っ白なヴェールの下の
君の黒髪が好きだ。
(蝶々)
私は月の女神のようでしょう
小さな月の女神は 夜
天の橋から降りてきて
(ピンカートン)
人々の心を魅惑し
(蝶々)
心を捉えて
白い衣の中に包み込みます。
そしてこの世とは別の世界に
連れて行ってしまいます。
「まだ、きみが覚えていない英語があるようだ」
「何ですか?」
「アイ・ラヴ・ユーとまだ言ってくれない」
「アイ・ラヴ……ユー」
「日本語では、何と言う?」
「お慕いしております」
「シタイ……シテオリマス?」
「まあ、それでは」
蝶々は思わず口を押さえて、微笑んだ。「死んだ人の体のこと」
「俺ときみは、話すことをやめたほうが、うまく行くようだ」
ピンカートンは屈みこみ、彼女の首筋に触れて、唇をつけた。蝶々は突然襲ってきた快感に身震いして、あわてて離れようとしたが、彼はそれを許さない。
「蝶々さん――なんと素晴らしい名前だろう。きみは、か弱い蝶と同じだ」
「弱いことは、悪いこと」
蝶々は悲しげに首を振った。「聞いたことがあります。海の向こう。蝶を捕まえた子ども、ピンで突き刺し、板に留める」
「何故そんなことをするか、わかるかい?」
「いいえ」
彼は力をこめて妻の着物の襟を広げ、あらわになった鎖骨を親指の先でぐっと押さえた。
「もう決して逃がさぬように、そうするんだ。ほら、俺はきみを捕まえた。もう逃げられない。いいね?」
「はい、私の命すべてをかけて、あなたに従います」
蝶々は夫の腕にすべてを委ね、身体をしならせて夜空を見上げた。
(蝶々)
ああ 甘い夜 たくさんの星!
こんな美しい星は 見たことがないわ。
すべての星が
瞬きのように 震え輝いています。
ああ、なんとたくさんの瞳が
至るところから注意深く見つめていることでしょう。
大空にも 陸にも 海にも
たくさんの視線。
天が愛に酔い痴れて
笑っています。
ピンカートンは妻を軽々と抱き上げて、庭から縁側に上がり、奥の間へと進んだ。
「怖いわ。目が回る」
彼女は夫のうなじに、両腕を強くからませた。「喜びで、どうかなってしまいそう」
「俺の蝶々。その身体も心も、今夜からすべて俺のものだ」
彼は深い愛情のこもった声で、耳元にささやき続けた。
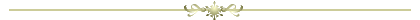
第二幕(第一部)
『スズキ、スズキ』
女主人の呼び声に、はっと顔を上げた女中は、あわてて台の上に置いた仏像を風呂敷に包んだ。
『また、仏さまに祈っていたのね』
蝶々は、咎めだてするわけでもなく、素っ気なく訊ねた。『何を祈ってたの?』
『いろいろと』
スズキは顔をそむけ、聞こえないようにつぶやいた。『蝶々さんが、もう泣くことがありませんように、と……』
『仏さまは、きっと太りすぎておられるのよ。アメリカの神さまは痩せているから、もっと早く願いを訊いてくださるわ』
『まあ、本当でございますか?』
たちまち蝶々さんは笑顔を失い、悲しげに言った。『ただ、神さまは今ちょっと、長崎に目が向いておられないのよ』
スズキは溜め息をつくと、立ち上がって部屋の障子を開けた。
春の陽光が射し込み、部屋の中を照らし出す。もう畳は青々とはしておらず、調度もふすまも、どこかくたびれて見えた。
『ねえ、スズキ。お金はまだある?』
忠実な女中は、奥の箪笥から文箱を取り出し、主人の前で蓋を開けた。
『もう、これだけなの。使いすぎてしまったわ』
『来月から、もっと倹約しないと』
『でも、英語の先生には、これからも来ていただくわ。私もあなたも――それにあの子も、英語を覚えていないと、あの方がお帰りになられたときに、お困りになるもの』
『本当にお帰りになるのでしょうか』
蝶々は気色ばんで、答えた。
『お帰りになるわ』
『長崎に長い間住んでおりますが、外国人の夫が戻ってきたという話は聞いたことがありません』
『他の外国人たちと一緒にしないで。じゃあ、毎月この家の家賃が支払えるように、領事さんを通して手配してくださったのは、何故?』
たちまち完璧な自信を取り戻して、彼女は立ち上がった。
『この家の玄関に、頑丈な錠前をつけさせたのも、ピンカートンさんよ。花嫁を、泥棒や親戚や求婚者から守るため。蝶々を大切に、籠の中に閉じ込めておくためなのよ』
『家賃は……』
『何よ、まだ言いたいことがあるの?』
『手切れ金ということではないでしょうか』
蝶々は悲鳴を挙げて、スズキに掴みかかった。
『よくも、そんなことが』
『お、お赦しください』
『ピンカートンさんはね。船に乗る日、私に言ったのよ。いつものあの微笑みを浮かべて、でも少し悲しそうに、こう言ったのよ。「俺の蝶々。駒鳥が雛を抱く時季には、きっと帰ってくるよ」って。ねえ、スズキ、これを聞いたら、あなたもお帰りになると思うでしょう』
『……』
スズキは答えずに、袖でそっと涙をぬぐう。
『まだ信じていないのね』
(蝶々)
或る日 海の彼方に
ひと条の煙の上がるのが
見えるでしょう。
やがて 船が姿を見せます。
その白い船は
港に入り 礼砲を轟かせます。
見える? あの方がいらしたわ。
私は迎えに出ないの。出ないわ。
あそこの丘の端に立って待つわ。
長い時間 待つわ。
長い時間待っても なんともないわ。
すると 人々の群から離れ
小さな点のように見えるひとりの人が
丘に向かって来るわ。
誰でしょう 誰でしょう
どんなふうにして着いたのかしら。
なんと言うかしら。
蝶々は、ほうっと吐息をつくと、うっとりした眼差しで空を見上げた。
『あの方は昔のように、「バーベナの香りのするかわいい妻」と私を呼んでくれるわ。ねえ、約束する。あなたは何も心配しなくていいのよ。信じていいのよ』
『はい……奥さま』
スズキは両手で顔を覆いながら、何度もうなずいた。
そのとき、門のほうからバタバタという足音が聞こえ、やがてゴローが庭に飛び込んでくる。
縁側から首を伸ばして、中を覗くと、
「おりました。どうぞ入ってきてください」
「こ、この坂は、年ごとに、ますます勾配がきつくなるようだな」
帽子を取って、額の汗を拭き拭き庭に現われたのは、合衆国領事のシャープレスだった。
「領事さま」
蝶々は嬉しそうに立ち上がり、彼を出迎えた。
「私の声が、おわかりでしたか。もう三年近くお会いしていないのに」
「もちろんです。どうぞ中にお入りください」
蝶々は彼を導きいれ座布団を勧めたが、彼の後ろにいたゴローを見ると、ツンとあからさまに顔をそむけた。ゴローは頭を掻きながら、庭に突っ立っている。
「ずいぶん、英語がお上手になりましたね」
「ええ、主人に教えてもらいましたもの。それに今でも先生に就いて習っています」
「それはすばらしい」
「どうぞ、お煙草はいかが」
「いえ、結構です。今日は折り入って、お見せしたいものが……」
「アメリカの方がいらしたら、ぜひとも伺いたいことがありましたのよ」
彼女は自分の思考にすっかり夢中になり、来客のことばを遮った。
「どんなことでしょう」
「駒鳥は、お国ではいつ頃、巣作りをしますの?」
「なんですって?」
「主人は私に、『駒鳥が雛を抱く頃に帰る』と約束しました。もう日本では三度も巣をかけていますのに。お国では気候が違うので、そうたびたびは巣を作らないのでしょうか」
「い、いや、わたしは鳥類学には詳しくないので……」
それを聞いたゴローが大きな声で笑った。
蝶々は彼をキッと睨み、「悪い男です。気をつけて」とシャープレスに小声で言った。
「あの人は、ピンカートンが船に乗ると、すぐに私のもとにやってきて、男の人をあれこれ紹介し始めました。特に、どこかの大金持ちだという胡散くさい男を」
「ヤマドリ公のことですよ。領事さまもよくご存じの名士だ」
ゴローは、悪しざまに言われたことに不平を鳴らしながら、シャープレスに訴えた。
「しかも先方は、蝶々さんをぜひにと望んでおられる。親類全部に見捨てられ、困窮した暮らしをしている蝶々さんにとって、最高の縁談じゃないですか。なのに、この人と来たら、公爵さまを蛇蝎のごとき扱いで……」
「ほら、来たわ。あの人です」
ヤマドリ公爵は、シャープレスよりも年配と見える男だった。ゴローの肩を借りて人力車から降りてきた老公爵を見て、領事はうめいた。
「これは蝶々さんが可哀そうだ。だが……」
ヤマドリは、領事にぎこちなく会釈をすると、障子のところで半身をそむけて座っている蝶々に言った。
『このあいだの話は、考えていただけたかな』
『お返事は何度もいたしたはずです。ヤマドリさま』
蝶々の答えは丁寧だが、にべもない。『私には、夫がおります』
「まだ結婚したままだと思っているのです」
斡旋屋は、シャープレスに耳打ちした。
『確か、公爵さまにもたくさんの奥さまがいらっしゃるはずですね』
『すべて離縁しました。あなたのために』
『まあ、無駄なことを』
温厚な領事は、蝶々の無邪気な自信に心を痛めながら、持っていた手紙をそっとポケットにしまった。「やはり、私には伝えられそうにない」
『家屋敷、召使、別荘。すべてあなたのものです。あなたが望むなら、こ高齢のお母上も喜んで引き取りましょう。親戚との仲も取り持ちましょう』
『どんなに素晴らしい条件を並べても、操を捨てることはできません』
『とっくにあなたを離縁してしまった男に、一生操を尽くすとでも言うのですか』
『離縁など、しておりません!』
『三年も音沙汰ないんじゃ、離縁と同じだよ』
ゴローは嘲るように言った。
「日本の法律では、そうかもしれません」
蝶々は、男を睨むと、完璧な英語で言った。「でも、私はアメリカ人の妻です。合衆国の法律で守られておりますのよ」
「ああ、なんと不幸な人だ」
シャープレスは、うめくように言った。「ピンカートンの人でなしめ!」
「日本と違って、アメリカでは裁判を起こさないと離婚はできないのです。そうですわね、領事さん」
「そうです、でも……」
「ああ、しゃべりすぎてしまいましたわ。スズキ、領事さんにお茶をお出しして」
蝶々が奥の間に退くと、ゴローは曖昧な笑いを浮かべながら、シャープレスに近づいた。
「いやはや、完全に信じ込んでいるようですな」
「気の毒な方だ」
「もうすぐ、ピンカートンさまの船が入港します」
「あの男が帰ってくるのですか!」
ヤマドリ公は失望の叫びをあげた。「それでは、蝶々さんはまたあの男のもとへ」
「いいえ。ピンカートンはここへは決して来ないでしょう」
シャープレスは唇を噛みしめた。「わたしは、そのことを彼女に伝えに来たのです。ですが……おお、私には、この辛い報せを伝えられそうにありません」
「私は今日は失礼します」
ヤマドリは憔悴したような面持ちで、帽子をかぶった。「疲れました。人の心の嘆きほど、年を取らせるものはありません」
ヤマドリは、またゴローに手伝わせて人力車に乗ると、丘を下っていった。
「あら、うるさい人たちはお帰りになったのね。よかった」
蝶々は、庭にスズキが用意したお茶のテーブルの前に腰掛け、領事にお茶を注いだ。
「蝶々さん」
意を決して、シャープレスは口を開いた。
「今日、うかがったのは、B・F・ピンカートンの手紙が私のところに来たからです」
「あの方の手紙が!」
蝶々はカップを取り落とし、領事から手紙をひったくって、キスをした。
「ああ、なんと素敵な日。私は世界じゅうで一番幸せな女です」
「わたしが読みましょう」
「ええ、お願いします……あ、少し待って」
領事に手紙を返すと、彼女は立ち上がった。「わたし、髪を整えてまいります。愛する方のことばを聞くのに、汚い恰好では聞けませんわ」
そそくさと立ち去った蝶々の後姿を見つめながら、シャープレスは頭を抱えた。「なんという、ひどい役目だ!」
戻ってきた蝶々は、椅子に座って居住まいを正した。
「どうぞ、始めてください」
「【友よ。あの美しい娘を訪ねていただけませんか】」
「本当にそう書いてあるのですか」
「そうです」
「うれしい」
しかし、呆れたような領事の顔を見て、あわてて口を押さえた。「すみません。もう黙っています」
「【あの幸せな時から、三年が経ちました】」
「まあ、あの方も毎日、指を折って数えておられたのだわ」
「【たぶん、蝶々さんは私のことを覚えていないでしょう】」
「まあ、スズキ。聞いた?」
彼女は鈴をころがすような声で笑った。「覚えていないでしょう、だなんて!」
「【もし、彼女がまだ私を愛していて、まだ私を待っていたら――】」
「なんと、おやさしい言葉」
「【慎重に、彼女に心の準備をさせるようにお願いいたします】」
語尾は、シャープレスの喉の奥に消えた。「……【訪れる衝撃に対して】」
「領事さま、どうなさったの? 続きをお願いします」
気高い男は、手紙を置くと、異国の少女の顔をまじまじと見つめた。
「蝶々夫人」
「ピンカートン夫人ですわ」
「もし、ですよ。あくまでも仮定の話ですが、彼があなたのもとに二度と戻らないとしたら、どうします?」
蝶々は少し首を傾げて、うっすらと微笑んだ。
「芸者に戻るか、死ぬか、ふたつにひとつです。芸者に戻るくらいなら、死ぬほうがいいわ」
「あなたを、もうこれ以上偽りの希望で縛りたくないのです。悪いことは言いません。あのヤマドリ公の縁談をお受けなさい。それが私のできる、せいいっぱいの助言です」
「なんてことを……」
彼女の桜色に染まっていた頬が、みるみる蒼ざめた。
「あなたはお味方だと思っていましたのに! そんなひどいことをおっしゃるなんて!」
「失礼な言い方を赦してください。でも……」
「スズキ。お客さまがお帰りです」
蝶々は、庭を小走りに駆け出した。「お見送りを!」
「私を追い出して、真実から目をそむけるのですか?」
「ごめんなさい。でも、じっとしていられないほど心臓が苦しいのです。痛いのです、とてもとても」
「お座りになったほうが」
「いいえ、大丈夫。苦しみはすぐに過ぎ去ってくれますわ。雲が空を過ぎ去っていくように」
彼女は、咲き誇る桜の花を透かして、青く晴れ上がった空をじっと仰いだ。その横顔からは次第に少女っぽい怒りが消え、成熟した思慮深い女性の面立ちになっていった。
「あの方は、私をお忘れになったということでしょうか」
「……」
「真実から目をそむけているつもりはありません。……けれど、私にはあの人のいなくなった人生など考えられないのです」
「……お察しします」
「だとしたら、あの子は……あの子はどうなるの?」
蝶々はふたたび興奮し、何かに取り憑かれたような表情になった。そして家に上がり、奥の間に姿を消すと、ひとりの男の子を連れて戻ってきた。
(3)につづく