

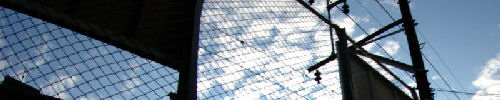
|
BACK | TOP | HOME Chapter 9-5 「待ってくれ。それじゃ、俺は夜叉だってことか」 茶化して笑いとばそうとしたが、うまく笑えない。 「はじめから話そう。おまえは死の瞬間、大きな恨みと憎しみ、それに持って生まれた霊力ゆえに、霊指という大きな能力を持った」 「……」 「その時点で、すでに夜叉に変化しかけておった。そして自分の意思で死した体を動かしたばかりか、この世にとどまり続けようとしたのだ。わしは、おまえさんの記憶を奪い、この『はざまの世界』で、なんとか導こうとした。おまえさんは素直な心で、自分のなした悪を悔い、善への道を歩み始めたな。もちろん愛海ちゃんという強力な助けがあってこそだ」 「ああ」 愛海がいなければ、俺は今でも世を恨み、他人をかえりみない悪人のままでいたはずだ。 「このまま、おまえさんが夜叉にならずにすむことを願っておった。だが、愛海ちゃんが殺されようとする土壇場になって、おまえは極限の憎悪に身をゆだねてしもうた」 「叢雲(むらくも)」 草薙が、爺さんの肩に手を置いた。「もうこれ以上は、つらかろう。あとはわたしが話そう」 『叢雲』。太公望ではなく、それが爺さんの本名なのかと、俺はぼんやりと考えた。 若い貴公子は、感情を抑えた黒曜石のような目で俺を見つめた。 「淳平。おまえは、あのとき一瞬にして、霊体ではなく物理的な肉体を得た。あれが、おまえが夜叉に変じた瞬間だったのじゃ」 「俺が……夜叉」 あまりにも話が荒唐無稽すぎて、想像が追いつかない。 確かに、あのときは我を忘れて暴走した。渡良瀬たちを八つ裂きにできるだけの力を持っていた。 だけど、あれは愛海のためだ。愛海が殺されるのを止めるためだった。 「俺は俺だ。何も変わっちゃいねえ」 「わかっておる。淳平」 草薙は、涙目でうなだれている太公望のそばで、つらそうに言った。 「わかっておるよ。おぬしが、あの女人を心から愛しておるのが。だからこそ、おぬしにとって、あの女人は最大の弱点なのじゃ」 「弱点?」 「これからも、あの女人が危険に巻き込まれることは起ころう。言いよる男も後を絶たぬに違いない。おぬしは、そのたびに夜叉の力をもて、女人を守ろうとするじゃろう。だが、度を越した執着は、彼女の回りに近づく者を害し、やがて彼女自身をも害してしまう」 「冗談じゃねえ。俺は、そんなことはしない!」 「するつもりはなくとも、してしまうのが、力を持つ者の定めなのじゃよ」 「そんな……」 俺はがっくりと座り込んだ。 頭では、そんなことはありえないと否定しながらも、体のどこかが肯定していた。 途方もない力を持つことの快感を、体が覚えていた。ちょっとしたきっかけがあれば、俺はまた暴走してしまうかもしれない。 愛海を守ることを口実に、愛海を独占し、がんじがらめに縛り、ちょっとした疑念を抱いただけで、すべてを破壊してしまうかもしれない。 「俺は、もう愛海のそばにいてはいけないのか?」 「ああ、もはや地上にとどまってはならぬ」 「その浄化とやらを受けて……消滅しちまうのか?」 「わからぬ。天界の裁きにゆだねられることになろう」 「無理だ。……愛海から永久に離れちまうなんて、できねえ。愛海は、愛海は俺にとって」 突然、わけのわからない怒りがふくれあがり、体を満たした。 「俺は、絶対に愛海から離れねえ!」 とんでもない力が自分の内側から放出されるのを感じる。「あいつが死ぬまで、そばにいると誓ったんだ!」 俺の力に押されて、『はざまの世界』の淡い光に満ちた景色が、オーロラのように、うねうねと動き始めた。 ここを壊して、何が何でも脱出してやる。愛海のところに戻るんだ。 誰にも邪魔させない。――邪魔すル者はコロス。 草薙が両手を合わせて手印を結ぶのが、視界の片隅に見えた。 「オン・トン・バザラ・ユク。ジャク・ウン・バン・コク」 「うわあっ」 俺はたちまち、体じゅうに荒縄をかけられたようになって、地面に膝をついた。 体じゅうの力が奪われて、動けない。 今の呪文は、夜叉追いが使う真言というものだろう。 今ので、よくわかった。俺はそんなもので封じ込めなければならないような化け物になっちまったんだな。 みじめに体を折り曲げながら、俺は恥も外聞もなくすすり泣いた。 「お願いだ。見逃してくれ。善行でも修行でも、やれと言われたことは何でもするから」 ふたりは黙って、俺を見降ろしているばかりだ。 「愛海のそばにいさせてくれ。あいつは朝だってロクに起きられない女なんだ。俺がいなきゃ、ドジばかり踏んで、また回りからダメ刑事だってバカにされちまう。能天気でおっちょこちょいで、家の鍵だって閉め忘れるような危険なヤツなんだぞ」 「淳平」 草薙が俺のかたわらに来て、静かに言った。 「おぬしがそばにいても、もう愛海どのの助けにはなれぬ」 その言葉に、俺はようやく顔を上げた。 「それどころか、かえって害をおよぼすことになろう」 「害……」 夜叉になっちまった俺は、愛海に害を及ぼすのか。愛海を愛すれば愛するほど、不幸にさせてしまうのか。 そんなはずはない。俺は絶対に愛海を不幸になんかさせない。 愛海を幸せにできるのは、俺しかいない。俺は愛海を心から愛しているし、愛海も俺を愛してくれているんだ。 結婚して、子どもを産み育てる、そんな普通の幸せなんか比べ物にならないくらいの幸せを、俺なら与えてやれる。愛海をよその男に渡すなんて、できない。 もしそんな奴が現れたら、片っ端から殺してやる。いや、いっそのこと、愛海を殺して、魂ごと永久に自分のものにしてしまえばいい。 ――ああ、何を考えてるんだ、俺は。これこそが、俺が邪悪な者である証拠じゃないのか? 草薙の言うとおりだ。俺は、もう愛海のそばにいてはいけないんだ。 本当に愛海を愛してるというのなら――俺は愛海のもとから去るべきなんだ。 太公望がいつも釣りをしていた霊泉の凪いだ水面に、不意にさざなみが立ち、ゆっくりと広がっていく。 「淳平」 憔悴しきって立ち上がった俺を見て、太公望は目をしばたいた。「わかってくれたようじゃの」 「……俺はこれから、どうなるんだ」 「真言によって霊力を封印する。抵抗しなければ、さほど苦痛はあるまい。すぐに意識がなくなり、たちまちすべてを忘れ去る」 すべてを忘れ去る。つまり、今まで俺の送ってきた人生のすべてを忘れてしまうのか。 愛海のことさえも、全部忘れてしまうということなのか。 「待ってくれ」 うなだれたまま、声をしぼりだした。 「最期にひとつだけ願いを聞いてほしい。せめて――せめて、一目でいいから愛海に会わせてくれないか」 「淳平!」 愛海は俺の姿を見つけたとたん、駆け寄ってきた。「おかえり!」 抱きつこうとして、すかっと倒れかかるが、あやうく踏みとどまる。さすがに、この二年のあいだに学習したな。 「体、またもとの幽霊に戻っちゃったんだね」 「ああ、それに無駄に使いすぎたせいか、霊指の力も前よりうんと弱くなっちまった。すまねえ」 「全然平気だよ。それより見て」 電気を消した部屋のあちこちに、ろうそくが灯されている。テーブルの上には特大のケーキとローストチキン。 愛海は、首にボアのついた白いニットドレスをまとっていた。 「そうか。今日はクリスマスイブだったんだな」 「うん、淳平が帰ってくるって予感がして、ちゃんと用意しておいた」 「そうか」 「……てへ。ていうのはウソ。久下さんが淳平が帰ってくるって電話をくれたんだ」 フー公が不思議そうな顔をして、蒼く光る俺の体を見つめている。そして、おずおずと近寄ってきて、「ふみゃー」と甘えるような声で鳴いた。けれどそれ以上は近づかなかった。 「フニちゃんも、寂しがって、ずっと元気なかったんだよ」 という愛海の大きな目からは、すでに涙が壊れた水道みたいにだだ漏れになっている。 「会いたかったよ……淳平」 「俺もだ」 俺は愛海をふわりと抱きしめ、それからソファに座らせた。 「本庁での取り調べは、もう終わったのか」 「うん、とりあえず」 「でも渡良瀬たちのケガは、結局おまえがやったことになってるんだろう」 さぞかし、つらい取り調べを受けたんだろうな。 「私、すごい怪力の合気道の達人ってことにされちゃったよ」 愛海は、せいいっぱい朗らかにふるまった。 「いろいろと厳しく追及されたけど、佐内課長が私を助けてくれたんだよ」 「あの、背後霊か」 「課長って、実は元警察庁の特別監察官だったんだって」 「やっぱり」 突入してきたとき、捜査一課にきびきびと指図する様子を見て、そうではないかと思っていた。 監察官は、公務員が違反行為を行なっていないかどうかを監察する職務だ。南原署には、ずっと以前から暴力団との癒着をはじめとする黒いウワサがあった。 宇佐美昌造の殺害事件も、俺の親父の事件も、署ぐるみで隠ぺいされているのではないかと長い間疑われていたが、通常の監査をしても、何も浮かび上がらなかったのだ。 佐内は、刑事課課長として任命されて南原署に来たときから、極秘にその内偵役を務めていたらしい。あくまでも、目立たぬように。まったく、あの気配の消し方は常人ではないと思っていた。 「佐内さんが、留置場の隅に追い詰められた私の恐怖をわかってやれと取り調べ官を説得してくれて。正当防衛ってことになるみたい」 「よかったな」 「でも、事件は、全然解決してないんだよ」 愛海は、涙をぬぐいながら、くやしそうに言った。 「渡良瀬署長も赤塚さんも、ずっと否認し続けてるの。淳平を殺したのも、黒田さんを殺したのも、木下警部補ひとりがやったことだって」 「なんだよ、それは」 木下は、まだ重体のまま、意識を取り戻していないのだという。それをいいことに、あいつらは木下ひとりに罪をかぶせるつもりなんだ。 「私ね……刑事、やめようかと思ってるんだ」 愛海の肩が、小刻みに震えている。 「どうしてだ」 「だって、なんだか、何もかもイヤになっちゃった」 愛海の気持ちは聞かなくてもわかる。 ドジであわてもので、ぐーたらで朝寝坊で、ほんとにダメなやつだけど、炎天下の張りこみも、冬の川さらいも、文句ひとつ言わずにがんばっていたのは、刑事という職業に誇りを持っていたからだ。 それなのに、渡良瀬たちは暴力団と癒着し、殺人を犯して無実の人間に罪を着せ、その事実を署をあげて隠蔽した。 同僚たちが全部敵になってしまった中、二時間も署内を逃げ回った恐怖は、どれだけ愛海を傷つけただろう。 おまけに、このことはマスコミによってセンセーショナルに書き立てられ、南原署は今、日本中の好奇の視線にさらされてしまっている。 そんな中で、愛海が刑事を続けていけないと思うのは、あたりまえだ。 「けど、本当にそれでいいのか?」 「え……」 「子どものころから、テレビに出てくる刑事にあこがれて警察に入ったんだろう。どんなピンチにも動じない、カッコいい刑事になりたかったんだろう」 「……だって、だって、だって」 「今みたいなときこそ、踏んばりどきじゃないのか? そんなに、さっさとあきらめちまうのか」 「もうヤだよ!」 愛海は、俺の霊体に顔を押しつけるようにして、わあわあ泣いた。 「淳平を殺した犯人を捕まえるんだって、ずっとがんばってきたのに……、その犯人が警察にいたなんて……もう捜査なんかしたくない。本当のことなんて、何にも知りたくないよ!」 俺は愛海の肩の上に、そっと霊力をこめた。 「けど、俺はおまえに、すごく感謝してるんだぜ。真実をさぐりあててくれて。俺や俺の親父や、宇佐美や黒田や、たくさんの死んでいった人間の無念が、おまえのおかげで晴らされた」 愛海はそれを聞いて、伏せていたまつ毛を震わせた。 「死人だけじゃないと思う。人間は生きている限り、誰かに自分の本当の思いを知ってほしいんだ。おまえが今まで解決した事件で、どれだけの人間が救われたか、わかるか?」 老舗旅館を立て直そうとしていた三橋さゆり。 華やかな芸能界で女の身ひとつで必死で生きていた高見リカコ。 ピアノが怖いと泣いていたピオッティ涼香。 巨額の遺産を受け継いだものの、誰も信じられず孤独の中にいた佐田亜希子。 俺がだまして、人生を狂わされたたくさんの女たち。 「みんな、おまえがいたから、前に向かって進み始めることができたんだ」 「だって、それは淳平がいたから――」 「刑事をやめるな。愛海、おまえは刑事になるために生まれてきた女だろ。これから、もっとたくさんの人間を助けるんだろ」 「淳平ったら」 愛海は、くすっと濡れた笑い声をあげた。「やっぱり詐欺師だね。そんなふうに女をその気にさせて、コロリとだましちゃうんだ」 「水主淳平の手にかかって、だまされない女はいなかったんだぞ」 「それじゃ、一生私のそばにいて、だまし続けてくれる?」 愛海は、流れたマスカラで目の周りをパンダみたいに真っ黒にしたまま、上目づかいで俺を見上げた。 「約束して。一生私のそばにいて、コンビを組んでくれるって」 「ああ」 俺は愛海の頬に、かすかに霊指を当てた。俺の霊力をがんじがらめに真言で縛り上げている太公望たちも、キスするくらいの力は残しておいてくれたらしい。 「約束する。ずっとおまえのそばにいる」 ごめん。俺はウソをついている。 「淳平……」 「愛海。愛してる」 首筋に触れると、愛海は耐えきれないように吐息をもらした。 「淳平と、ひとつになりたいよ」 「……うん」 「抱いて。私の全部をめちゃくちゃにして。殺してもいいから。……私も死にたい。死んで、淳平といっしょの幽霊になりたいよ」 うめくような、せつなげな誘いの声。 いつもきちんと自分を律している愛海が、こんなに熱く高ぶった姿を見たことは一度もなかった。 きっと、俺の夜叉の力がそうさせているんだな。これだけ封印されていても邪悪な念が漏れ出して、愛海の中に絶望や混乱や、破壊的な願望を生み出している。 きりきりと胸が痛む。 やはり、俺はもう愛海の隣にはいられないんだ。 俺は全身がバラバラになるような苦痛を感じながら、愛海から霊体を放した。 「淳平?」 「せっかくのクリスマスの御馳走が冷めちまうぜ。食べろよ。今晩は徹夜で、ゆっくりと過ごそうぜ」 結婚詐欺師のメンツにかけて、一生忘れられない楽しい夜にしてやるから。 窓ごしに見下ろすクリスマスの夜景は、きらきらと滲んで、まるで壮大な宝石のネックレスのようだった。 俺たちは窓ぎわにソファを寄せて座り、いつまでも飽かずに美しい聖夜を眺めていた。 「なあ、愛海」 「うん?」 「もし、俺たちが生きてるときに巡り合えてたら、今みたいな恋人同士になれたかな」 「どうかなあ。もし私が刑事で、淳平が結婚詐欺師なら、敵同士だよね」 「追いつ追われつの関係か」 「『こら、水主容疑者。いつかおまえを逮捕するぞー』って地の果てまで追いかけていって……やっぱり、いつのまにかホレちゃってたりして」 「ああ、俺もおまえのドジさ加減に呆れて、わざと手がかりを残して。そしていつか、おまえに捕まりたいと願うようになるんだろうな」 「どんな人生を送っていても、どんな場所で出会っても、きっと淳平を見つけ出したよ」 「俺もだ。ただ、現実は、出会いが少し――遅すぎたかな」 「ううん。そんなことないよ。これでよかった。私はこれで、最高にシアワセだよ」 「専属の美容師兼マッサージ係、朝は優しくキスで起こしてコーヒーを沸かして、出かけるときは戸じまりをして、掃除やフー公の世話をして。俺みたいな、いたれり尽くせりの恋人はいないからな」 「はーい。感謝してまーす」 「これからは、ちっとは自分で起きろよ」 「うん」 「出かけるときは、ガスと電気の指差し確認、それに戸じまり」 「わかってるってば」 夜が、しらじらと明けていく。部屋は蒼白い光に満たされ、俺の体は少しずつ消え始めた。 「寝る前も……きちんとメイクを落として、美容……液をつけるんだぞ」 「淳平?」 愛海は、きょとんとした顔で俺を見つめた。 いや、正確には――俺のいたはずのあたりを。 ソファの愛海の隣はからっぽだった。まるで初めからそうだったかのように。 「淳平、どこ? どこにいるの?」 愛海は立ち上がり、部屋中を見回している。その顔が、みるみる悲しみにひきつっていく。 ごめん、愛海。 俺は最後の力をふりしぼって、愛海の髪をふわりと撫でた。 フー公は、まだ俺の方を見ている。すまない。フー公。愛海を頼むぞ。 意識がとぎれる。 俺のすべてが、大気に溶け出す。 愛海、おまえを愛している。 俺はこれから、おまえのことを忘れちまうと言われたけど、忘れるものか。おまえみたいにドジで間抜けで、誰よりも愛しい女を、忘れるはずはない。 きっと、いつか、どこかで――。蟻になってるか、毛虫になってるかもしれねえけど、絶対に俺はおまえのそばに行くからな。 そのときは、俺のことをちっとでも思い出してくれよ。 太公望の爺さんよ。 「なんじゃ」 俺の封印された霊力を、少しでいいから使わせてくれないか。瀕死の木下警部補に、ちょっとでも分けてやりたいんだ。 「ああ、やってみよう」 もし他に死にかけている奴がいたら、全部分けてやってくれ。こんな邪悪な俺の力でも、もし役に立つなら――少しでも俺の罪をつぐなえるなら、そうしたいんだ。 それから、愛海をよろしく頼む。あいつがいつまでも泣かないように、伝えてやってくれ。 俺は幸せだと。 おまえのことを、いつも想っていると。 だから、おまえは前に進んでくれ。幸せになってくれと――。 「きっと伝えようぞ」 ありがとうな。爺さん。草薙も、迷惑かけたな。 ああ、俺の霊力が、今解き放たれたのを感じる。 木下や、たくさんの人間の命の中に、俺の命が少しずつ入っていくんだな。 こんな悪にまみれた人生でも、俺、人の役に立てたんだな。 ……愛海……。 おまえに会えて、よかった。 おれ……生きてて……よかったよ。 chapter 9 end NEXT | TOP | HOME Copyright (c) 2006-2011 BUTAPENN. |