

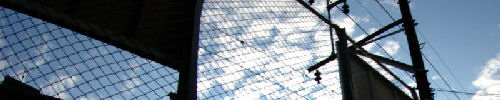
|
BACK | TOP | HOME Chapter 9-4 鉄格子の扉を開け、偵察のため、俺が先に中に入った。 看守係の警官用の事務机がある。いつも誰かが必ず詰めているはずのそこは、無人だった。 その向こうは狭い通路になっていて、奥に小さな監房がずらりと一列に並んでいる。 南原署は小さな署だが、それでも留置場は、けんかや窃盗の現行犯やら、未決の被疑者や拘置所への移送待ちやらで、午前中などはいつもいっぱいだ。それなのに今は、看守も収容者の姿も見えず、しんと静まりかえっている。 署内で発砲事件が発生したとあって、ここの連中まで避難させちまったのだろうか。 俺は一瞬ためらったが、愛海の手をひっぱって入口の扉をくぐらせると、鉄格子を厳重に施錠した。 これで少しは時間を稼げるはずだ。 まさか敵も、愛海が留置場に立て籠ったとは最初は考えないだろう。 おまけに、宙を飛ぶは、大の男を突き飛ばして気絶させるはの、チョー怪力女だ。追手も用心しながら行動しているはずだ。 愛海は監房の前の通路で、へたへたと座り込んだ。 「疲れた……」 「ああ、俺もだ」 知らないうちに、けっこう霊力を使っていたらしい。霊体が不安定で、ときおりノイズが入ったようになるのが、自分でもわかる。 「携帯は。都築からの返信は?」 携帯のスイッチを入れた愛海は、弱々しい声で答えた。 「……まだないよ」 電波でヤツのところへ飛んで、様子を確かめたくても、愛海を残していくわけにはいかない。 俺は次の手を何も思いつかないまま、留置場の中を見渡した。 「ここの独房で、俺の親父は死んだんだな」 愛海は顔を上げて、こくんとうなずく。「そうだね」 二年間、愛海について毎日のように南原署に通っていたのに、とうとう一度もここを訪れる勇気がなかった。親父の幽霊に会えるかもしれない。そう思いながらも、俺は親父に会うのがこわかった。 俺たち一家が全滅してしまったことを、親父に伝えるのがこわかった。 こんなときに来ることになるとは、なんという皮肉だろう。それとも、これこそが因縁というものだろうか。 だが、今は感傷にひたってる場合じゃない。 「そこの扉は?」 「お風呂場だよ。その向こうが洗濯室」 愛海は刑事になる前、ここで看守係をしていたことがあるらしい。反対側にある、女性用監房の看守だ。 「あっちは」 「運動場」 そこにあったのは、マンションのバルコニーに毛が生えたような狭いスペースだった。バルコニーと言っても、四方を高い壁で囲まれているため、外の景色はまったく見えない。ただ、天井のあたりは素通しの金網になっていて、冬の晴れ上がった空が見えた。 閉じ込められた人間にとって、青空は、何よりも外界へのあこがれを掻き立てるものだったに違いない。 俺の親父も、こうやって空を仰いで、家族を想っていたのだろうか。 「ここから脱出するぞ、愛海」 「ええっ」 愛海は絶望的な顔をして天井を見上げた。「こんなに高いんだよ。どうやって」 霊指の力で愛海を抱きかかえて飛び、金網をぶち破って、三階の高さから地上に降りる。 だが、もし、途中で力尽きれば、愛海はまっさかさまに墜落だ。想像すると、さすがの俺も不安になる。 「長い紐をさがしてくる。天井から垂らして、登るとき支えてくれればいい」 「紐なんてあるのか?」 「移動のときに手錠に結わえる青い紐が何本か、詰所のロッカーにしまってあったと思う」 愛海は言うが早いか、走って出て行った。 そうか。そんなものがあるのか。 留置場に入るとき、靴紐やベルトの類は一切取り上げられてしまう。自殺防止のためだ。 面会のときに、そう親父がこぼすのを聞いていた俺は、親父が留置場で首を吊ったと知らされて、衝撃とともに不思議に思ったのだ。 着ていたシャツを裂いて紐を作ったのだと説明されたが、きびしい看守の目を盗み、そんなことができるものだろうか。 「きゃああっ」 愛海の悲鳴が扉の向こうから響いてきた。 「淳平!」 顔色をなくした愛海が走りこんできた。 「ほう。こんなところにいたのか」 銃をかまえた渡良瀬警視と赤塚が、にやにや笑いながら扉をくぐってきた。無駄とは知りながら、俺は透明な体の背後に愛海を隠す。 「留置場にみずから飛び込んでくれるとは、押し込める手間がはぶけて助かったよ、小潟くん」 「なんだと?」 そう言えば、留置場の鉄格子の扉に鍵がかかっていなかったことを思い出した。 「……くそ、俺たちは渡良瀬の罠にかかったのか」 「罠?」 愛海のつぶやきを聞いて、渡良瀬が哄笑した。 「はは、よくおわかりだ。今頃わかっても遅いのだがね」 愛海を殺すことを決めた渡良瀬は、周到な準備を経て留置場内まで空っぽにし、一般人のいない署内で署員全員で愛海を追いつめるつもりだったのだ。 しかも、強盗事件で署内の刑事が出払っているという千載一遇のチャンスを狙った。 いや、もしかすると、強盗事件そのものが、渡良瀬たちの狂言かもしれない。 「機動隊や、ほかの署員は外で待機させている。ゆっくり、その紐を使う時間はあるよ」 「紐を?」 愛海は、ぼんやりと手に持っている青い紐を見つめた。 俺は、「あ」と叫んだ。愛海もほとんど同時に、ぶるりと震えた。 こいつら、愛海に自殺しろと勧めているのか? 「かわいそうに、刑事が上司を射殺するなんて、きみの人生は、もう終わりだよ。いっそ自決したほうが、いさぎよいのじゃないかな」 「じ、冗談じゃない。木下さんを撃ったのは、署長、あなたです!」 「誰が、それを信じてくれる?」 渡良瀬の声が、作りものの優しさを帯びた。その、てらてらと勝ち誇った表情に、俺は虫唾が走る。 「この赤塚をはじめ、署内にいた人間は全員、証言してくれるよ。きみは素直に投降せずに、あばれ回り、逃げ回った。無実の人間のすることじゃない」 「私は、殺人鬼から逃げようとしただけです」 恐怖で卒倒しても不思議ではない状況で、愛海は敢然と、彼らの罪を告発した。 「宇佐美昌造さんを殺し、水主宏平さんに罪をかぶせた。水主淳平を裏路地で背中から刺し、証人の黒田智也さんを殺した。あなたたちは、四人もの人間を死に追いやった殺人鬼よ!」 「困った人だね。妄想がひどすぎる」 渡良瀬は、しゅっとヘビのような音を立てて短い息を吐いた。 「そんな妄想の世界で生きるのは、さぞつらかろう。楽にしてさしあげなさい。赤塚くん……その紐で」 と後ろの巡査部長に命じながら、愛海の手にある青いザイルロープのような紐を、銃の先で指す。 「冗談じゃない。またここで首吊りかよ」 赤塚はおびえたような眼をして、首を振った。 「あんたが自分で銃で殺るって言ったじゃないか。なにもかも俺たちに押しつけやがって。覚えてるだろ、あのときのことを。木下はゲロ吐きまくったし、俺も何年も悪夢にうなされた。もう俺はごめんだ」 それを聞いた愛海は、はっと目を見開いた。 「あのときって?」 「おまえには関係ない」 「言いなさい! それって水主宏平さんのことなの?」 赤塚は、顔を真っ赤にして、くしゃくしゃに歪めた。 「ああ、そうだよ!」 愛海の気魄に押され、ふくらみきった風船が破裂するように、赤塚は17年間封印していた事実をぶちまけた。 「奴が、どうしても言うことをきかないからだ。素直に殺しましたと自供しておけば、せいぜい十年ですんだのに。三人がかりで押さえこまなきゃならないほど、暴れやがって!」 「てめえたちが、親父を……」 「無理やり首を吊らせたの?」 愛海は、拳をぶるぶる震わせながら、涙を目にいっぱいためて叫んだ。「淳平のお父さんまで……、あなたたちはよってたかって殺したんだ!」 渡良瀬は「余計なことを」と共犯者を睨むと、ふたたび愛海に銃を突きつけた。 「そうだな。手に硝煙反応をつける意味もあったんだ。やはり銃で自殺という筋書きにしておこう」 渡良瀬は周到に、手袋をはめていた。すでに拳銃の指紋も丁寧にぬぐってあるのだろう。 「押さえつけろ」 今度は赤塚は、素直に従った。洗いざらい自分の罪状をしゃべってしまった。もう愛海を殺すしかないと観念したのだろう。 愛海は必死に抵抗したが、あっけなく赤塚にはがいじめにされた。俺もありったけの霊指の力で奴を引きはがそうとしたが、無駄だった。 霊力を使い過ぎた。もう俺は、ガス欠の車同然だ。 体の自由を奪われた愛海に、渡良瀬は近づき、持っている銃を愛海に握らせようとする。 「いやっ。淳平、淳平!」 「愛海!」 必ず守ると約束したのに。死人はもう、何もできないのか。このまま愛海が殺されてしまうのを、黙って見ているしかないのか。 俺の目に、17年前の幻影がだぶったような気がした。 必死で生きようともがく親父を、奴らは無理やり紐を首にかけて、吊り上げて……。 「やめろおおおっ!」 天井から青空が覗いているはずの運動場が、まるで暗幕に覆われたように暗くなった。 「お、おまえは――」 赤塚が、すっとんきょうな悲鳴を上げた。「誰だ、おまえは!」 その目はまっすぐ俺を見つめている。 「淳平。からだが……」 愛海が、ぽかんと口を開けた。 自分でもわかった。今の俺には体がある。青く透き通ったチンケな霊体じゃない。本物の体だ。 力だって使える。 軽く手を動かしただけで、赤塚がうしろに吹っ飛んで、壁に叩きつけられた。 少しずつ奴の体が浮き上がっていく。俺は一切、奴に触れないままだ。 赤塚は首を絞められ、飛び出さんばかりに目を見開き、苦しげに舌を出した。 「誰だ、おまえは」 恐怖一色に染まった顔で、渡良瀬が銃口を俺に向けた。 俺は赤塚に興味を失い、向きなおった。赤塚は地面に落ち、そのまま気絶してボロクズのように横たわった。 「俺か。俺は水主淳平。おまえたちが殺した、ケチな結婚詐欺師さ」 「そんなバカなことが……」 「さあ、どうやって俺たちの味わった苦しみを返してやろう」 俺は、腹の底から湧き出てくる笑いに喉を鳴らした。 渡良瀬が絶叫した。腕が次第に変な方向にねじれ、たまらずにぽとりと銃を落とす。 本気になれば、体じゅうの骨を粉々に砕くことだってできそうだ。 ああ、力を持つって、なんて気持ちの良いことだろう。 「淳平!」 愛海が突然、俺と渡良瀬の間に立ちふさがった。両腕を広げ、目にいっぱい涙をためている。 「やめて、淳平。こんなの、ダメだよ」 「邪魔するな」 「ううん、邪魔する。こんなやり方、ダメだよ。悔しい気持ちはわかるけど、相手にやられたことをやり返したら、同じになってしまうんだよ」 「赦せっていうのか。こいつを。親父を殺して、俺の人生をめちゃめちゃにしたこいつを!」 「真実をあばくの。みんなに、どんなに淳平が悔しかったか知ってもらうの。それでいいじゃない」 「良くない。俺は赦せねえ。こいつだけは絶対に赦せねえ!」 「淳平。あなただって、みんなに赦してもらったんだよ」 俺は、体じゅうを満たしていた熱い怒りに、すっと冷たい棒杭を当てられたのを感じた。 そうだ。 そうだった。 俺も、だました女たちに赦してもらった身だった。 「愛してる」とさんざん偽りの言葉をささやき、裏切って金を巻き上げ、それでも、そんな俺のために彼女らは涙を流してくれたのだ。 「俺は……」 地面にころがって、のたうちまわっている渡良瀬を見下ろした。 次第に、心の荒波が鎮まり、凪いでいく。 気がつくと、ふたたび天井からは、光が射していた。 その光の中で、愛海は天使のように輝いて見える。 「愛海」 愛海。おまえは俺の天使だ。また極悪人の俺を救ってくれた。 おまえが願うなら、俺はなんだってできる。なんにだってなれる。 俺は愛海を抱きよせ、唇を重ねた。 ちゃんとした体で愛海とキスできるのは、これが最初……と思ったら、愛海がくたっと胸に寄りかかってきた。 なんだ、気絶しちまったのか。 床に愛海をそっと横たえると、大勢の男たちの怒声が入口から聞こえてきた。警視庁の都築警部の声も混じっている。 俺はあわてて姿を消した。 真っ先に飛びこんできたのは、なんと佐内刑事課長だ。存在感が薄く、いつも背後霊のように刑事たちの後ろで目立たずに立っている。 ……といくら説明したって誰もが忘れてるだろう。そんな奴だ。 佐内は、意識を失って倒れている赤塚と渡良瀬に目を走らせたあと、愛海のそばに片膝をついた。 「だいじょうぶか、小潟くん」 そして、いっしょに部屋に入ってきた刑事たちに命じた。「都築くん、そっちのふたりを拘束」 「はい」 驚いた。佐内のやつキビキビしていて、まるで別人だ。警視庁の捜査一課を陣頭指揮してるってことは……そうか。そうだったのか。 俺は安堵を覚え、あっけなく意識を手放した。 次に目を覚ましたのは、『はざまの世界』だった。 霊力を使い果たしたからか、ずいぶん長く寝ていたような気がする。 顔を動かすと、そばに太公望がいた。 だが、いつもなら、霊泉でのんびり釣りをするか、寝そべっているか、ブチブチお小言を言っている爺さんが、今日はあろうことか、白髪頭に黒い烏帽子をかむり、小豆色の狩衣を着て正座していた。 そして、その隣には、絶世の美青年に変化した草薙が、若草色の狩衣姿で立っていた。 「気がついたか。淳平」 「どうしたんだよ、爺さん。その格好は」 「まあ、ちょっとした、わしの仕事着だ」 「ふうん、あんたでも仕事をするときがあるのか」 「必要な時ならの」 俺は起き上がった。いつものジーンズとシャツを着た仮の体に戻っている。 あのときは、いったい何が起こったのだろう。下界では透き通った幽霊のはずの俺に、一時的にせよ目に見える肉体ができたのだ。 「愛海はどうしてる?」 「無事じゃ」 草薙が代わりに答えた。「安心せよ。おぬしがここにいることは久下を通して伝えた。かの女人は事件の全容を解明するために、今は本庁で取り調べを受けておる」 「取り調べ? やはり木下を撃った犯人だと思われてるのか」 俺はついカッとなって立ち上がった。 だが、「落ち着け、淳平」と太公望に諭されて、また胡坐をかいた。確かに今俺が戻っても、愛海の立場がよくなるわけじゃない。 「木下は死んだのか?」 「いや。だが、こん睡状態が、もう三日続いておる」 「渡良瀬と赤塚は」 「渡良瀬は腕を複雑骨折、赤塚も肋骨にひびが入って、警察病院に入院しておる。愛海ちゃんが取り調べを受けておるのは、そのためもあるんじゃよ」 ああ、そうか。 俺が奴らにさせた怪我は、すべて愛海がやったことになっているのか。 「なんてことだ」 もし南原署の奴らが全員、口裏を合わせたりすれば、愛海ひとりが悪者になってしまう。親父がむりやり奴らに吊るされて殺されたことも、赤塚が俺を刺したことも、何の証拠も証言もないままだ。 「やっぱり、愛海のところに帰る」 じっとしておれず、俺はまた立ち上がった。 「淳平。座れ。話はまだ終わっておらぬ」 太公望がいつになく厳しい口調で言った。 「さっき、わしの仕事の話が出たの」 と、くそまじめな顔で話し始めた。 「わしは、ここで門番をしておる。毎日、天界あるいは地獄へと向かう魂が、何万、何十万と、ここを通っておる」 「何万、何十万?」 「おまえさんの目には見えぬはずだ。小さな光の球のようなものが、ひっきりなしに、ふよふよ飛んでおるのじゃがの。だが、わしの管轄は、そういう魂ではない。地上から送られてきた特別に邪悪な存在だ」 「俺のような悪人か」 「少し違うのだ。おまえさんは、夜叉とか鬼というものを知っておるか」 「ああ」 俺たちに、やたらと因縁がある『久下心霊調査事務所』の面々が――ここにいる草薙も含めて――『夜叉追い』と呼ばれているのは聞いた。 人間が強い恨みや執着の果てに、死後に凶悪な化け物になって、人間に悪さをするようになっちまうのが、夜叉らしい。 「わしは、ここにいる草薙とふたりでひとつの存在。草薙が地上で調伏(ちょうぶく)した夜叉を、わしがここで受け止め、浄化する。つまり消滅させるのだ」 「消滅」 なんとも言えぬ悪寒に、俺はぶるりと震えた。 「淳平。わたしが今日着ている装束は、夜叉を浄化するときに身につけるもの」 爺さんは、悲しそうな目をして俺を見た。 「言ってることが、いまいちピンとこねえんだが」 不安な心地におちいり、俺は冗談のつもりで言った。 「つまり爺さんは、俺を浄化するとでもいうのか」 「そのとおりだよ。淳平」 NEXT | TOP | HOME Copyright (c) 2006-2011 BUTAPENN. |