

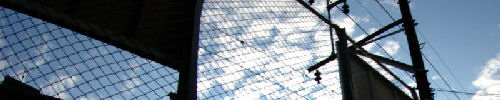
|
BACK | TOP | HOME Chapter 9-3 暗がりに血と硝煙のにおいが充満する。 赤塚が木下の体を乗り越えて、愛海に飛びかかろうとする気配を見せたので、俺は我に返った。 「愛海、降りろっ」 愛海は手すりをつかみ、よろよろと階段を駆け下りた。腰を抜かさず動けるだけ、まだマシだ。 俺はありったけの霊力をこめて、赤塚を押し返そうとした。 できないなんて、言ってられない。奴らの仲間である木下さえも、愛海を助けようとしたんだ。 俺が、この俺さまが、愛海のために何もできないはずがあるか。 赤塚は「うっ」とうめいて、とっさに後ろに下がった。 「どうした」 「なんだか壁のようなものが、ビリッと電気みたいな」 「もういい、こっちだ」 渡良瀬は苛立った怒鳴り声をあげ、踵を返して署長室に戻った。赤塚も、俺もその後を追った。 署長は、緊急配備用の指令台に手を伸ばして、スイッチを入れた。 「全署員に連絡。たった今、小潟刑事が木下警部補に向かって発砲、そのまま逃走した」 「な、なんだって?」 あまりの意外なセリフに、俺は唖然とした。 「ただちに、署内にいる一般人を退避させろ。小潟刑事はまだ武器を携行している。見つけ次第、現行犯逮捕。武装して臨め」 ……何を言ってやがる。木下を撃ったのは、てめえだろう。なぜ愛海が撃ったことになる。 渡良瀬の企みが、一瞬にして読めた。 こいつは、愛海が逆上して木下を撃ったことにし、署員全員を使って捕まえさせようとしているのだ。 そして、あわよくば――ドサクサにまぎれて愛海を殺してしまう。すべてを闇に葬る一石二鳥の作戦だ。 愛海があぶない。署員たちは署長のことばを信じて、愛海を錯乱した武装犯人だと思いこみ、向かってくるだろう。 署内の同僚たちがすべて、敵に回っちまった。 俺は愛海の姿を追いかけて、階段を降りた。 踊り場には、木下が倒れている。その目は虚空に向かって見開かれていた。 「おまえは……誰だ」 俺のほうをじっと見ながら、彼は血に濡れた唇をかすかに動かした。 魂が体から離れかけている。だから、同じ霊体である俺が見えるのだろう。 「俺は、水主淳平だ」 「そう……。もうここは、あの世か」 「一歩手前だ」 俺は、奇妙な気持ちで木下を見下ろした。 こいつは、俺を殺した犯人だ。直接手を下したのは赤塚だが、こいつも共犯者としてそばにいた。 渡良瀬に脅されて、やむをえず加わったのかもしれない。選択の余地はなかったのかもしれない。けれど、俺の最期の苦悶を、こいつはそばで見ていたのだ。憎んでも憎みきれない、罵っても罵り足りない仇。 だが、俺の口から出てきたのは、反対のことばだった。 「愛海を助けてくれて、ありがとう」 木下は、ぼんやりと俺を見つめ返した。そして、ゆっくりと目を閉じた。 かつて経験したことのない哀しみと怒りが、俺のはらわたを焦がして駆け上がってくる。 今まで漠然としていた憎悪が、ひとつに収束されていく。頭の中で電気がショートするような、強烈な感覚。 「渡良瀬、赤塚」 俺はおまえたちを赦さない。絶対に、絶対に赦さない。 「愛海。どこだ」 「ここ。ここよ」 か細い声が、俺の耳に聞こえてきた。聴力は、たぶん人間のより敏感なはずだ。 愛海は、二階奥の女子トイレに隠れていた。身障者用に改造されたトイレは、扉が引き戸式になっていて、愛海は取っ手にモップの柄を差し込んで、開かないように固定していた。霊体の俺は問題なく通り抜けられるが。 「どうして、こんなところに」 「だって、だって……」 署長の指令が全署に駆け巡っているのを聞いたのだという。これ以上先に進めば、署員たち全員を敵に回して戦わねばならない。進退きわまって、ともかくもトイレにたてこもったのだ。 「ここの窓から飛び降りてみる。二階だったら何とか」 愛海が指差したのは、縦に細長いすべり出しの窓だった。とてもじゃないが、人間の体が抜け出られる大きさじゃない。 「だいじょうぶ。頭さえ抜ければ、ちゃんと全身が通り抜けられるっていうし」 「バカ、それはネコだ。おまえのでかい乳や尻が、通るわけあるか」 愛海のやつ、相当パニくっているな。まあ無理もないが。 「とにかく、トイレから出るんだ。今ならまだ、おまえがここにいることは感づかれてねえ。うまく行けば、奴らの目を盗んで移動できる」 「移動ったって、どこへ行くの」 俺は少し考え込んだ。 「マル暴の部屋は、どうだ」 愛海をトイレに待機させておいて、俺は廊下の突き当たりのマル暴の部屋へ飛んだ。 一般市民を退避させることを優先させているのか、部屋に人影はない。 一番肝心なのは、南原署の誰が渡良瀬とグルで、誰がそうでないか、だ。 組織犯罪対策課の大崎課長は信用できると、俺は踏んでいた。愛海のことをすごく可愛がっていたし、何よりも、五年前に関西から南原署に異動してきたという経歴の持ち主。渡良瀬とつるんで、過去の事件に関わっている可能性は薄い。 うまく行けば、大崎を味方に引き入れて、ここから脱出するのを手伝ってもらえるかもしれない。 女子トイレに戻ると、愛海は一生懸命、携帯にメールを打ちこんでいた。 「何してる」 「都築警部に簡単に状況を説明する。もし応援に駆けつけてくれれば、きっと何とかなるよ」 「そうだといいが」 果たして、渡良瀬署長が木下を撃ったという愛海の説明と、愛海が木下を撃ったという渡良瀬の説明のどちらを、都築は信用するだろう。いざとなれば、組織の人間である刑事は上司を信じてしまうかもしれない。 こんなとき証人になれない、幽霊の自分がはがゆい。 メールの送信が終わると、そっとトイレのドアを開け、愛海はマル暴の部屋に走りこんだ。 「隅に隠れていろ」 俺はロッカーの陰に愛海を押しこみ、そのへんに置いてあった段ボール箱を、その前に積み上げた。これで、本庁から応援が来るまで、少しでも時間を稼ぐしかない。 「都築警部から返信は」 「まだない」 「くっそー。野郎、どこで何やってんだ」 とりあえず、愛海には携帯の電源を切らせた。息をひそめて隠れている身には、マナーモードのバイブ音でさえ命取りだ。 そのとき、ドアが開いた。 入ってきたのは、おあつらえむきに大崎課長ひとりだ。 大崎は入ってきたとたん、小鼻をふくらませた。クンカと空気を吸うようなしぐさをすると、部屋を見渡し、愛海の隠れている段ボールの山にさっと目を留めた。 「お嬢ちゃん。隠れてないで出てきな」 なんという鋭さだ。俺が苦労して積み上げた段ボールのカモフラージュを数秒で見破りやがった。 「頭の後ろで手を組んで、ゆっくり立ち上がれ」 「……はい。課長」 愛海は観念して、言われたとおりのポーズで立ち上がった。 「どうして私がいるってわかったんですか」 大崎は銃を持ったまま、鬚だらけのツラにニヤリと笑みを浮かべた。 「この獣くせえ部屋に、若い女のいい匂いがしたからさ」 ……野生の王国か、ここは。 「説明してもらおうか。どうして、木下があんなことになったのか」 マル暴の課長は愛海に銃を向けながら、ドスの利いた声でたずねた。 「木下さん……亡くなったんですか」 「意識はないが、かろうじて生きとる。今救急車を呼んだところだ」 「よかった……」 愛海は安堵のあまり、ぎゅっと目を閉じた。 大崎はウソをついているかもしれないと俺は思った。死んでいても生きていることにしたほうが、犯人に自首を促しやすいからだ。 「ということで、おまえは今のところ殺人犯ではなく、殺人未遂犯だ。この差は大きい」 「違います」 愛海は、両手を後頭部につけたまま、訴えるような眼で大崎課長を見つめた。 「木下さんを撃ったのは私じゃありません。渡良瀬署長です」 「下手なウソだな」 「ウソじゃありません。木下さんは、水主事件の真犯人を知った私をかばおうとして撃たれたんです」 「……なんだと?」 大崎の構えた銃口がピクリと揺れた。 「どういうことか説明しろ」 愛海は舌をもつれさせながらも、懸命に説明した。つっかえそうになると、俺が助け舟を出した。 渡良瀬と暴力団同勇会との黒い癒着。金銭の受け渡しをしていた宇佐美が邪魔になったこと。 「渡良瀬署長は、宇佐美さん殺しの罪を水主宏平さんになすりつけようと、無理な取り調べを行なって自白させたんです。彼の息子である水主淳平は、そのことを突き止め、渡良瀬署長を脅そうとして逆に殺された。証人の黒田さんも、赤塚さんと木下さんが署長の命令で殺したんです」 「証拠はあるのか?」 「証拠?」 証拠などない。死んだ者の記憶だけだ。幽霊の証言など、誰も聞きはしない。 佐田亜希子の家で見つけた宇佐美の手帳だって、渡良瀬との金銭の受け渡しの決定的な証拠にはならない。 結局、俺たちの手では渡良瀬の有罪を立証することはできないのだ。本人たちが自白でもしない限り。 しかし、愛海はためらうことなく、まっすぐに大崎に視線を返した。 迷いのない瞳で。 「証拠はありません。けれど、真実は犯人の心の中にあります。署長と赤塚さんに聞いてみてください」 大崎は銃を持つ手を少しずつ下げた。まるで重くてたまらない荷のように。 「話はわかった」 「信じてくださるんですか」 「ああ、信じる。嘘を言ってるかどうかは目をみりゃわかる」 「ありがとうございます」 「だがな」 次の瞬間、銃口はまたピタリと愛海を狙った。 「だったら、なおさら、あんたに犯人になってもらわんとな」 「大崎!」 俺は、奴の胸倉をつかまんばかりの勢いで怒鳴った。 愛海は目を見開いたまま、黒光りする拳銃を見つめた。 「課長……じゃあ、課長も」 「ああ、誤解するなよ。17年前のいきさつなんか、俺は知らない」 大崎は、まるで死刑囚相手に説法する坊さんのように、眉間を寄せた。 「だが、マル暴で何年もやってりゃ、過去に何か同勇会と、後ろ暗いいきさつがあったことは薄々わかる。調べたい気持ちも湧いたよ。だが、真実を暴いたからってどうなる」 「どうなるって……」 「署長が殺人を犯し、17年ものあいだ組織をあげて隠蔽していたんだぞ。バレれば、えらいことになる。南原署そのものが崩壊だ。マスコミは大スキャンダルだと騒ぎ立て、地域の住民は警察を信用しなくなり、犯罪者は俺たちをバカにする」 「……」 「だから、南原署の刑事たちは、みんな見て見ぬふりをしてきたんだ。警察を守るために。あんただって刑事のはしくれだったら、そのくらいわかるだろう」 「それじゃあ」 愛海はふらふらと壁にもたれかかり、力なく言った。「みんな、知ってたの?」 「当時の署員たちは全員で、この秘密を闇に葬る覚悟だったと思うぜ。空気読めねえお嬢ちゃんが来るまではな」 「だって、おかしいよ……じゃあ、真実は隠されたまま? 正義はどうなるの?」 「正義が、ナンボのもんじゃい!」 大崎は吐き捨てるように言った。 「正義を振りかざせば、その正義を守るために存在する警察の組織が、ガタガタになる。そんなこともわからんのかい!」 マル暴課長の火の出るようなタンカに、愛海は膝の力を失って、ぺたりと座りこんだ。 決着がついたと確信したのか、それを見た大崎は銃を下に向け、彼女に歩み寄った。 「お嬢ちゃん。あんたひとりが犠牲になれば、八方丸くおさまる」 「私……?」 「大ゲンカの末、木下警部補を撃っちまったと自供しろ。悪いようにはせんから」 愛海は必死で首を横に振った。「いやです。だって……それじゃ、殺された人たちの無念は……」 大崎は、フフンと鼻の先で笑った。 「それこそ、死人に口なしって言うだろう」 その次の瞬間、大崎は吹っ飛び、段ボールの山の中に倒れこんだ。 俺が霊指の力で渾身のこぶしを、ヤツの横っツラに叩きこんだのだ。 倒れたまま起き上がれない大崎のかたわらに立ち、俺は、ありったけの怒りをこめて睨み下ろした。 「あいにくだな。死人にだって、口くらいあるんだよ」 俺は大崎の手から拳銃を抜き取ると、腰を抜かしている愛海を立たせ、銃を渡そうとした。愛海は全力で首を振ったので、部屋の隅に放り投げた。 「行くぞ」 とにかく、この部屋から出る。 愛海を可愛がっていた大崎課長なら、味方になってくれると思ったが、甘かった。しょせんは組織の人間。警察に不都合な事実は、組織ぐるみで徹底的に隠蔽する気なのだ。 こうなったら、階段で一階に降りて、この建物から一気に脱出する。もう、署の仲間たちとは戦えないなどと言っている場合ではない。俺の霊力の全部を使ってでも、立ちふさがるものはぶっ倒す。 扉を開けると、案の定、囲まれていた。開け放した扉やロッカーの影から、大勢の刑事たちが愛海に狙いを定めて銃を構えていた。 つい昨日まで苦楽をともにしていた同僚たちが、みんな敵になっちまいやがった。 「ひるむな」 励ますように言うと、愛海はこくんと小さくうなずき、一歩踏み出した。 「愛海」 どこかの物陰から、名前を呼ぶ声がした。 「由香利?」 「ねえ、出てきてよ。ゆっくり話そう」 おびえたように、少し裏返った声音。同期の親友でさえも、署長のことばを信じて、愛海を殺人犯だと思いこんでいるのだ。 「由香利」 愛海はみるみる涙声になって訴えた。「信じて。私、何もしてないよ」 「うん、わかってる。みんな信じてるよ。だから抵抗しないで。ちゃんとゆっくり話そう」 見れば、階段室の一階への踊り場には、盾を構えた機動隊員たちが並んでいる。相変わらず、あちこちから銃口が愛海を狙っている。 「みんな信じてる」なんて、真っ赤なウソだ。 「愛海」 俺は、低く彼女に命じた。「走るぞ。右だ」 「無理」 愛海の喉の奥から、こらえていた嗚咽が漏れた。恐怖と疲労の限界を超えてしまったのだろう。 「もう無理だよ。走れない。私、投降する。取り調べでちゃんと話す……から」 「ダメだ」 俺は言下に否定した。 「取り調べの厳しさが、わかっているのか。俺の親父だって、必死で無実を叫んだんだ。家族のために無罪を勝ち取ると、絶対にがんばると毎日言い続けていた。それなのに、あっけなく、してもいない殺人を自供させられたんだ。そんな取り調べ、おまえには耐えられねえ」 叫びながら、まわりの空気が真っ赤に燃えあがるような気がした。 なぜ、こんなことになった。なぜ愛海が、こんな目に会わなきゃならねえ。親父が、黒田が、俺たちが、いったい何をしたって言うんだ。 全部、おまえのせいだ! 渡良瀬! 「いいから、走れ!」 俺は愛海を無理やり抱きかかえるようにして、階段室へと飛んだ。 待ち構えていた機動隊たちも、宙を飛んでくる愛海に度肝を抜かれて、盾の後ろで微動だにできなかった。俺は一階に降りることをあきらめて、愛海をひっぱって三階へと駆け上がった。 三階は静まり返っていた。誰もいないことを確かめると、俺たちはふたりで階段室の扉を閉めて鍵をかけた。 結局、逃避行はふりだしに戻ったのだ。 署長室にも人影はない。渡良瀬と赤塚は、下に降りてしまったのだろう。 扉の向こうの階段を、大勢の追手が上がってきた気配がする。ぐずぐずしてはいられねえ。 三階は、署長室や会議場のある南側と、留置場のある北側が、分厚い防火扉で仕切られている。 「淳平……そっちは」 「うるせえ、黙ってろ!」 後から考えれば、この時の俺は、すでに常軌を逸していた。 いや、幽霊という存在そのものが常軌を逸しているわけだが、とにかく臨界点を越えていた。 渡良瀬に対する憎悪は際限なくふくれあがり、それにつれて霊力もどんどん高まっていったのだと思う。 ロックされている厚さ1ミリの鉄板張りの防火扉を、俺は何のためらいもなく開け放った。 北セクションに入ると、通路の端にまず扉があり、受付や接見室があり、その奥の鉄格子の向こうが留置場だった。 何か得体のしれない力に、どんどん奥へ奥へと、引っ張られているような気がする。 NEXT | TOP | HOME Copyright (c) 2006-2011 BUTAPENN. |