

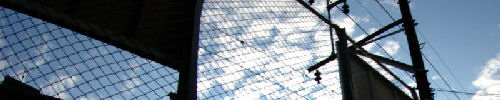
|
BACK | TOP | HOME Chapter 9-2 「でも、その前にお願い、もうひとつだけ確かめさせて」 そう言って、愛海は朝早く、家を出た。 佐田亜希子は、ねぼけまなこで玄関で愛海を迎えた。 「どうしたの? こんなに早く」 「このあいだ、お話ししてくださった、証券会社の上司と名乗る人物ですが」 愛海は、一枚の写真を差し出した。「この人ではありませんか」 「う……ん、似てる。少し感じが違うかな……、いや、でも、顎のあたりとか似てる。そうよ、たぶんこの人よ」 「そうですか」 愛海は、故人を見るような悲しげな目つきで写真をじっと見た。それは木下警部補の写真だった。 「亜希子さん、突然ですみませんが、一週間ほど家を空けてくれませんか?」 「え?」 「友だちの家に泊めてもらうとか。旅行でもいいです。しばらく姿を隠してほしいんです」 「どういうこと?」 亜希子は、ありありと不安な顔になった。「私、犯人に狙われてるの?」 「あなたのことは、最大限に安全を確保します。けど――」 愛海は、次に言うべきことばを失った。彼女を守るべき警察自体が、今は敵なのだ。 参考人として事情聴取を受ける直前に殺された黒田も、赤塚をはじめとする刑事たちの手にかかったのだから。 「わかった。一週間ね」 亜希子は、にこりと笑んだ。「ちょうど、九州の温泉めぐりに行きたいと思ってたの。だいじょうぶ。殺人事件に関わってるんだもの。それくらいの覚悟はしてるわ」 「ごめんなさい」 愛海は半泣きになりながら、ぺこりと頭を下げた。 「それと、決して誰にも行先は言わないでください。警察から問い合わせがあっても、絶対に応対しないでください」 しつこいほど念を押しながら、愛海は刑事として、いたたまれない思いだっただろう。 「これから、どうすればいいの」 「本庁の捜査一課に、洗いざらい話そう」 俺は、愛海と捜査でコンビを組んだことのある、都築警部の名を挙げた。 「あいつなら、必ずおまえの味方になってくれる。ヘタな人間に相談すると、渡良瀬と通じてる恐れがあるからな」 「わかった」 愛海は、まだ何もかもが信じられないという虚ろな表情をしている。 「ねえ、加賀美係長にも相談したらダメ?」 「いや、あいつもグルだ」 俺は、男子トイレで連れションをしていたときの加賀美と木下の会話を聞いていたのだ。 『意外だったな』 あの言葉に込められていた意味がようやくわかった。ふたりは経験の浅い愛海を木下の相棒とすることで、事件を迷宮入りにすることを画策していたのだ。 ところが、愛海は短期間のうちに刑事として成長し、片っ端から参考人との面会を取りつけ、ずんずん捜査を進めていった。もちろん、俺という影の情報網があったからこそだが。 奴らはさぞ、あわてただろう。このまま放っておけば、愛海が事件の核心へと迫ってしまう。黒田の殺害は、せっぱつまった奴らがおかした最大のミスだった。 「じゃあ、いったい南原署の誰が信じられるの?」 「わからん。全員を警戒したほうがいいな。用心に越したことはない」 「うん……」 そのとき、愛海の携帯が鳴った。 「え、どうしたの、由香利」 それは、愛海の同期で親友、少年課の石崎由香利だった。 「愛海、何してるの。加賀美係長がカンカンだよ!」 携帯から飛び出してきたのは、隣にいても聞こえるぐらいの大声だった。「ちっとも来ないから、『あいつはクビだ』って湯気立てて怒ってるよ」 「げえ、しまった」 愛海は、今日は早番に入っていたらしい。見れば、定時の九時さえ過ぎている。 「す、すぐ行くから、何とかなだめといて!」 「わかったよ。その代わり、高くつくからね」 愛海はダッシュで地下鉄の駅に向かった。 「おい、愛海」 俺はあとを追いかけて飛ぶ。「やっぱり南原署に行くつもりか」 「行かないと、事件の真相を公表する前に、刑事をクビになっちゃうよ」 「だけど、罠かもしれねえ」 今のところ、敵だとわかっているのは、渡良瀬署長、木下警部補、赤塚巡査部長の三人。それに、加賀美係長も一枚噛んでいる。それ以外の署員たちも、誰がグルになっているか見当がつかない。 「だいじょうぶ。私が事件の真相に気づいていることは、まだバレていない。平然と何も知らないふりをするから」 走りながら愛海は、自分に言い聞かせるように言った。 「それに由香里だって、話せば絶対、味方になってくれる。ほかの署員だって、味方になってくれる人はおおぜいいるよ」 これまで苦楽をともにした同僚たちを、全員疑えというほうが無理なのだ。信じたいという気持は、理屈を超えている。 「わかった」 とうとう俺も折れた。「何が起ころうと、俺がついてるからな。俺が愛海を守る」 澄みきった冬空の下に、南原署は見なれた姿で立っていた。コンクリート四階建ての古びた、何の変哲もない建物が、今の俺には悪魔の城に見える。 そして、そこに突入していく俺と愛海は、さしずめ悪魔を退治しに来た騎士と姫君か。自分で自分のとんでもない妄想に笑ってしまう。 「何が可笑しいの?」 「なんでもねえ。行くぞ」 愛海は、大あわてで出勤してきた演技をして、玄関から飛び込んだ。 署内はいつもと、まったく変わらない。 会計課では、落し物を引き取りにきた耳の遠い老人が大声で署員とやりとりしている。交通課は免許の更新や車庫証明の手続きに来た人たちが順番待ちをしている。待ち合いスペースでは、振り込め詐欺や自転車事故への注意を呼びかけるビデオが、ずっと流されている。 平和そのものの光景だった。肩すかしを食らった気分だ。 二階に上がると、ひとりのチンピラが、手錠をはめられて三階の留置場から降りてくるのに出くわした。へらへら笑いながら、捜査三係の刑事たちにこずかれて、取り調べ室に入っていく。 大きな深呼吸をひとつすると、愛海は刑事課の扉を開け放った。 「すいません、遅くなりました!」 想像に反して、刑事課には、ほとんど人間がいなかった。 内勤の女性警察官が、「あ、小潟刑事」と椅子から立ち上がった。 「さきほど南原西町で強盗事件が発生し、みなさん出かけられました」 「あちゃー。遅かったか」 定時に遅刻したうえ、出動にまで遅れたとなれば、ただではすまない。「また叱られるよ」と、愛海は首をすくめる。 良くも悪くも、いつもの日常だ。 「それから、加賀美係長が、『小潟刑事が来たら、これを渡すように』と」 いかにも同情に満ちた目つきで、女性警官は一枚の便せんを渡した。 『辞表を持って、ただちに署長室へ行け』 愛海は、よろっとバランスを崩して机に手をついた。 「いよいよ、クビになるんだ……」 「まあ、予想していたことではあるな」 いくら専従捜査員をはずされたとは言え、愛海は俺の事件について一番くわしい人間、また興味を持っている人間だ。 やつらが黒田智也を殺してまで隠そうとした真相が、いつか愛海に見破られてしまうかもしれないと恐れる渡良瀬署長は、なんのかのと理由をつけて、クビにしてしまえと考えたのだろう。 南原署の刑事を辞めさせられれば、愛海には何の捜査権限もない。俺の事件も、十七年前の宇佐美昌造が殺された事件も、二度と調べることはできない。 渡良瀬たちにとって都合の悪い事実を、すべて愛海の辞職によって闇に葬ることができるのだ。 「どうしよう」 「とにかく、署長室へ行ってみよう。おまえがどこまで真相をつかんでいるのか、奴らも探りを入れたいに違いない。あくまでシラを切り通すんだ。何食わぬ顔をして、平然としていればいい」 「わかった」 愛海は両手のこぶしを握りしめて決意を固めると、おもむろに自分の机の引き出しを開けて、白い封筒を取り出した。 「なんだ、それは」 「辞表だよ。持っていけって書いてるでしょう」 「……いつも引出しに入れてるのか。用意周到だな」 「だって、テレビドラマの刑事はカッコよく、さっとスーツの内ポケットから出してるもん」 署長室は、建物の奥の階段を使って三階に上がり、つきあたりの角部屋にある。同じ階の留置場とは、防火扉のような分厚い扉で区切られている。 ノックをすると、すぐに「どうぞ」という応答があった。 愛海は入ってお辞儀をし、扉を閉めた。俺は正面のデスクの向こうで立ち上がった渡良瀬の顔をじっと睨みつけた。 俺を殺し、親父を自殺に追い込んだ、影の張本人。 頬はたるみ、体も肥満気味だが、動作は決してトロくはない。 見る者にまとわりつくような眼光は、ヘビの執念深さと薄気味悪さを感じさせる。相変わらずの威圧感だ。十七年前と比べても、まるで衰えていない。 「小潟くん」 「すみません。遅刻しました」 署長のことばをさえぎるように叫ぶと、愛海はぺこりと体を百二十度に折り曲げた。 「反省しています。もう二度とこのようなことはしません」 「まあまあ。いきなり、そんなに謝らなくとも」 渡良瀬は機嫌よさそうに、巨体をゆすりながら笑った。 「きみのお手柄のおかげで解決している事件も多い。きみが優秀な刑事だということは、わかっているよ」 「は、はあ」 愛海はしゃちこばって、神妙な顔をしている。 「ただちょっとスタンドプレーが多いようだね。結婚詐欺師殺害事件に関して、茨城県で証人の黒田という男を殺されてしまったのは、明らかな失態だった」 「はい、申し訳ありません。あのときはご迷惑をおかけしました」 「それで、専従捜査員をはずれたんだったね」 「……はい」 渡良瀬署長は、ゆっくりと机の縁を回ってくると、愛海のかたわらに立った。 「それなのに、まだ事件の捜査に関わろうとしているらしいね。有休まで取って、結婚詐欺の被害女性のひとりと接触しているそうじゃないか」 愛海は、はっと目を見開いた。 しまった。佐田亜希子に接触していたことが、バレていたのか。 亜希子はついさっき、愛海の携帯にメールをよこした。もう家を出てタクシーで新幹線の駅に向かう途中だという。とりあえず亜希子が無事であることは確かだ。 「すみません」 愛海は、あくまでも冷静さを保とうとした。間近に立っている署長を、まっすぐに見上げる。 「一度始めた捜査を、最後までやりとげたいと思いました。私にとって、水主淳平事件は、刑事となってはじめての専従事件だったんです」 「なるほど、気持はわかるよ」 「それなのに、捜査は全然進まなくなって。殺された被害者はどれほど悔しい思いをしているかって考えたら……どうしても、犯人を探してあげなきゃって思って」 次第に、走った後のように息がはずみ、声がうわずってくる。 「愛海」 俺は首を振った。だめだ。これ以上何も言っちゃいけない。何も知らないふりをして、トボけるんだ。 「……でも結局、証人にいろいろ話を聞いても、何もわかりませんでした。すみませんでした」 愛海は最後にそう言って、大きく深呼吸した。 「そうか。何もわからなかったか」 「はい」 渡良瀬署長は、ぽんと愛海の肩を叩いた。 そして机に戻って、電話の上に屈みこみ、内線ボタンを押した。「ちょっと来てくれ」 ややあって、署長室にふたりの男が入ってきた。 赤塚巡査部長と、木下警部補だ。 ふたりは愛海を見て、顔をひきつらせた。大の男、しかも、いかついツラをした定年間近の刑事が、若い女におびえている図は、こっけいですらあった。 こいつらはこうやって、ずっとおびえ続けてきたのだろうな。 渡良瀬と赤塚と木下の三人は、十七年前からグルだった。暴力団と警察の橋渡し役をしていた宇佐美が何かの理由でじゃまになり、殺した。そして、いあわせた俺の親父に罪をなすりつけた。二年前、事件の真相をさぐっていた俺を殺した。そして、ついこの前になって、彼らの顔を目撃した黒田を殺した。 そうやって殺人を重ねながら、一方で、真実を突き止めようとしている同僚の愛海を恐れている。 心の安らぐときなどなかっただろう。そう考えると哀れだと思う。 だが、それは当然の報いだ。罪のない人たちを殺し、その家族たちをも不幸におとしいれたのだから。 できるならば、俺の手で八つ裂きにしてやりたいところだ。 だけど、俺自身が、たくさんの罪のない女たちの心をもてあそんできた極悪人だ。同じ罪人に、罪人をさばく権利などない。 だから俺は、無垢な愛海の口を借りて、恨みを代弁してもらうしかないんだ。 「小潟くん。きみは」 渡良瀬署長は、鳥肌がたつような優しい声で言った。 「すべてを知っているんだろう?」 「す、すべてって、どういうことですか?」 愛海は、なんとかして平然とほほえもうとした。 「ここにいる資料係の赤塚くんに、佐田亜希子の調書を見たいと言ったそうだね」 「あ、あれは断られちゃいましたけど」 「あとで調べたら、こっそり調書を見た形跡があったそうだ」 俺と黒田の幽霊が、資料室に忍び込んだんだ。慎重に探したつもりだったのに。赤塚のやつ、何かすぐにわかるような細工をしていたな。 「うそ。だって」 止める暇もなかった。愛海はあわてるあまり、大変な失言をしてしまったんだ。 「そんなことできっこありません。だって、調書そのものが、なかったんですから」 今まで、笑みすら浮かべていた渡良瀬が、すっと能面のような無表情になった。うしろにいた赤塚と木下は、逆に般若のように険しく、眉をつりあげた。 調書がないことを知っているとは、とりもなおさず資料倉庫にまで立ち入ったと白状しているようなものだ。人間の身で、鍵のかかった倉庫に忍び入ることは、不可能に近い。幽霊の俺だからできたんだ。 彼らにとって、愛海は超人かモンスターのように見えただろう――すみやかに抹殺すべきモンスターに。 「残念だよ。小潟くん」 署長はかすれた声で、うめくように言った。「きみが、わたしたちの考えていたとおり無能な刑事であれば、こんなことにはならなかったのに」 愛海は蒼白になった。自分のおかした致命的なミスに気づいたのだ。 そして自分が、三人の殺人犯に取り囲まれていることを。 「愛海!」 俺は叫んで、愛海にのそばにいた渡良瀬署長に飛びついた。 「この部屋から逃げろ」 そして、ありったけの霊指の力で、渡良瀬の巨体をねじりこむようにして、床に倒した。 愛海はすぐに、俺のことばに反応した。 とっさに、署長室に置いてあったキャスター付きの椅子に手を伸ばすと、両手で肘掛けをつかみ、背をかがめて椅子を盾がわりにして、扉のそばにいたふたりの刑事に突進した。 赤塚と木下は、あわてて飛びかかろうとしたが、愛海がぐるりんと椅子を回転させたため、「うわっ」とバランスを崩す。 もちろん、愛海だけの力では、大の男ふたりは振り回せない。俺も霊指で加勢したのだ。 「こいつ!」 赤塚が体勢を立て直し、わめきながら飛びかかってきた。愛海と俺は力を合わせ、勢いをつけて椅子をぶつける。 こいつらから見ると、愛海はすごい怪力女に見えるだろうな。 赤塚がころんだその隙に、愛海は扉のノブに手をかけようとした。 「動くな!」 渡良瀬のドスのきいた声が響いた。 気圧されて、たちまち動きを止めた愛海は、おそるおそる背中越しに後ろを見た。 渡良瀬の手には、拳銃が握られている。 「ひゃあ……」 声にならない悲鳴を漏らし、愛海は両手を上げた。 「そのまま、こっちに向くんだ」 カツカツと足音を響かせ、署長は銃口を向けたまま近づいてくる。 「困ったお嬢さんだ。もう少し腰を落ち着けて話せないものかな」 「む、無理です」 高々と上げた手をぶるぶると震わせながら、それでも愛海は律儀に返事をした。 「さっきは、どんな技を使った。触れてもいないのに、わたしの体を吹き飛ばすなんて」 「何もしませんっ」 渡良瀬がニューナンブM60の撃鉄を上げる音がした。 「おまえは誰だ? 本庁からの特別監察官か」 「ひっ、ち、ち、違います」 愛海は硬直してしまっている。無理もない。いくら刑事とは言え、目の前に拳銃が突きつけられる経験はないだろう。 俺は愛海の背中に回り込み、ドアのノブをこっそりと回した。もし危険になれば、愛海の体を外に引っ張り出す。 問題は、俺にそれだけの強い霊力があるかどうかだ。だが、無理でもやらなきゃならない。 「きみたち、今起こったことを証言してくれるね」 署長は、赤塚と木下に命じた。 「小潟刑事を呼び出し、遅刻と欠勤が多いことを理由に退職を言い渡した。逆上した小潟刑事は、止めようとするわたしたちに暴言を吐き、暴れまわった。やむなく威嚇のために取り出した銃を取り合ううちに、小潟くんは自分の胸を自らの手で打ち抜いてしまった」 「はい」 「わかりました」 「は、反対」 愛海はひとり、むなしく抵抗の声をあげた。 「愛海、いいか」 俺は彼女の背後でささやいた。「いちにのさんで合図をしたら、俺が一気にドアを開く。柔道の受身の要領で後ろに倒れこめ。廊下に出たら、階段に向かって走り出すんだ。だいじょうぶ、めったなことで弾は当たらねえ」 「めったじゃなかったら?」 「それでも、俺が守る」 かたくなに繰り返す。 本当は勝算なんてない。幽霊の体は銃弾を全部通してしまい、愛海の弾よけにさえならない。 それでも、俺の全存在をかけて、愛海は絶対に死なさない。 「行くぞ!」 俺は三まで数えて、扉を開け放った。 愛海は、開いたドアから思い切りよく転がり出た。区民ミュージカルに妖精役で出演したときの特訓が生かされたのかもしれない。 予想に反して、渡良瀬は銃を撃ってこなかった。背後の扉がいきなり開くというありえない事態に、あっけに取られたに違いない。 「階段だ!」 俺は、署長室のわきにある奥の階段室を指差した。その一方で、霊指の力でなんとか署長室のドアを閉めようとする。一秒でも二秒でも、愛海が逃げる時間をかせがねばならない。 下に降りれば、同僚の警官や一般人もいる。渡良瀬たちといえども、そこでは拳銃は振り回せないはずだ。 だが、三人がかりで押し返されては、俺の力などひとたまりもなかった。 この世では、人間の怒りと憎悪ほど、強く恐ろしいものはない。幽霊などにかなうはずはなかった。 太った渡良瀬や赤塚より先に、敏捷な木下警部補が廊下に飛び出した。そして、階段から降りようとしている愛海に飛びかかる。 「きゃああっ」 悲痛な悲鳴を上げて、愛海はバランスを崩した。ふたりはもつれあうようにして、二階との踊り場へ転げ落ちた。 とっさに回り込んだ俺は、なんとか愛海が床に激突しないように支えた。 「にゃろおっ!」 言葉にならない咆哮を上げて、赤塚が階段を駆け下りてくる。 ――絶体絶命だ。 ほとんどの署員は入口に近いほうの階段を使うから、奥の階段にはまったく人影はない。助けを呼んでも、誰も答えてはくれないだろう。 木下は立ち上がり、目を血走らせながら、愛海の襟首をぐいとつかんだ。 「木下さん……」 愛海はほとんど、失神寸前になっている。 「木下、てめえ!」 俺は声のかぎりに叫んだ。聞こえないとわかっていても、そうせざるを得なかった。 「専従捜査員として三年間、彼女はてめえの尻にくっついて走り回ったんだぞ。さんざん嫌味を言われ、罵声を浴びながら、それでも、おまえを上司と仰いで」 その男に、今殺されようとしている。愛海の衝撃と絶望はどれほどだろう。 「それでも人間か。保身のために愛海を殺して、平気なのか」 木下は歯を食いしばって、愛海をにらみ続けていた。 つかんでいた拳が、ぶるりと痙攣したかと思うと、すっと離れた。かっと見開いていた目が、気のせいか、ほんのわずか、あきらめの色を帯びた。 俺の声が届いたのか? まさか、そんなはずはない。 「逃げろ、小潟」 木下は、くるりと振り返って赤塚の前に仁王立ちになると、両腕を開いた。 「行け!」 静寂は、数秒のようにも数時間のようにも感じられた。そして、一発の銃声がとどろきわたった。 渡良瀬署長は、銃を右手に階段の上に立ち、踊り場を冷たい目で見降ろしていた。 「おやおや、いけないね。小潟刑事。恩ある上司を撃ってしまうとは」 「ひ、ひゃああ」 寄りかかるように力なく崩れ落ちる木下警部補から飛びすさり、愛海は空気の抜けたような悲鳴をあげた。 NEXT | TOP | HOME Copyright (c) 2006-2011 BUTAPENN. |