

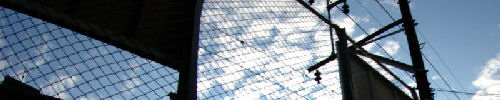
|
BACK | TOP | HOME Chapter 9-1 暖かいぬかるみの中から、ようやく俺は浮き上がった。 なつかしい感覚だ。死んでから最初の一年間、俺はこの中で眠り続けていたのだから。 意識が定まり始める。俺は【はざまの世界】に全裸で仰向けに寝ていた。ハダカと言っても、別に恥ずかしい部品がついてるわけじゃない。寒さも感じない。俺の体は霊が形を取ったもの。いつも着ている洋服は、生前に一番なじんでいたものを、俺が無意識に選んだだけだった。 太公望のおっさんが、しげしげと俺をのぞきこんでいる。 「目覚めて最初に見た顔が、こんな爺さんじゃ、起きる気もしねえな」 「それだけの憎まれ口がきけるのなら、もう心配はいらんな」 ゆっくりと起き上がって、あたりを見回す。いつもどおりだ。見えるものは何もなく、ゆらゆらと光が揺れているだけの世界。 「俺はどうしちまったんだ」 「殺されたときのことを思い出したのじゃ。そのショックで一時的に霊力が暴走し、消耗したすえに霊体がバラバラになってしもうた」 「そうだった……」 路地裏に立ったとき、どっと苦痛が押し寄せてきたのだ。まるで、あの瞬間に戻ったように。 背中にナイフが差し込まれ、心臓が鼓動を止めて、血圧が急激に下がり、脳が活動を停止したあの瞬間。 生きようとする意志そのものが、【生命】そのものが、奪われたあの瞬間。 人語では語ることのできない恐怖に、今でも俺の体はわなないている。あの苦痛を思い浮かべないように必死で頭から追いやりながら、それでも、絶対に追いやれない事実が残った。 「全部、思い出したよ」 俺は苦々しく言った。 「俺を殺したのは、南原署の赤塚と木下のふたりだ」 「ああ」 太公望は、神妙な顔でうなずいた。 「そして、ふたりに俺を殺せという命令をくだしたのは、南原署署長の渡良瀬だ」 「ああ」 「まったく笑っちまうぜ。よりによって俺の事件の捜査員の木下が、俺を殺した実行犯だったなんてな」 「いや、それは逆じゃよ。犯人だったからこそ、おまえさんの事件の担当に据えられたんだ」 「なるほど、そういうことか」 はじめから渡良瀬署長は、署ぐるみで俺の事件を迷宮入りに仕立てようとしていたんだ。赤塚を資料課に配属し、真犯人につながる重要な捜査資料を処分させる。そして木下は専従捜査員として、的はずれな捜査ばかりして、真相があばかれないようにする。 まだ新人刑事だった愛海を相棒に選んだのも、そのためだ。ドジばかりやってた彼女なら、木下の言いなりになると踏んだのだろう。 「そういえば、愛海はどうしてる?」 俺は、愛海のことを思い出してあわてた。突然、俺の霊体が目の前で消滅したのだ。さぞ今ごろパニくっていることだろう。 「愛海ちゃんには、久下に頼んで連絡を取ってもらった。ゆっくり骨休めしているところだから心配はいらぬと」 「そうか。すまん」 久下とは、太公望とつながりの深い心霊事務所の所長だ。俺はほっとしたと同時に、さっきから太公望が俺の話を聞いても、ちっとも驚いていないことに気づいた。 「最初から知ってたのか、あんたは。俺を殺した犯人を」 「知っておったよ」 じいさんは、ひどく疲れたような動作で、霊泉のほとり、いつもの定席に腰をおろした。 「おまえさんが殺された現場を、わしは偶然にもここから覗いておった。いや。偶然ではなく、天の導きだったかもしれんの。なにしろ、実に合計三人もの命が、正義を守るべき者たちの手で奪われたのだ」 湖面を見つめながら、しょぼしょぼと瞼を上下させる。 「わしの役目は、よるべない魂を地上から受取り、しかるべき場所に送ること。おまえさんが来たときも、悪行をなした者として、ただ黙ってあの世に送るべきだったのかもしれぬ。しかし、わしには、それができなかった」 「じゃあ、俺の魂が、死者のリストにないと言ったのは」 俺は太公望に最初に会ったとき、いきなり言われたのだ。『予定にない死に方をしたため、あの世に行く資格のない宙ぶらりん状態だ』と。 「ウソだったのか。俺は、あんたのおかげで地獄に送られずにすんでいたわけか」 「おまえさんは本来なら、まっとうな人生を歩むことのできる人間だった。おまえさんが悪に走ったそもそもの原因を野放しにしたまま、地獄に送ることが果たして公正なさばきなのか。そう訴えたわしに、天界は判断をゆだねてくださった」 「幽霊になった俺に、霊指の力を使って奴らの罪をあばくチャンスをくれたんだな」 太公望は、「いや、違う」と首を振った。 「罪をあばくためではない。おまえさん自身が、自分の罪を悔い改めるチャンスを与えたのじゃよ」 「自分の罪を……」 俺は太公望のわきに立って、何も映っていない湖面を見つめながら、これまでのことを思い返していた。 俺を愛してくれた女たちを嘲笑いながら、金を巻き上げるという最悪の手段で心を傷つけて、彼女たちの人生を台無しにして来た。自分が悪人になったのは世間のやつらが悪いのだと、ちんたら言い訳しながら。 その罪は、人の命を奪ったも同然なのだ。そんな俺に、俺を殺した奴らをののしる資格はない。 「そうだった。俺は地獄に行く前に、自分の罪をつぐなうチャンスをもらったんだったな」 俺は頭を下げた。「ありがとう、おっさん」 「淳平よ」 太公望は、うるんだ目で俺を見つめた。「忘れるでない、何があろうと犯人をうらむな。決して自分で復讐しようとしてはならんぞ。すべてを天にまかせるのじゃ」 「ああ」 「約束せい。指切りげんまんじゃ」 「なんだよ、それは。子どもじゃあるまいし」 おっさんは、有無を言わせず小指をからめてきて、「指きりげんまん、嘘ついたら針千本飲ーますっ」と力いっぱい指を切った。 「ふふふ。わしは地獄に知り合いが多いからの。本当に針千本調達してくるぞ」 「冗談じゃねえ。おっさんの辞書には、レトリックということばはねえのか」 驚いたことに、太公望は俺の首に両腕を回して抱きついてきた。 「淳平。くれぐれも気をつけるのじゃぞ」 「気持ちわりい。どうせなら愛海みたいな美人に抱きついてもらいたいぜ」 このときの太公望は、うすうす感づいていたのかもしれない。――これから俺と愛海の運命に、どんなことが待ち受けているのかを。 俺はすっかり元気を回復して、【はざまの世界】から地上に戻った。 まずは、愛海に事実をすべて説明しなければならない。どうするかは、それから決めればいい。 「淳平?」 俺の姿を見つけた愛海は、大声で叫んだ。 この頃は俺も用心して、姿を見せる前にあたりの様子を確かめることにしている。捜査会議の席上や人通りの多い街頭は避けるとか。愛海がカップや皿といった壊れものを持っていないかとか。二年間、数々の修羅場をくぐってきた経験のたまものだ。 幸い、そのときの愛海はたったひとりだった。あたりに人目はなく、手にも何も持っていない。 それも、そのはず。愛海は自宅の風呂で入浴中だったのだ。白い入浴剤を入れた湯船から我を忘れて立ちあがったため、とろりと濡れた女神のようなナイスボディが拝めるというおまけつきだ。 思わぬ眼福にガッツポーズをしている俺に、愛海は「きゃあ」と体を両手で隠した。 「淳平、目がエロい!」 俺の横っつらを張り倒そうとして、すかっと浴槽に倒れこんで、盛大に湯しぶきをあげる。うーん。久しぶりだな、この光景。 俺も浴槽に横たわり、愛海を霊指の力で抱きしめた。 「心配してたんだから。ばかあ」 「心霊事務所の所長から連絡があったろ」 「それでも心配したの。もしかして、もう死んじゃってるんじゃないかって」 「もしかしなくても、死んでるって」 ふざけ合いながら、俺たちは何度もキスを交わした。 マンションの窓から見降ろす夜の街は、すっかりクリスマスムード一色だった。俺が姿を消してから一週間もの日が過ぎていたのだ。 「さびしかった」 「ごめんな」 俺は、愛海がうんと喜ぶような償いをしようと思った。これから話さなきゃならない残酷な事実に備えるためにも。 「今夜はロマンチックなデートがしたいな。おめかしして食事に出かけるってのはどうだ」 「もう、お化粧も落としちゃったから面倒くさいよ」 「じゃあ、豪華に一流レストランからケータリングといこうぜ。俺がおごるよ」 「うそつき。淳平がお金持ってるわけないじゃん。結局、全部私が払うんだもん」 うう。幽霊ってのは、男の甲斐性ゼロだな。裕福な御曹司や社長を演じてきた俺にとって、実弾を全部抜かれた心地だ。 「私は、淳平といっしょにいるだけでいいの。ほかには何もいらない」 「……愛海」 ありのままの自分を愛してくれる女がいるというのは、なんと安らぐことだろう。 醜いところも、情けないところも、もう全部見せた。今さら何も隠したり、取りつくろったりする必要はない。 愛海は、いつものようにコンビニ弁当で夕食をすませた。今月の新製品は、「ベトナム風・生春巻の素揚げ」だそうで、コンセプトそのものが破たんしているとしか思えねえ。 食後のコーヒーを入れてやったあと、俺は霊体の膝枕に愛海を寝かせ、首から鎖骨にかけて丹念にマッサージする。 「なあ。驚かないで聞いてほしいんだ」 「なに?」 「俺を殺した犯人を、思いだした」 「え……ええっ」 愛海は、ガバとはねおきた。もし生身の体なら、俺は顎にアッパーカットを食らっているところだ。 「本当なの、犯人がわかったの?」 「ああ」 「誰? ……ダメ、やめて、待って」 愛海は、冷めたコーヒーをがぶがぶ飲んでから、無意味にうろうろと部屋の中を歩き回り、ドレッサーのところへ行って髪をとき、それから戻ってきて、クッションを抱えてぺたりと座った。 「誰なの?」 「おまえの相棒の木下警部補と、資料課の赤塚巡査部長」 愛海は、これ以上開いたら落ちるというくらい、目をまんまるに見開いた。 「うそ」 「本当だ」 「いくらクリスマスが近いからって、言っていい嘘と悪い嘘があるよ」 「嘘じゃない。それにクリスマスは嘘をつく日じゃない」 「だって」 愛海は言うべきことばをさがして、もぞもぞと体を動かした。「だって、ふたりとも南原署の刑事なんだよ」 「黒幕は、署長の渡良瀬だ」 「な、なにかの間違い、ぜったい、違う。だって」 「愛海。落ち着け」 俺は愛海の肩をぎゅっと握った。 「はじめから、順を追って説明する。黙って聞いててくれ。もしそれで納得いかなかったら、俺の言ったことは笑いとばして忘れてくれていい」 俺にとっても、死んだショックで忘れていた真実。俺があの世に行けば、永久に闇に葬られていたはずの事実。 俺が幽霊になってまで、この世に存在しているのは、この秘密を公にするためなのだろう。 ――亜希子の伯父・宇佐美昌造。俺の親父・水主宏平。そして俺・水主淳平の三人を死に追いやったのは、すべて渡良瀬署長と、南原署の刑事たちであることを。 さっきまで情を交わした女は、ぐっすり寝入っていた。 俺は彼女の寝息を確かめると、そっと布団から這い出し、ふすまを閉めた。 佐田亜希子は、俺の親父が殺したことになっている宇佐美昌三の姪だ。俺は偶然そのことを知って、いつものように近づいた。 亜希子をものにし、家に泊りこむような仲になってからは、隙を見て家探しをしている。 宇佐美を殺した犯人につながる証拠は、何かないか。十五年前は高校生で何もできなかったが、今なら真犯人をさがして親父の汚名をすすぐための、ノウハウも実力もある。 俺は何日もかけて、宇佐美昌三の使っていた書斎を皮きりに、宇佐美夫妻の寝室、居間へと調べを進めた。 床の間の地袋を開けてさぐっていたとき、三十冊以上のノートを見つけた。いや、家計簿だ。亜希子の伯母はとてもマメな性格だったらしい。三十年分の家計簿は、年の順にきちんと整理されていた。 宇佐美昌三の殺された年の家計簿を手に取って、めくってみた。 やはり、昌三の死んだ日付の翌日から、ずっと空白のページが続いている。代わりに葬式の費用のメモらしき数字が書き散らかされ、夫の死以降のあわただしい様子がうかがえる。 宇佐美の死んだ十二月十五日はと見ると、項目欄に、そば屋らしき店の名と金額が記されていた。 なるほど、宇佐美はその夜、居酒屋で飲んでいたのだから、夫婦二人暮らしの妻は、ひとりで出前でも取ったのだろう。 俺の親父が職人仲間と飲みに行く日は、母と姉と俺は、ここぞとばかり店屋モノを頼んで食べるのが、ささやかなぜいたくだったことを思い出す。 「ん?」 家計簿をめくっているうちに、ある規則性に気づいた。 ほとんど毎月十五日に、亜希子の伯母は出前を取っている。十五日が土日か祝日のときは、その前日。判で押したように、殺されるまでの一年半続いた。 たとえば、給料日には必ず飲みに行く習慣のサラリーマンもいるが、宇佐美の経営する会社の給料日は二十五日だ。 いったいなぜ、宇佐美昌三は、必ず十五日に飲みに行くのか。 俺の脳裏に、ひとつの可能性がひらめいた。毎月決まった日に、人に会っていたのではないか。そこまで正確に日を守る理由は、おそらく金の受け渡し。 書斎に戻り、宇佐美のスケジュール手帳をもう一度出した。いったん警察に証拠品として押収されたものだ。死ぬ時も身につけていたのか、表紙に小さな血痕らしきシミが残っている。 毎月の十五日の欄を懐中電灯で照らし、丹念に調べた。そして、いくつかの文字が巧妙に消されていることを発見した。 「15M」「20M」「W」「ワ」 数字は金額。「20M」は二十万円。そして「W」「ワ」は会った人物のイニシャル。 宇佐美昌三は、「ワ」の名のつく人物に毎月会って、金をやり取りしていたのではないか。そして、そのことを隠すために証拠品に細工ができるとしたら――警察しかありえない。 「ワ」と聞いて真っ先に俺が思い浮かべたのは、いやらしい笑みを浮かべたあの男だ。 渡良瀬警部。十五年前、一貫して親父の取り調べを担当した、太った中年の刑事だった。 『十五年前、宇佐美昌三を殺したのはあんたなんだろ。渡良瀬警部さん……いや、今は署長さんだったな』 『誰だ。おまえは』 『誰でもいい。偶然知っちまったんだよ。あんたと同勇会との黒いつながり。暴力団に便宜をはかってやった謝礼として毎月、大金を受け取っていた。その仲介役が宇佐美だった』 『なにを言ってるか、わからん』 『だが、次第に宇佐美の存在が邪魔になってきて、とうとう自分の手で始末した。もうすでに動かぬ証拠も握ってるんだぜ』 『くだらぬことを。いったい何が目的だ』 『わかってるくせに。宇佐美が渡していたのと同じ金額でいいよ。……また連絡する』 俺は電話を切り、手に持っていたブランデーのグラスをあおる。 絶対に足のつかない携帯を使っている。声色も変え、逆探知もされていない。俺の正体が水主宏平の息子であることを、ヤツはまだ気づいていないだろう。 「動かぬ証拠」など、どこにもなかった。ただのハッタリだ。ヤツから金をせびりとる気も、まして法の裁きに訴える気もない。 ただ、親父の味わった恐怖を万分の一でも味わわせてやりたい。 渡良瀬は、最初から宇佐美を殺すつもりだった。たまたま奴と飲み屋で隣り合った俺の親父に狙いを定め、わざとふたりを口論させるように仕向けたのだ。 取調べ役の刑事が真犯人であることも知らず、激しい追及のすえ身に覚えのない罪を自白させられ、留置場で首をくくったときの親父の絶望は、どれほどのものだったろう。 時間をかけて、じわじわと苦しめてやる。勝利の美酒が心地よく喉を伝い落ち、俺は声を殺して笑った。 だが後から考えると、渡良瀬は電話の主が俺であることを、とっくに見抜いていたのだ。その直後に俺の足取りを調べさせ始め、千葉県のおかまバーで働いていた黒田智也のもとに、赤塚と木下を聞き込みに送った。 そして、俺が佐田亜希子と接触していることも、すぐに突き止めた。 俺はまだ何の警戒もしないまま、二年前のあの日、亜希子からのメールを受け取った。 「なんだ、二百万って」 『二百万円用意できたから、駅前で待ち合わせましょう』という最初のメールで、俺は首をかしげた。 亜希子から金をだましとるつもりは全くなかった。ただ、ときどき「資金繰りがうまくいかない」などと呟いていた。結婚を匂わせる亜希子をけん制するためだ。 だが、宇佐美に関する調べもほぼ終わったし、そろそろ亜希子の前から姿を消す準備をしてもいいな。 俺の悪にまみれた心は、すぐに欲に傾いた。それが、渡良瀬のしかけた罠だとも気づかずに。 すぐに、二通目のメールが来た。『待ち合わせ場所を変えてもいい?』 それが、あの裏路地だった。よくよく思い出してみれば、二通目のメールは登録された亜希子の携帯からではなかった。 『電池が切れたので、友だちの携帯を借りたの』 と言い訳がひとこと添えてあったが、実際は、俺を殺そうとする犯人からの、死への直通メールだったのだ。 そうとも知らず、新しい待ち合わせ場所に、俺はのこのこ赴いた。しばらく待つと、路地の東側から男がひとり歩いてきたので、コートの襟を立てて、顔をそむけようとした。 突然、背中にすさまじい衝撃を受けた。 ――それが、水主淳平の地上での最期の瞬間だった。前のめりに倒れる直前、犯人の荒い息が俺の首すじにかかった。 「それが赤塚だった。後ろから、もうひとりが走り寄る気配がしたのは、木下だったと思う」 「……や」 「今なら、奴らが逃げ去るときの会話も表情も、はっきり思い出せる。俺はもうそのとき、事切れてたと思う。けど、悔しくて……渡良瀬も、俺を殺した奴らも、のうのうと生きていくんだろうなと思ったら情けなくて。俺も親父も、本当はもっと生きられたんだ。何とかこのことを誰かに伝えたくて……気づいたら、死んだまま地面を這ってた」 「いやあ、やめて。やめてえ!」 愛海は両耳をふさいで、悲鳴をあげた。 「ちがうよ。何かの間違いだよ。いっしょに捜査したのに……。毎日必死で、淳平の事件を解決しようって、静岡とか東北とか、走り回ったのに。木下さんが、木下さんが、そんなこと……」 「愛海」 俺の腕の中でガタガタ震える愛海を、俺は必死で抱きしめた。 「聞きたくないのは、わかる。けど、死んじまった俺の声を受け止められるのは、おまえだけなんだ。おまえだけには、本当のことを知ってほしい。奴らのせいで死ななきゃならなかった者たちが、どんな悔しい思いをしているか」 宇佐美昌三も、俺の親父も、病気で死んだおふくろも姉貴も、黒田智也も……そして俺も。 「みんな、あいつらのせいで、人生をめちゃめちゃにされたんだ!」 「わか……ったよ」 愛海は、泣きやんだ。ひくひくとしゃくりあげながらも両手で涙をぬぐって、それから毅然と顔を上げた。 「淳平たち殺された人の思いを、みんなに伝える。事件の真相を公表する」 涙でかすれた鼻声だったけど、その声は決意に満ちていた。 「どんなにつらくても、そうしなきゃならないよね。だって私、刑事だから」 NEXT | TOP | HOME Copyright (c) 2006-2011 BUTAPENN. |