| 夏のおわりに | 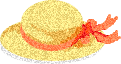 |
|
「はあい。じゃあみんな、今から川に行くからね。坂道ですべらないように、先生のあとについてくるんだよ。 ――レッツ ゴー トゥー ザ リバー!」 魚とり網とビーチボールをかかえた私のうしろから、ぞろぞろと10人くらいの小学校低学年が、アヒルの子どものようについてくる。 ときどき振り返ると、みんなのひょこひょこ動く帽子は、木の葉の影のまだら模様だった。 今日は英会話キャンプの2日目。カレーライスのお昼ごはんが終わったあと、キャンプ場からすぐの渓流で、ひんやり気持ちのいい川遊び。 「ショウくん、ドント・ラン! ちゃんとマアくんと手をつないで!」 「真奈ちゃん、すっかり先生の風格やな」 まるごとスイカをスーパーの袋に入れて、両手にひとつずつぶらさげた片瀬くんが、うしろからヤジを飛ばしてくる。短パンからニョキッと出た長い脚は、ちっとも日に焼けていなくて、悔しいくらい白い。 「去年はまだどっちが小学生か、わからんかったのにな」 「ふっ。もうすぐ二十歳の乙女をつかまえて、スカタン言わんといて」 片瀬くんは、「どこが『乙女』や。『太め』の間違いちゃうか」と、ゲタゲタ笑っている。 回し蹴りをしかけたら、スイカのひとつに命中した。 「ありゃあ。お見事」 スイカ割り用のスイカは、川辺に着く前に、もろくも砕け散った。 私は、教会付属の英会話教室に小学校6年のときからずっと通っていた。 だから、大阪近郊の能勢川で開かれる恒例の夏のキャンプも、もう9回目。 能勢電にゴトゴト揺られて、緑がいっぱいの山の景色と、じいじいとうるさいセミの声に歓迎されて、3日間を過ごすのが私の夏の始まりやった。 英会話教室は、2年交替でアメリカからやってくる宣教師が教えてくれて、教会の青年会の人たちがそれを手伝っている。 片瀬くんはミッションスクール出身なので、中1の頃から教会に来ているらしい。英語がぺらぺらで、大学生のときは英会話教室でも先生の助手をしていた。 今はもう大学を卒業してサラリーマンになったので、こうやって夏のキャンプのときだけ、参加しに来ている。 彼が就職した年、大学の英文科に入学した私が、代わりに助手見習いになった。 アイ ハブ ザ ジョイ ジョイ ジョイ ジョイ ダウン イン マイ ハート…。 ダウン イン マイ ハート トゥ ステイ…… 夜のキャンプファイアー。 片瀬くんのギター伴奏、ベッキー先生のリードで、小学生から中学生までの50人の生徒が大合唱する。 そのあと、ゲーム係の片瀬くんは、みんなをてきぱきグループに分けて、「フルーツバスケット」とかいろんなゲームをした。 お祭り男の彼がいないと、キャンプは始まらない。9年間、私は毎年そんな片瀬くんを見てきた。 「え? もう今晩帰っちゃうの?」 「明日から会社。新卒2年目のペーペーがこの時期に有給とるの、すごく勇気がいるんやで」 広場の中央でパチパチはぜている炎を見つめながら、彼は長いため息をついた。 「2日休みを取るのに、サービス残業一週間もして」 「めっちゃ苦労しとるんねんなあ」 「こらこら、川路真奈さん。きみは東京生まれなんだから、そんなまがいモンの関西弁はやめなさい。『してんねんなあ』でしょ」 「英会話キャンプに来て、関西弁教えてもらうとは思わんかったわ」 「生粋の関西人としては、気になるんや」 そういえば。春菜さんも片瀬くんに関西弁を直されるって言ってたなあ。彼女も高校を卒業してから関西に就職してきた人やし。 「……そうだ。片瀬くん、ひとつ頼みたいことがあるんやけど。帰る前に時間とれる?」 「ええけど。能勢電の最終は10時やから、それに間に合うんやったら」 消灯後、大食堂でのスタッフの打ち合わせが終わったあと、外のベンチに腰かけた私に、片瀬くんは自動販売機のジュースをご馳走してくれた。 「頼みごとってなんや?」 「ぷはーっ。ああ、うまい!」 「ビール飲む親父か、おまえは」 「あのね。毎年うちの大学は、ホテル借りてサマーパーティってのをやるの」 「ひええ。ホテル借りてパーチー? さすがお嬢様大学やなあ」 「去年初めて出たんやけど、なんかね、みんな彼氏を連れてくることになってるらしくって。エスコートって言うの?」 「ほほお」 「去年は友だちも彼のいない子が多くって、別に平気やったけど、今年は……」 「友だちにはみんな、彼氏ができとった」 「……ぐさっ」 「エスコートしてくれる彼がいないのは、真奈ちゃんただひとりになってしもうた」 「ぐさぐさっ」 私は胸をおさえて、前のめりになった。 「よくも人の心の傷をえぐるようなことを」 「真実は真実やろ? で、僕に何をせえと?」 「その日だけちょっと……、エスコートを頼めないかな?」 片瀬くんは意地悪げに、いひひと笑った。 「さて、正解はどれでしょう。その1。真奈ちゃんは、実はひそかに僕を好きだった。その2。僕に片想いだった。その3。僕に惚れていた」 「ぜーんぶ、ハズレ! 歯磨きと間違えてムヒで歯をみがくようなアホを、だれが好きになるか!」 「な、なぜその秘密をっ」 「日下部クンが、今朝食堂で教えてくれたもん」 「ひ、ひどい。もうお嫁に行けない……」 「行くなっ」 私が投げた空き缶は、盛大な音を立てて、狙ったゴミ箱からはるか遠くの、夜の闇にころがっていった。私はぶつぶつ言いながら、それを拾いに行くと、 「どうせニセモノの彼氏なんやから、送り狼になりそうもない一番無害な男を選んだだけ」 「あ、そう。信じてくれてるんや」 「ヘンなことしたら、春菜さんに言いつけてやるから」 「あーわかったわかった。あ、もうこんな時間や。電車に遅れてまう。それっていつ?」 「8月の最後の土曜日。5時から」 「まだ1カ月も先の話やな。土曜日なら、なんとか大丈夫や」 「引き受けてくれるの? やったーっ」 私は万歳しかけて、そしてにわかに口ごもった。 「あの、……春菜さんには私から、ちゃんと訳を説明しとくからね」 片瀬くんはくしゃくしゃと私の頭をなでて、立ち上がった。 「そんなこと、せんでええ。おまえみたいなガキとの仲を疑うようなヤツは、誰もおらへん」 虫の音に囲まれた山道を下ってゆく片瀬くんを、私はキャンプ場の入り口まで見送った。 彼の後姿は、月明かりに照らされて小さくなっていった。 駅に着いたらすぐ、春菜さんに電話するんやろうな。 春菜さんは、教会に来ている、とても綺麗な女の人。 片瀬くんと春菜さんは、もうすぐ婚約することになっていた。 キャンプから帰ると、もう夏まっさかり。 私は、大阪の淀屋橋のビジネス街で、夏休み中アルバイトをしていた。 父の知り合いの小さな貿易会社で、英文の書類を作成したり、輸入した商品の取り扱い説明書を翻訳したりが主な仕事で、あとコピーや銀行への使い走りなどもあった。 毎日とても楽しかった。 仕事はやりがいがあったし、みんな親切にしてくれたし、アルバイトだから、たとえ失敗してもフォローがある。 きっと本当に社会に出れば、もっともっと厳しいことが待っているにちがいない。現に5時に私が退社するときも、社員は誰も帰らない。 その日も私は定時に退社して、地下鉄の御堂筋線に乗って梅田で降りた。阪神電車に乗り換えるため、無秩序な人の流れで混雑する、デパートわきの地下広場を縫って歩いていたとき、片瀬くんが 歩いてくるのに、ばったり出会ってしまった。 「あれ。真奈ちゃん」 彼のほうでも私を見つけて、手を振ってくれた。紺色のスーツで、縞模様のえんじ色のネクタイを締めている。こんな片瀬くんを見たのは初めてで、胸がどきっとした。 「買い物か?」 「アルバイトしてんの、淀屋橋で。片瀬くんも、今帰り?」 「ああ、会社にな」 「えっ。今から会社に帰るの?」 「外回りは、5時からが本当の仕事なんや。今日もたぶん10時まで、家には帰られへん」 「……」 片瀬くんのスーツからは、ほんのり柑橘系のコロンの香りがする。雑踏のざわざわが私の中でどんどん大きくなって、それに呼応するように私の心臓は、ますますどきどきし始めた。 「ああ、今度のパーチーのことなら大丈夫やで。その日はちゃんと空けてるから」 「うん……。あ、ありがと」 彼は「じゃあ」と言うと、四つ橋線のほうに急ぎ足で向かっていき、あっという間に人ごみの中に消えてしまった。 私は深呼吸して、気持ちを落ち着かせようとした。 どうしよう。まだどきどき言ってる。 私、片瀬くんのこと、好きになってしもたんかな。 「ねえ、まなちゃん。英会話教室の中で誰といちばん、けっこんしたい?」 「ええとね。前田くん。2番目は浅川くん」 「片瀬くんは?」 「3番か、4番かもっともっと下。だってアホなことばっかり言うし、たよりなさそう」 片瀬くんは、いつもそばにいた。いつも笑わせてくれた。一人っ子の私のお兄さんみたいやった。 私が高校のとき、彼が春菜さんと付き合ってるって聞いたけど、何とも思わへんかった。 そのあいだに私も初恋をして、失恋をした。 教会で、片瀬くんと春菜さんが仲良くしゃべっているのを見て、なんだかうれしかった。私もいつか誰かと、あんな恋人どうしになりたいなって思っていた。 それやったら、なんで片瀬くんをエスコート役にって思いついたんやろ。 もしかして私、いつのまにか片瀬くんのことが好きになってたの? 今ごろそのことに、気づいたっていうの? だってだって、彼には春菜さんがいるんやで。 ふたりはとっても愛し合ってると思う。 それに、春菜さんはとってもいい人。英会話教室の女の子たちを、しょっちゅうアパートに遊びに呼んでくれた。整理ダンスの上には、ちゃんと片瀬くんとツーショットの写真が飾ってあった。 今さら好きになったって、どうしようもないやんか。 苦しいだけやんか。 でも。 今度のパーティーで、片瀬くんは私をエスコートしてくれる。 こないだみたいなスーツを着てネクタイを締めて、大人の男の人の香りをさせて、私の手をとってくれる。 私はバイトのお給料で買ったピンクのドレスを着て、彼の隣に立つ。 だめだ。どうしよう。断らなきゃ。 こんな気持ちやったら、春奈さんに悪い。 もう戻れなくなる。今までみたいに、片瀬くんと冗談言えなくなる。 でも、それでも私は、片瀬くんといっしょにパーティーに出たい……。 結局私はパーティーに行けなかった。 その前日に、9度3分という高熱を出してしまったのだ。 「真奈ちゃあん。義樹くんがお見舞いに来てくれたよ」 玄関からぱたぱたと母のスリッパが音を立てる。 「えーっ。こ、困るゥ。だめっ。断って!」 「今さら何言うてんの。もう入ってもらったわよ」 「よっ」 片瀬くんは、普段着のまっ黄色のポロシャツを着て、私の部屋のドアを、ヌッとくぐった。 「具合どうや。熱は?」 私はあわてて、思いっきりタオルケットを目の下まで引っぱり上げた。 「うん……。ちょっと下がったんやけど」 「そうか? なんか顔がまだ、真っ赤やけどなあ」 そう言いながら、「はい」と大きな花束を差し出した。 「お見舞い」 「ありがと。ごめんね、せっかく予定空けてもろてたのに、自分の方からダメになって」 「風邪なんやから、しかたない。それにせっかくのパーティ出られなくて一番がっかりしてるのは、真奈ちゃんやろ」 彼は、ドアのそばに吊ってあったピンクのドレスを、顎でしゃくってみせた。 「あれ着て行くつもりやったんや」 「バチが当たったんやなあ。人の彼を自分の彼です、って、嘘をついてまでエスコートさせようとした私に」 「キリスト教の神さまは、バチを当てたりせえへんで」 「ううん。ほんとは、半分ほっとしてたんだ。もし片瀬くんとパーティーに出てたら、きっと春菜さんに次会ったとき、だましてるみたいな気持ちになったと思う。そんなのイヤやから。だから神さまが 熱を出させてくれたんやと思う」 「そんなこと、心配してたんか」 彼は困ったように優しく微笑んだ。 「春菜……さん、とは別れたんや」 「え……?」 「彼女、は、高校んときの同級生と、今度結婚することに、なったんや」 片瀬くんは、一語一語区切るように話した。 「うそ……」 「僕が就職してから、何かおかしなった。残業でめったに会われへんかったし。会ってもなんだかぎくしゃくして」 喉の奥に、すっばい味が広がる。 「自然消滅、ってやつかな。その間に彼女は、昔の彼と連絡とってたらしくって」 片瀬くんは言いさして、びっくりしたように叫んだ。 「なんで、真奈ちゃんが泣くんや?」 「ごめん……、ごめん、片瀬くん」 私は頭までタオルケットをすっぽりかぶって、えんえん泣き始めた。 片瀬くんがとても可哀相で。 春菜さんとのあいだに割り込もうと少しでも考えていた自分が、イヤで大嫌いで。 「どうして、あやまるんや?」 「どうしてもや。……もうすぐ二十歳の乙女は、多感なんや」 くすっと笑う声が聞こえて、片瀬くんの大きな手が、タオルケットを通して私の頭をぽんぽん叩くのを感じた。 「ありがとう。真奈ちゃん」 「……う」 「見舞いに来たつもりやったのに、かえって病気悪化させてしもたかな。お詫びに、今度食事おごったろか」 「え……?」 私は泣くのをやめて、真っ赤になった目を少し出して彼を見た。 「大学のパーティーがあった同じホテルのレストランに、エスコートしたる。そのピンクのドレス着てこいよ。今度の日曜がええかな。もう9月やから、 サマーパーティーにはならへんけど」 「……ほんと?」 彼は笑顔でこっくりうなずいた。 9年間いつも見てきたはずのその顔は、大人びてステキで、全然ちがう男の人に見えた。 私は、また心臓がどきどき鳴って、ぼうっと目の前がうるんできて、もう一度タオルケットの陰にかくれた。 神さま。こんな醜い心の私に、幸せをくれていいんですか? 片瀬くんは、私のことを相変わらず、妹のようにしか見ていないけれど。 でも私は、こんなにこんなに、片瀬くんのことが好きです。 夏も終わりだというのに、私の恋はまだ始まったばかりやった。 BUTAPENN恋バナ・夏スペシャルをお届けしました(笑)。 あ、もちろん、かなりフィクション入ってますけどね。 続編「セカンド・キス」をアップしました。ぜひお読みください。 タイトルのイラストはYOU ROOMさまからいただきました。 |