CLOSE TO YOU
2nd chapter
2nd chapter
CLOSE TO YOU (第1章) 〜a precious moment〜 CLOSE TO YOU (第2章) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) |
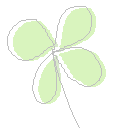 |
(3) そばにいるだけで、よかったはずなのに。私の心も身体も、もっとその先を求め始めた。 雨が朝から降り続く日。私は久しぶりに女友だちと会った。 会社帰りに居酒屋で飲んで、ほろ酔い気分で夜中近くに家に戻ると、廊下で私の部屋の前に彼がうずくまっていた。 「彩音?」 少し浅黒い彩音の肌が、暗がりで紙のように白く見えた。顔を上げ、彼はビー玉のような生気のない目で私を見た。 |
|
「どこ、行ってたんだよ……。琴音サン」 「あなた、今日は用事で出かけるからって……。いつから? どうしてここにいたの?」 「怖いよ……。ひとりで部屋にいるのが…」 「私の部屋に勝手に入って、テレビでもつけてれば良かったのに」 「琴音サンがいねえのに、あんな部屋に入れるかよ。洗濯ロープにずらっと女モノの下着を干しやがって。運動会の万国旗じゃねえんだぞ」 「つ、梅雨なんだもん。しかたないでしょ」 私は鍵を開けて、あわてて洗濯物を両腕に抱え込むと、玄関をふりむいた。 前触れもなくいきなり、彼は私の胸にとびこんできた。 私は、すこし湿気た匂いのするタオルや下着の山を落として、その上に尻餅をついた。 彼は震えている。雨にぬれた子猫のように震えている。 どうして? 彼はときどき、とんでもなく何かを怖がっている。いつもの傍若無人で口の悪い姿はすっかり影を潜めて、まるで別人のように幼い子どもになってしまう。 でも、私はその理由が聞けないでいる。 私たちは、遠くに聞こえる雨の音が自分の内側にすっかり染みこむまで、火の気のない部屋の中で抱き合っていた。 会社から帰ると、彼の部屋から声がした。透き通るような少女の声。 知り合った初めの頃は、彩音は毎日のように女の子を連れ込んでいた。 私の部屋とのあいだの壁に大きな穴を開けてからは、さすがに遠慮しているみたいだった。 「どうしちゃったの」と聞くと、「ラブホ、行ってるから」と小声で白状する。 今日の女の子は、いつもの甘ったるい声の子たちではなかった。すすり泣いている。 いたたまれず、ごみを出すために廊下に出て、そのまま部屋に戻りかねていると、彩音の部屋のドアがバタンと開いて、高校の制服姿の髪の長い少女が飛び出してきた。目を真っ赤に 泣きはらして、階段を駆け下りる。 ガチャンと音を立てて閉まろうとするドアをあわてて押さえると、玄関に彩音が立っていた。きちんと服を着ていた。 私を見ると、少し怒った目をした。なぜ見たんだ。そう言いたげな表情。 言葉が凍りつく私にひとことも言わずに、彼は中に入ってしまった。 私って、何を今さら傷ついているんだろう。 そうだよね。若い男の子に特別な女の子がいないほうが不思議。 高校生らしいカップル。長い髪の可憐な彼女は、彩音にお似合いだった。 27歳の私なんかよりずっと。 彼が20歳になれば、私は30歳。彼が30歳になれば、私は40歳。 その残酷な数字はどこまで行っても埋まることはない。 彩音は、私を一度も求めたことがなかった。キスはするけど、それは恋人のキスじゃない。 そばにいるだけでよかったはずなのに。 それなのに、私の心も身体も、もっとその先を求め始めた。 彼を想うだけで、体の奥がじんじんと痛む。 海の底にいるように、私の肺は溺れかけていた。 「昨日の女の子、誰?」 隣のベランダにたばこを吸いに出ている彩音に、仕切り越しに声をかける。冷たい口調をなんとか取りつくろいながら。 「高校の同級生?」 「……関係ねーだろ」 「そっか。関係ないよね。私には」 「……」 「ただの飯炊き女だもんね、私」 「なんだよ、それ。どういう意味?」 「どういう意味って、ことばの通り」 「へんだよ。琴音サン。琴音サンじゃないみたいだ」 「あんただって、昨日から黙ってばかり。いつもの彩音じゃない」 私は、止められなかった。 彩音の黒い瞳が見開いて私を見つめるのを痛いほど感じながら、心の中のにごった澱が私の口から、毒を吐き出し続けていた。 「あんたにとって、私は何なんだろうね。部屋の明かりをつけて、花を飾って、食事を作ってじっと待ってる。あんたは平気でほかの女の子とラブホテル行ってるのにね」 「琴音サン……」 「私だって、女なのよ!」 「ごめんね、彩音……」 真っ暗な部屋で、壁の穴の前に崩れこんだ。 彼が自分の部屋で、穴のそばの壁にじっと体をもたせかけているのは、なぜだか見なくてもわかった。 「私、彩音に恋をしている。こんなオバサンの私がおかしいよね。笑っちゃうよね。でも、もう自分が自分で止められない」 部屋の仕切りの二枚の布が、かすかに揺れる。 それを見て、私は両手に顔を埋めて、激しく泣き出した。 「お願い、私を好きになってくれなんて言わない。もう言わないから……。こっちに来て。 顔を見せて……私をひとりにしないで!」 外では、激しく雨が降り続いていた。 私のしゃくりあげるのが治まるまで、彼は長い間なにも言わなかった。 「琴音サン。……俺は」 彼の声は、板に打ち込まれる釘のように、冷たくまっすぐな響きがした。 「人を愛しちゃいけない人間なんだ」 「……どうして…」 「俺は、きっと愛した人を殺してしまう。それが俺にかけられた呪いなんだ」 「……どういう意味よ。彩音」 「俺は、琴音サンを殺したくない……」 いつもは軽々と越えていた、彼と私のあいだの10センチの壁が、その夜は、銀河よりも遠く感じられる。 暮れなずむ公園の、雨でシミができたブランコの上に私は腰かけた。 さっきまで遊んでいた子どもたちは家に帰って、食卓を家族といっしょに囲んでいるのだろう。 部屋に戻りたくない。ひとりが怖い。 このあいだ彩音がひとり廊下で震えていたときの気持ちが、いま本当の意味でわかる。 今日私は、元婚約者の智哉の家に行っていた。 婚約を一方的に破棄したことを、両親とともに詫びるためである。 あれから3ヶ月たった今も、私のしたことはまわりの人たちの心を大きく傷つけていることを思い知った。 智哉は、最後まで会合の席に降りてこなかった。 向こうのご両親は、私がわずか結婚式の2週間前に心変わりをしたことで、どれだけ息子の将来が傷ついたかを何度も繰り返して、私を罵った。 父は、私の頬を叩き、母はただ泣いていた。 智哉が話したのだろう、みな私が高校生と同棲していることを激しく責めた。 私は何も弁解せず、ただ頭を下げた。それしかできることはなかった。 そして、心の中で幾度も反芻していた。 あのまま心を殺して智哉と結婚すれば、幸せになれたのだろうか。 何十年かを彼と過ごせば、私の小さなこだわりなどただの笑い話になったのだろうか。 違う。 私は後悔はしていない。自分の心のままに選択したことを。 彩音と出会って、自分に正直になることを教えてもらったことも。彩音を愛したことも。 それでも、私が罪をおかしたことに変わりはない。 私はもう、父と母の家に戻ることはないだろう。 今味わっているどうしようもない孤独は、私の犯した罪への罰なのだ。 視界の端に見えていたサルスベリのピンクの花が、ふと影にかくれた。 「琴音サン。ひでえ顔」 公園の背の高い園灯に輪郭だけをふちどらせた、細いシルエットが私の頭上にあった。 彩音だった。 いたずらっ子のように無邪気な瞳に、このうえなく優しく大人びた光を同居させて。 「やっぱ、オバサンだよなあ。そんな年増スーツ着て、しょぼくれてる姿って」 「な、何なのよ。何の用?」 私は今にも泣き崩れて、彩音の胸に飛び込みそうな自分を押さえていた。 「ああ。どーでもいいや、琴音サンのファッションセンスなんて。それよか、食うもんない?」 「え?」 彼は、隣のブランコに、ため息をつきながら腰をおろした。 「俺さ、この1週間、ロクにめし食ってないんだ。また肉も魚も食えなくなっちまったし。なんでかコンビニおにぎりも不味くて、ぜんっぜん食う気がしねえんだよな。 不思議だよな、2年間食ってたのに」 そして、照れくさそうに地面を見つめて小さくつぶやく。 「俺さ。琴音サンがごはん作ってくれなきゃ、生きていけないみたい」 私は、ぽかんと彼の、女の子みたいにきれいな横顔を見つめて、そして吹きだした。 無性におかしかった。 だって、これ以上のコクハクがあるだろうか。あなたのごはんがないと生きていけません、なんて。 彼が私を女性として愛してくれなくてもいい。 私は彼がそばにいてくれれば生きていける。そう思った。 思いながら、おかしすぎて、涙があとからあとから湧いてくる。 「笑いゴトじゃねえよ!」 「ごめんごめん、でも今日買い物行く暇なかったし、何にもないよ、うちには。あるのは冷やご飯と納豆くらいかなあ」 「な、納豆。……それって」 「んん。人間の食い物じゃねえって? はい、それなら飢え死にしなさい」 「わーったよ。わかったから」 彩音は、私の乗っていたブランコの鎖を力強く引き寄せると、言った。 「その前に、こっち食わせて」 バランスをくずした私の首筋に手を添えて、唇にかぶさる。 それは、恋人のキスだった。 (4)につづく | |
|
TOP | HOME
|
| Copyright (c) 2002 BUTAPENN. . |