CLOSE TO YOU
2nd chapter
2nd chapter
CLOSE TO YOU (第1章) 〜a precious moment〜 CLOSE TO YOU (第2章) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) |
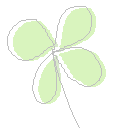 |
(6) 「俺ね。自分の名前が大好きなんだ。だって、父親と母親が愛し合ってたことがわかる、たったひとつのものだから」 俺はパリで生まれた。 父親はその頃、パリに留学してた新進の油絵画家だった。母親はイギリス国籍を持つインド人で、同じように絵の勉強に来ていた。 |
|
ふたりは画学校で出会って、1年も経たないうちに結婚した。貧乏だけど、楽しかったって母さんがよく言ってたよ。 それから、俺が生まれたんだ。 クリスチャンだった母親は、俺にZionていう名前をつけた。「Zion」は今のイスラエルやパレスチナのあたりを指すことばで、聖書で天国を意味しているらしい。 父親は一晩必死に考えて、それに彩音という漢字をあてた。音楽を聞くのが大好きだったからだと言ってた。 俺ね。自分の名前が大好きなんだ。だって、父親と母親が愛し合ってたことがわかる、たったひとつのものだからさ。 幸せな生活って長く続かなかった。 絵が売れるようになってから、父親は精神を病み始めた。 画壇での人間関係や、画商たちとの駆け引き。もともと神経質な男だったから、そういうものに耐えられなかったんだと思う。 暮らしが立ち行かなくなって、医者にも勧められて、俺たち一家は、日本の父親の故郷に帰ることになった。 俺はそのとき3歳だった。 父親の実家は栃木県の山奥でさ。すっげえ田舎なの。 久世のうちは、そこの旧家だった。 戦前はそこらへんに広い土地を持ってて、小作人をいっぱい使ってたらしい。 家は古くて、黒光りのする床柱のやたらでかい、広いお屋敷だった。笑っちまうけど、最初俺は引っ越した頃、自分ちで何度も迷子になったんだぜ。 俺たちは、じいさんとばあさんとふたりの使用人がいるその家の、離れで暮らすことになった。 ばあさんは、小さいのに背筋をぴんと伸ばして、おっきな声で怒鳴るものすごく怖え女だった。 家族も村の人も、誰も逆らわなかった。 ばあさんは、俺の母親と俺のことが気にいらねえみたいだった。黒い肌がイヤだったんだろう。いつも冷たい眼でにらまれた。 母親にとって、つらい毎日だったと思う。 しゅうとめにいびられ、日本の食事にも、すきま風の吹く山奥の寒い冬にも、慣れるのが大変だったはずだ。 父親の病気はちっとも良くならず、かえってどんどん悪くなっていった。 アトリエにしていた部屋は、いつも雨戸がぴったり閉まっていて、真っ暗だった。そして、いつもブツブツ言いながら、真っ黒な絵を描いていた。 俺は小さい頃、あいつのアトリエに入るのが、怖くてたまらなかったよ。 皮肉なことに、病気が進行するにつれて、絵はますます評価が高まっていったんだ。 俺の覚えてる母親は、ときどき悲しい目をしていた。 離れの座敷の縁側に所在なげに坐って、空を見上げながらこっそり涙をふいていた。 俺はいつも母親にまとわりついていた。母親だけが長いこと俺の世界のすべてだった。そして、母さんにとっても俺が唯一の生きがいだったと思う。 とてもきれいな人だったよ。 こうして今琴音サンがしてくれてるみたいに、膝に頭を乗っけて昼寝をした。俺が寝るときはいつも子守唄をいい声で歌ってくれた。 ときどき、ふたりっきりで散歩した。スケッチブックを持っていって、いっしょに、いろんなものを写生した。鳥とか、木とか、川にかかる木の橋とか。 夏の昼下がりは真っ白な綿のワンピースが光ってとても似合っていた。笑うと、きれいに並んだ白い歯がのぞいた。 夕暮れ時、山の端に日が沈んで、空が透き通った淡い紫から濃紺に、子供心にも泣きたいくらい美しく染まるとき、「あれが天国の景色なのよ」と教えてくれた。 幸せだったよ。あの頃はとても。 ああ、なんだか眠くなってきた……。琴音サン、少し寝るよ。 どこまで話したっけ。 俺と母さんはいつもいっしょにいたから、俺は小さい頃日本語がしゃべれなかった。母親とはいつも英語かフランス語で話していたし、父親や祖父母ともほとんど顔を合わせなかったし、小学校にあがるまで村の人たちと しゃべったこともなかったから。 小学校に入学したときも、回りが何を言ってるか、ほとんどわからなかったな。 村の小学校は、全校で50人くらいの小さな学校だった。 同級生たちは、俺みたいな外国人をテレビ以外で見たのは初めてという奴らばかりだった。 最初はケンカばかりしていた、けどすぐ仲良くなった。 俺はもともと、外で遊ぶのが大好きな子どもだったんだ。 すぐに日本語も覚えて、毎日寺の境内や、田んぼや、ひんやりした森の中で暗くなるまで遊び回った。サッカーをしたり川遊びをしたり、大勢集めてドロケイごっこをしたり。 楽しかったぜ。俺はその中でガキ大将をやってた。 俺が同年代の子どもと遊ぶことに夢中になっていくにつれて、母親はひとりぼっちになってしまった。 外が真っ暗になった頃、泥だらけになって帰ると、ひどく怒られた。 さみしかったんだ、たったひとりの話し相手の俺がそばにいなくなって。でも俺にはその寂しさがわからなかった。 その頃、じいさんが死んだ。かわいがってもらった覚えもないから、悲しくもなかったけど、その後、遺産相続の書類のことで、弁護士が家に出入り するようになったんだ。 顔のひょろ長い男で、眼鏡をかけていた。冴えないヤツだったけど、英語がしゃべれたから、いつのまにか母親と話をするようになった。 今でも覚えてるよ。母親は、やつの声がすると、パッと顔を輝かせてそっちを振り向くんだ。 俺たちの前では悲しそうな顔をするくせに、やつには笑顔を見せる。 俺は悔しかったよ。よその男にそんな顔を見せる母親が大嫌いだった。 今なら、母さんの気持ちがわかる。 あの孤独の中で、何かにすがらなきゃ生きていけなかったんだと思う。 弁護士はあとで、身体の関係はなかったと言ったらしいけど、俺はどっちでも同じだと思った。 あれは6月で、雨と風がきつい晩だった。 俺は両親の口論で目が覚め、布団から起き上がって、声のするほうに向かった。 天井の明かりが大きくゆらゆら揺れて、その真下で、父親が馬乗りになって、母親の胸に何度も何度も包丁をさしこんでいるところだった。 部屋中、血で真っ赤だったはずだ。 だけど、不思議なことに俺はそのときの血の色を覚えていない。 俺の目にはその光景は真っ黒に見えた。 そのときだけじゃない。それからあと長い間、俺のまわりは色のない世界に変わってしまった。木を見ても、夕焼けを見ても、全部真っ黒にしか見えなかった。 ……琴音サン。泣かないで。 涙が落ちてきて、冷たいよ。俺は……もう平気だから。 それから、俺は学校に行かなくなった。 いや、少しは行ったのかな……。記憶が飛んでる。 毎日毎日、母親のいなくなった離れで、ひとりで過ごした。ばあさんとも使用人とも、誰ともしゃべらなかった。ことばを忘れてしまうくらい、誰とも話さなかったんだ。 精神病院に収容された父親のアトリエは、手付かずで放っておかれた。雨戸をぴったり締め切ったその暗がりが、俺の居場所になった。 屋根裏にあがる階段があって、そこには父親の残した小説本や画集がたくさん積んであった。俺はほこりの舞う薄明かりの中で、朝から晩までそれを貪り読んだ。 やがて、その画集の絵を鉛筆で模写することに、のめりこみ始めた。絵を描いているあいだだけは、何も考えずにすんだ。 そして、俺が中学生になった頃、見よう見まねで描いていた俺の油絵がたまたま、未発表の父親の作品を探しに来た画商の目にとまった。 色をなくした俺の絵はどれも真っ黒で、あいつの絵に寸分違わぬ出来だった。 その画商は、俺に話を持ちかけてきた。久世俊之のタッチをそっくり真似た絵を描いてくれと。精神病院で新作を描いたことにして法外な値段で売るのだと。 俺は久世の家と縁を切りたかった。 部屋や生活の世話も、都内の中学校への転入手続きもすべてしてやると言われて、俺はその話に乗ることにした。 中学3年からここに越してきて、都立の芸術コースになんとかもぐりこんで、一ヶ月に一枚のペースで絵を描いて、金をもらった。 こっちに来たことで、だんだんと俺は色を感じるようになりつつあった。あのときのことを忘れている時間のほうが多くなって、笑うこともできるようになった。 高校生活はそれなりに楽しかった。高校で、俺は光穂と出会った。 光穂の笑顔は、昔俺が小さかった頃の母親の笑い方によく似ていた。 光穂といっしょにいることで、まるで昔の自分に戻れるような気がした。 けど、ある日の放課後、3年生が空き教室の隅に光穂を連れ込んで、襲いかかろうとしているのを見ちまった。 俺の頭の中は真っ黒になった。 なぜかわからないが、そのとき上級生ではなくて、光穂が憎くて憎くてたまらなかった。 気がついたら、俺は何人もの人間に押さえ込まれて、3年の男は血だらけになっていた。 でも、本当は俺は、頭の中で光穂を血だらけにしていたんだ。 そのとき、わかった。 俺は父親と同じだ。誰かを愛しても、きっと殺してしまう。俺の脳は、あいつと同じだ。あいつの絵と同じどす黒い塊なんだって。 そのときの光穂が俺を見る目は、母さんが、狂ったあいつを見るときの目とそっくりだった。 もう、人を好きにならない。そう固く心に決めた。 それからあとに、……琴音サンと出会ったんだよな。 会った頃の琴音サンは、俺と同じだったな。相手の男を愛しちゃいけないって心を閉じようとしているのが、バレバレなんだから。 琴音サンを好きにならないように、俺、がんばったんだよ。 でもダメだった。 琴音サンのそばにいられるなら、どんなことでもしようと思った。本当に何でもできそうな気がしたんだ。 だけど、それは幻想だったよ。 俺はやっぱりあいつと同じ絵しか描けない。明るい光の中の絵を描こうとしても、俺の心には闇しかない。 ……だから、ごめん。琴音サン。 俺は、もう琴音サンといっしょにいられない。 琴音サンを、母さんみたいに不幸にしたくない。 だから、……さようなら。 (7)につづく | |
|
TOP | HOME
|
| Copyright (c) 2002 BUTAPENN. . |