CLOSE TO YOU
2nd chapter
2nd chapter
CLOSE TO YOU (第1章) 〜a precious moment〜 CLOSE TO YOU (第2章) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) |
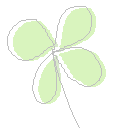 |
(1) 気がつくと、私の心には彼が住んでいた。偽りの同棲生活のはずだったのに。 「彩音。ごはんできたよーっ」 ふた呼吸ほど置くと、壁の大穴を気だるそうにくぐって、まぶしげに目を細めた彩音が入ってくる。 テレビの上の壁の大きな「禁煙」の張り紙を私が指さすと、顔をしかめて、くわえていたタバコを捨てにまた部屋に戻ってゆく。 |
|
相変わらず上半身は裸で、髪はライオンのたてがみのようにぼさぼさ。睫毛の長いきれいな目は半分隠れて見えない。 「ね。もしかして二日か三日寝てないんじゃない?」 「ん……。絵、仕上げてたから」 「ごはんも全然食べなかった? いくら呼んでも来ないんだもん」 「昨日の朝からなんも食ってない……。ハラ……減った。死ぬ」 「やだっ。くさいよ。彩音。どうせその間お風呂も入ってないんでしょ。食事の前にうちのシャワー浴びてらっしゃい」 「あんなあ。俺の人生の優先順位は、一に食欲。二に性欲。三に睡眠欲。あとの有象無象は、どーでもいいの」 「そんな情けない人生、やり直しなさい。とっとと風呂場行って」 「……琴音サンが一緒に入ってくれたら、入る」 「10年早い!」 「ちぇーっ」 うだうだと愚痴りながら、それでも彼は素直に立ち上がった。 シャワーの心地よい音が響く中、私はほうっと吐息をつきながら、小さな四角の白いテーブルに二人分の夕餉を整えた。 私、白神琴音がこの賃貸マンションに越して来て、3ヶ月。 これが、27歳のドタキャン女と、17歳の不登校高校生、久世彩音の奇妙な半同居生活。 「今晩のおかず、何?」 「太刀魚の塩焼き、小松菜のごまあえ、たこの酢の物、納豆」 「なんだよっ、それ。俺のキライなもんばっかし! 太刀魚は骨多いし、酢は咳が出るし、たこも納豆も人間の食いもんじゃねーよ」 「こっちはね。あんたのタバコで汚れたドロドロ血をサラサラにしてやろうと、懸命に献立考えてるんですからね。嫌ならもう作らない!」 彩音は、しぶしぶごはんを頬張り始める。 私と食事をしているときの彼は、笑ってしまうくらい真剣そのものだ。注意深くひとつひとつの材料を噛みしめて、味を確かめている。酢の物を食べるときは本当に咳をして涙目になっている。 「そういえば、今朝男の人が来てたでしょう。また高校の先生?」 「ううん。今日のは保護司」 「保護司? いったい何悪いことやらかしたの?」 「へへ……。聞きたい?」 「聞きたくないっ。どうせロクでもないことに決まってるもん。不純異性交遊とか、わいせつ物陳列罪とか」 そう答えながら実は、彩音のことを知りたくてたまらない。 こうして毎日いっしょに過ごしているのに、私は彼のことを何も知らないのだ。 彩音は都立高校2年のときに不登校になり、この春進級できないまま休学している。 田舎にいる家族とは、中学のときからずっと離れて暮らしている。 両親のどちらかが外国人らしい。 油絵の天性の才能があるらしく、ときどき何かに憑りつかれたように眼をぎらぎらさせてキャンバスに向かっている。 絵筆を握っているときは何日も寝ないし、話しかけても返事もしない。 知っているのはそれだけ。 プライベートのことは何も話さない。何も聞かない。 それが私たちが暗黙のうちに決めた、ふたりのルール。 それでいいと思っていた。ついこないだまでの私は。 想いにふけりながら台所で白桃をむいていると、とぎれとぎれの彼の声がした。 「琴音サン……。ねむい……」 「あーっ。だめだよ、寝ちゃだめ。ちゃんと自分の部屋に帰って寝て!」 でもその言葉が終わらないうちに、彩音は手足をちぢこめて、もう寝息を立てている。 丸まった綿毛みたいに、幸せそう。 私はため息をつきながらも、そんな彼から視線が離せない。 彩音にどんどん魅かれてゆく自分を、正直もてあましていた。 もう二度と人を愛さないと、3ヶ月前にあれほど固く思ったのに、私は彼を愛し始めている。 桜の花びらの舞うころ、私は結婚2週間前というときに、婚約者のもとから逃げ出してここに来た。 彼、智哉には私のほかに、長い間付き合っていた恋人がいたのだ。 私と彼との結納が済み、すべてが順調に進んでいたある日、その女性は自分のマンションで自殺未遂を起こした。 なにかにせかされるように彼女、有紀さんのもとを訪れた。 彼女にきちんと説明しようと思った。 過去にどんないきさつがあったかわからないが、彼は私を選んだのだ。 あなたの抱いている愛情は間違っている。あなたは別の人を捜すべきなのだ。 そう、面と向かって彼女に知ってもらおうと思っていた。 だが彼女の頬にの大粒の涙が伝うのを見たとき、私はそれが思い違いだと知った。 彼女の愛は間違ってなどいなかった。私と同じ燃えるような想いで智哉を愛したのだ。同じように幸福な未来を夢見ていたのだ。私と有紀さんに何も違いはなかった。 泣き崩れている彼女の姿は、私自身の姿に重なって心に焼きついた。 「ちゃんと、金で解決したから」 私が有紀さんと会ったことを知ったとき、憮然として彼はそう私に弁解した。 そのときの彼の瞳の奥にあった冷え冷えとした塊を、私は一生忘れない。 私は、智哉との別れを決意していた。 彼にひとことも言わず、会社を辞め、マンションを引き払った。たった一通の手紙をのこしたきり。 そんな別れ方でもなければ、智哉への想いを断ち切ることなど、私にはできなかったのだ。 彼をまだ愛していた。そして同時に彼を赦せなかった。ふたりの女性を同時に愛せる男の残酷さが。身勝手さが。 未来に進むこともできずに、ただひとりで膝を抱えて、毎日をぼんやり過ごしていた私の前に現われたのが、彩音だった。 彼のまっすぐな瞳。おとなびた、すべてを見透かすような表情。 彩音が私をかばって、私と「同棲している」と智哉に宣言してくれたおかげで、彼は二度と私の前に現われなかった。 私は過去を捨てて、新しい人生を歩み出すことができた。 そして彩音は、自分のついた嘘を真実にするためと言って、私との部屋の壁に大穴を開けた。 彼との毎日の夕食が、いつのまにか私の生きがいになっていた。 でも、それは迷子の子猫との、ほんのひとときのじゃれあいだったはずなのに。 子猫は飽きたら、またよそに行ってしまう。そう割り切って始めた「恋人ごっこ」だったはずなのに。 気がつくと、私の心には彼が住んでいた。偽りの同棲なんかじゃなく、ちゃんとした住人として。 私の部屋で寝てしまった彩音にタオルケットをかけてあげると、私は彼の漆黒の髪に手をそっと触れた。 「彩音、好きだよ」 彼が聞いていないのがわかるときだけ、安心して呟ける。 (2)につづく | |
|
TOP | HOME
|
| Copyright (c) 2002 BUTAPENN. . |