CLOSE TO YOU
2nd chapter
2nd chapter
CLOSE TO YOU (第1章) 〜a precious moment〜 CLOSE TO YOU (第2章) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) |
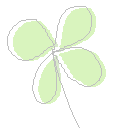 |
(2) 彼の前では、私の気持ちなんか全部見透かされているような気がしてしまう。 彩音の絵は黒が多かった。 私はときどき彼の部屋に入って、家具も何もないがらんとした床に坐って、彼といっしょに描きかけの絵を眺めた。 「彩音の絵を見てると、ときどき音楽が聞こえる」 「音楽?」 |
|
「うん。静かな音楽。バーバーの弦楽アダージョみたいな。少し淋しくて、悲しくて涙が出てくる」 「……俺には聞こえないよ」 「この絵、とても好きだよ」 「俺はキライだ」 「キライなの?」 びっくりして私はたずねた。 「絵はキライ……、死ぬほどキライ」 休みの日の早朝、ベランダで鼻歌交じりで大きなベッドシーツを干していた私は、間違って洗濯バサミを爪ではじいて、下に落としてしまった。 あわてて手すりから下をのぞきこむと、ちょうど真下の玄関ホールから出てきたばかりの男性がふたり、立ち止まっている。 ひとりは、大きな平べったい四角い荷物を抱えながら、何かを捜すように、きょろきょろしている。 ひとりは頭を押さえながら、もう片方の手にはピンクの洗濯バサミを持っている。 私の落とした洗濯バサミが当たったのだ。小さな軽いプラスティック製とは言え、この高さから落下したのではかなりのダメージだろう。 「す、すみませーん!」 私は蒼白になった顔を突き出して、大声であやまった。 男はじろりと私をにらむと、そのまま兇器の洗濯バサミを忌々しげに、そばの植木の茂みの中にほうりこんだ。 そして、もうひとりの男を促して、歩き始めた。 (いやな目つき) 自分が悪かったことも棚に上げ、私は彼らの風貌がなぜか好きになれなかった。 そして、あっと気づいた。洗濯バサミが当たらなかったほうの男が手に持っている、布にくるまれた四角いもの。 あれは、彩音が何日か前に描いていた油絵のキャンバスじゃないかしら? かなりの大作。確か50号サイズだと彩音は言っていた。 あやしい男たちは、玄関脇に止めてあったワゴン車のハッチバックを開け、荷物をそっと差し入れると、そのまま乗り込んで行ってしまった。 私はあわてて、ベランダから部屋に入ると、彩音の部屋とのあいだの壁の穴から、叫んだ。 「彩音!」 眠たそうな声で返事があったので、「入るよ」と、穴をまたいだ。 やはりなくなっている。真っ黒なカーテンを閉め切ったガランとしたワンルームの部屋の中央に、きのうまで絵を架けていたところには、からっぽの画架があるだけ。 フローリングの床に散らばった油絵の具や絵筆から漂う新しい匂いが、ついさっきまで彼が絵を描いていたことを知らせている。 そして、部屋の隅で彩音は、寝袋を宝物みたいに抱いて、精根尽き果てたように伸びている。 「彩音、あの50号の絵、今人相の悪い男の人たちが運んで行ったよ」 「……会ったの?」 「ベランダから、洗濯バサミを落としたら、ひとりに当たった。ものすごくにらまれて、怖かったんだから」 「はは……。文字通り、天罰だな」 「あの絵、売っちゃったの?」 「……ウン」 半分眠りの世界からの返事。 そう言えば、私は完成した彩音の絵を一度も見たことがない。 いつも、いつの間にか部屋の中から消えている。 そしてまた、いつの間にか新しい真っ白なキャンバスが運び込まれている。 あの人たちは、画商なのだろうか。でも、それにしては何だかイヤな印象の人たちだった。 私の心配をよそに、彩音はそのとき、マフィアとドンパチ銃撃戦を演じている(銃弾は洗濯バサミ)私の夢を見ていた、とあとで笑いながら報告してくれた。 「彩音。デートしよっ」 ある晩、私はお皿が片付いたばかりのテーブルの上に身を乗り出すようにして宣言した。 「こ、琴音サン、生理前の欲求不満かなんか? いきなり怖えよ」 「……あのねえ」 私は2枚のチケットを差し出した。 「横浜にオープンしたばかりの美術館の特別展の招待券。あんただって絵なら興味あるでしょ」 「はあ」 「不健全な昼夜逆転の生活は、日光を浴びることで改善されるのよ。毎日毎日、暗室で栽培されてるモヤシじゃないんだから、ちっとはお日さまと仲良くしなさい!」 「はあ」 「何よ、その気の抜けた返事は。行くの? 行かないの?」 「初でーとだね。琴音サンと」 「な……」 「気合入れて、スーツ着ていくかな。ついでにホテルも予約しとく? あ、琴音サン真っ赤になった」 「馬鹿っ」 にやにや笑って私を見ている彩音には、ときどき私の気持ちなんか全部見透かされているような気がしてしまう。 「なーにが、スーツにネクタイよ。Tシャツしか持ってないくせに」 「俺は、もともとハダカで勝負する男なんだよっ」 などと言い合いながら、私たちは梅雨の晴れ間の土曜日の横浜を歩いていた。 彩音が目を覚ましたのはお昼近くだったため、横浜に着いたのはもう2時過ぎ。 とりあえず、彩音に日光浴させることが目的だったので、私たちは美術館に向かう前に山下公園を散策することにした。 「いい気持ちだねえ。海を渡ってくる風って」 少し高い気温を和らげるように、停泊している大きな汽船の向こうから初夏の風が吹いてくる。 「今住んでるところは海が見えないのが悲しい。この近くに住んでたときは、いつも海を感じていたから」 「そして、昔の恋人とふたりで、窓から海を見ていたんだろ?」 鉄柵にもたれかかった彩音の黒い髪が風でもつれあうように、彼の目を隠している。 「え……?」 「わざわざ横浜を選ぶなよな。どうせ、ここもあいつとの思い出のデート場なんだろ?」 「……うん」 「はあ、俺ってまぬけ。昔の恋人の代役で連れてこられたんだもんなあ」 「違うよ!」 私の叫び声に、近くをよちよち歩いていたハトが、びっくりして飛び立った。 「違うよ。そんなんじゃない。……ただ試してみたかっただけ」 「ためす?」 「自分の気持ちを……」 智哉に対する気持ちと、彩音に対する気持ちのどちらが強いのか。自分でも本当にわからなくなっていたから。 「で、どーだったの?」 「うん。だいじょうぶだった」 彩音の後姿に智哉の後姿を重ねてはいなかった。 私は、彩音の浮気な視線だけを一生懸命、追いかけていた。 「ふーん。良かったね。おめでとう」 全然意味がわからないはずなのに、彩音は、涼やかな笑顔で祝福してくれる。 ああ、彩音らしいなあって、私はしみじみとうれしくなって微笑み返した。 美術館は、本当にひさしぶりだった。 もともと私は絵に関心のあるほうではない。 彩音の隣に暮らすようになって、やっと少しずつ新聞の記事や電車の吊り広告を注意して見るようになったけど、 誰からも誘われずに自分から行こうと思ったのは初めてかもしれない。 カーペットの上を、大勢のギャラリーが音を立てずにゆっくりと歩き、気に入った絵の前で立ちすくみ、ときにひっそりとため息をもらしたり、 横にいる知人とことばを交し合う。 とても落ち着いた時間だった。 彩音は真剣な顔をして、長い時間をかけてひとつの絵を見ていたかと思うと、ろくに見もしないで、部屋の中央のベンチに腰かけてあくびしていたりする。 食べ物と同様、絵でも好き嫌いの激しさが度を越している。 「琴音サン。腹へったよお。メシ食いに行こ。中華料理」 「まだ5時じゃない。もうちょっと。次の部屋で最後だから」 特別展の最後の展示室に入った。 暗い照明の中、ひとつひとつの絵が名優のようにスポットライトの中に浮かび上がっている。 奥に、有名な作品ででもあるのか、数人が人だかりしている絵があった。 「あ、あの絵」 私は驚いて、思わず彩音の袖をつかんだ。「あれ、彩音の描く絵に感じが似てる」 それは、黒い色の抽象画だった。同じ黒でもこうも違うのかと思わせるほど、あらゆる色調の黒が執拗に塗り重ねられ、奥行きと深みを出している。 抽象であるはずなのに、そこに浮かび上がってくる形は、思わず肌が粟立つほど美しく、怖ろしかった。 彩音が細い両腕をからだの脇にだらりと垂らすのが、わかった。 ぼうぜんとした声でつぶやく。 「……ちくしょう、油断した」 「え?」 「あいつの絵が、こんなところにあるなんて」 言い捨てると、彩音は私の手をふりほどいて走り出した。 展示室を出て、螺旋階段を駆け下り、ようやく美術館の入り口で立ち止まった。 「ごめん、琴音サン……、今日はこのままひとりで帰る」 「彩音、どうしたの?」 「今日は俺、何をしちまうか、わからない」 振り向いた彩音の顔は、別人のように見えた。青ざめた唇が、かすかに震えていた。 (3)につづく | |
|
TOP | HOME
|
| Copyright (c) 2002 BUTAPENN. . |