CLOSE TO YOU
2nd chapter
2nd chapter
CLOSE TO YOU (第1章) 〜a precious moment〜 CLOSE TO YOU (第2章) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) |
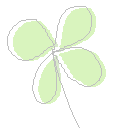 |
(4) 彼の中には、まだ私に見せたことのない大きなブラックボックスが隠れているのだ。 「定期持った? ちょっとほんとに髪の毛といたの、それで」 「俺は小学生かよ」 「小学生以下じゃん。こんだけ世話を焼かないと、まともに高校にも行けないなんて。ああ、遅刻しちゃう。遅刻3回で欠席1日分。わかってんの。 また留年しないためには、もう絶対1日だって休めないんだからね」 |
|
都立高校のブレザーを着こむと、妙に幼く見える彩音は、歯をむき出して私を威嚇してから、やってきたエレベーターに乗り込んだ。 「じゃな。琴音サン」 振り返ると、産休に入ったとなりの岩崎さんの奥さんが、こっそりドアの影から私たちを見ていたらしい。 「おほほほ」と愛想笑いをし合って、その場をごまかす。 そりゃ、学校の先生としては、気になるだろうな。 隣の高校生の身の回りの世話を焼いている27歳のオンナ。 薄い壁は、岩崎さんとの間も同じなわけで。 私と彩音が毎晩ごはんを食べながら談笑しているのも、ベランダでときどきキスしてるのも、全部バレてるんだろうな。 それにしても不思議だと、首をひねってるかもしれない。お互いのドアが開くようすもないのに、私たちがいつのまにか行き来してることに。 彩音が半年前に壁の真ん中に大穴を開けて、そこから出入りしているなんてことは、常識のある人なら決して想像もしないはずだから。 長いあいだの説得に根負けして、彩音が長い不登校にピリオドを打ち、高校に通い始めたのは6月末。 夏休みのあいだ、彼の遅れた勉強を見てやっていて、ほんとうに驚いた。 彼は分数が全然わかっていない。2けたの掛け算、割り算さえおぼつかない。 そのくせ、動植物や天文学には専門の大学生なみの知識がある。 簡単な英単語も綴れないのに、洋画は原語で理解している。 聞いたことのないような古いことばや、難しい漢字でも知っている。 そのアンバランスさは、彼の危うい生き方そのものでもあった。 「どうすんのよ。こんなんじゃ、出席日数足りても落第だよう」 「あ、大丈夫。俺、芸術コースだから。授業中居眠りしてようと、テストで0点取ろうと、みんな大目に見てくれる」 確かに彼は、毎日寝るために学校へ行ってるようなものだったらしい。 秋になってからは、それこそ昼夜を分かたず、絵を描いていた。 夢遊病者のようになっている彼のほっぺたを叩いて身支度をさせ、学校に送り出すのは、私の朝の日課になった。 絵のことになると、彩音は人が違ってしまう。鬼気迫るという言葉が月並みにさえ思える。 もし絵筆を無理やり奪い取られたりしたら、彼は自分の命を質に入れてでもそれを取り返すだろう。 それほど身を削るようにして、彼は描くことにのめりこんでいた。 彩音の絵は、黒を基調にした抽象画だった。美しい反面、どこか人間の立ち入ってはいけない世界であるような怖さがある。 心のままにただ描きなぐっているように見えるときがあるかと思えば、5ミリ単位の緻密な線をびっしりと書き込んでいるときがある。 床に散らばった風景や静物のスケッチは、絵のことがさっぱりわからない私でも目を見張るほど、正確な構図で描かれてある。 誰に習ったのと聞いても、誰にも、とかたくなに首を振る。 あの横浜の美術館に展示されていた絵が誰のものか聞きたいと思ったが、あのときの彼の動揺ぶりを思い出すと、とても聞けない。 彼の中には、まだ私に見せたことのない大きなブラックボックスが隠れているのだと思った。 この秋はじめて手袋をひっぱりだすほど寒かった日曜の午後のこと。 私は買い物から帰って来て、彩音の部屋の前に、ひとりの少女がたたずんでいるのを見つけた。 クリーム色の半コートをはおった私服姿だが、間違いない。以前彼の部屋から飛び出した、制服のあの子だ。 「あの、久世くんは今日は用事があるって、朝から出かけましたよ」 おそるおそる声をかけたら、黒目がちのきれいな瞳を見開いて、私に振り向いた。 「今日は、遅くなるって……。もし良かったら、うちでお茶飲まない?」 なかば強引に彼女を部屋に入れた私には、嫉妬という穏やかならぬ感情よりもむしろ、 彩音のことを知りたいという願いのほうが強かったのかもしれない。 「彼のご家族とほんの少しだけつながりがあってね。彼のことを頼まれてるの」 アールグレイのカップをさしだしながら、彼女のもの問いたげな視線に負けて、ウソをついた。 「私は、島中光穂。彼と同じ都立高の芸術コースの3年です」 彩音は留年して、今2年生だ。去年まで同じ学年だったというわけか。 「彼、学校ではどんなふうなの?」 「前よりずっと人を寄せ付けなくなりました。クラスメートを避けているみたい。そしてみんなも……」 「孤立してるんだ」 「でも、以前はそんなんじゃなかったんです。入学のときから、本当に目立つ生徒でした。堂々と遅刻するし、先生の指示にはわざと逆らうし。でも男子にも女子にも人気がありました。みんな、あこがれの存在として彼を見ていたんです。英雄視してる男子生徒すらいました。 先生方も彼のことは不思議に黙認しているみたいでした。彼の絵の才能があまりに素晴らしいから、何も言うことができなかったのかもしれません。それに彼のお父さんのこともあるし……」 「お父さんのことって?」 「ご存知ですよね。あ、あの」 彼女は少し困ったように眉をひそめて、あわてて話題を変えた。 「私は2年の初めまで、彼と話したこともありませんでした。でも……」 光穂さんの頬がそのとき、ほんの少しだけ上気して見えた。 「彼が庭でデッサンを描いているところを見てしまって。餌をついばんでいるスズメの絵でした。そのときの久世くんの眼が本当に優しくて。私、思わず声をかけました」 私はやり場のない気持ちで、彼女の話を聞いていた。 彩音と光穂さんは、それをきっかけに付き合い始めた。 デートはもっぱら美術館めぐり。高校生らしいおずおずとした付き合いだったという。 だがある日、光穂さんを好きだという上級生が現われ、無理やり彼女の唇を奪おうとした。 「そのとき、久世くんがそれを見てしまって……。彼はその人に殴りかかりました。止めようとしたけど、あまりにひどい剣幕で手のつけようがありませんでした。もし、偶然先生方が通りかかって3人がかりで止めなかったら、 久世くんはその上級生を殺していたでしょう」 彼女はすすり泣いていた。 その上級生は手の骨や肋骨が折れるほどの大怪我をして、彩音は家庭裁判所に送られて保護観察という処分を受けた。 彼はそれから学校に行かなくなった。 光穂さんとも二度と会おうとしなかった。 彼女は、自分が原因で彼を辛い目にあわせてしまったことを、ずっと思い悩んで彼のもとを訪れていたという。 「光穂さん。聞いていい? 今でも彩音のことが好きなの?」 彼女は怯えたような眼をして、しばし口をつぐむと首を振った。 「私は久世くんが怖い……。あのときの彼は正常ではありませんでした」 その夜おそく帰ってきた彩音は、廊下で私の顔を見てもしばらく誰だかわからないという表情だった。 「彩音!」 呼びかけにも答えず固くドアを閉めてしまった彼に異変を感じた私は、穴を通り抜けて彼の部屋に入った。 彼は何もない部屋の真ん中に、膝をかかえてうずくまっていた。 「彩音……」 「さわるな……」 「え……?」 「さわるな、琴音サン。俺にさわるな」 彼は膝のすきまから、宇宙の深淵のような暗い目で私を見た。 「俺は琴音サンを殺してしまう。……いつかきっと」 「彩音、どうしちゃったの?」 「俺はヤツと同じなんだ」 「彩音! 答えて。今日どこに行ってたの? 誰に会ったの?」 「俺はきっと、あいつと同じになってしまう……」 彼は私がそばにいることすら許さなかった。 まんじりともしないまま夜が更けて、いつのまにか私は自分の部屋のソファの上で泣き疲れて眠ってしまい、はっと気がついてはねおきたときは、もうベランダの東側のサッシのレースのカーテンが薔薇色に染まっていた。 いやな予感がして、私はあわてて壁の穴をくぐった。 彩音の部屋だけは、まだ暗い夜の底のよう。 その闇にしばりつけられた囚人であるかのように、彩音は床に突っ伏していた。 「彩音……」 答えはない。 そっと近寄って、もう一度彼の名前を呼んだ。 暗さに慣れ、焦点を結び始めた私の目に、瞼をきつく閉じた彩音の顔が、そして、そのすぐそばに置かれた彼の左手が映る。 薬の空瓶を握りしめたままの。 「きゃあああっっっ!」 叫んだつもりだったが、私の喉からはかすれた息しか出てはこない。 「彩音! うそだよ、なに冗談やってんの。彩音、彩音!」 彼の身体をつかみ、上半身を抱き起こす自分の動きが、まるでスローモーションのようだ。 私は彼の口をこじ開け、人差し指を思いっきり喉に突っ込んだ。 「げほっ、げほっっ!」 彩音が苦しそうに身をよじって、咳き込んだ。 「吐いて!飲んだものを全部吐いてっっ!」 「琴音サン……?」 彼は不思議そうに、薄く目を開いた。 「彩音、死んじゃいや!」 「誰が、死ぬの?」 「だって、薬……飲んだんでしょう?」 わけがわからないという顔をして見上げている彩音に、私は水を浴びせられたような心地だった。 「飲んだよ。バッファリン一錠。それしかねえんだもん、俺んちに頭痛の薬って」 「だって、からっぽに……」 「だから、最後の一錠だったの」 「……」 彩音はやっと納得したような、呆れたような声を出した。 「もしかして、琴音サン、俺が自殺したって思ったの?」 私は、脱力して尻餅をつき、その拍子に私の膝が彼の後頭部に当たった。 「いてっ。マジ痛えっ! 俺に死んで欲しいのか、死んだらヤなのか、はっきりしろ!」 「……ばかぁっ! 死んだらイヤなのに……決まってる……じゃん」 私は、大きく口を開けて、わんわん泣き始めた。 こんなに泣いたのは小学生のとき以来じゃなかっただろうか、というくらい。 本当に怖かった。 彩音がいなくなることが、こんなに怖いなんて。 彩音は、胡坐をかいて、きれいな項を垂れて、私が泣き止むのを長い間待っていた。 「俺さ。自殺なんかしねえよ」 彼は、しごく真剣な調子でつぶやいた。「まだ死にたくねえもん」 「……ほんと?」 「だって、まだまだセックスし足りないし、琴音サンの料理も食べたいし……。あ、それに、琴音サンのハダカもまだ 見せてもらってないよ」 「……」 ……この男は何を考えてるんだか…。 心配して損した。 ふつふつと怒りが湧き上がる。 「ばかああっっ」 私は彩音の背中に腕を回し、彼を抱きしめた。 「好きだよ! 彩音。世界で一番、好き! もうやだからね。死んじゃいやだからね!」 「琴音……サン」 「私だって死なないよ。もし、彩音が私を殺したくなっても、平気。反対にやっつけちゃう。私って合気道12段で剣道20段なんだからね」 「そんな段、あるわけねーじゃん」 楽しそうな笑顔のまま、彼は私の髪を両手でぎゅっとつかんで、めちゃくちゃに、私の唇や首筋をむさぼった。 「琴音サン、どうしよう。俺も、琴音サンが好きだよ。もう止まらないよ」 「彩音……」 「もう俺のアソコも、待てねえ……よ。今から……ヤッてもいい?」 彼が私を押し倒そうとしたとき。 「あーーっっっ」 私は、突然気づいて、はねおきた。 「今日、月曜じゃないの! ゴミの日! わっ。それにこんな時間。早くしないと、会社遅刻だわ。彩音、あんたも学校よ!」 「そんな……」 彩音は放り出されて、情けない顔で床にうずくまっていた。 「ここまで来て、おあずけかよーっ。欲求不満で死んじまうよ!」 「だって、私の裸をみるまでは死ねないんでしょ」 私はすまして立ち上がり、彩音の額にピストルみたいに人差し指を突きたてた。 「そんじゃ永久に見せてあげない。そしたら、彩音はずっとずっと死なないんだからね」 (5)につづく | |
|
TOP | HOME
|
| Copyright (c) 2002 BUTAPENN. . |