CLOSE TO YOU
2nd chapter
2nd chapter
CLOSE TO YOU (第1章) 〜a precious moment〜 CLOSE TO YOU (第2章) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) |
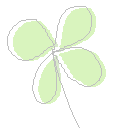 |
(5) 「俺のこと、知っちゃったんだね。琴音サンだけには知られたくなかったよ」 駅に着くと、車両の中からどっと、澱んだ生暖かい空気とともに、たくさんの人間が吐き出される。 階段に向かって、人々はそのまますごいスピードで流れていく。少しでも遅れる者は、川の中の岩のように、ぴしぴしと波しぶきを当てられる。 私はその岩になって、階段の手すりをつかみながら、はた迷惑なゆっくりさで下っていた。 会社から自宅へ、あと乗り換えひとつ。 |
|
本当は飛んで帰って、私の部屋で待っていてくれる彩音に一秒でも早く会いたいのに、からだが言うことをきかない。 とまどっていたのかもしれない。 私をまっすぐに求めてくる、彩音のとどまるところを知らない激情に。 あの日の夜、私と彩音ははじめて結ばれた。 それ以来、彩音が私を見つめる瞳は、怖いくらい。私のからだの隅々まで射抜くようだ。 長い間、家族とも離れて暮らして、人を愛さないように自分の気持ちを抑えていた若い彼が、その反動で、寄り添う私に狂おしい思いすら抱くのは当然だろう。 でも私には、彼の思いのすべてを受け止めるだけの若さがない。 推進力の足りないロケットみたい。 彩音はまだ17歳なのだ。結婚すらできない年齢なのだと、常識という鎖がたえず私を引き戻す。 息ができないほど彩音に恋しながら、ため息だけがやたらと多くなる。 「ああ、オバサンだって、また彩音に笑われちゃうな」 駅の通路を歩きながら、壁面広告のガラスに映った自分の少しよれたスカートを見て、笑ってしまった。 ようやく、自宅の最寄の駅で降りて、近くのスーパーに入り、買い物かごを手に取る。 彼の顔を思い浮かべながら、「今日は何食べたいかな」とひとりごとを言って、肉や野菜をかごに放り込んだ。 幸せを数えていくと何故か、それと釣りあうだけ不安がこみあげる。 マンションのエレベーターを自分の階で降りたとき、ホールで2人組の男たちにもう少しでぶつかりそうになった。 顔を見て「あ」と声を出しそうになった。 半年前に一度会った覚えがある。私がベランダから洗濯バサミを落として、頭にぶつけてしまい、ものすごく睨みつけた画商の2人。 彩音の部屋から出てきたらしい二人は、会釈をした私を一顧だにせず、閉じかけたエレベーターの扉をこじあけて乗ってしまった。 「彩音」 中から出てくる気配もないので、私は鍵をかけるために彼の玄関に入った。 部屋の中に入って仰天した。 彩音は、唇から血を流した無残な姿で、ようやく起き上がろうとしていたところだったからだ。 「彩音! どうしたの? 殴られたの? さっきのヤツらに」 「あいつら、まだ外にいる?」 かすれた、悔しげな声を上げる。 「ううん、帰ったみたい。いったいなんで殴られたの?」 私は、ハンドバッグからありったけのポケットティッシュを出して、彼の顔の血を拭き取ろうとした。 「いてえ……」 「ひどいよ、彩音。警察行こう。相手の名前とか知ってるんだよね。こんなことする奴らは捕まえてもらわなきゃ」 「……ダメなんだ」 彩音は私からティッシュを取り上げると、その紙のかたまりに、何度も口の中の血だらけの唾を吐きだした。 「行けば、俺も捕まる」 「……いったい、何があったの?」 私は彼の昏い表情に身震いをしながら、たずねた。 「俺、もう描けないって、言ったんだ」 「絵を……?」 「奴らの要求してくるような絵は、もう描かないって。そしたら、いきなり殴ってきやがった」 「描かないって、本気なの?」 「俺はもう、自分の描きたいものしか描かないって決めた。金のために、あいつらに言いなりの絵を描くのはイヤだ。 ……そう決めたんだ。琴音サンを好きになったときから」 「彩音」 私はそこで話を中断して、彼の傷を冷やすための氷を取りに立ち上がった。 これ以上何かを聞き出すのは、彼を傷つけるばかりだとわかったのだ。 彩音は何か後ろめたいことに関わっている。でもそこから抜け出したがっていることだけはわかる。 彼を守りたい。 私には何もできないかもしれないけど、私の命にかえて、彼の絵を守りたいと思った。 彩音は、次の日小さなキャンパスを買ってきて、ふたたび絵を描き始めた。 いつも黒一色だったパレットに、鮮やかな絵の具が重ねられていく。 彼は自分の描きたいものを描いているのだ、とうれしくなった。 だが、順調なのは、はじめのうちだけだった。 次第に、筆の進みが滞り始め、膝をかかえて部屋の隅でぼんやりと、タバコをくわえているだけのことが多くなった。 「描けないんだ。琴音サン」 ペンだこのある長い指を神経質に組み合わせたその手が、震えている。 「どうして……。あれほど、楽しそうだったのに。あんなに楽しそうに絵を描いている彩音を見たことなかったのに」 「俺は、やっぱりあれしか描けないのかもしれない。……あいつと同じ絵しか……」 「彩音……」 苦しんでいる彼を、私はどうすることもできなかった。 彼の中に、いったいどんな暗闇があるのだろう。彼を苦しめている「あいつ」とは、いったい誰なのだろう。 聞いて彼を傷つけたくない、と私は思っていた。 でもそれは、間違っていた。 私は、恐れたのだ。彼の過去を知ることで、彼を永久に失ってしまうかもしれないことを、私は本能で知っていたのかもしれない。 私は彼に内緒で、こっそりと横浜の美術館へ出かけた。 6月に彩音といっしょに見た、彼の絵にそっくりな抽象画をもう一度見てみようと思ったのだ。 だが、その絵はなかった。あれは常設ではなく、開館記念の特別展示だったのだという。 私は受付の人にしつこいほど食い下がって、ようやくあのときの展示作品のカラーカタログを見せてもらうことができた。 果たして、私の求めていたものはあった。 「あの、すみません。この画家は……」 受付の年配の女性は、私の手元をちらりと見ると、めんどくさそうに答えた。 「ああ。久世俊之ですね」 「あの、これは本名でしょうか」 「さあ」 「この人、若い男の子ってこと、ありませんよね」 「そんなはずありません。名前の下に生年が書いてあるでしょう。1953年だから、もう50歳近いですよ」 私は、美術館を出るときにすでに確信していた。 光穂さんが、口走ったあのことば。 『彼のお父さんのこともあるし……』 久世俊之は、彩音の父親なのだ。「あいつ」と呼んでいたのは、父親のことだったのだ。 そして、最後の残酷な真実は、ほどなく偶然にやってきた。 私はその日、仕事で都心の得意先を訪問していた。 用件が済み、地下鉄の駅に戻ろうとしたとき、一軒の画廊が目にとまった。 私は吸い込まれるようにして、その中に入った。 本当は、偶然ではない。私はあれから、勤め帰りや外回りの途中で、画廊という画廊を丹念に見て回っていたのだ。 だから、その絵が壁に架かっているのを見たときも、驚愕したというよりは、古い知り合いに出会うべくして出会ったような気がしていた。 それは、彩音の絵だった。 黒いカーテンを閉め切った部屋の中で、彼が何日も何日も、挑みかかるようなまなざしで描いていた絵。 その絵の下には、名刺のような紙がピンでとめてあって、そこには想像をはるかに超えた売値がつけられていた。 そして、さらにその下にプレートが。 「無題 久世俊之」 ああ。 私は膝の力が抜けて、立っていられなくなりそうだった。 彩音は有名な画家の父親の贋作を描いていたのだ。 あの人相の悪い画商たちは、彩音に贋作を描かせて、儲けていたのだ。だから、彼が絵を描かないと拒否したとき、金づるを失って怒り、彼を殴ったのだ。 そして、彼も警察に行くことを拒んだのだ。 ハンドバックからハンカチを取り出し、鼻に押し当てた。彩音はこの絵を描くとき、どれだけ辛かっただろう。涙があふれて止まらなかった。 画廊の店主らしい、紫のスーツをまとった年配の女性が、私が泣いているのに気づいたのか、「いらっしゃいませ」と声をかけてくれた。 「お気に召しましたか? すばらしい絵でございましょう」 「え、……ええ」 「最新作ですの。近年ますます深みを帯びていると、評論家も絶賛しております」 「あの……」 私は意を決して、店主に問いかけた。 「この画家のことを何も知らなくて……。この方はまだ、生きていらっしゃる方なのですよね」 私のうちに疑問が湧いていた。彩音の父親は、なぜ息子が贋作を描いていることを黙認しているのだろう。 こんなことは、あっというまに本人の耳にも入って当然なのに。 上品な老婦人は、あいまいな微笑を浮かべて、私を見た。 「ご存知ないのですか、本当に」 「はい……」 「久世俊之は」 そのあとに続いた彼女のことばは、口の動きとは別の場所から聞こえてくるような気がした。 「10年ほど前、ご自分の奥様を包丁で刺し殺したんですよ。それ以来、精神病院の一室で油絵を描いていると聞いています」 『洋画家、妻を刺殺。8歳の息子の目の前でめった突き』 『栃木県旧家の血の惨劇。英国人妻、有名画家の夫に』 『精神鑑定の申し立て。不倫を疑い錯乱か』 図書館を出て、どこをどう歩いて電車に乗ったのか覚えていない。 気がつくと、車窓の外は、11月も終わりの濃い夕闇におおわれていた。 図書館で9年前の新聞を調べて、彩音に起こったことをすべて知った。 彩音は小学校3年のとき、嫉妬に狂った父親が母親を包丁で刺し殺すのを、目の前で見てしまったのだ。 久世俊之はそのとき以来、精神病院に措置入院している。 彩音は……、その父親の絵を真似て、真っ黒な絵を描き続けていたのだ。 自宅マンションに辿り着き、エレベーターを降り、自分の部屋の前に立ったとき、雨の中、廊下にうずくまっていた彩音の姿を思い出した。 あれはたしか6月。 9年前の6月に彩音の母親は殺されたのだ。命日で、彼は実家の墓に参っていたのだろう。 そして、否応なしに、幼心に刻み付けられたあの悲劇を何度も何度もリプレイしていたのだろう。 私はまた、壁をはさんで話したときの彩音の声を、耳の中で聞いていた。 「俺はきっと愛する人を殺してしまう。それが俺にかけられた呪いなんだ」 私はいったい、彩音の何をわかっていたのだろう。 何も知らなかった。彼がどんな思いで、私を愛さないようにしていたのか。 今、どんな思いで、私を愛しているのかを。 鍵がガチャリと回る。私はゆっくりとノブを回す。 部屋の明かりをつけた。 「遅かった……ね。琴音サン」 彩音が目をこすりながら、ソファから起き上がる。「残業?」 「そうなの。ごっめーん」 私は明るい声を出して、部屋に入った。 「急にクレームが入っちゃったの。電話すればよかったね、ごめん。だから、今日は出来合いのお惣菜ばっかりなんだ」 台所の調理台で、スーパーで買ってきたものを袋から取り出しはじめる。 「ごはんは冷凍のがあるから、急いで味噌汁だけ作るね。おなかぺこぺこだったでしょう?」 「……琴音サン?」 彩音は、まっすぐに私を見ていた。 どんなにとりつくろっても演技しても、私の声は震えている。私の笑顔はひきつっている。 「琴音サン、もしかして……」 「彩音……」 「知っちゃったんだね、俺のこと」 「……」 「……知られたくなかったよ、琴音サンだけには」 低くそう言うと彼は、はにかんだような横顔だけ見せて、すっと歩き始めた。 「彩音!」 彼が穴をくぐって姿を消したとき、私はよろよろと一歩一歩ふんばりながら彼のあとを追った。 そうしないと、足が言うことをきかない。 穴の向こうの、暗い何もない部屋の中で、彩音が痩せた肩を丸めた後姿で静かに立っていた。 手にパレットナイフを握っている。 「彩音!……やめて」 彼は私の方にちらりと一瞥をくれると、その手をふりかざし、さっきまで描いていたであろうキャンバスをめちゃくちゃに切り刻み始めた。 「やめてーッ!」 私は突進して、後ろから彼の両脇を抱えて止めようとした。 「俺には……、俺にはあいつと同じ絵しか描けない! 俺は、あいつと同じなんだッ!」 「ちがう、ちがうよ。彩音!」 「俺はいつか、気が狂って、何もわからなくなって、琴音サンを殺してしまう!」 「彩音!」 「いやだ! いやだッ! ……誰か、助けてぇぇ!」 「彩……音」 彼は力尽きて床に座り込み、私は彼の首にすがりついて、ただ泣いていた。 (6)につづく | |
|
TOP | HOME
|
| Copyright (c) 2002 BUTAPENN. . |