CLOSE TO YOU
2nd chapter
2nd chapter
CLOSE TO YOU (第1章) 〜a precious moment〜 CLOSE TO YOU (第2章) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) |
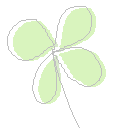 |
(7) 「私があなたの名前を呼んであげる。これからもずっと。彩音。……彩音」 「今……、なんて言ったの?」 「さよなら、琴音サン。俺、明日ここを出て行くよ」 長い話を終えた彩音は、上半身を起こすと、私にまっすぐ向き直った。 |
|
「壁の修理費は、俺のほうでちゃんと出すから。俺が作った穴だもんな」 「……どこへ行くの?」 「まだ、考えてねえや。これから捜すよ。でも絵が売れなくなっちまったから、安いボロアパート捜したほうがいいかもな」 「彩音!」 私は彼の細い両腕をつかんだ。 彩音は、このうえなく優しい、大人びた微笑をうかべた。 でも、彼はほんとうは大人なんかじゃない。 彼がときどき、大人びて見えたのは、なにもかもあきらめていたからだ。 自分の人生を、人を愛することをあきらめていたからなのだ。 「彩音、どこへも行かないで。私のそばにずっといて」 「ムリ言うなよ。琴音サン。俺は久世俊之の息子だ。いつ俺もおかしくなるかわからない」 彼は長いまつげを伏せて自分の手を見た。 「あいつが入院している精神科に、ひと月にいっぺん見舞いに行ってる。あいつ、もう俺が誰だかわからないんだぜ? 絵を描くどころか、めちゃめちゃに壊れちまってる。会うたびに思い知らされる。俺もいつかこうなるんだって」 「彩音は、お父さんとは違うのよ。おんなじになるわけないじゃない!」 「でも、俺は光穂を頭の中で殺したよ。……琴音サンだって、いつ殺したくなるかわからない。琴音サンがちょっとよその男としゃべっただけで……。 頭の中が真っ黒になって、なにもわからなくなって……」 彩音は、自虐的な笑い声をもらした。 「怖いだろ……。ほんとは怖くて逃げ出したいだろ。光穂だって、俺を見ていつもおびえてる。琴音サンだって……」 私は次々にあふれる涙のしずくをまきちらしながら、懸命に頭を振った。 「……私は一生、彩音のそばにいたいよ。もう、離れたくないよ」 「……やめて。琴音サン……」 「彩音の全部をわかりたい。辛かったことを全部教えてほしい。いっしょにそれを分け合いたいの。ね、悲しかったことを全部話して。いっしょに泣こう」 「同情なんて、してほしくないんだよッ、琴音サンに! 俺は同情されながら、怖がられながら琴音サンと暮らしたくないんだ!」 「同情なんかじゃない!」 自分でもびっくりするくらいの大声で怒鳴った。そう、この安マンションの薄い壁なんか2枚くらい突き刺すような大声で。 「私は、ただ悔しい。彩音のお父さんがお母さんを刺したとき、私がそばにいられなかったのが、すごく悔しいの。こんなふうに抱っこして、彩音の目を隠してあげたかった。守ってあげたかったよ。 私はそのとき、もう18だったから、きっと彩音のことを守れた。 彩音が誰ともしゃべらないで、ひとりで屋根裏で何年も過ごしていたとき、私が話し相手になってあげたかった。いっしょに本を読んで、冗談を言って笑って……。 その頃私は、大学や会社の友だちと毎日おしゃべりしていたのに。彩音のことを何も知らずに……。 ひとりぼっちで、眠れないくらい寂しかった夜は、私もいっしょのおふとんで子守唄を歌ってあげたかったよ。 彩音、ごめんね、ごめんね。そばにいられなくて、ごめんね」 「琴音サン……」 彼の目から、こらえきれずひと筋の涙がこぼれた。 「これからは、絶対にひとりぼっちにしないから。私がいつも、いるから。 そして、頭の中が真っ暗で何も見えないときは、私が彩音の名前を呼ぶよ。お母さんのかわりに、 「サイオンって天国っていう意味なんだよ」って、何度も名前を呼んであげるよ。これからもずっと。 彩音。彩音。……彩音!」 「こと……ね……さ」 彩音は私の腕の中で、声をあげて泣き始めた。 「もっと泣いていいんだよ」 「琴音サン、……怖かったよ。とっても怖かったよ!」 「そうだね」 「血で真っ赤だった。なにもかも、真っ赤だっだんだ。父さんが母さんを……とがったナイフで」 「辛かったね、彩音」 「エッ、エッ、エェン」 彼は、まるで8歳の子どもにもどってしまったかのように、いつまでも泣き続けた。 私たちはそうやって、朝になるまで抱き合っていた。 * * * 「琴音。琴音!」 「はあい」 なーによ、えらそうに、琴音だなんて呼び捨てにしちゃって。 ネクタイ一本だって、自分で結べないくせに。 私は、お化粧をあわてて終えると、壁の穴をまたぎ、洗面所の鏡の前にいる彩音のところに行く。 あれから、2年たった。 相変わらず、私たちはまん中の壁に穴のあいた隣同士で住んでいる。 この2年間でいろいろなことがあった。 彩音は去年の春、どうにか高校を卒業したあと、ずっと絵に没頭している。 父・久世俊之の贋作を描いていたことを公に発表してのち、彼は画壇からしばらく見向きもされなかった。 それでも彩音は、描くことがうれしくてたまらないみたいだった。 彼は故郷栃木の自然を、美しい森や夕暮れの風景画を描いた。 公園で遊ぶ子どもと母親たちを、水辺で戯れる小鳥たちを、優しい色で描き続けた。 彼が最初に認められたのは、去年の秋のこと。光あふれる天にむかってまっしぐらに飛ぶ鳥の絵が、ニューヨークの国際コンクールで入選したのだ。 そして今日は、日本国内で開かれるはじめての個展の初日。 20歳の彩音は、少し肩幅も広くなり、背もまた伸びて、スーツの似合う男性になった。 相変わらずぼさぼさだった黒い髪の毛も、今日はきっちり櫛を入れて、あらわになった漆黒の瞳がじっと私を見つめている。 ゆがんだネクタイを整えてあげると、彼は私を包み込み、キスをした。 「ダメ……。遅れちゃうよ」 「だって、琴音きれいなんだもん。……5分あったら、ヤれるから」 「ダメッ! この、年中発情期男!」 彩音は、しぶしぶ諦めて、とたんに「じゃあ、もう行くぞ! 遅刻する!」と、私をせかし始めた。 ほんとに、いつまでたっても子どもみたい。 実は、今日のスピーチで、私との婚約を爆弾宣言することになっているらしい。 本人は内緒のつもりだけど、とっくにバレてる。化粧台の引き出しをこっそり開けて、私の指輪のサイズを確かめていたのも、お見通し。 それでも、私はびっくりしたふりをしてあげる。 「行こ。琴音」 「はい」 ハンドバッグを持つ反対の手で、差し出された彩音の手をしっかりと握って、私たちは玄関を出た。 もう私は、彼のそばにいるだけじゃ満足しない。 彼のそばを歩き続ける。同じ歩調で。 これからもずっと。 FIN | |
|
TOP | HOME
|
| Copyright (c) 2002 BUTAPENN. . |